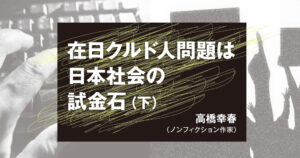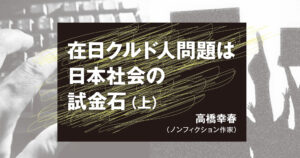【タイトル画像】1953年4月、防衛大学校(当時、保安大学校)に入学し、整列する1期生=神奈川県横須賀市。写真=共同通信イメージズ
サンフランシスコ講和条約により日本が主権を回復してほどない1952(昭和27)年8月、防衛大学校は保安大学校という名称で設立され、翌年春、約400人の新入生を迎え入れ正式に開校した。当初の2年間は小原台でなく同じ横須賀市久里浜地区の仮校舎が、学び舎となった。
前回の記事はこちら【ジャーナル】第46回◎三山喬 民主主義の〝軍〟を目指して(1)
再軍備
日本の再軍備そのものは1950(昭和25)年8月、勃発して間もない朝鮮戦争に米軍が出兵する間、留守となる日本国内の武力組織として警察予備隊と海上警備隊がつくられて始まった(両者は1952年に保安隊と警備隊、54年に陸上自衛隊と海上自衛隊に改組された)。
一連の流れをつくったのは、時の首相・吉田茂だ。戦前からリベラルな外交官として反軍部の思いを持っていた吉田は、GHQによる占領期、非武装のスタンスを強く打ち出したが、朝鮮戦争の司令官となったマッカーサーから警察予備隊の設置を強く求められ、否応なく日本の再軍備を進めることになる。

防大一期生で自衛隊勤務のあと三菱総研研究員となった中森鎭雄は著書『防衛大学校の真実 矛盾と葛藤の五〇年』(2004年)で、吉田の思い描く「新国軍」のイメージには、吉田自身、独自の和平工作を咎められ憲兵隊に囚われた体験が反映されていると書く。
もともと陸軍と帝大が日本をダメにしたとの持論を持っていた吉田の体には一層、陸軍嫌いが染みついた。二度と同じ轍を踏んではならない。軍備は必要だが、旧軍の復活だけは断固阻止し、旧軍の悪弊を二度と持ち込んではならない、との思いが強かった吉田が描いたのは、国民主権国家にふさわしい民主的な開かれた軍隊だった。
保安大学校は、将来の新国軍の核となる担い手を養成する学校である。旧来の陸士、海兵であってはならない。吉田の意図するところは、立派な社会人としての教養を身につけた幹部隊員の養成だった。
そしてその吉田が保安大学校の初代学校長に選んだのが、槇智雄だ。推薦者は当初、吉田が学校長を打診した皇太子の教育役・小泉信三。小泉が慶応大塾長だったとき、大学の理事を務めていた政治学の教授が槇だった。オックスフォード大学への留学歴を持ち、『青春の小原台』によれば、家人は「本当にイギリス人のような人でした」と評していたという。
この本では、防大卒業から約三十年になる一期生たちが口々に槇から受けた影響の大きさを語っている。

旧軍への反省
槇をはじめとする創設時の担当者らは、戦前の陸士、海兵から米国のウエストポイント陸軍士官学校、アナポリス海軍士官学校、フランスのエコール・ポリテクニークの特徴を研究した。関係者が共通して念頭に置いたのは、あまりにも精神主義に走り、陸軍と海軍がいがみ合った旧軍への反省であり、新たな学校では「科学的思考を基礎に置くこと」を合意していたという。そんな理由から、当初設置した講座は理科系のみ。東京工大や東大工学部の大学運営を参考にしたという。
その結果、土木、化学、電機、機械の四学科で教員60人ほどの体制が整えられたという。
『青春の小原台』には保安大学校の開校前、副校長の手元には千人分ほどの履歴書が集まったとある。「戦後の混乱がまだ続いていた時代、失職中の学者も多く、量の点では問題なかった」。あとで調べると、私の父親の採用は保安大学校開校から半年ほど遅い1953年11月。その前の父は米国から帰国して都立高校に化学の教員として在籍中。失職こそしていなかったが、目まぐるしく職を変え、研究職のポストを求めていた。
さて、そういった知識をある程度仕入れたあと、改めて一期生の卒業アルバムを眺めると、なるほどと感じる点がある。
総勢339人の卒業生たちは、4人で1ページ、ひとり2枚ずつの個人写真のほか、たっぷりと人物紹介の文章が組まれている。ところが大学職員や教員の名前入り写真は、槇学校長以下7人分しか見当たらず、人名リストさえ掲載されていない。
「化学教室」と題された3ページには、実験や講義風景のスナップ写真のほか1枚だけ教員と思しき中年男性18人の集合写真があり、若き日の父親かもしれない人物も目星が付くのだが、いかんせん人名表記が皆無のため「おそらく」としか言えない。
文字通り〝軍隊式〟の縦社会でもあったはずの防大で、卒業生が手作りした写真集。教職員リストを落としたのは〝チョンボ〟だったにせよ、各ページから滲み出る屈託のない明るさは、戦後民主主義の萌芽期ならではの空気感かもしれない。
ちなみに英国紳士風のノブレス・オブリージュ(上位者の責務)や教養主義を重視したマキイズムの伝統を知り、私がふと思ったのは司馬遼太郎『坂の上の雲』に描かれた秋山真之や児玉源太郎など、専門書を原書で読みまくる明治の武人たちの教養人ぶりだ。
あくまで小説の話であり、精神論を振り回す昭和の軍人との対比は、先入観による決めつけかもしれないが、私自身、三十五年前の取材時に一期一会で接したふたりの自衛隊関係者の、その立ち居振る舞いが強く印象に残っている。
ひとりは防大訪問時に案内をしてくれた広報担当者。当初は若干距離を置き差し障りのない対応しかしなかった人物だが、私が元防大教官の息子と知ったとたん、一気に身内のようにくだけた口調に一変した。「せっかくいい大学を出ているのに、何でまた朝日の記者なんかになっちゃったの? お父さんも反対したでしょう」。本人におそらく悪気はない。左派系の朝日への反感が気の緩みで洩れてしまったのだろう。ただそのしつこさには正直かなり閉口した。
もうひとりの印象は真逆だった。当時すでに現役を離れていた元統幕議長・栗栖弘臣[くりす・ひろおみ]が取材に応じてくれたのだ。質問は前回記事で述べたような死生観のこと。回答はやはり漠としたものだったが、私が感じ入ったのはその知的な物腰だ。「有事における自衛隊の超法規的行動はあり得る」という問題発言がニュースになり、更迭された人だけに、さぞ報道機関には思うところが多々あるに違いない。そう覚悟して会いに行ったのだが、意外にもその物腰は終始穏やかで、やり取りは歴史や文学などあちこちに楽しく〝脱線〟し、私は前もって抱いていたイメージの偏りを感じざるを得なかった。朝日記者の私に対しても「自分の知る朝日記者は、取材テーマを本当によく勉強して理解力のある人が多いですよ」と気遣いのある言い方をした。
栗栖は旧軍出身だが東大卒業生。マキイズムの薫陶を受けた防大出身者ではないが、槇智雄が若い防大生に求めたのは、彼のような将官になることではなかったか。そんなふうに私には感じられた。
(つづく)
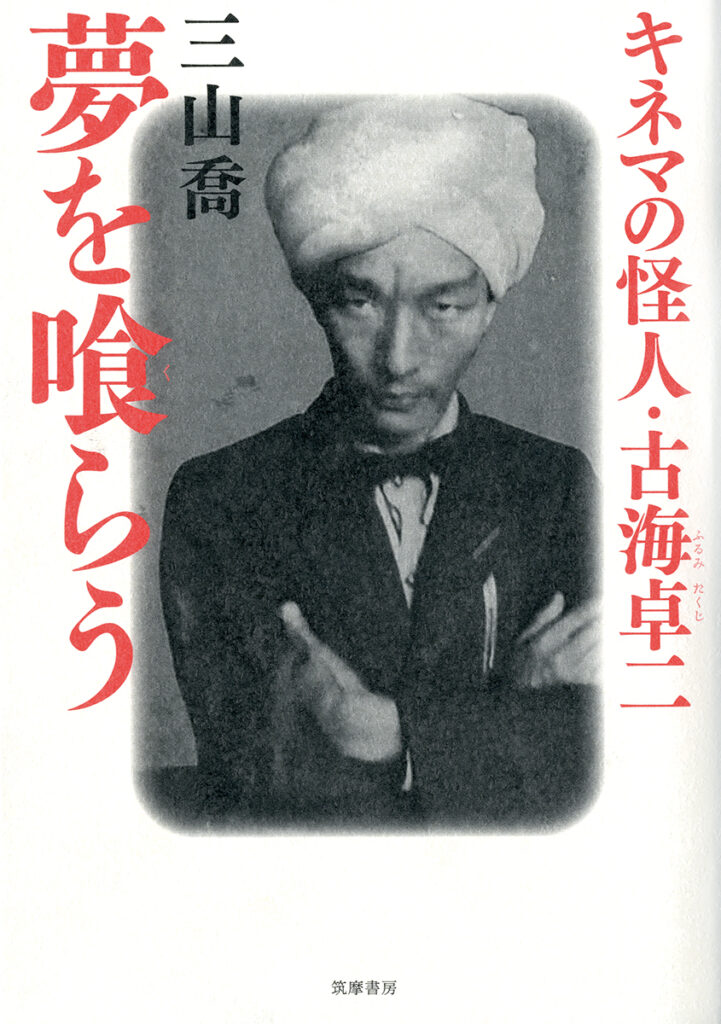
みやま・たかし 1961年、神奈川県生まれ。東京大学経済学部卒業。朝日新聞学芸部、同社会部記者を経てフリーに。2000年から06年にかけ、ペルーを拠点として南米諸国のルポルタージュ記事を各誌に発表。帰国後、ルポやドキュメントの取材・執筆で活躍している。著書に『日本から一番遠いニッポン――南米同胞百年目の消息』(東海教育研究所)、『さまよえる町――フクシマ曝心地の「心の声」を追って』(東海教育研究所)『ホームレス歌人のいた冬』(東海教育研究所、のち文春文庫)、『夢を喰らう――キネマの怪人・古海卓二』(筑摩書房)、『国権と島と涙――沖縄の抗う民意を探る』(朝日新聞出版)、『一寸のペンの虫――〝ブンヤ崩れ〟の見たメディア危機』(東海教育研究所)などがある。
バックナンバー