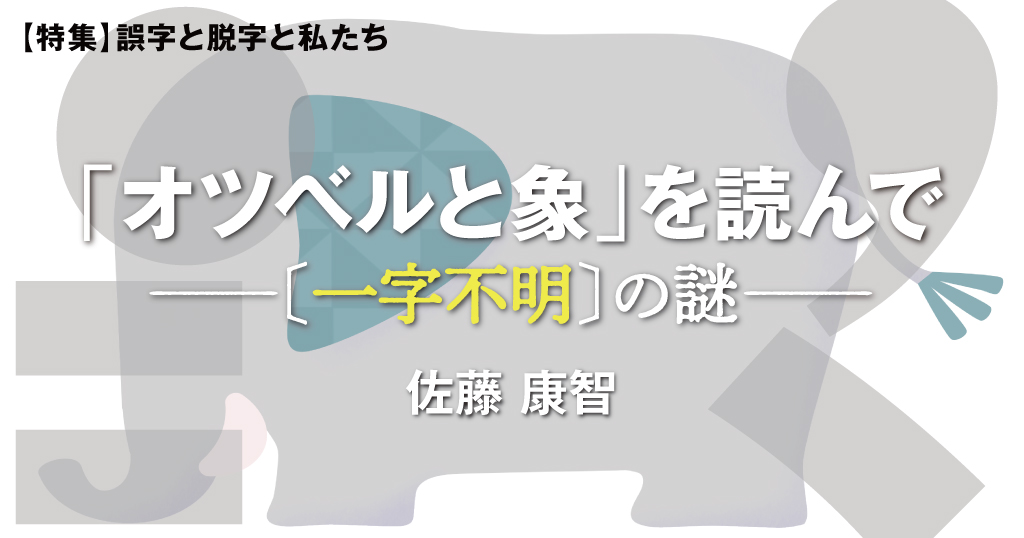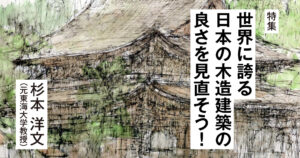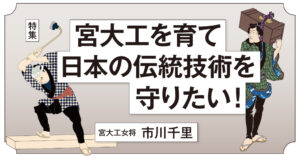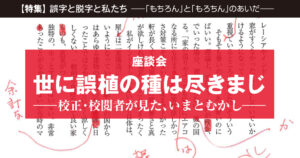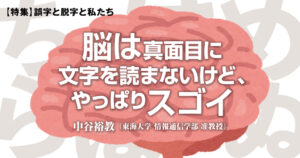小学生だったころ、宮沢賢治の童話集を図書館で借りて、夏休みに読んだ。宿題の読書感想文を書くためである。私は岩手県花巻市の生まれなので、同郷の有名作家で感想文を書こうと思い立つのは割と自然だし、無難だったのだ。
色々と読んだ中に、「オツベルと象」があった。
《オツベルときたら大したもんだ。稲扱[いねこき]器械の六台も据ゑつけて、のんのんのんのんのんのんと、大そろしない音をたててやつてゐる。》
といった調子で、牛飼いの「おれ」が、何者かに語り聞かせている体の、短い物語である。「大そろしない」は、おそらく〝おそろしない〟と読む。怖ろしい、という意味の東北弁だ。耳なれた方言が混じる導入に親近感を覚えた。
オツベルが16人の百姓を働かせる小屋に、ぶらっと白象がやってくる。面白そうに農作業を見つめる白象を、オツベルはスカウトし、言葉巧みに鎖と分銅をつけ、水汲みや、たきぎ運びに従事させだす。はじめはご機嫌に働いていたが、日に日に酷使の度合いが高まり、支給の藁[わら]の量も減り、白象はやせ衰えていく。もう限界、となったとき、月が笑って話しかけ、仲間に手紙を書くようアドバイスする。言うとおり、手紙で助けを求めると、山の象たちがものすごい勢いで押し寄せ、オツベルをくしゃくしゃに潰す。白象は九死に一生を得るのであった。
今でいう〝ブラック企業〟の〝やりがい搾取〟みたいな話だが、労働経験のない小学生の私はあまりピンと来ていなかったろう。ストーリーに関しては、さほど印象に残らず、白象が助かって良かったな、くらいの読後感だったはずだ。
それよりも、ラストの一文に心を持っていかれた。
《「ああ、ありがたう。ほんとにぼくは助かつたよ。」白象はさびしくわらつてさう云つた。
おや、〔一字不明〕、川へはひつちやいけないつたら。》
引用はちくま文庫版の全集より。私がかつて読んだのは子供向けの本だったので、現代仮名遣いだったが、やはり「〔一字不明〕」と載っていた。
ん?と思った。とりあえず、川へ入っちゃいけないという呼びかけが唐突である。川の話なんか、たいして出てこなかったのでは? というか、川へ入るなと、誰が誰を制止しているんだ?そこへ「〔一字不明〕」ときたものだ。こんな表記、他の本で見た試しがない。どういうこと?
混乱した私は、母に尋ねた。すると母は、「昔の原稿だろうから、虫食いでもあったんじゃないの? でも、本当は何と書かれていたか、いつかわかる日がくるかもしれないね」と言った。
なんだかこの「〔一字不明〕」が、妙にかっこよく見え、私は「オツベルと象」で読書感想文を書いた。母の「いつかわかる日がくるかもしれない」という感想を、感想文のオチに使って。

あれから三十数年の時が流れた。
ふと気になり、調べてみたが、今なお「〔一字不明〕」の謎は判明していなかった。というのも、判明させるには、かなりハードルの高い謎だったのだ。ちくま文庫の『宮沢賢治全集 8』巻末の天沢退二郎「後記」によればこうある。
《発表誌は「月曜」一月創刊号(大正十五年一月一日発行。尾形亀之助編集)。草稿なし。本巻本文は発表形に拠る。最終行の〔一字不明〕は発表誌では一字分の黒四角(中央に,点のみの本もある)。題名は、発表誌が人の目にふれなくなったまま、全集本その他で「オッペルと象」として長い間親しまれたが、校本全集で正された。草稿はいっさい現存しないが、作者自筆の題名列挙メモ二種にも「オツベル」「オツベルと象」とある(「ツ」が促音か否かは明らかでない)。》
上記「中央に,点」の「,」の表記は、「・」の点部分がコンマになっているとお考え下さい(私のパソコンで出せない字なので)。加えて、ちくま文庫版より後に出た『【新】校本宮澤賢治全集第十二巻』校異篇では「〔一字不明〕の箇所は、発表誌では一字分の黒い四角(ゲタ)になっているが、刷本によっては小さな黒い点のものもある」と解説され、底本との相違を列挙する校訂一覧には「■→〔一字不明〕」と示されている。
つまり宮沢賢治の直筆原稿が残っていないので、「オツベルと象」本文のよすがは初出の掲載誌『月曜』にしかなく、くだんの箇所は『月曜』で「黒い四角(ゲタ)」や「黒い点」になっているため、一字不明としておくほかない、という話である。
額面通り受け取れば、印刷ミスか校正ミスによる脱字だったということになる。が、刷本によって表記が異なるのが気になるし、「黒い四角(ゲタ)」という表現(黒い四角? ゲタ? どっちよ⁉)もモヤモヤする。
こうなると、自分の目で確かめたくなってくる。ただ、大正15(1926)年発行の雑誌ゆえ、近くの図書館で簡単に見つかるわけもない。それどころか国会図書館にさえ無い。かなりレアな資料なのだ。
検索の結果、大阪府立図書館に蔵書ありと出てきた。東京在住の私は、大阪旅行としゃれこむべく準備した。矢先、東京の大宅壮一文庫にも蔵書があるらしいと知り、ダメ元で出向くと、無事『月曜』創刊号を閲覧することができた。長年、多くの人がひもといてきたことを物語るように、ところどころページが外れている。手が震えた。
サイズは今の『文藝春秋』(あるいは紙の本時代の『望星』)より少し大きめの菊判。各ページ三段で組まれ、全50ページほど。目次には、島崎藤村、室生犀星、岡本一平、サトウハチロー、稲垣足穂といった有名どころも並ぶ。
賢治の「オツベルと象」は「第一日曜」「第二日曜」「第五日曜」の三章構成だが、前半の二章が10~13ページ、後半の一章が(「一三頁よりつゞく」と付記され)34~36ページに、なぜか分けて掲載されている。全二章で完結と勘違いした編集者が、あとから三章まであることに気づき、あせって後ろのページに付け足したのだろうか。あるいは、「第二日曜」から「第五日曜」にかけての三週の間[ま]を、あいだに別の原稿を挿しはさむことで醸し出そうとしたのか。だとしたら、ちとわかりづらい演出だが、気持ちとしてはわからないでもない。
ラスト一行は36ページの上段にあった。
《おや、■、川へはいつちやいけないつたら。》
このような感じで印刷されている。ただし、厳密にいうと「■」は単なる黒い塗りつぶしではなく、真ん中あたりに、うっすらではあるが、針で引っかいたような二筋の白い横線が確認できた。たしかに、ゲタ文字に近いように思える。
ゲタ文字とは、活版印刷の時代、必要な活字(ひと文字分のハンコのようなもの)が無かった際、その文字のかわりに、いったん他の活字の裏側を組み込んで印刷した文字のことをいう。活字の裏側には溝があり、下駄の歯のように印字されることからこの名がついた。デジタル社会の現在でも、解読不明の文字や、表示できない特殊文字を表すときに使われることがある。パソコンやスマホでも「げた」と入力すると「〓」と変換できるはずだ。
でもって「〓」くらい鮮明に白い筋が見えればゲタ文字と特定できるのだが、いかんせん、「オツベルと象」不明部分の筋は、あまりにかぼそいのである。活字裏の溝の具合によっては、ほぼ「■」に近いゲタ文字が印字されることもあるものの、かといって、これが絶対にゲタ文字だとは言い切れない。なるほど、新校本全集の「黒い四角(ゲタ)」という、煮え切らない表現には、そういった悩ましさがこもっていたのか。
基本的にゲタ文字は、一時しのぎで使われる。掲載前の校正段階で刷られることは多いが、たいていは必要な活字を間に合わせて完成させたものが掲載誌に印刷される。『月曜』創刊号の全ページを確認すると、インクのかすれで読めない文字こそあるものの、ゲタらしき文字は「オツベルと象」の当該部分だけだった。せめてもう一つ似た文字があればゲタ文字と特定しやすいのだが。
新校本全集の「刷本によっては小さな黒い点のものもある」という記述と照らし合わせると、「■」がゲタ文字であった見込みはもう少し高まる。追加で印刷された二刷で、訂正されたということか。いや、だとしても「黒い点」では、訂正になっているのやらわからない。ヌエのように、どこまでも人を惑わす罪作りな誤植なのである。
ところで、レア本だった初出誌『月曜』が発掘され、それに伴う校訂がなされた『校本宮澤賢治全集第十一巻』が出る1974年くらいまで、「オツベルと象」は「オッペルと象」という題名で世に普及していた。そして、一字不明の「■」部分に「君」と当てはめた書籍も流通していた。根拠は不明だが、ともかく誰かが、「君」に違いない!と決めつけたのだろう。他に、一字不明部分を丸ごとカットする書籍もあった。
各掲載書がラスト一行をどう表記しているかについては、清水正『宮沢賢治を解く 「オツベルと象」の謎』に詳しい。清水は最終行の一字不明を「きわめて重要なキーワード」と捉えている。その上で、前掲した天沢退二郎の校訂態度を批判している。
《『オツベルと象』の本文を《発表形に拠る》のであれば、当然のこととして最終行は《おや、■、川へはひつちやいけないつたら。》にすべきであろう。この一字分の黒四角(■)をどのように解読するかは、それこそ読者の側の問題なのであるから。この■を、《〔一字不明〕》としたのは一校訂者の〝解釈〟であって、その〝一解釈〟を本文テキストに入り込ませたことに問題がある。》
一字不明と見なすことも解釈に過ぎない、という意見にはうなずける。しかし、■だか〓だか判別できない曖昧な発表形を見た上で考えると、単に■と代入するのも解釈になってしまい、どうにも悩ましい。
見方を変えればそこは、あらゆる解釈の余地を残すブラックボックスともとれる。
たとえば清水は、最終行の〔一字不明〕が「中央に,点のみの本もある」ことから類推し、賢治がヘブル語のアルファベットであるヨッド「י」と記していた可能性を指摘している(『宮沢賢治の神秘 「オツベルと象」をめぐって』)。
一字不明部分に何が入るか、理由付きで生徒に考えてもらう授業を行う中学校もある。その際、一番多かった回答は「象」だったそうだ(日能研ホームページ、茗溪学園中学校の濱島先生へのインタビュー)。
また、鈴木貞美はラスト一行を、牛飼いが白象に投げかけたセリフと捉え、ゲタ文字の部分は「難読漢字などではなく、崩し字をタイピストが読み取れなかっただけで、『君』という軽い敬称でよいはずだ」と解釈している(「宮澤賢治『オツベルと象』について」『水門――言葉と歴史――』第31号)。
ラスト一行の発話者が誰なのかについては、牛飼い説や作者(賢治)説などがあり、被発話者(川に入ろうとしている者=一字不明で呼びかけられている者)に関しても、牛飼いの話の聞き手説、牛説、白象説、賢治説、読者説などがあり、そのシチュエーションについても様々な説が、様々な研究者によって唱えられている。先行研究を網羅的かつ事細かに紹介した村上英一「『オツベルと象』の解釈―先行研究について」(『雲の信号』第5号)を読むにつけ、百花繚乱の大喜利のように盛況だ。
私としては、牛飼いが飼い牛に対して呼びかけている説が、オツベルと白象との関係とパラレルになって綺麗かなと思うが、何はともあれ、一字不明に起因して様々な解釈が生まれることが、「オツベルと象」の大きな魅力と言えるだろう。「『〔一字不明〕」の欠落』=不在こそが、そのまま表現なのではないでしょうか」(ツチノコ珈琲『奇っ怪なポタリング』)という指摘もある。その伝でいえば、罪作りな誤植も、読者の手によって表現になるのだ。
そしてもちろん、宮沢賢治の直筆原稿が発見される可能性も大いに残されている。本当は何と書かれていたか、いつかわかる日がくるかもしれない。

さとう・やすとも 1978年生まれ。名古屋大学卒業。文芸評論家。 2003年 、「『奇蹟』の一角」で第46回 群像新人文学賞評論部門受賞。その後、各誌に評論やエッセイを執筆。『月刊望星』にも多くの文学的エッセイを寄稿した。新刊紹介のレギュラー評者。