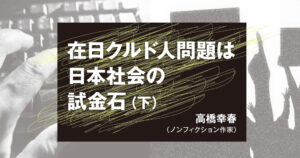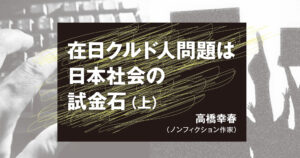【タイトル画像】1953年4月、防衛大学校(当時、保安大学校)に入学し、整列する1期生=神奈川県横須賀市。写真=共同通信イメージズ
前回の記事はこちら【ジャーナル】第47回◎三山喬 民主主義の〝軍〟を目指して(2)
防大で年に何回か発行され続けてきた『小原台』という雑誌がある。開校から二年弱、まだ保安大学校時代の1955(昭和30)年1月に出た創刊号には、槇智雄学校長も「筆立たずして人に読ましめ、その意図するところを伝へることは出来ない。唯読むことを知つて、人に知らしむることが出来なければ人生の意義は半減する(略)文の発表には勇気を要し又責任の伴ふことを知るであらう」と発刊への祝辞を寄せている。
巻頭にある目次をひもとくと、ロシア文学や日ソ関係にまつわる論考のほか、詩、短歌、紀行文、小説、戯曲、随想とあらゆるジャンルの寄稿が並んでいて、ちょっとした同人誌の趣だ。
草創期の防大生のイデオロギー
『心の華』と題した短編小説には、保安大生になった青年の苦悩が描かれている。空襲で生き別れになった幼少期の女友だちと高校時代に再会し、恋人になったにもかかわらず、保安大学校に入学後、そんな彼女から別れの手紙が送られてくる。気がつけば非戦論を思い詰めるようになった彼女は、幹部自衛隊員を目指す主人公の生き方を受け入れられなくなったのだ。しかしそんな折、横須賀の街にぶらりと外出した主人公を、新たな出会いが待っていた。相手はその前日、大学校の柵の外に十字架の落とし物をした少女だった。聞けば彼女は戦地からの引揚者で、帰国時の混乱で母親を失っていた。
それでも母の形見の十字架を大切にするこの少女は、もはや戦争への憎悪はないといい、過去の出来事を許す境地になったのだと語った。主人公の心に浮かんだのは、議論よりも「互いに理解し合う」大切さ。平和という理想はおそらくその努力の先にあるのではないか。主人公はさまざまに思い悩む心の持ちように、ひと筋の光明が見えたように感じたのだった──。
同年11月の第3号は、その春に行われた京大新聞部と『小原台』編集部の「対談」を取り上げている。
記事によれば、やり取りは当初、防大の立派な新校舎、生活費の手当まで出る恵まれた待遇が話題となり、次いで京大側から米軍依存の再軍備の是非を問う声が上がった。
防大生の発言者は(東西冷戦から距離を置く)中立論が実現できるならいいことだと思うが、あいにく日本にその力はないと主張。なかには「米国に依存しない再軍備ならいいのか」と京大生に問い返す者もいた。
話題が憲法問題に切り替わると、防大側出席者は一人ひとり考えを述べる形になり、「外国の圧政下につくられた憲法はふさわしくない」「十分自衛力は持てるから現行のままでいい」「日本の方向が確かでない限り、改正は疑問だ」などとさまざまな意見が出たという。
実はこの「対談」、『毎日新聞』の連載を書籍化した『青春の小原台』(四方洋・飯島一孝著)でも触れられていて、そこでは京大新聞部の『学園新聞』に載ったルポ記事が紹介され、「規律と統制にしめ上げられた環境で若い魂の可能性が変質させられていく」と、京大側から見た印象が書かれている。同時に防大一期生の談話として「われわれを特殊な目でみて、はじめからカーテンをおろしてしまうようなことはやめて頂きたい」という要望も掲載されている。
この書籍の執筆者はそのうえで、草創期の防大生気質をこうまとめている。
一期生が入ったころ、自治会を結成して全学連に加盟しようという動きもあったと聞いた。ただし、その意見を強く吐いていた男は一年間いただけで学校を去っていった。一方では、右翼のような発言をする者もいた。彼らは「軍神」と呼ばれたりした。全体に防大生たちのイデオロギーは健全であり、両極端の考えは自然に排除されていった。
防大生と京大生の議論
雑誌『小原台』の同じ号には、ひと組の防大生と京大生がやり取りした書簡も掲載されている。ふたりは高校時代の親友で、帰省中に対面し、ふた晩にわたって議論を交わしたあと、改めてそれぞれの思いを手紙に綴っていた。
防大生のほうは、核兵器の時代にも局部戦(局地戦)はあり得るから備えが必要だと主張。進歩派のインテリに多いソ連や中国共産党を賛美する声に疑問を呈している。「僕も米国の軍事基地提供や軍事援助は独立した日本の為に歓迎してはいないが、日本の置かれている歴史的現実は反米を合唱することに依っては解決されないと思っている」。そのうえで改めて非武装では日本の安全は保障されないと言い、このように訴えている。
日本の中立が出来たら良いと云う事と可能であると云う事は別問題であり、無防備国家日本の主権を外国は侵すべきでないと云う事と、将来侵されないであろうと云う問題とを混同してはならないのだ。それは願わしい事であるが、厳しい現実の上に立って、可能か否かを判断しなければならない。
一方京大生のほうは、外国からの侵略もあり得ないこととは言えないが、あくまでもそれは「将来の問題」であり、それよりも目下直視すべきことは在日米軍基地の存在など日本が米国の「半植民地状態」にあることだと主張した。このような状況下の再軍備は、米国にとっての「太平洋の防壁」になることにほかならず、日本の再軍備がむしろ東西両陣営の力の均衡を不安定にする可能性もあると言っている。
僕は君が戦争を好んでいるとは決して思わない。むしろ戦争を嫌い、それを防ぐ最善の道として今の方法を選んだことも知っている。二人とも同じものを目指していながら考え方がまったく反対になってしまったとは皮肉な話だ。しかしそれにもかかわらず僕は君に深い友情を持っているし、君も僕を信頼してくれていると思う。
そんな議論が交わされた時代から七十年、日本国内では専守防衛の自衛隊と在日米軍の組み合わせの国防体制がすっかり定着し、大多数の国民に支持されている。そういった令和の感覚から振り返ると、京大生らが主張した「非武装中立」はあまりに危うげで、防大生の言い分に理があるように見える。
一方で注意しなければならないのは、米国などとの「片面講和(単独講和)」により西側の一員になることと、ソ連東欧も含む全面講和により「中立」(ここでは武装中立という前提で考えたい)の立場をとることを比較して、戦争のリスクはどちらが低いのか、1955年の時点で見通すのは困難であったということだ。
東西両陣営から距離を置く立場に身を置いても、どこの国からも絶対に侵攻を受けないでいられる保証はない。かと言って米軍の同盟国として冷戦構造に組み込まれ、日本に戦火が及ぶ事態もまた、あり得ないこととは言えなかったのだ。
結局、米国の庇護を離れ中立国を目指すには、あまりに高度な外交力が必要で、それよりは片面講和と米軍駐留の継続、そして再軍備という流れが現実的だった。
私個人は、この1955年というタイミングならば、防大生や京大生が議論を交わした、上記のような「保革」の大論争でなく、むしろこの年の保守合同により、自由民主党が誕生するに至る前段の保守論者内部の意見の差異に注目したい。
その部分にこそ、防大の生みの親・吉田茂の精神や「槇イズム」につながる価値観が潜んでいるように思えたからである。

吉田茂のスタンス
再軍備や講和問題に対する吉田のスタンスは折々で変化しており、その本音はつかみにくい。
新憲法について審議した1947(昭和22)年の衆議院の論戦で、日本共産党の野坂参三議員が9条の戦争放棄について「戦争一般の放棄でなく、侵略戦争の放棄とすべきでは」と問うたのに対し、吉田は「近年の多くの戦争は国家防衛権の名において行われた」と自衛戦争も含めて放棄すべし、と答弁した逸話は広く知られている。
マッカーサーの要請で警察予備隊を設立するときには、GHQのもとでさまざまな工作活動をする旧軍幹部らの登用に強く反対した。かと思えば、講和条約の早期締結を目指すため、米国との単独講和や米軍の駐留継続を日本サイドから持ちかけた。それでいて50年代になって強まった米国からの軍備増強要求には、経済優先を理由として抵抗し続けた。
このような曖昧な態度に不満を示したのが、公職追放を解除され、政界に復帰した鳩山一郎らのグループで、憲法改正や明確な再軍備を掲げて日本民主党を結成した。公職追放から復帰した旧軍関係者もその多くが鳩山のもとに結集した。55年体制の出発点となる保守合同は、吉田が長期政権から退いたあとの自由党と日本民主党が合体し、自由民主党を立ち上げた出来事だ。
旧軍嫌いだった吉田が創設した防衛大学校。そこには旧軍の士官学校とどのような違いがあったのか。そこにこそ私の関心は向いていた。

(つづく)
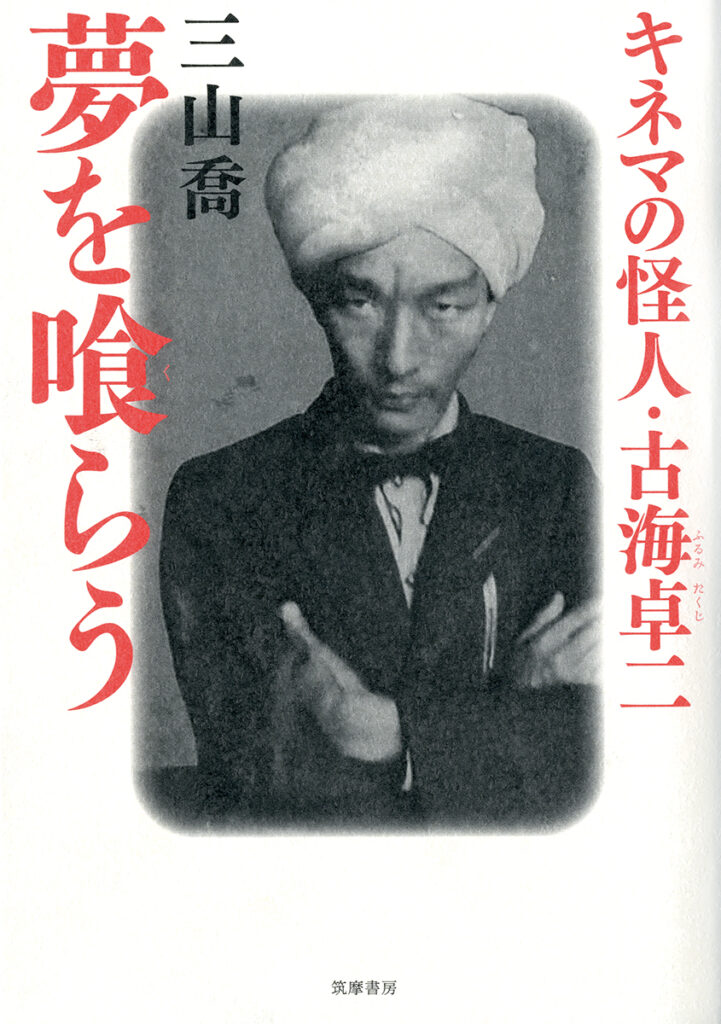
みやま・たかし 1961年、神奈川県生まれ。東京大学経済学部卒業。朝日新聞学芸部、同社会部記者を経てフリーに。2000年から06年にかけ、ペルーを拠点として南米諸国のルポルタージュ記事を各誌に発表。帰国後、ルポやドキュメントの取材・執筆で活躍している。著書に『日本から一番遠いニッポン――南米同胞百年目の消息』(東海教育研究所)、『さまよえる町――フクシマ曝心地の「心の声」を追って』(東海教育研究所)『ホームレス歌人のいた冬』(東海教育研究所、のち文春文庫)、『夢を喰らう――キネマの怪人・古海卓二』(筑摩書房)、『国権と島と涙――沖縄の抗う民意を探る』(朝日新聞出版)、『一寸のペンの虫――〝ブンヤ崩れ〟の見たメディア危機』(東海教育研究所)などがある。
バックナンバー