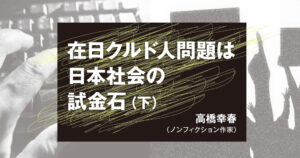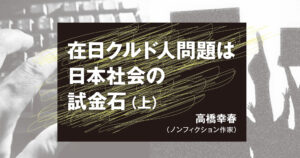【タイトル画像】1953年4月、防衛大学校(当時、保安大学校)に入学し、整列する1期生=神奈川県横須賀市。写真=共同通信イメージズ
前回の記事はこちら【ジャーナル】第48回◎三山喬 民主主義の〝軍〟を目指して(4)
「防衛大卒のトップ就任で自衛隊は本当に変わるのか⁉」
東京・世田谷区の雑誌図書館「大宅文庫」で資料を探すなか、週刊『プレイボーイ』1989年9月19日号にそんなタイトルの記事を見つけた。
執筆者は少年期、陸上自衛隊の生徒教育隊(現・少年工科学校)から航空学校などで学んだあと、地方紙の記者などを経て軍事アナリストとなった小川和久(80歳)だ。元号が昭和から平成へと変わったこの年、海上自衛隊を統括する幕僚長に防大一期生の先陣を切って佐久間一が就任したことを受けての記事だった。
一期生の気概

各種メディアからこの人事の解説を求められた小川は、自衛隊にまつわるマスコミの誤解や偏見を改めて痛感したという。
そのひとつは防大関係者の〝学閥〟の存在を疑う声。幹部自衛官(士官)として任官する若者には一般大学の出身者も44%混ざるのに、将官(旧軍における大将~少将)クラスにまで昇進した自衛官は防大卒業生が82.7%を占めていたからだ(いずれも記事掲載時の数値)。
小川はこの差異をあくまで結果論に過ぎないと説明し、防大出身者を優遇する仕組みは自衛隊にないと否定した。そして具体例として、自身と同様に生徒教育隊を出た高卒の同期生に、将官目前の一等海佐がすでに出ていることを挙げ、内部の選抜試験を経て将官になる道は、さまざまな学歴の幹部自衛官に開かれていると強調した。
もうひとつの偏見は、自衛隊トップがいよいよ戦後世代となることで、あの戦争の教訓が忘れ去られ、〝怖いもの知らずのイノシシ武者〟の集団に自衛隊が変化するのでは、という危惧だった。
その否定材料として小川が持ち出したのが、初代学校長・槇智雄の教育「槇イズム」のことだった。〝イノシシ武者〟どころか、むしろ真逆のタイプを防大は育てたのだと小川は言い、記事の中でこう綴っている。
私自身、防大1期生の高級幹部には親しい人が多いが、その発想は驚くほどリベラルだ。たとえば〝北方脅威論〟が吹き荒れて、いまにもソ連軍が北海道に攻めてくるような議論が行なわれていた’77年頃、その風潮に乗った企画を考えたマスコミに対して、〝北方脅威論〟が科学的根拠に基づいたものではなく、いたずらにソ連を刺激するだけの政治的議論だと科学的データをもとに説明したのは、ほかならぬ防大1期生の高級幹部だった。
小川はこのプレイボーイ記事の二年前、『リーダーのいない経済大国』というビジネス書めいたタイトルの本で、「任官拒否問題」の切り口から防大の実像を描いている。
防大の教育を受けたものの、在学中、もしくは何年かの自衛隊生活を経て民間のキャリアへと転身した13人の防大OBや中退者に、それぞれの防大体験や進路変更の決断について話を聞いたものだ。
各人の進路はさまざまだが、みな錚々たる肩書だ。弁護士や国立大教授、シンクタンク研究員、芥川賞候補作家、外務官僚、全国紙記者……。13人のうち一期生は5人を占めている。
高度成長期以前に誕生した防衛大学校(保安大学校)には、貧しい家庭から優秀な学生が続々と集まった。しかし、防大生や自衛官としての生活を送るなか、社会との接点のほとんどない閉鎖的な組織に生きる懊悩、外部で専門的な仕事に就く憧れなど、さまざまな動機から彼らは進路を変更した。
興味深いのは一期生の時代には野放図な梁山泊のような雰囲気だった防大も、七期生、八期生と代を経るにつれ、「部屋の入り方、挨拶の仕方、歩き方、服装、爪の切り方にいたるまで」さまざまな決まりごとが〝伝統化〟していったことだ。学内では「自由」が建前でも、丸山眞男の本を読んでいて上級生に没収された体験者もいた。一部の教育課程には、旧軍のような〝鉄拳制裁〟が行われる部署も存在したという。
ただ総じて言えば、この本に登場する13人の多くは、防大教育のプラス面をしっかり認めていて、とくに「ノブレス・オブリージュ」(高貴なる者の義務)という槇イズムの教えは、槇学校長以降の時代の防大生たちにも、幅広く共有されていた。
「振り返ると、ボクが防衛や軍事を専門とする記者になるなかで、〝先生〟になってくれた自衛官の多くは防大一期生でした。思想的には一人ひとり違っていましたが、共通して高いプライドを持つ反面、〝夜郎自大にはなるまい〟と自戒する様子もありました。何よりも、自分たちこそが戦後の軍隊をつくるんだ、という強い気概を持っていた。その点は一期生に目立つ特徴です。自衛官として生きてゆくなかで、実際に旧軍出身者とぶつかり合ったのか、その点はよくわからないですけど、少なくとも彼らがまだ防大にいた時代、旧軍出身の教官を吊し上げ、『そういうことだから旧軍は負けたのではないですか』などと言う学生もいたように聞いています」
小川に面会して尋ねると、そんな答えが返ってきた。

三島決起へのヤジ
私は念頭にあったひとつの思いをぶつけてみた。1970年、三島由紀夫の割腹自殺のときのことである。陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地の本館バルコニーに軍服のような「盾の会」の制服姿で三島が立ち、眼下にいる自衛隊員らに決起を呼びかけた。ニュース映像に見る現場の自衛官たちはしかし、口々に「バカヤロー」「降りてこい」などと激しく三島にヤジを飛ばしている。
クーデターの呼びかけに動じる様子もなく、痛烈にこれを罵倒する。これこそがリベラルに生まれ変わった戦後の〝軍〟の象徴的姿ではなかったか──。
しかし小川は「うーん」と首をひねり、「違うと思いますよ」と私の考えを否定した。
「あのとき、庁舎内では盾の会の連中に東部方面総監が縛り上げられていた。現場の自衛官たちには、そのことに対する怒りがあっただけでしょう」
それでも、と私は食い下がった。
もしも令和のいま、同じ光景が繰り返されたなら、結構な割合の自衛隊員らが静かにアジ演説に聞き入るのではないかと。
「そうかもしれません。だとしてもそれは、自衛官だけでなく社会全体の変化でしょう。自衛官の意識は結局、世間一般の意識とさほど違わないものですよ」
おそらく小川の言うとおりなのだろう。
吉田茂は戦後、皇太子(当時)の教育を慶応大塾長だった小泉信三に委ね、保安大学校の学校長に小泉の推薦で槇智雄を充てた。吉田にとって、このふたつの人事こそ戦後の日本に打ち込んだリベラリズムの楔[くさび]ではなかったか。私はぼんやりとそんなことも考えていたのだが、いささか決めつけが過ぎたかもしれない。
防大一期生のリベラルさは、槇イズムばかりでなく、戦後間もない時期の国民意識を映し出していた。

等松春夫教授の指摘
時代とともに移ろう自衛隊・防大生の意識。この点に関連して言えば、防大で三年前、こんな出来事が起きている。防大教授(政治学)の等松春夫[とうまつ・はるお]が『集英社オンライン』のサイトに、『危機に瀕する防衛大学校の教育』と題する内部告発的文章を発表したのである。
等松は、受験者の激減や中退者、任官辞退者の急増、パワハラやセクハラなどの問題発生の背景に、自衛隊の組織内から任ぜられる教官に「その任には堪えられない人」が少なくない問題があると指摘した。
そういった問題教官の一部には「安直な陰謀論に染まる。⾃分が担当する授業の枠内で、学外から招いた問題のある論客に学⽣たちに対する講演をさせる場合まであり、防⼤内に不適切な⼈⼠が⼊り込むチャンネルになってしまっています」と、いわゆる〝商業右翼的なの論客〟を講師に招く悪習があると訴えた。
防大側では、久保文明校長が大学校のサイトに「所感」を載せ、「議論の一部は推測に基づいていると感じられる。本校の名誉を大いに傷つけた」と反論した。
双方のやり取りは以後、学内での討議に切り替えられ、ネット上の応酬は終わったが、等松の指摘には重要な問題提起もあり、『集英社オンライン』には元防衛大臣として石破茂による「早急に事実確認をして、事実と認められる点、あるいは指摘により改善が考えられる点については改善策を講じるべきでしょう」とする談話も載せられた。
社会全体の右傾化の流れを考えると、防大のみが孤高を保ったまま〝リベラリズムの砦〟であり得るはずはなく、いわゆる〝槇イズム〟も、あくまで軍人精神や死生観のような旧軍的価値の押し付けを排するものだったと解すれば、それ以上の思想の右左へのばらつきは、あってしかるべきものなのだろう。
ただそれでも、槇イズムの価値をもう一度深く見直せば、等松教授の指摘するような状況には、やはり改善が求められる。
(つづく)
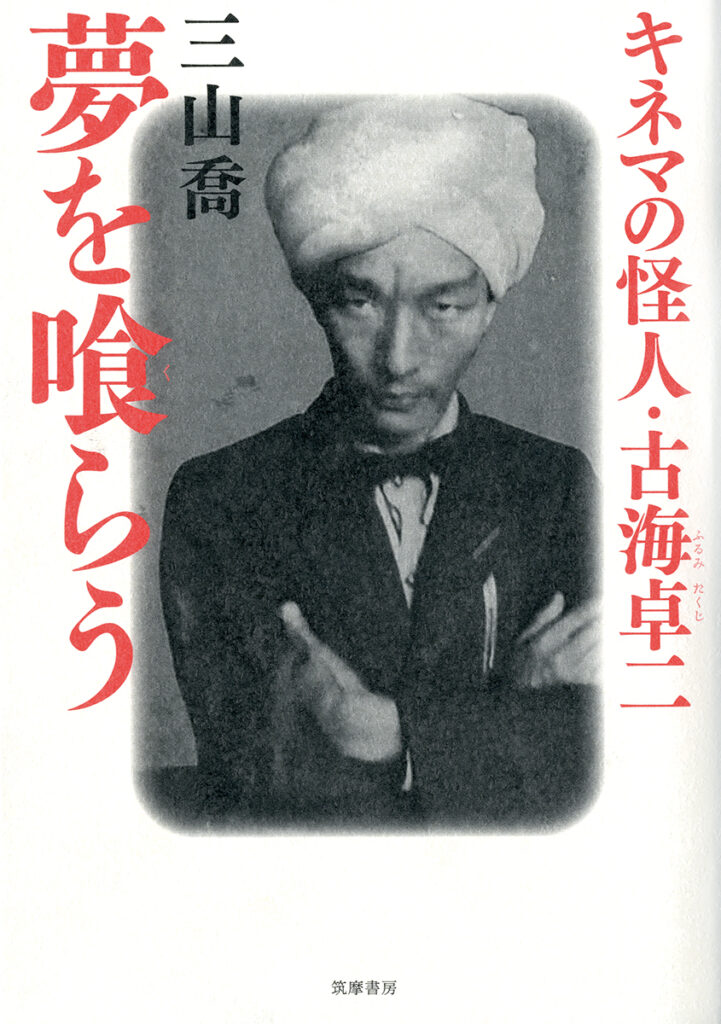
みやま・たかし 1961年、神奈川県生まれ。東京大学経済学部卒業。朝日新聞学芸部、同社会部記者を経てフリーに。2000年から06年にかけ、ペルーを拠点として南米諸国のルポルタージュ記事を各誌に発表。帰国後、ルポやドキュメントの取材・執筆で活躍している。著書に『日本から一番遠いニッポン――南米同胞百年目の消息』(東海教育研究所)、『さまよえる町――フクシマ曝心地の「心の声」を追って』(東海教育研究所)『ホームレス歌人のいた冬』(東海教育研究所、のち文春文庫)、『夢を喰らう――キネマの怪人・古海卓二』(筑摩書房)、『国権と島と涙――沖縄の抗う民意を探る』(朝日新聞出版)、『一寸のペンの虫――〝ブンヤ崩れ〟の見たメディア危機』(東海教育研究所)などがある。
バックナンバー