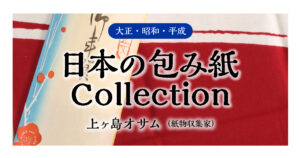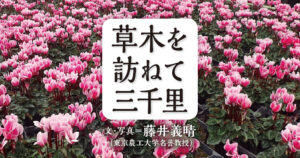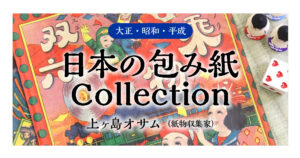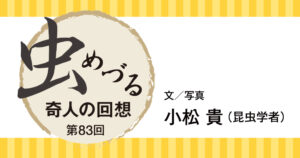第80回 貸し農園で見つけた営み
去年の真夏のある日、いつも使っている近所の無農薬貸し農園まで、野菜の収穫に出かけた。目的は我が家の夏のスタミナ源、モロヘイヤだ。ところが、いざ畑へ着いた私が目にしたのは、何者かによって葉が手ひどくズタズタに切り刻まれたモロヘイヤだった。
その憎き犯人は、意外にも早々に私の前に名乗り出てきた。一匹のバラハキリバチが飛んできて、目の前のモロヘイヤの葉に止まり、流れるようななめらかな動きで葉を切り取って抱え、飛び去ったのだ。その後を見失わないように追っかけてみると、彼女は隣の区画の畑へと飛んでいき、ナス科野菜用の支柱に使われていた一本の竹筒の中へと飛び込んでいった。
バラハキリバチは、中空の竹筒など既存の穴の中に花蜜を蓄えて巣とするハチだが、その巣部屋の仕切り材として通常は他所から切り出して来たバラの生葉を使う。まさか、モロヘイヤまでその用途に用いるとは。大事な野菜を痛めつけた彼奴を粛清するのは簡単ではあるが、しかし私は敢えて何もせず、見て見ぬふりをしてやった。別の時、彼女が同じ畑で育てていたインゲンの花にやってきて、受粉に貢献しているのを目にしていたから(ほっといても自家受粉して結実するにしても)。


どうせ植えたところで、収穫間際に憎たらしいアライグマにやられて全滅するのが分かっているので近頃は植えなくなったが、以前は五月くらいになるとこの畑でトウモロコシを植えていた。「風媒花のトウモロコシは、人の手で受粉した方が結実がよい」という話を農園の管理者から聞いていたものの、面倒くさくて私はやらなかった。にもかかわらず、畑のトウモロコシの結実具合はかなりよいものであった。
なぜなのかという疑問の答えは、夜中に草むしりのため畑に行ったときに分かった。開花したトウモロコシの花に、物凄い数のガが集まってきていたのだ。一見、うまそうな蜜など出ているように見えないそれに、ガがこぞってたかり、全身を花粉まみれにして一心不乱に何かを吸っていた。しかも、そのガの中で一番目についた種たるや、俗に「夜盗虫」とか「根切り虫」と呼ばれて農業関係者の間でも悪名高いヨトウガ、カブラヤガだった。彼らは幼虫こそ野菜の大害虫だが、成虫は野菜の受粉をしてくれていたのだ。(※)
昔話「ごんぎつね」で、村人に悪事を働いていた狐が、母を亡くした男のために栗や松茸を供える善行を重ねていたという事実が最後の最後になって日の目を見るシーンがある。私もそれに倣い、「夜盗虫、おまいだったのか。いつも、受粉してくれたのは」と彼らに言わずにはおれなかった。ヒトでもムシでも、一方の側から見ただけでその善し悪しを決めつけてはならないのだ。
※これはイネ科の病原菌「麦角菌」が産生する蜜に引き寄せられたものらしい。通常、イネ科植物の花は蜜を出さないが、これに感染した菌は胞子を含む蜜を出して虫を誘引し、胞子を運ばせる。なれば、上記の状況は必ずしも作物に好ましくないかもしれない。



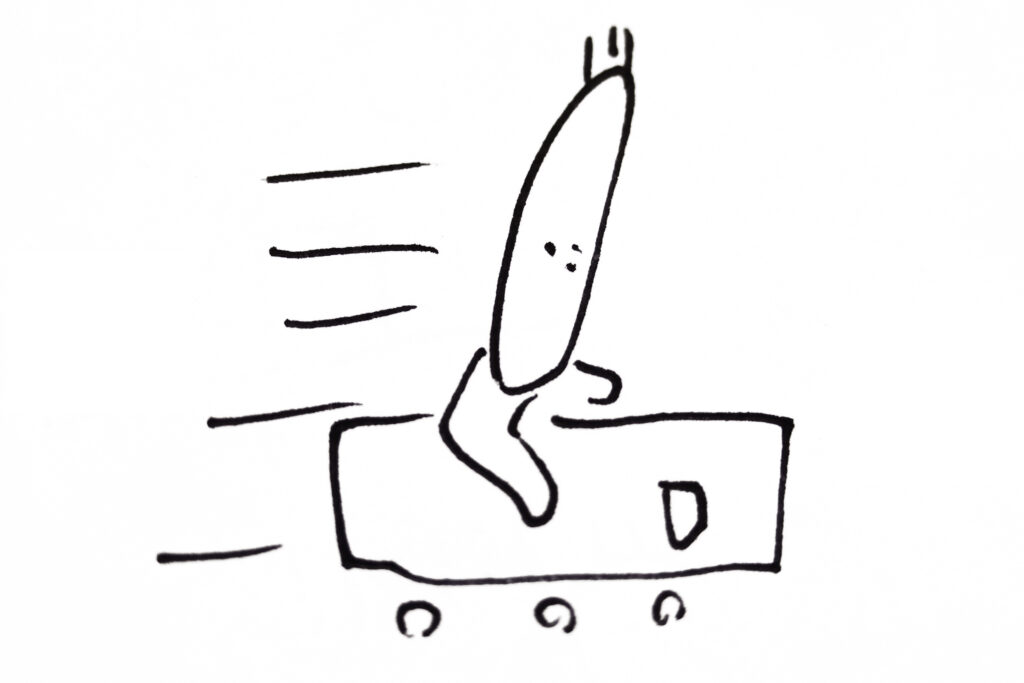
こまつ・たかし 1982年神奈川県生まれ。九州大学熱帯農学研究センターを経て、現在はフリーの昆虫学者として活動。『怪虫ざんまい―昆虫学者は今日も挙動不審』『昆虫学者はやめられない─裏山の奇人、徘徊の記』(ともに新潮社)など、著作多数。
バックナンバー