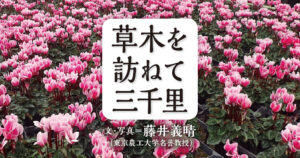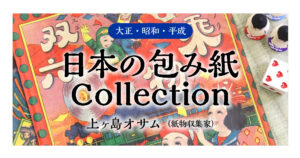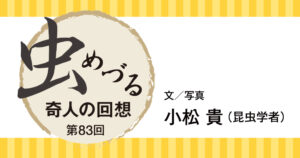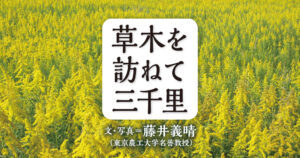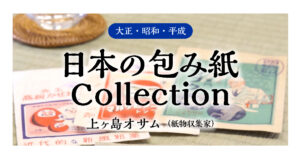第11回 日本人と月
あまたの星の中で、日本人がことさらに愛でた天体といえば、やはり月でしょう。
今年のお月見(中秋の名月)は10月6日。中秋とは旧暦の8月15日のことです。夏の時期の満月は空の低い場所を通りますが、秋から冬にかけては、南の空高くを通ります。
お月見の風習は中国から日本に伝わりました。秋の収穫を祝うお祭りに、月を眺める趣向が添えられたとされています。
奈良時代には貴族の間で月見の宴が催され、月の光の中で和歌を詠んだり楽器を演奏したりしていたそうです。江戸時代になるとお団子を供えるなど、地方によってさまざまな祭りが行われるようになりました。
「お月見どろぼう」もその一つで、長い棒の先に針金などをつけた道具を使って子どもたちがお供えのお月見団子を盗むという面白い行事です。小さな子どもが必死になってお団子を取ろうとする姿を思い浮かべると、なんだか楽しいですね。
現在でも、子どもたちが「お月見くださ~い」などと声をかけて近所の家をまわり、お菓子をもらう風習が残る地域があるそうです。おばけの恰好をした子どもが「Trick or Treat!」(お菓子をくれないといたずらしちゃうぞ)と言って家々を巡る外国のお祭り「ハロウィン」と似ていますね。
中秋の名月を過ぎると、次に「後[のち]の月」の祭りがあります。
後の月は旧暦9月13日に月を眺める行事で、今年は11月2日。栗や豆を供えることから「栗名月」や「豆名月」と呼ばれます。
日本人は古くから、月に特別な思いを寄せてきました。そのことは、月が数多くの物語や和歌、俳句、絵画、音楽などに登場したことからも分かります。最近では人気アニメのキャラクターの名前にもなっています。「月」がつく名前の神社は、なんと80以上もあるそうです。
私自身も月を眺めるのは大好きです。気持ちが落ち込んだときに月の光に慰められることが何度もありました。ときにやわらかく、ときに煌々と輝くその光に照らされていると、心がす~っと落ち着くのです。皆さんも月を見てそんな気持ちになったことはありませんか。
でも、もしかしたら未来の人々は、月を見て少し違う思いを抱くようになるかもしれません。なぜなら、「人が月に住む時代」がそう遠くない将来に実現するかもしれないからです。
現在、月面での長期滞在を目指して月を探査する「アルテミス計画」が、国際協力体制で進められています。将来は、火星などの遠くの星に行くためのゲートウェイが月に建設され、月で生活する人も出てくるでしょう。
そのころには月旅行も当たり前になって、年末年始や夏休みなどの旅行シーズンには、地球から月を眺める「お月見」ではなく、月から地球を眺める「地球見」ツアーが人気になるかもしれません。
100年後の人々は、どのような想いで月を見上げるのでしょうか……。
今年の秋は、そんな未来を想い浮かべながら、お月見を楽しんでください。

写真提供=「旅する星空解説員」佐々木勇太

ながた・みえ コスモプラネタリウム渋谷チーフ解説員。東京・品川生まれ。東京理科大学理学部物理学科卒業。キャッチフレーズは「癒しの星空解説員」。2000年からNHKラジオ第一『子ども科学電話相談』の「天文・宇宙」の回答者を務める。ご自身の名がついた小惑星(11528)Mie がある。著書に『カリスマ解説員の楽しい星空入門』(ちくま新書、2017年)など、監修に『小学館の図鑑NEO まどあけずかん うちゅう』(小学館、2022年)、『季節をめぐる 星座のものがたり 春』(汐文社、2022年)などがある。 コスモプラネタリウム渋谷の公式ホームページはこちら
バックナンバー