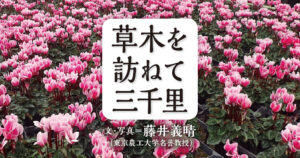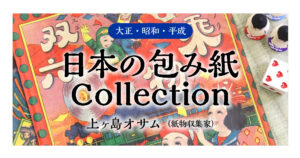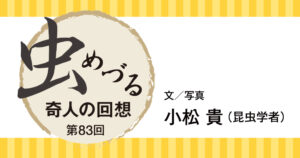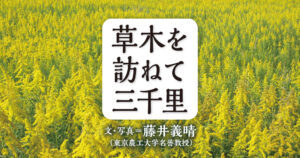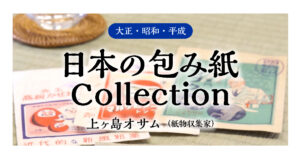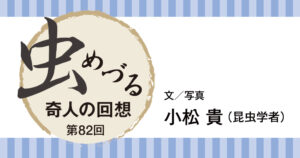第13回 クリスマス、西の空に十字架が立つ
街にクリスマスの飾りが目立つ時期になりました。
クリスマスのかわいらしいオーナメントを見ると、毎年のことながら心が躍ります。
クリスマスツリーの上に飾られている星を「ベツレヘムの星」と言いますが、この由来をご存じでしょうか?
聖書には、イエス・キリストが誕生したとき、東方にいた3人の博士をパレスチナの街ベツレヘムまで導いた星がベツレヘムの星と記されています。
カスパール、メルキオール、バルタザールの3人の博士は西の空にひときわ輝く星を見つけ、その星に向かって旅をしました。
途中ユダヤの支配者であったヘロデ王に会います。
やがてベツレヘムにたどり着いた3人の博士は、馬小屋で幼子イエスに贈り物をし、誕生を祝いました。
ところが自分の立場を危うくするユダヤの王が生まれたことに不安をおぼえたヘロデ王は、2歳以下の男の子を皆殺しにしてしまいます。
ヨセフとマリアはイエスを連れてエジプトに脱出し、ヘロデ王から逃れることができました。
さて、このベツレヘムの星とはいったいどの星だったのでしょう?
過去多くの天文学者がさまざまな説を唱えました。
その中に、有名な天文学者で太陽系の惑星の運動を発見したヨハネス・ケプラーがいました。
ケプラーは惑星の位置関係を計算し、惑星の会合説を唱えました。惑星の会合とは惑星が近づいて見える現象です。
計算すると、紀元前7年の6月から12月にかけて、木星と土星が、うお座で3回も近づいたことがわかりました。ケプラーはこれがベツレヘムの星だったのではないかと考えました。
しかし惑星同士が近づいても、西空でどの星よりも明るく輝いて見えたという点では説としては弱い気がします。
他にも彗星ではないか? 超新星では? などといろいろな説がありますが、未だに謎のまま。
たまには、そんな遠い過去に想いを馳せながら夜空を眺めるのもいいのではないでしょうか。
12月は日没後の西空に大きな十字架が立つように見える星並びがあります。
はくちょう座の北十字星です。
夏の間、天高く見えていたはくちょう座は、12月になると西空に傾き、まさにクリスマスの夜には宵空に大きな十字架の星が立つように見えるのです。
これをクリスマスの星と呼んでいます。
こちらはお天気がよければ、クリスマスの夜でなくとも見えますので、西の低い空が見渡せる場所にいるときには、夜空の十字架を探してみてください。
星の十字架はイエス・キリストが生きたころにも輝いていた十字架ですし、ヨハネス・ケプラーも見ていただろう十字架です。
星は時代を超え、変わらず私たちに無限の想像力を与えてくれるものですね。

写真提供=「旅する星空解説員」佐々木勇太

ながた・みえ コスモプラネタリウム渋谷チーフ解説員。東京・品川生まれ。東京理科大学理学部物理学科卒業。キャッチフレーズは「癒しの星空解説員」。2000年からNHKラジオ第一『子ども科学電話相談』の「天文・宇宙」の回答者を務める。ご自身の名がついた小惑星(11528)Mie がある。著書に『カリスマ解説員の楽しい星空入門』(ちくま新書、2017年)など、監修に『小学館の図鑑NEO まどあけずかん うちゅう』(小学館、2022年)、『季節をめぐる 星座のものがたり 春』(汐文社、2022年)などがある。 コスモプラネタリウム渋谷の公式ホームページはこちら
バックナンバー