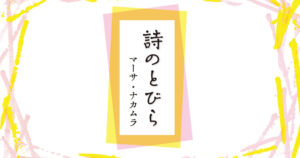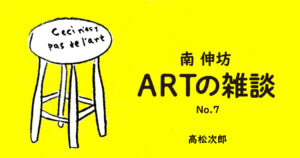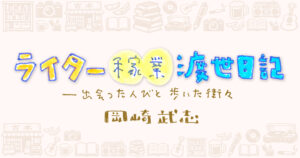第5回 サメ愛や活動について語り合う場を作る
実は過去に、母校である東海大学の海洋科学博物館から出入り禁止、いわゆる「出禁」を食らったことがある。
2012年の夏だったろうか。私が企画した人生初のサメ実習イベントだった。サメの頭から顎を切り出し、顎の乾燥標本を作るという内容で、東海大学海洋科学博物館の講義室を借用し、インターネットで事前申し込みを受けた20名を対象に行った。
解剖を伴うサメの実習を開催する場合、いくつかのハードルがある。魚体の大きいサメを取り扱うには、搬入、冷凍、搬出、処理に関わるコストがかかる。さらに、気温が高くなる夏場であれば、鮮度が悪くなるため、サメからは独特のアンモニア臭が放たれる。
その日、私は初めてのイベントということもあって、張り切っていた。サメの頭をデモンストレーション用に5個、参加者用に20個の合計25個を発注していた。配送業者によって、博物館に冷凍のサメの頭が届いたときに驚いた。宮城県気仙沼で水揚げされたサメが想像よりも大きいものだったからだ。
頭だけでひとつ約8kgほど。つまり、合計200kgの冷凍のサメの準備を、スタッフ1名(つまり小柄の女性である私のみ)で切り盛りすることになった。重機を使うことができない私は時間をかけて何往復もしてサメを運んだ。
また、イベント開始時間に合わせて、サメをいい塩梅に解凍しなければならないのだが、このいい塩梅というのが難しい。ベストの状態は、サメに包丁が入る程度の半凍り状態にしてお客様に提供すること。解凍し過ぎると腐敗してしまうのでダメ、解凍しなさすぎても硬くて包丁が入らないからダメなのだ。
イベント前日は雨が降り、夏にもかかわらず、気温がグッと下がった。解凍が間に合わないと実習ができないので、予定より6時間ほど早めて、前日の夕方から流水解凍をすることにした。しかし、悲劇が起きた。翌日はうってかわってのピーカン晴れとなり、サメたちを沈めた解凍用プールに灼熱の太陽が降り注いでいたのだ。当日の早朝に完全解凍してしまったサメの頭の周りには、大量のハエが乱舞していた。
実習会場である東海大学海洋科学博物館の講義室というのは、一枚のドアを隔てて、シロワニのいる大水槽やウツボのいる展示コーナーに繋がる。ドアの隙間から漏れ出た、鮮度落ちしたサメの臭気が一般のお客様へ届き、クレームの嵐になったのは言うまでもない。
― 関係者各位 ―
その節はご迷惑をお掛けしてしまい、申し訳ありませんでした。
サメ界のトキワ荘を目指す
連載の第2回でも触れたが、「サメサメ会議」というイベントを主催している。どんなイベントかを一言で説明することが難しいと思っていたが、AIが簡潔にまとめてくれていた。なんとも便利な時代になったものである。
「サメサメ会議」は、全国のサメ好きが集まり、互いのサメ愛や活動について語り合ったり、有識者の講演を聞いたり、オリジナルグッズを販売したりできる交流の場で、例年、サメ好きの子供たちによる自由研究発表や、専門家による特別講演などが行われています。
具体的な情報をお探しの場合は、主催者であるシャークジャーナリストの沼口麻子氏の関連情報や、サメ関連のコミュニティなどで情報を探すのが良いかもしれません。
(AI検索結果より一部抜粋)
サメサメ会議は2018年から毎年開催しているが、企画した目的は「サメにかんする情報共有の場を作ること」だった。今や誰でもネットにアクセスできるが、ネット上に流布される情報に惑わされることなく、一次情報をキャッチアップしやすい環境を作っておくことがこれからの時代に大切になってくると考えたからだ。一次情報とは、研究者本人から直接話を聞くことや、本物のサメの生体や標本を扱うことなど実際に自分が体験したことを指す。
また、自分の活動をアピールする場も設けている。その際、有識者からのフィードバックを行うことをルールにしている。たとえば査読のない論文のように、ときに内容の誤りや非科学的な内容が含まれている場合があるからだ。2025年11月2日に開催されたサメサメ会議2025シンポジウムでは約60名の参加者があった。最年少のプレゼンターは5歳。サメサメ会議は未就学児から参加できる小さなサメ学会のような雰囲気となった。

私にはやりたいことがもう一つある。それは継続的なサメの学習環境の構築である。日常的にサメを学べる環境を実現するためには、サメ学習専門の施設があればいいのではと考えた。幸いなことに、サメの水揚げ日本一の気仙沼がある宮城県内に、空き家になっていた私の母方の実家がある。町医者をやっていた祖父が残した廃病院だ。そのスペースをサメ学習施設として生まれ変わらせることにした。
施設の名称は、サメが大好きな人で作り上げるという意味と、サメサメ倶楽部やサメサメ会議に参加してくれるみんなで作り上げるという意味を込めて「サメサメ・サメ博物館」に決めた。施設の計画は以下のとおりだ。展示物に関しては、東海大学名誉教授の田中彰博士らより標本を寄贈していただいた。また、今後はサメ用の冷凍庫なども準備して、標本の製作も積極的に行う。施設が専用の物件であれば、周囲に迷惑をかけることもないはずだ。
病院の待合室:サメも売っている鮮魚販売コーナー
病院受付:サメ図書コーナー
診療室:サメ実習やワークショップなどの体験コーナー
レントゲン室:常設のサメ展示コーナー
「サメサメ・サメ博物館」の構想としては、サメ界の「トキワ荘」を目指す。将来的には宿泊もできるようなサメ好きの若者が集える環境を作りたい。世界で活躍するあのサメ研究者も、あの人気水族館スタッフも、敏腕のサメの標本師も、何万人もフォロワーがいるサメYouTuberも、振り返れば「サメサメ・サメ博物館」で過ごした経験があったよね、と言われるような施設にしたい。
私は2011年からシャークジャーナリストとして、SNSやテレビなどのメディアを通じてサメの情報発信を続けてきた。大学時代にサメを学んだことがきっかけで、サメの魅力に開眼するとともに、世間一般でのサメのイメージがとても悪いことに心が痛くなり、正しいサメの情報発信の必要性を感じたからだ。
サメサメ会議2025シンポジウムの会場では「サメの未来を守るために」と書かれた大きな模造紙に〝子どもたち一人一人にできること〟が書かれたサメの未来カードが掲示されていた。
〝サメの現状について興味を持ってくれる人を増やす!〟
〝まずは知る&理解〟
〝他の人にもサメは思っているよりおくびょうなことを知ってもらいたいです〟
〝ぜつめつきぐしゅのサメについてしり、まわりに知らせる〟
今、海の中から急激なスピードで魚が消えているという。2050年には魚よりも海洋プラスチックゴミの量が上回るとの予測もある。高次捕食者のサメが減ってしまえば、海の生態系のバランスはガラガラと音を立てて崩れていくかもしれない。
子どもたちをはじめ、多くの人がサメの正しい情報を伝えていく。そして、それを知った人がまた行動する。そんな連鎖が起きる場面を想像するだけで、ワクワクが止まらない。
私設の「サメサメ・サメ博物館」を作ること。大学や研究機関に属さないフリーランスである私の一世一代の大勝負が始まる。
今日も今日とてサメ日和。よろシャーク。
廃病院が変身!
泊まれる「サメサメ・サメ博物館」プロジェクト
※詳細が決まり次第、お知らせします。

ぬまぐち・あさこ 1980年生まれ。東海大学海洋学部を卒業後、
バックナンバー