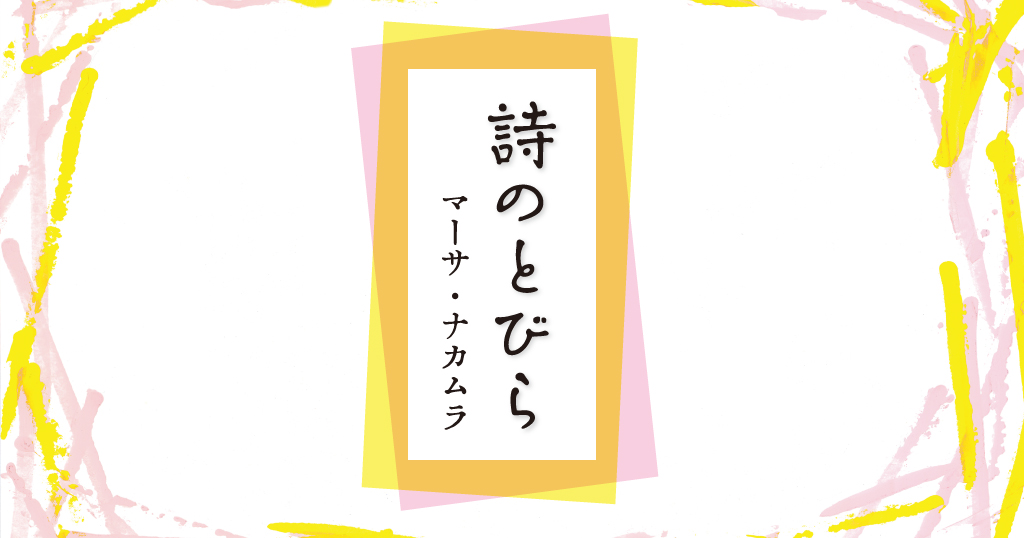第11回 自分の姿によろこぶ —まど・みちお「くまさん」をめぐって—
夜、詩を読む代わりに、絵本を手に取ることがある。
何冊か絵本を持っているけれど、詩集とはちがって、黙読はしない。
かならず、声にだして読む。詩は朗読を前提としないけれど、絵本は、基本的に読み聞かせを前提とした文学の形であると思うからだ。
このことを、わたしは絵本の出版社にいる編集者の方から教わった。その方は、絵本を紹介するときにはかならず、読み聞かせをするように、文を声にだして読み上げる。わたしは文字の読めないこどもではないけれど、ものを食べるときにはきちんと噛まなければならないように、絵本を消化するならば、読み聞かせという咀嚼を経なければならないような気がする。
絵本は、詩に似ているところがある。それは、不要な言葉を、なるべく削ぎ落とそうとする作者の意図が働いているからだと思う。絵本はなるべく、文字が少ないほうがいい。ときどき、まるで小説のように文字の多い絵本に行き当たることがあるけれど、あんまり文字が多いと、読み聞かせの息が続かない。長く愛読され続けている絵本のことばは、さっぱりとしたものが多いような気がする。
絵本を声に出して読むとき、不思議と、初見であっても、あまりつっかえないで読める。登場人物の声に行き当たった時には、無意識に、声に素朴な感情がこもる。朗読のやり方を誰かから教わったことはなく、学校で、教科書を音読したくらいの経験値しかない。けれども、教科書を音読するように読みあげているというよりは、ほとんど歌う意識に近い。散文を、繰り返し繰り返し声に出して読むことはあまりないものだと思うけれど、好きな歌は、誰もが繰り返し繰り返し口ずさんでしまうものだ。詩が「うた」ならば、絵本もまた「うた」なのかもしれない。絵本も、詩も、何遍声に出して読んでも飽きがこない。
詩集も絵本も、夜に読むことが多いから、ベッド脇の小さなテーブルの上には、お気に入りの絵本が幾冊も積み重なっている。
私が最近、毎日のように読んでいるのは、『くまさん』(こぐま社)という絵本。良い絵本だなと、内容に惹かれて購入したのだけれど、これはまど・みちおの詩を絵本化したものだった。
はるが きて
めが さめて
くまさん ぼんやり かんがえた
さいているのは たんぽぽだが
ええと ぼくは だれだっけ
だれだっけ
まど・みちお「くまさん」(下部に全文掲載)
絵本を選ぶとき、やはり絵の印象は重要だ。この絵本に描かれているのが、人の言葉を操り、毎日風呂に入っていそうな熊ではなく、獣のにおいを全身にまとった、人の言葉が通じなさそうな熊であることも、わたしがこの絵本を気に入った理由の一つだ。
冬眠から目覚めたばかりの熊の親子が、大木の根元にあいた洞穴から顔を出している。頭も目もぼんやりとした状態で、周囲を見回し、洞穴から抜け出て、まず目についた「たんぽぽ」のにおいを嗅いでいる。
まど・みちお作詞の童謡「ぞうさん」と同じく、この「くまさん」という詩にも、実はメロディがついていて、童謡としても知られている。ソプラノの声ではなくて、地声で歌いたくなる曲調で、読んでいるうちに、自分の声が、詩と歌のはざまをさまようのを感じる。
先にあげたのは「くまさん」の一番で、二番まである。二番は次のように続く。
はるが きて
めが さめて
くまさん ぼんやり かわに きた
みずに うつった いいかお みて
そうだ ぼくは くまだった
よかったな
「よかったな」のところで思わず「ふふ」と笑ってしまう。五歳のこどもに、この絵本を読んであげると、やはり「よかったな」のところで、大笑いした。見ると、この絵本の最後に描かれている熊のような顔で笑っている。
お金持ちだからとか、美人だからとか、そういった喜ばしい根拠もなにもなく、ただ自分であることを「よかったな」と無条件に喜んでしまうことが、五歳のこどもにとっても、冗談のように感じられて面白かったのだと思う。
我が家の昔のホームビデオで、七五三のとき、わたしが手鏡を覗き込んで、「うん、美人」と言うシーンがあって、今でも苦々しく思いだすことがある。このとき、わたしは女優の誰々に似ているとか、うまくヘアメイクが仕上がっているとか、そういう基準と照らし合わせて自分を「美人」と判断したのではなく、この「くまさん」の熊のように、ただ鏡に映った自分の顔を見て、何の根拠もなく「美人」だと喜んでいたのだ。
今では、自分の姿を見て喜ぶことは本当に難しい。だから、「よかったな」のところに行き当たるたびに、七五三の頃の自分がよみがえってくる感じがする。その頃のわたしは、今のわたしを見ても、「うん、美人」ときっと言うはずだと思う。
先日近所の映画館で、アニメ『赤毛のアン』がリバイバル上映されていた。主人公のアン・シャーリーが、養母となったマリラから、夜には神様にお祈りをするものだとたしなめられるシーンがあった。
聖書を手にしていなくても、夜に読み上げる言葉には、不思議と、祈りの思いがこめられるものだ。夜の言葉は、朝の言葉よりも重たい感じがする。知らず知らずのうちにこめられる、明日への祈りの思いが、夜の言葉の質量を重くしているのかもしれない。
わたしの「くまさん」を読む声も、そんな重さをもっている。熊も人も、誰もが、この世に生まれ落ちた自分の姿を見て「よかったな」と心から喜ぶことができる時間があればいい。そう祈りながら、夜に「くまさん」を読み続けている。
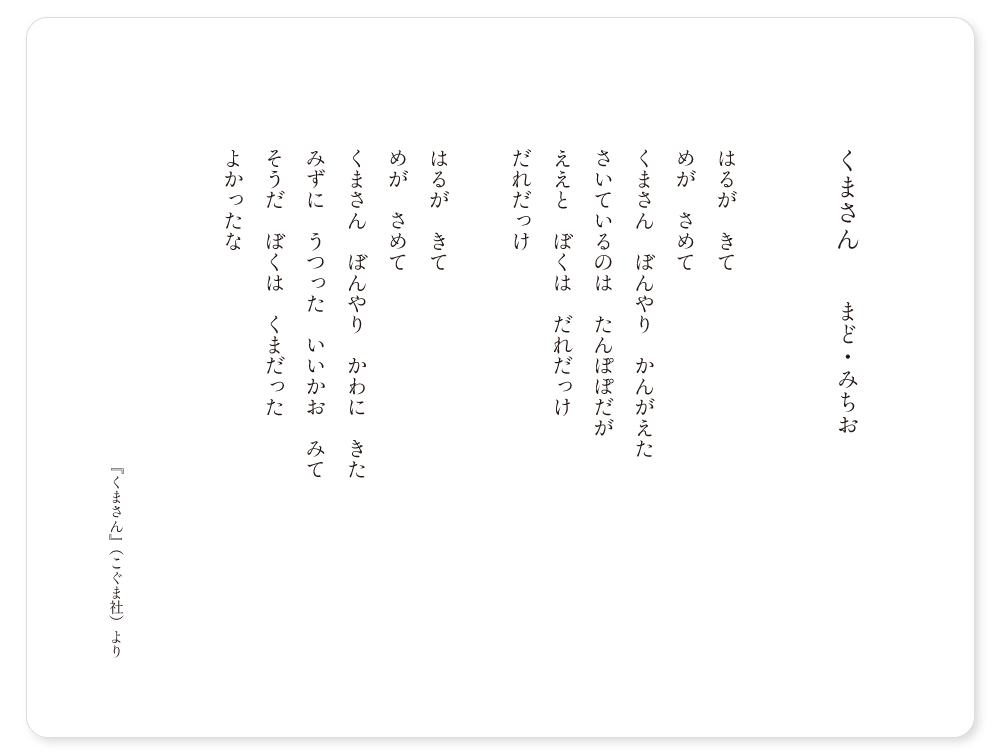
くまさん まど・みちお
はるが きて
めが さめて
くまさん ぼんやり かんがえた
さいているのは たんぽぽだが
ええと ぼくは だれだっけ
だれだっけ
はるが きて
めが さめて
くまさん ぼんやり かわに きた
みずに うつった いいかお みて
そうだ ぼくは くまだった
よかったな
「投稿の広場」はこちら

1990年埼玉県生まれ。詩人。第五十四回現代詩手帖賞受賞。『狸の匣』(思潮社)で第二十三回中原中也賞、『雨をよぶ灯台』(思潮社)で第二十八回萩原朔太郎賞受賞。