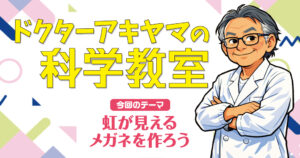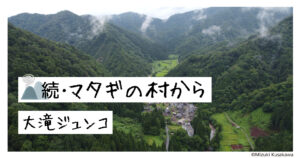第14回 春の日に
三年生の娘のクラスには、娘をふくめて二十九人の子どもたちがいる。当たり前だが、彼らは顔も違えば、性格も違う。が、服装はどことなく似ている。手軽に買える子ども服のブランドが限られていて、その決して多くない選択肢のなかから、ユニクロやAmazon経由のブランドを選ぶ親が多いからだ。たぶん。
ユニクロで買った服を着せると、かなりの確率で「学校で同じ服を着てる子がいた」と息子も娘もいう。そりゃそうだよな、と思うが、背に腹は代えられない。
娘は今年、ずっと伸ばしていた髪を短く切った。親バカで申し訳ないが、とてもよく似合っているし、何度見ても、かわいいなと思う。
実際、学校に行くと、クラスの女の子たちが寄ってきて、「髪きったの?」といい、「かわいい」といった。
ぼくも「かわいいよね」といったが、娘はぼくの腰辺りに顔を押し付けるだけでなにもいわない。が、校舎から一歩でも外に出ると、うれしそうな顔をし、「◯◯ちゃん、かわいいっていってくれたよね?」と話をふると、満面の笑みで「うん」という。
娘はみんなのことをよく見ていて、家のなかでは、◯◯くんが授業中にタブレットを見ていたとか、◯◯ちゃんが◯◯くんの話にすごいウケていたなどというが、教室のなかではほとんど口を開かない。
が、ぼくがクラスメートたちと話していると、ときどき、ぼくの頭をパチンと叩いたりして、彼らを笑わせようと試みる。
「痛いって、バカ、やめろよ」
そんなふうに注意すると、すごくうれしそうな顔で笑う。
ぼくはそんなふうにしか同級生とコミュニケーションをとることができない娘を幼いと感じるが、一方で、彼女がニコニコと笑ってくれているだけで幸せを感じる。
娘が生まれてきてよかった、というよりも、自分が生まれてきてよかったぐらいの幸福を感じる。
週に一日ぐらいだけれど。
毎日学校に行き、娘の授業に付き添っている、というと、ほとんどのひとは「たいへんですね」という。
仕事のできる時間が減った、という意味ではたしかにたいへんだ。でも、ぼくは本来仕事をしているはずの時間をつかって、娘といっしょに国語や算数を学び直していて、遠足や社会科見学にもいっしょに行っている。ぼくは娘だけでなく、二十九人のクラスメートたちみんなと話をし、彼らの言葉に耳を傾ける。そのことで、ぼくは仕事では決して経験できないであろうことを経験している。
それはたぶん、子どもの目をとおして、社会を見るということであり、小学校三年生のころの自分にもどって、身近な景色を見つめ直すということである。
こんなこと、ほかではできない。
ぼくは娘に感謝したいくらいだ。
四月の遠足では学校から三キロちょっと離れた大きな公園に行った。ぼくは娘とふたりで列のなかに入り、ぼくたちの前に歩く男の子と道中ずっと、『ゼルダの伝説 ティアーズ・オブ・ザ・キングダム』の話をした。
彼はすでにゲームをクリアしており、ぼくは彼の冒険譚にあきれるくらいに、「マジで?」と同じ言葉を繰り返した。娘も男の子の話に耳を傾けていたようだが、あんまりにもぼくが根掘り葉掘り聞くので、途中で飽きていたようだった。
お昼は芝生にレジャーシートを敷いて、子どもたちといっしょにお弁当を食べた。その姿を同行のカメラマンがパシャパシャ撮った。そのあとの遊びの時間でもぼくを何枚か撮ってくれたので、「ありがとうございます」と礼をいうと、「先生もずっと子どもたちと遊ばれて、たいへんですよね」というので、「いや、先生じゃなくて、この子の親なんです」と娘を指さした。すると、相手は心底おどろいたというような顔をした。よほど、遠足の集団のなかに馴染んでいたか、あるいは、ぼくが先生のような眼差しで娘や彼女のクラスメートたちを見つめていたからかもしれない。
夏のような暑い春の日に、ぼくは娘たちといっしょに芝生の斜面のいちばん高いところから、寝転がったままゴロゴロと転がり落ちる遊びをし、落ちている木の枝の樹皮を剝いてだれがいちばん枝の芯をピカピカに磨き上げるかという遊びをした。
そのあいだ、娘はずっとニコニコと笑っていた。
(続く)

しまだ・じゅんいちろう 1976年、高知県生まれ。東京育ち。日本大学商学部会計学科卒業。アルバイトや派遣社員をしながらヨーロッパとアフリカを旅する。小説家を目指していたが挫折。2009年9月、夏葉社起業。著書に『父と子の絆』(アルテスパブリッシング)、『長い読書』(みすず書房)などがある。
バックナンバー