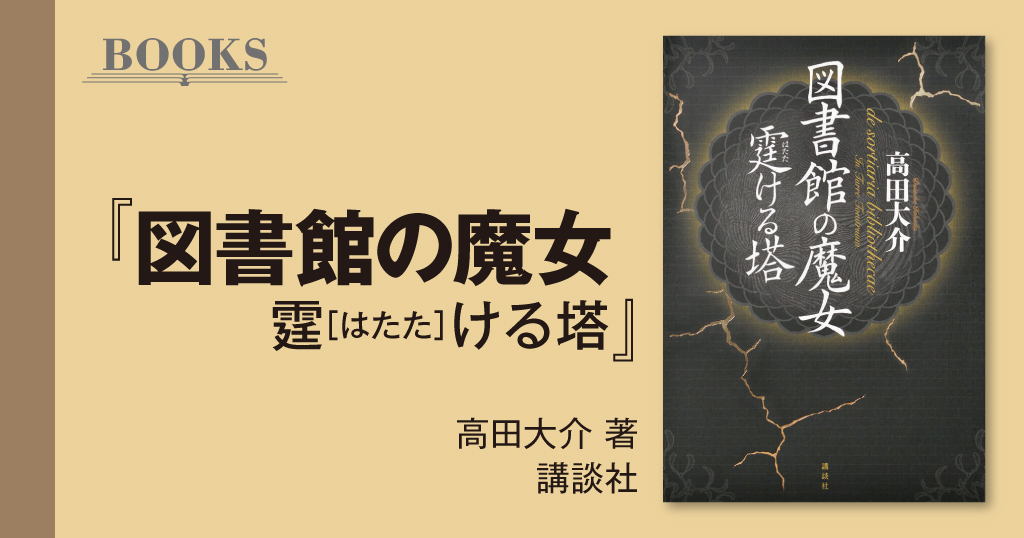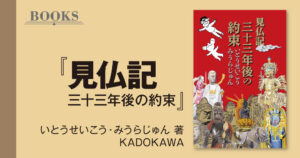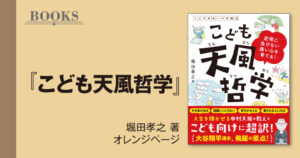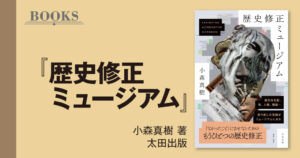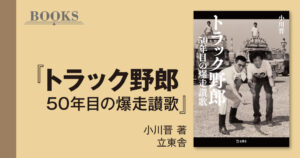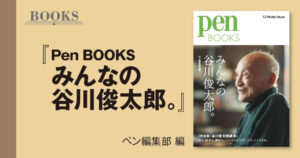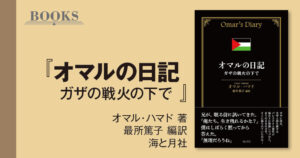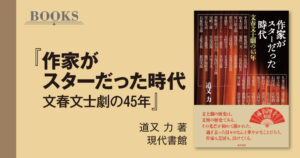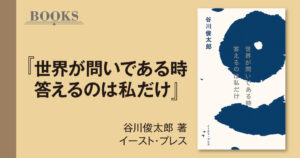モデルとなった国に思いをめぐらすのも楽しい
『図書館の魔女』『図書館の魔女 烏の伝言』『図書館の魔女 高い塔の童心』に続くシリーズ第四作。『烏の伝言』『高い塔の童心』が外伝とも見える物語だったので、実質この『霆[はたた]ける塔』が第一作の続きとなるだろうか。
古代の西方帝国の末裔で、島々に囲まれた東大陸南部に座する大国、一ノ谷。そこには古くから世界各地の書物を集めた図書館、高い塔がある。長は代々、図書館の魔法使いと呼ばれ、あらゆる知識を持つと言われてきた。そのことは国外にも知られて敬われ、ときには恐れられている。
今の高い塔の長は図書館の魔女と呼ばれるマツリカ。まだ十代の少女だ。図書館の魔女は魔法を使わない。膨大な知識と記憶力、そして鋭い推理でもって、政治的な謀略を見通す。そして、マツリカの左右の手というべき司書の女性二人、独自の情報網で国内外の情報を収集するハルカゼと、軍師として戦いの趨勢を予想するキリン。この三人が高い塔を動かしている。要するに高い塔は、図書館と言えども、役割は本の貸出でも文献研究でもない。実際は、一ノ谷の国政に助言し、ときには国政を動かすこともできる情報戦略機関だ。書物はその重大な情報源。
一ノ谷と対立する大国ニザマは、東方から来た民族が西大陸北部を征服した、緻密な官僚制からなる帝国。皇帝が統治しているが官僚たちに実務を握られていて、皇帝派と官僚派が対立している。宰相ミツクビが官僚たちの頂点。ミツクビ——三つ頭があると言われるほど知力と策略に長けた強者。一ノ谷の属領や周辺国をあおり、一ノ谷が戦役によって疲弊していくのを狙っていた。
前作の『図書館の魔女』で、マツリカが皇帝への援助と一ノ谷と対立する周辺国と戦の芽を摘み取ることを申し出て、皇帝派と一ノ谷で和議が結ばれた。さらに皇帝は、反対する官僚たちに公職からの追放命令を発し、そして官僚の専横を招いたのは自分の罪である、と退位を宣言した。これでニザマの官僚組織は崩れはじめた。ニザマ宰相だったミツクビにしたら、マツリカは、自国と自分の地位を崩した憎い敵だ。
マツリカは、ニザマ皇帝の後継、皇太子がある所にいるらしいとの話を聞き、好奇心を抑えられず、西大陸の古寺院にまで赴いた。が、ニザマのミツクビの手のものに捕まり、どこともしれない深い山中の砦に閉じ込められてしまった。そこは毎夜ずっと、激しい落雷にさらされている塔。「霆[はたた]ける塔」の「霆[はたた]く」とは、古語で雷鳴、雷が激しく鳴り響くという意味。逃げ出すにも救出するにも落雷で命を落としかねない。
ハルカゼ、キリンほか高い塔の衛兵たちは、マツリカが捕まった現場を細かく捜査。掠っていった連中はニザマ兵ではなく、西方の山に住む狩猟騎馬民だとつきとめた。ニザマ官僚に雇われたのだろう。充分な装備を持っていなかったことから、マツリカを連れて行ったのは近くだとわかった。ニザマ領内に古代の西方帝国が作った砦があるが、マツリカが捕らわれていそうな所は地図にない。折しも冬の山奥で、捜索は難航する。一方、囚われ人のマツリカにも生命の危機がせまってくる。
このシリーズはファンタジーというよりも架空歴史に近いように思える。著者の専攻は言語学。高い塔のマツリカほか司書たちが文献を解読する場面に、言語学者の視点が表れている。それに都市の構造や建物の造り、さらに気象や植生までもくわしく解説されている。そして、歴史に興味がある人には、一ノ谷はこの国、ニザマはこの国、古代の西方帝国は……、とモデルになった実在の国を考えはじめると止まらないだろう。
マツリカたちのように、図書館の情報が戦争を止められるならいいのに、と本当に思う。
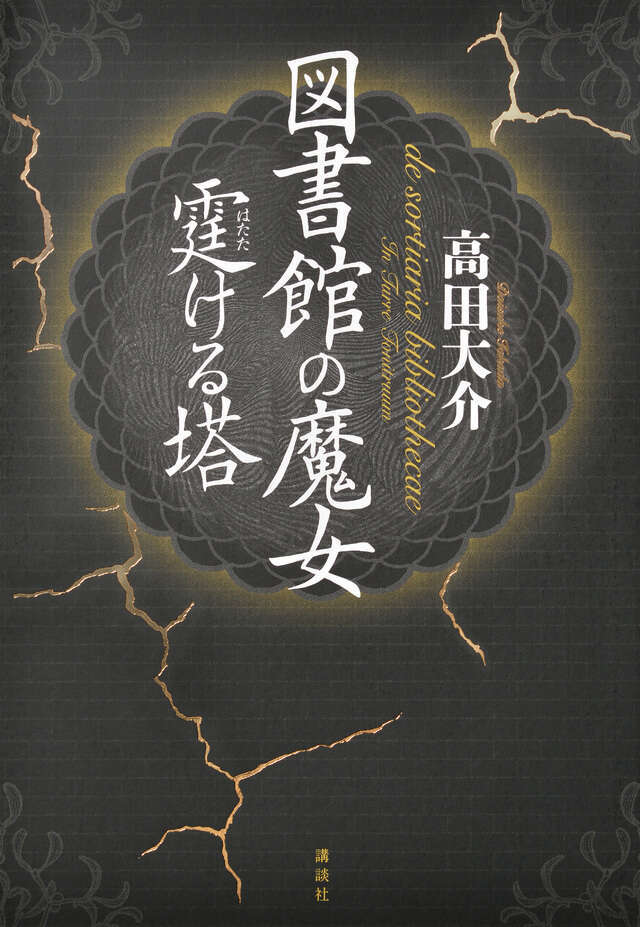
たかだ・だいすけ 1968年東京都生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。早大、東京藝大などで講師を務めたのち渡仏。専門分野は印欧語比較文法・対照言語学。『図書館の魔女』で第45 回メフィスト賞を受賞。他の著書に『図書館の魔女 烏の伝言』『図書館の魔女 高い塔の童心』などがある。

さわ・いずみ 1968年、神奈川県生まれ。東海大学大学院博士課程前期修了。専攻は中世アイスランド社会史。出版社勤務を経て司書。公共図書館・博物館図書室・学校図書館勤務のあと、現在介護休業中。アイスランドに行きたい毎日。写真は、今は亡き愛犬クリス。
バックナンバー