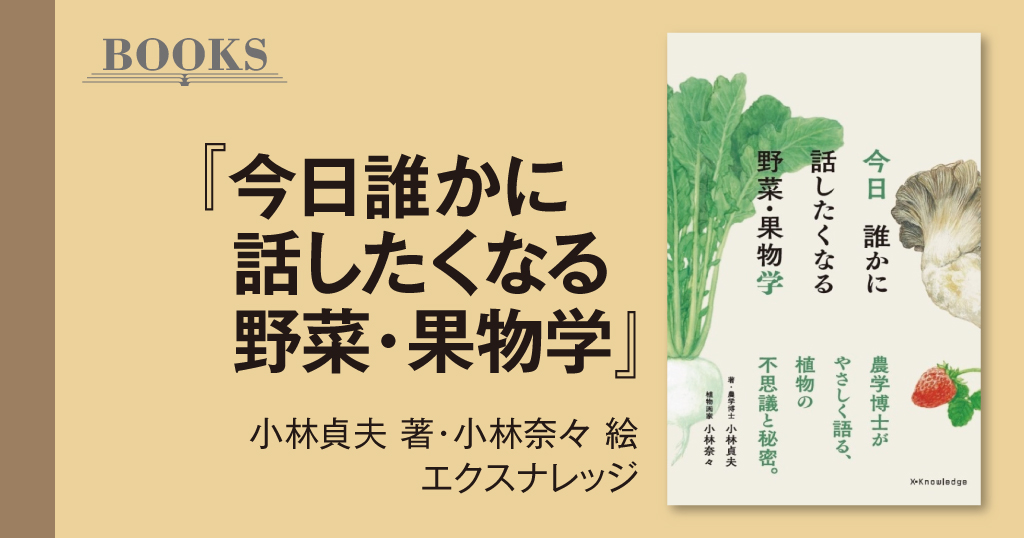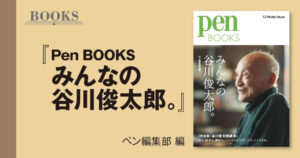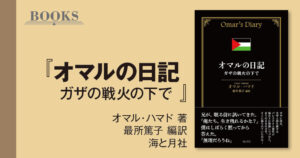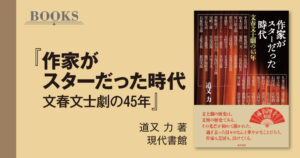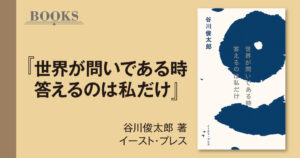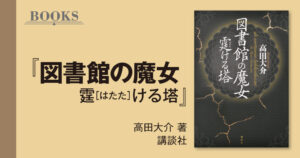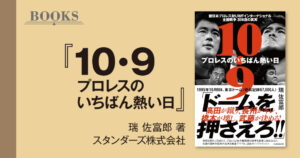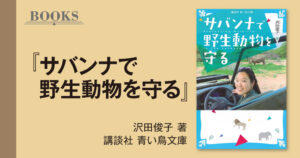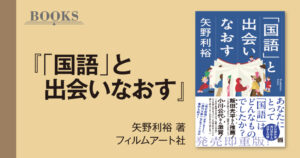それはなぜ誕生し、私たちの口に入るようになったのか?
私たちが日ごろよく目にする草花、日々何げなく口にしている野菜や果物にも、思いがけない性質や背景があることに気づかせてくれる植物エッセイだ。読者がイメージをつかみやすいよう図版が多用され、ゆったりとした落ち着きのある紙面に仕上がっている。ボタニカルアート調の挿絵も美しい。
第1章では、京都の聖護院かぶや鹿児島の桜島大根、熊本の晩白柚、福岡のあまおうイチゴ、重さ1キロを超える青森のリンゴ「世界一」など、大きさで知られる日本の作物がいくつも並ぶ。さらに、合計473本もの実がついた130キロもあるカナリア諸島のバナナの房(通常は20~30キロ)、長さが通常の10倍・重さ70倍にもなる巨大エリンギ、1粒の種子から育てた1本のトマトから26万762個もの実が採れた北海道の水耕トマトなど、度肝をぬかれるような記述もある。
重要なのはそれらが単にめずらしいデータとしてだけでなく、植物のもつ特性やその歴史、誕生の経緯などとともに語られる点にある。バナナは木ではなく草であるため、茎は太くても草刈り鎌でバッサリ倒せてしまうこと。ザボンの一品種・晩白柚が世界最大の柑橘といわれるようになったのは、農業視察のため東南アジアを訪れた台湾総督府の農業技師が船内の食事に出たザボンを気に入って、ベトナムの植物園から苗木を分けてもらったのがきっかけだったこと。巨大エリンギが誕生したのは、栽培時の光の量を間違えて多くしてしまったからなど、いずれも専門家ならではの視点が感じられるエピソードだ。
第3章「『科』を見分ければ植物がわかる」の、400以上ある科から厳選した10科の特徴と主な植物、第5章で扱う身近な毒草にも意外な発見がある。第2章で紹介される植物同士、あるいは他の生きものとのコミュニケーション能力については、ただ驚異というほかはない。植物がにおいや音までも感じ取り、危険に備えて準備をしているとは……。
けれど第4章「人とともに進化を続ける新品種」こそ、本書の真骨頂といえるだろう。新品種を作ること=品種改良または育種について、本書では1)突然変異したものを探す、2)偶発実生(ぐうはつみしょう。人が意図的に交配したのではなく、偶然生まれたもの)を見つける、3)交配する、4)その他の方法、の4つに分けて詳しく解説していく。
新品種がどうやってできるのか、それは読めば読むほど興味深い。私たちがふだん当たり前のように食べている米や野菜、果物の多くは、突然変異の利用や偶発実生によって生み出された新品種に由来する。公の研究機関や種苗会社だけでなく、農家や一般の愛好家の人々が作った新品種も多いという。個人育種家による新品種の2022年の登録件数割合は、果樹で43%、草花類42%、観賞樹ではじつに75%にものぼり、新品種作りが遠い夢物語ではないのだと思えてくる。
もともと、コロンビアで出版された子ども向けの図鑑の一部を、日本の読者向けに書き直したという本書。大部な原書とは異なる魅力にあふれているのは、著者の温かみのある文章と、ていねいに描かれた著者のお嬢さんの挿絵、それらを十全に生かした編集・デザインの妙によるところが大きい。どのページを開いても植物のもつ多様さと、人とのかかわりのなかで見せる変幻自在な能力に感嘆せずにはいられない。

小林貞夫[こばやし・さだお] 1953年千葉県生まれ。農学博士、植物病理学専攻。東京農工大学農学部植物防疫学科卒業。東京大学大学院農生物学研究科修士および博士課程修了。その後、理化学研究所、日本モンサント株式会社、日産化学株式会社を経て、2012年に国際協力機構(JICA)のシニアボランティアとしてコロンビア農業・畜産研究機構に派遣される。2014年、同機構で博士研究員として勤務し、植物ウイルスの同定、およびウイルスの防除方法を研究。現在は同研究所客員研究員。書籍3冊(スペイン語)を共著で出版。
小林奈々[こばやし・なな] 千葉県生まれ。多摩美術大学、日本画専攻を卒業。主に植物画(ボタニカルアート)と日本画を描き、屛風画、襖絵などの制作も行う。コロンビアで出版された書籍『Verduras y Frutas para Todos』挿絵を担当。絵画教室を主宰するほか、保育園や高校にて美術講師を務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)。
まつなが・ゆいこ 1967年東京都生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。千代田区・文京区界隈の中小出版社で週刊美術雑誌、語学書、人文書等の編集部勤務を経て、 2013年より論創社編集長。