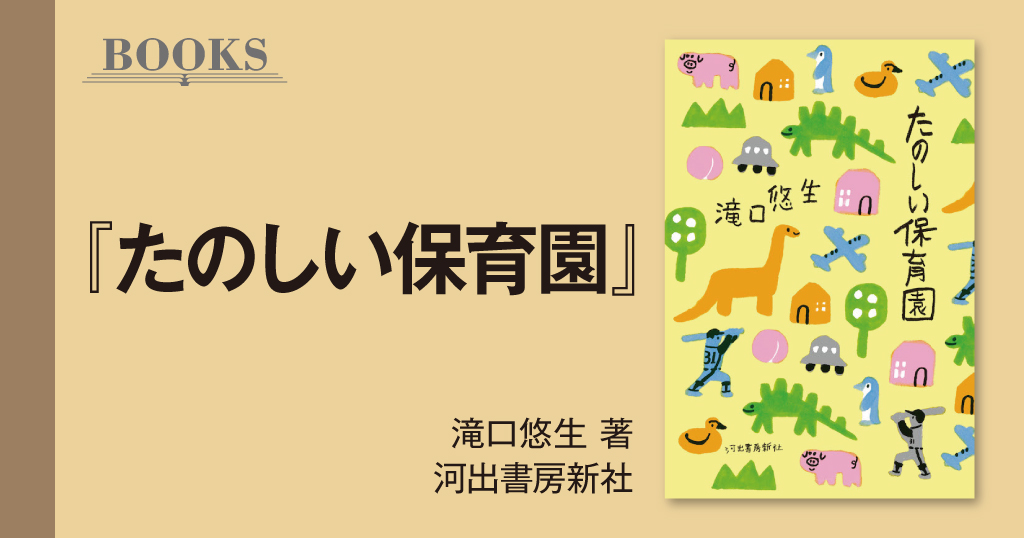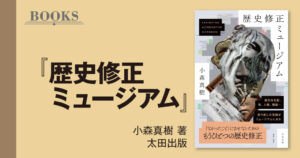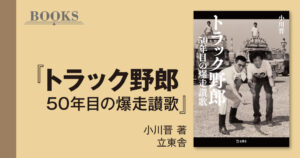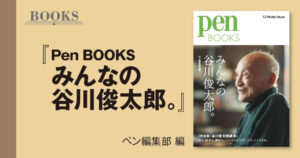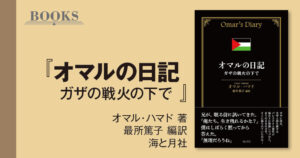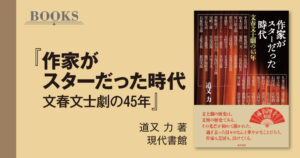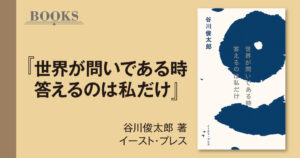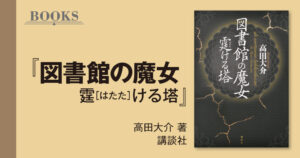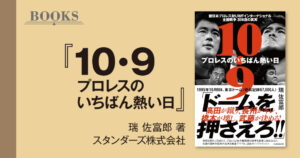〝子をめぐる記録〟をめぐる記録
保育園児の「ももちゃん」と、文筆業を営む父親との日々が、当人たち、母親、保育士、パパ友、近所の人など、いくつかの視点から記録される連作短篇小説である。もう少し言い足せば、父親が日々を記録しようとする様子を、未来にいる、父親であるかのような誰かが記録している、とも捉えられるのだが、複雑な構造についてはさておき、まずもって本作は、〝子育てあるある小説〟として、大いに読みでがあった。
梅の実を拾ってポケットに入れがち。アバンギャルドな言い間違えをしがち。鼻の穴に鼻くそ残しがち。左右を反転させた鏡文字を書きがち。といった、幼児あるある的な描写に頬がゆるむ。ぐずる子を無理に抱っこしようとしてフィギュアスケートのペアみたいになる、みたいな絶妙な喩えに膝を打つ。
ももちゃんが〇歳で保育園に入園したのは、「感染症の流行真っ只中」(おそらくは2021年)だった。よって、コロナ対策に取り組みながら、保護者や保育士が育児する姿も多々描かれている。当時、私の娘も保育園児だった。ので、あの頃はたしかに大変だったなあと、登場人物たちに戦友っぽい共感を覚えたし、もしかしたら感染源になるかもとおそれ、シャボン玉で遊ぶのを控えるくだりを読むにつけ、完全に忘れていたけれど私も同様のことを感じていたと思い出させてもらった。
ももちゃんの父親が感じる、哀しさや寂しさにも、つまされる。
保育園での引き渡しの際、友達の輪に入っていったももちゃんが、別れのあいさつをしても振り向いてくれない哀しさ(わかるなあ)。言葉が洗練されるほどに、言葉にできないような子どもの文脈が失われていく寂しさ(これもわかる)。抱っこしたときの、昔の軽さの「思い出せなさ」(わかる)。ももちゃんのお友達「ふいちゃん」との何気ない会話が、自分が書き残しでもしなければ、世の中から忘れられてしまうのはさびしい(少しわかる気が)。だから、ふいちゃんとの細かなやりとりも、保育園の連絡帳アプリのコメント欄に書き残し、保育士さんに伝える(……ん?)。連絡帳を介しての保育園との連絡は三歳までゆえ、娘について書き伝える宛先が無くなりさびしい(まあね……)。だから、三歳を過ぎても、送信する予定のない長文コメントを書き続ける(ええっ!?)。
時にさびしさは、あるあるを越えて激化する。かくして、前述した複雑な構造の記録ができあがる。つまりはこの小説全体が、作中の時間よりも未来にいるももちゃんの父親により、宛先もはっきりせず綴られた、連絡コメントの束である、と読むことも可能な、入り組んだ叙述の記録が。
そのため読者はところどころで、じゃあこれを連絡されている自分は何なのだ、という気分になる。「私もできるだけ長くあなたに話しかけていたい」という一文に、「あなた」って、私(読者)のこと?と、ドキッとする。
あるいは未来のももちゃんが、読者になる可能性もある。そう想像し、未来のももちゃんになったつもりで読むと、〝子育てあるある〟の数々が、〝育てられあるある〟に反転するような、別個の味わいが漂ってくる。まわりの大人たちの抱く哀しさや寂しさ、「思い出せなさ」のなかで育てられたももちゃん。もう忘れてしまったけれど、はたまた自分も、そうだったのかもなあ、と遠い目になる。
複数の登場人物のあいだで視点が揺れ動き、読者の視点をもぐらつかす本作は、〝育てられ小説〟としても、いたって魅力的だった。
ちなみに、「もも」という名前をリンクして本作は、滝口の過去作『水平線』のラストとかすかにつながっている。また、矢野利裕『「国語」と出会いなおす』では、本作の一篇「恐竜」をもとに作られた国語の長文問題を、滝口本人に解いてもらうという面白い試みがなされている。ぜひ、併せ読んでみてほしい。
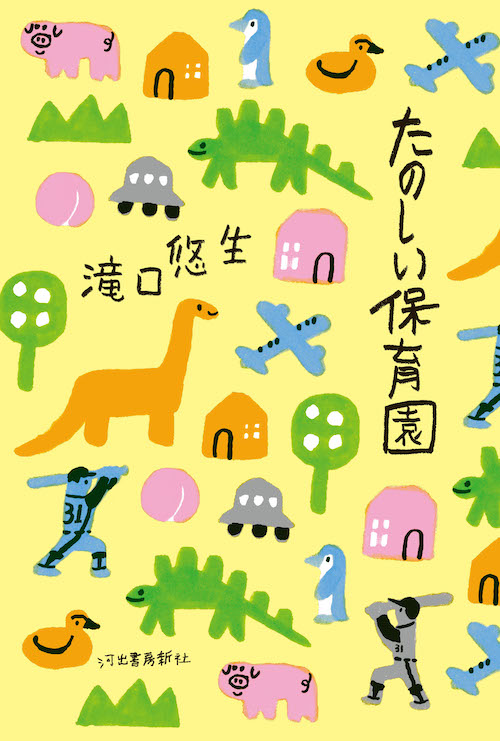

さとう・やすとも 1978年生まれ。名古屋大学卒業。文芸評論家。 2003年 、「『奇蹟』の一角」で第46回 群像新人文学賞評論部門受賞。その後、各誌に評論やエッセイを執筆。『月刊望星』にも多くの文学的エッセイを寄稿した。新刊紹介のレギュラー評者。
バックナンバー