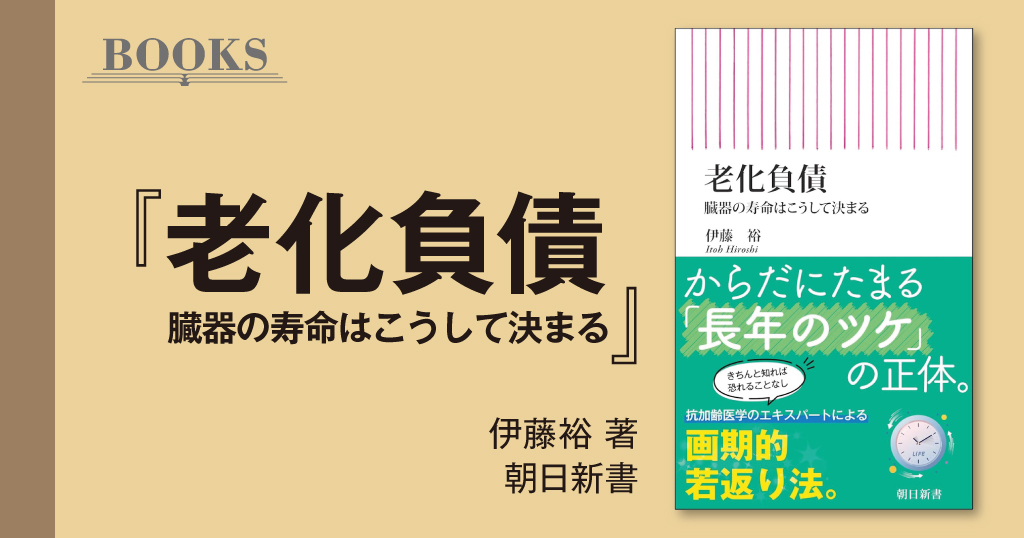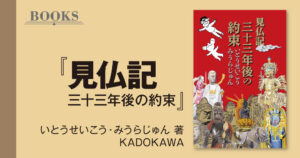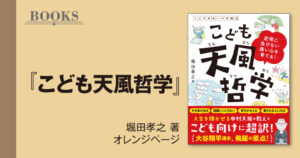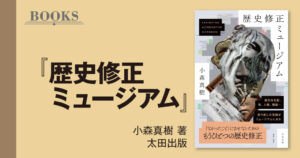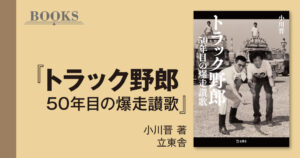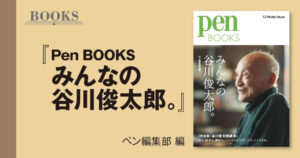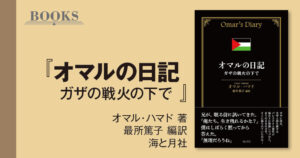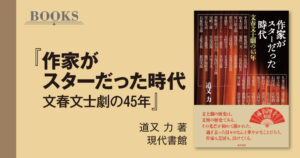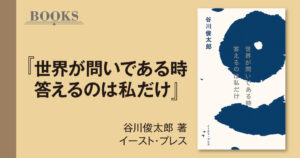なんと、臓器は若返る!
老化の原因を探り、健康長寿をめざす〝アンチエイジング〟医学。本書は日本抗加齢医学会の理事も務める内科医が臓器若返りの方法について語ったもので、老化をからだに溜まる負債=借金ととらえた点に最大の特徴がある。
誰しも加齢によって避けられない自然な老化現象はある。けれども同時に、老化は治療や予防が可能な病でもあり、コントロールできる可能性がある、という考え方がその根底にある。実際、人の寿命には遺伝的要因よりも、生活習慣や環境など後天的要因のほうが、はるかに大きな影響を及ぼすことが知られている。
さらに、私たちの体の変化の度合いには年齢的な大きな節目があることをつきとめた、海外の画期的な研究成果を紹介している点も重要だ。
25歳から75歳までのさまざまな人種・生活習慣をもつ健康な男女108人を対象にしたスタンフォード大の研究者らによる調査では、おおよそ44歳と60歳ごろが老化を決める二つの節目になることが示されたという。
それによると遺伝子、タンパク質、代謝産物、腸内・鼻腔・皮膚の細菌など、体のさまざまな種類の生体情報の変化が、これらの年齢前後に大きなピークを迎えることがわかった。私たちの体はゆるやかにではなく、あるとき大きく変化する。著者は〈この節目をいかに乗り越えていくかが、その人のその後の人生、老化を決めると考えられる〉と分析している。
第一の節目ではたとえばお酒に弱くなった、便秘気味、夜中に目が覚める、以前より風邪が治りにくくなった、などの変化が現れる。第二の節目では視力・聴力の衰え、つまずき、腰痛、皮膚のたるみ、怒りっぽくなったなど。これらすべてが「老化負債」である。
人は遺伝子の損傷と修復をくり返しながら生きている。老化負債の本体は、この遺伝子の傷を修復しようとした結果起こるエピゲノム変化(遺伝子の使われ方が変わる)の蓄積である。けれど実際に負債を抱えてしまったあとでも、返済すること、つまりエピゲノム年齢を逆戻しさせることは可能だと、本書では説明されている。
臓器を若返らせるための方法として伊藤医師が推奨するのが、カロリー制限やよいエピゲノム変化を起こす酵素を含む食物の摂取、レジスタンス運動などきつめの筋肉トレーニング、マインドフルネスによるストレス低減等の方法だ。また、借金返済を助ける「ホルモン三銃士」なる存在についても言及されている。食欲ホルモンであるグレリン、血圧降下作用のあるナトリウム利尿ペプチド、そして愛情ホルモンとして知られるオキシトシン。著者の専門であるこれらホルモンやエネルギー代謝を司るミトコンドリアなど、内分泌代謝に関する解説はとりわけ筆がなめらかで、ホルモンという存在への興味が自然に湧いてくる。
生きるためのエネルギーをお金に喩え、お金は出し惜しみせず使うべき時に使おう。たとえば44歳と60歳という大きな節目には思い切って投資しよう。そう薦める本書は、健康を取り戻すには若い時には若い時なりの、老いた時には老いた時なりの方法が必ず見つかるという、中高年への大いなる励ましの書である。
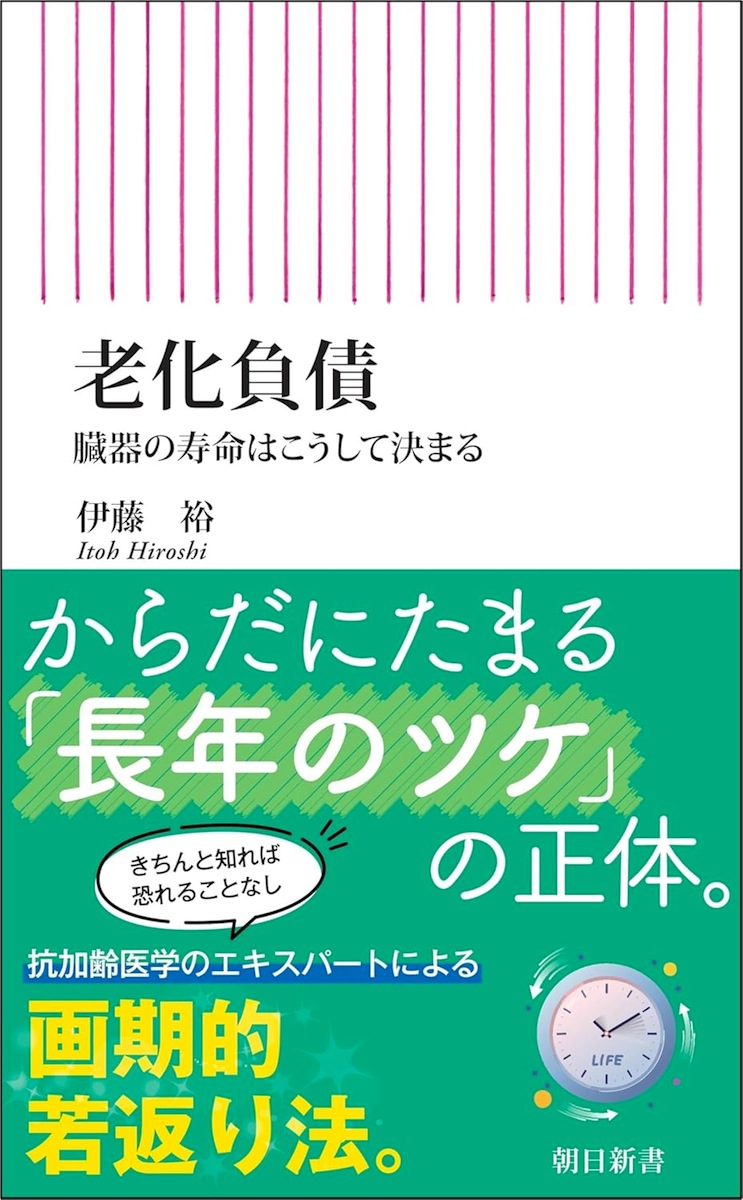
いとう・ひろし 慶應義塾大学名誉教授、慶應義塾大学予防医療センター特任教授、医学博士。1957年、京都市生まれ。京都大学医学部卒業、同大学院医学研究科博士課程修了。ハーバード大学及びスタンフォード大学医学部博士研究員、京都大学大学院医学研究科助教授、慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科教授を経て現職。専門は内分泌学、高血圧、糖尿病、抗加齢医学。世界で初めて「メタボリックドミノ」を提唱。高峰譲吉賞、日本高血圧学会栄誉賞など受賞多数。著書に『幸福寿命─ホルモンと腸内細菌が導く100年人生』『なんでもホルモン─最強の体内物質が人生を変える』(以上、朝日新書)などがある。
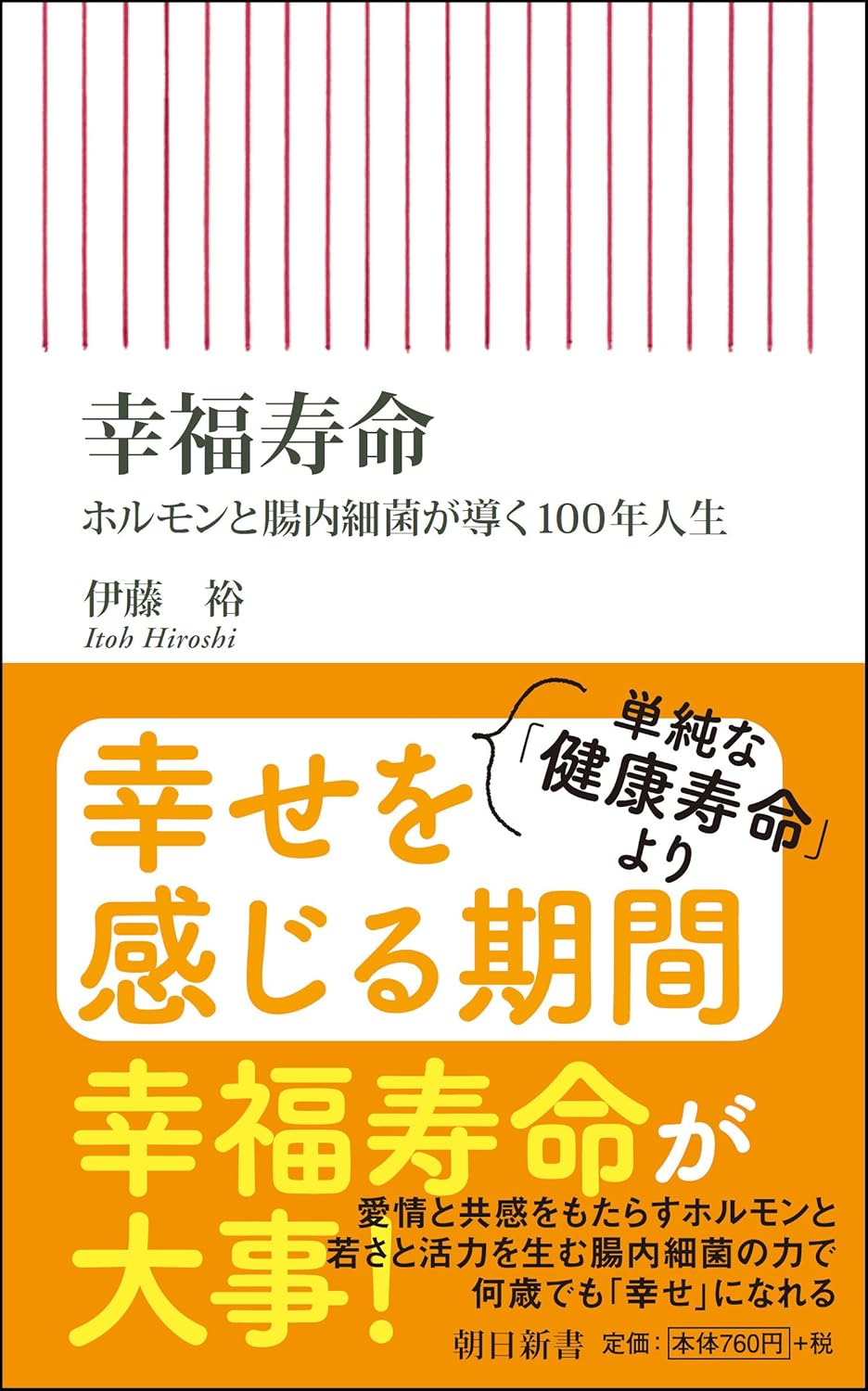
『幸福寿命――ホルモンと腸内細菌が導く100年人生』
(朝日新書、2018年)
まつなが・ゆいこ 1967年東京都生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。千代田区・文京区界隈の中小出版社で週刊美術雑誌、語学書、人文書等の編集部勤務を経て、 2013年より論創社編集長。