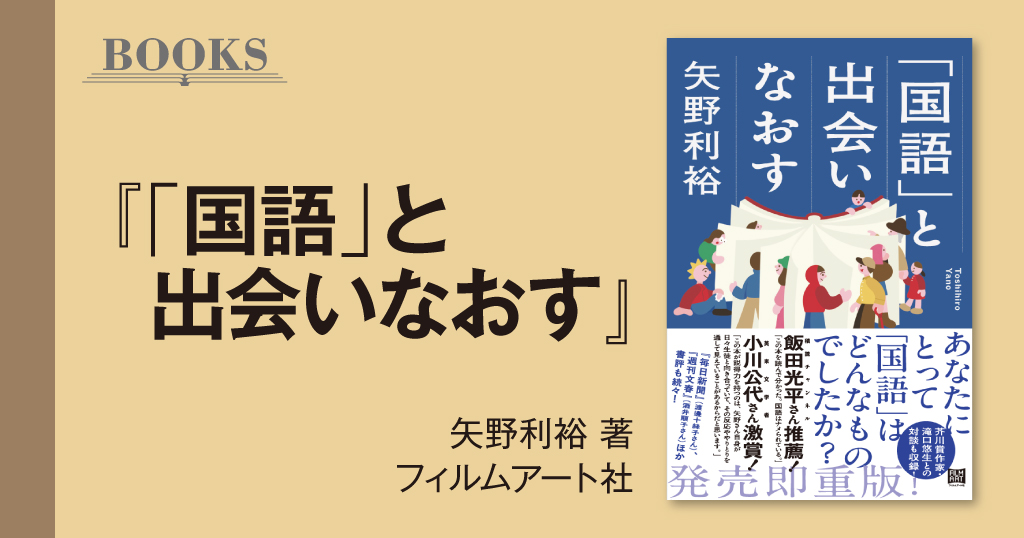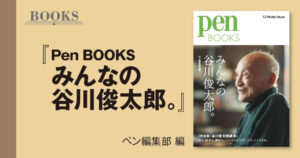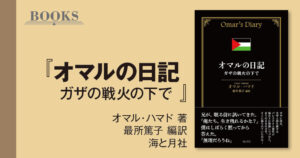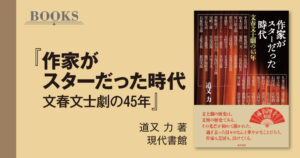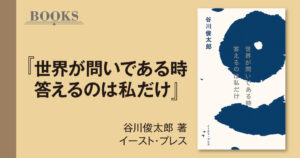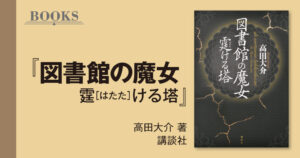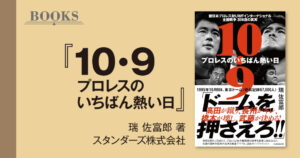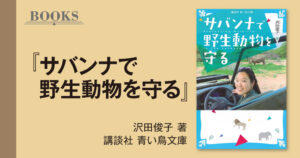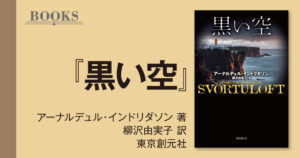「国語」と「文学」の雪解けにむけて
歳をとると、昨日読んだ本の内容すら忘れがちになる。のに、若い頃に読んだ本の内容は、いまだ忘れられず、脳にこびりついている。国語教科書の定番教材についてもそうで、教室の雰囲気とセットで思い出される。
宮沢賢治「やまなし」。得体のしれないクラムボンが、かぷかぷ笑ってたなあ。新美南吉「ごんぎつね」。兵十[ひょうじゅう]、やっちまったなあ。中島敦「山月記」。漢字が難しくてかっこいい。森鷗外「高瀬舟」。首、痛そう。夏目漱石「こころ」。先生、やっちまったなあ……。
でもってこういう思い出話は、日本で国語教育を受けた人と、世代を超えて、わりと共有できるのが嬉しい。かつて清水義範が述べていたように(『虚構市立不条理中学校』など)、学校で勉強した思い出は大人になると、あまり趣味が被らない人とも共通する面白い話題、エンターテインメントになりうるのだ。
だから、漱石「こころ」や、やはり定番であるヘッセ「少年の日の思い出」、島崎藤村「初恋」などを、国語教育の現状と照らし合わせながら再解釈する本書は、小説好きや教育関係者のみならず、多くの人にとって、とっつきやすいように思える。
文芸評論や音楽評論を執筆する批評家であるとともに、私立中高一貫校の教壇に立つ現役の国語教師でもある著者による、「国語」と「文学」を建設的につなぐ試みが本書だ。著者は「文学」という語に宿る様々なイメージを探ったうえで、難解でハードルの高い文芸誌的な「文学」と、学校で習う「国語」との相性の悪さを見出す。
たとえば20年ほど前、文芸誌で国語教科書についてアンケートをとった際には、「国語」で「文学」は学べない、といったような、批判的な意見が強かった。反面、高校の教科書が「論理国語」と「文学国語」に分かれた昨今では、「文学」を扱う時間を減らすべきでないと、日本文藝家協会が声明を出している。著者も補足するように、20年前の、「文学」は「国語」の教科書に不要とする論者と、現在の必要論者とは、顔ぶれがほとんど違う。ので、「文学」側が二枚舌というわけではないのだが、いずれにせよ各時代で、「文学」側と「国語」側は、対立物として言及されがちだった。
さりとて、多くの人にとって、「国語」の教科書を読む教室のほかに、「文学」に出会える場は少ない。そして「文学」には、「国語」を通して形作られる面がある。そういった観点から著者は、両者を結ぶ回路を探していく。
解釈を一つにしぼるような「国語」の長文問題は、読者の多様な解釈の道を閉ざしているように見えるが、実の所は、文学作品を読むにあたっての前提となる常識的なコード(規則)を問うており、そこで養われたコード読解を応用することで、読者は多様な解釈にたどりつく。教科書的な文学史は、多様な歴史観があるなかで一様に見えるが、そういった文学史批判や相対化が有効であるためには、多くの人のあいだで教科書的な(正史的な)文学史が共有される必要がある。生徒同士の共感から作品を読む教室の共同性は、作品の個別性(共感不可能な性質)を無視しているように見えるが、ばらばらな個人であるはずの生徒が一つの作品をともに読み、話し合い、疑似的な共同性をつくりあげる教室はむしろ、個別性とは何かを捉え返す現場である。といった具合に。
思い起こしたのは「真の小説は小説に対して発する《否[ノン]》によって始まる」というティボーデの言葉だ。否[ノン]を唱えるには、まずは否定先となる既存の小説を読んでおく必要がある。あるいは、型を知ってこそ型破りができる、みたいな言葉も想起する。その「型」と「型破り」みたいな関係で「国語」と「文学」を結ぶ見方に大いに納得したし、一般的にとっつきやすい「国語」の話から、とっつきにくい「文学」の話に滑らかにつなげる手腕は、自分もいつか授業とか飲み会でマネしてみたくなった。
巻末には、滝口悠生の小説をもとに著者が作成した長文問題を滝口本人が解く、という対談が載る。出題者と、引用された作者とが、問題文をはさんで話し合うなんて、前例を知らない。こういう好企画がどんどん続けば、「国語」と「文学」の雪解けの日も近まる気がする。
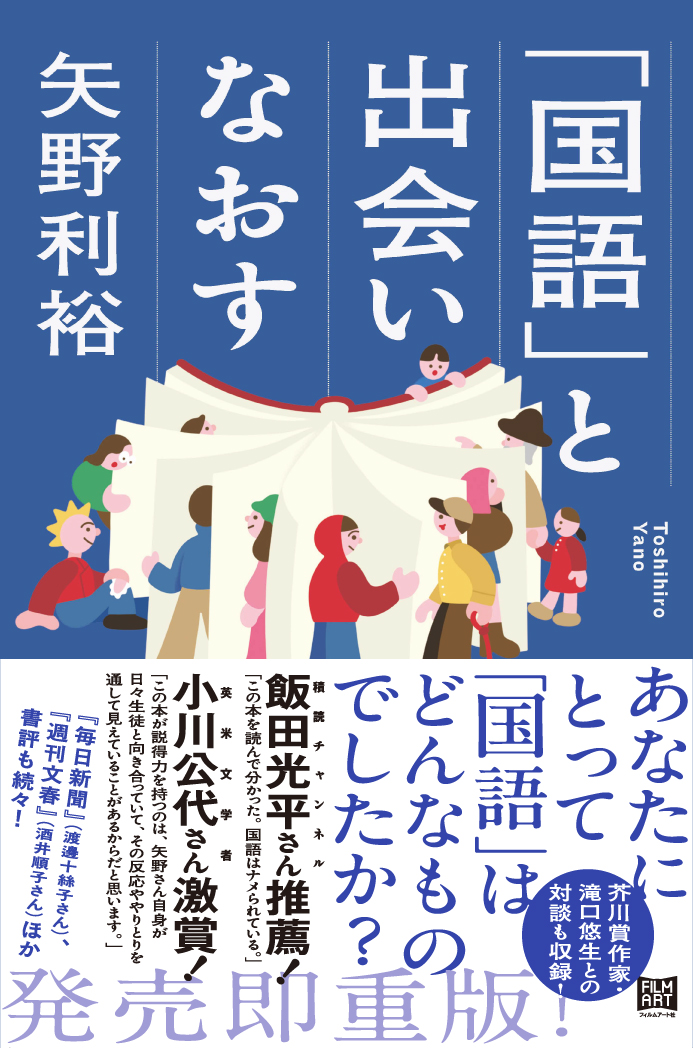

さとう・やすとも 1978年生まれ。名古屋大学卒業。文芸評論家。 2003年 、「『奇蹟』の一角」で第46回 群像新人文学賞評論部門受賞。その後、各誌に評論やエッセイを執筆。『月刊望星』にも多くの文学的エッセイを寄稿した。新刊紹介のレギュラー評者。
バックナンバー