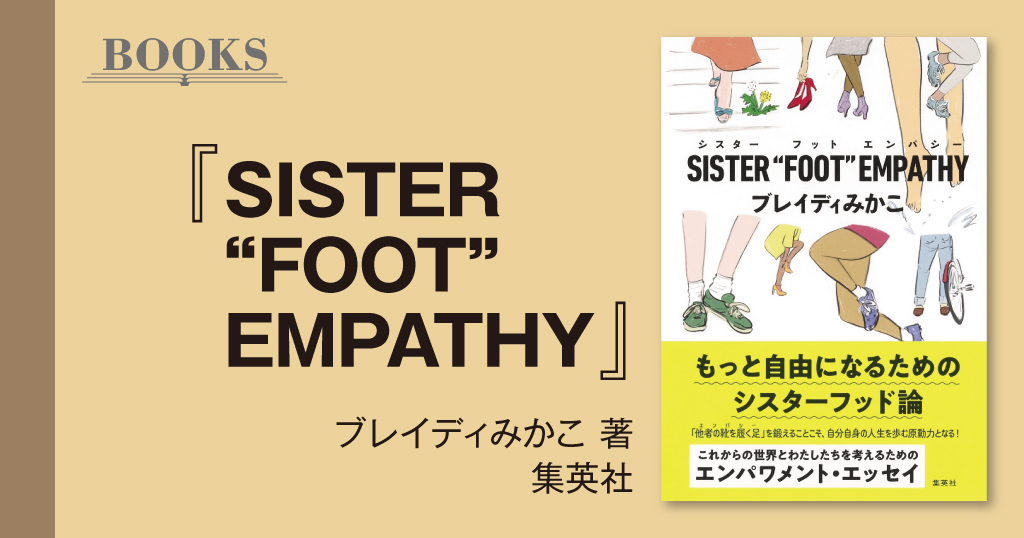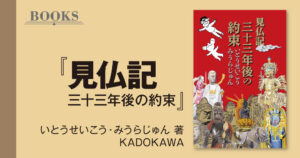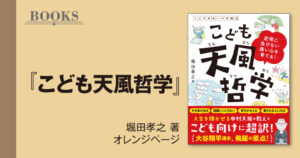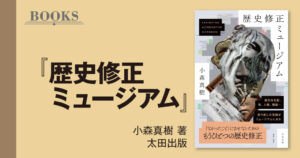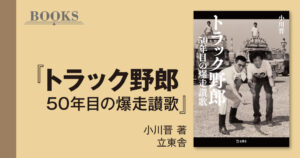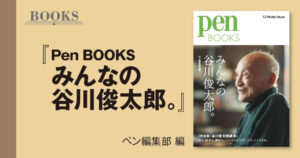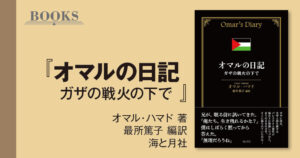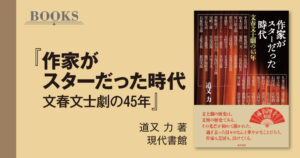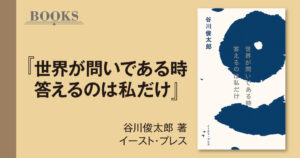世直しは〝共感力〟あってこそ
タイトル『SISTER “FOOT ” EMPATHY』は、「シスターフッド」――女性同士のつながりや絆のことに「フット(足)」をかけて、足もと、つまり地べたから考える、「エンパシー」は共感と訳されるが、英語の定型表現では「自分で誰かの靴を履いてみる」、つまり他人の立場を想像できる理解力のこと。
どれも著者が長年取り組んできたテーマだ。女性誌『SPUR』から連載の依頼が来たとき、このタイトルでお願いしたいとの文を見て、著者は「私が書かずに誰が書く」とがぜん乗り気になった。とくにエンパシーについては、イギリスのブライトンに家族と住む著者が、中学生の息子をめぐる多民族階級社会ならではの日常を描いた『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』で言及している。中学校のテスト問題「エンパシーとは何か」に対して、息子が書いた名解答が「自分で誰かの靴を履いてみること」だった。
地べたからのシスターフッドが国政を動かした出来事に、アイスランドで1975年10月24日に起きた「女たちのストライキ」がある。労働者も主婦もさまざまな立場の女性がいっせいに仕事を放棄したのだ。経済や社会にとって女性の仕事が不可欠であることと、男女間の賃金と雇用の格差への抗議を示すための行動だった。「女性たちの休日」とも言われている。多くが女性である教員や保育士もストライキに参加したため、学校や保育園は閉鎖された。家庭の女性たちも家事をストライキした。男性たちは子どもたちを職場に連れて行くしかなかった。その日の新聞はいつもの半分まで薄くなり、銀行の窓口には上司の男性が座った。ストライキ参加者は女性の九割に達した。
どうしてそんなことができたのか。たくさんの女性たちが道ばたでの情報発信や参加呼びかけをおこなった。そこでの話し合いにはエンパシーの介在があったに違いない、と著者は見る。それが女性たちの小さなグループやコミュニティから大きな団体まで、九割の女性のネットワークをつくった。五年後のアイスランドには、世界で初めて民主的に選ばれた女性大統領ヴィグディース・フィンボガドッティルが誕生する。このストライキが、現在のアイスランドを世界ジェンダーギャップ指数ランキング一位の国にした大きなステップとなった。
一方、2020年にメキシコでは、女性に対する暴力や殺害に抗議し、国家が対策を強化することを要求に掲げて、女性たちが全国いっせいのストライキを決行した。メキシコは女性を標的とした殺人が多発しており、夫やパートナーなどに殺される女性は毎年約九百人にものぼるという。
この本には、このほか女性の抱えるいろいろな問題と、それに立ち向かう女性たちが取り上げられている。女性たちがつながるために使うエンパシーは、何も女性だけのものではない。他人の立場を想像し理解する力は、男女問わず全く違う人々をつなぐことができる。そのつながりは、地べたから広がって世界をもっと暮らしやすいところに変える波を起こすだろう。
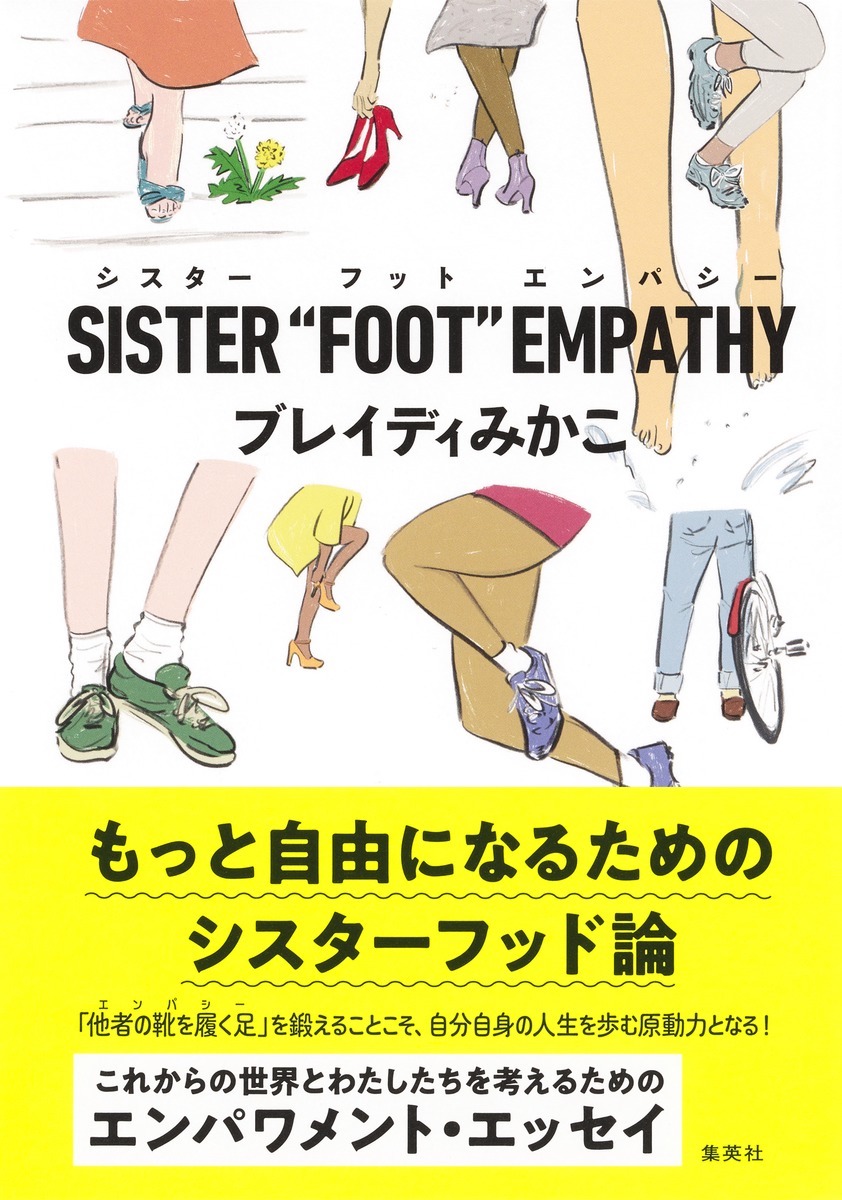
ぶれいでぃ・みかこ ライター・コラムニスト。1996年より英国在住。2017年、『子どもたちの階級闘争 ブロークン・ブリテンの無料託児所から』(みすず書房)で第16回新潮ドキュメント賞受賞。19年、『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社)で第73回毎日出版文化賞特別賞受賞、第2回本屋大賞ノンフィクション本大賞などを受賞。小説作品に『私労働小説 ザ・シット・ジョブ』(KADOKAWA)、『両手にトカレフ』(ポプラ社)、『リスペクト――R・E・S・P・E・C・T』(筑摩書房)などがある。近著には『地べたから考える――世界はそこだけじゃないから』(筑摩書房)。

さわ・いずみ 1968年、神奈川県生まれ。東海大学大学院博士課程前期修了。専攻は中世アイスランド社会史。出版社勤務を経て司書。公共図書館・博物館図書室・学校図書館勤務のあと、現在介護休業中。アイスランドに行きたい毎日。写真は、今は亡き愛犬クリス。
バックナンバー