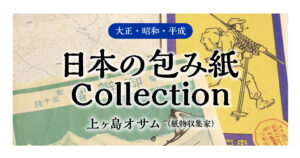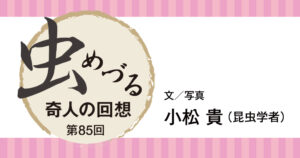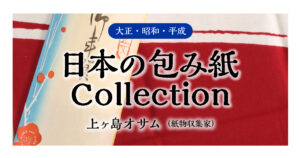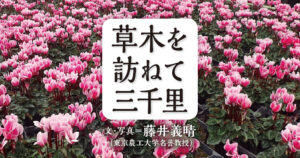第9回 流れ星――彗星からの〝贈り物〟
待ちに待った夏休み、海や山へ旅行に出かける方も多いと思います。
自然の豊かな場所に行ったら、夜空を見上げてみてください。ふだんは見ることができない数多くの星に気づき、心に残る風景となるはずです。
この季節の代表的な星といえば、やはり「夏の大三角」でしょう。
こと座のベガとわし座のアルタイル、はくちょう座のデネブを結んだ三角形。正三角形ではなく、どちらかというとショートケーキのような形です。こと座のベガは「織り姫星」、わし座のアルタイルは「彦星」。前回ご紹介したとおり、旧暦の七夕(今年は8月29日の金曜日)が近いこの時期にこそ見たい星ですね。
さて、夏といえば有名な流星群があります。
それは毎年8月12日前後にやってくる「ペルセウス座流星群」。ペルセウス座のあたりから星が四方八方に飛んでいくように見えるため、この名前が付けられました。
ペルセウス座流星群は、流れ星を見たことがない、という方に特におすすめの流星群の一つです。なぜなら、年に何度も現れる流星群の中でも、流れる星の数がトップクラスだから。お天気がよくて街の明かりが少ない場所に行けば必ず見られます。ぜひ、旅行の計画に入れてみてください。
ところで、流れ星はどうして起こるかご存じですか。
流れ星のもとになるのは、太陽から遠く離れた場所から飛んでくる「彗星」という天体です。彗星は軌道上にたくさんのチリを落として飛んでいくのですが、このチリが大気に激しくぶつかり、高温になって光を放つ現象が流れ星です。彗星の落とし物が流れ星になる、というわけですね。
ちなみに、〝落とし物〟をして私たちにペルセウス座流星群を見せてくれるのは「スイフト・タットル彗星」と呼ばれる天体で、約130年周期で太陽の周りを回っています。彗星が地球に近づく8月に、夜空に輝くたくさんの流れ星……。それは、スイフト・タットル彗星の〝落とし物〟というより〝贈り物〟なのかもしれません。
今年のペルセウス座流星群は8月13日(水)の午前5時ごろがピークとなりますので、12日の夜から13日の明け方が見ごろ。ペルセウス座が昇ってくる13日の午前3時ころが特におすすめです。
少し眠い時間帯ですが、早起きができそうな方はぜひご覧ください。
方角は意識せずに、できるだけ暗い方向を見るのがポイントです。空が広くて明かりが少ない場所であれば、1時間に30個ほどの流れ星を楽しめるでしょう。
数は少ないですが、都会でも見えないことはありません。コツは、とにかく長い時間眺めること。できるだけ明かりが目に入りにくい場所で、根気よく空を見上げてみてください。
日本では古くから星を愛でる風習がありました。
清少納言は『枕草子』の中で
「星は昴[すばる] 彦星 ゆふづつ よばひ星すこしをかし」
と書いています。
これは、「星といえばすばる。彦星や金星もいい。流れ星も興味深い」という意味で、「よばひ星」とは流れ星のことなのですね。
今年の8月は宵の空に彦星、明け方には東の空にすばると金星が見えます。もし流れ星も見られたら、時空を超えて、清少納言が愛でたすべての星を楽しむことができますよ。
ペルセウス座流星群だけでなく、流れ星は毎日飛んでいます。ぜひ夜空を眺めて、みなさんの心の中に素敵な風景を増やしてくださいね。

佐々木さんがモンゴルで撮影したペルセウス座流星群(2024年)。
撮影時、ちょうどオーロラが発生したため、空が赤い。
稀有な状況での貴重な一枚だ

ながた・みえ コスモプラネタリウム渋谷チーフ解説員。東京・品川生まれ。東京理科大学理学部物理学科卒業。キャッチフレーズは「癒しの星空解説員」。2000年からNHKラジオ第一『子ども科学電話相談』の「天文・宇宙」の回答者を務める。ご自身の名がついた小惑星(11528)Mie がある。著書に『カリスマ解説員の楽しい星空入門』(ちくま新書、2017年)など、監修に『小学館の図鑑NEO まどあけずかん うちゅう』(小学館、2022年)、『季節をめぐる 星座のものがたり 春』(汐文社、2022年)などがある。 コスモプラネタリウム渋谷の公式ホームページはこちら
バックナンバー