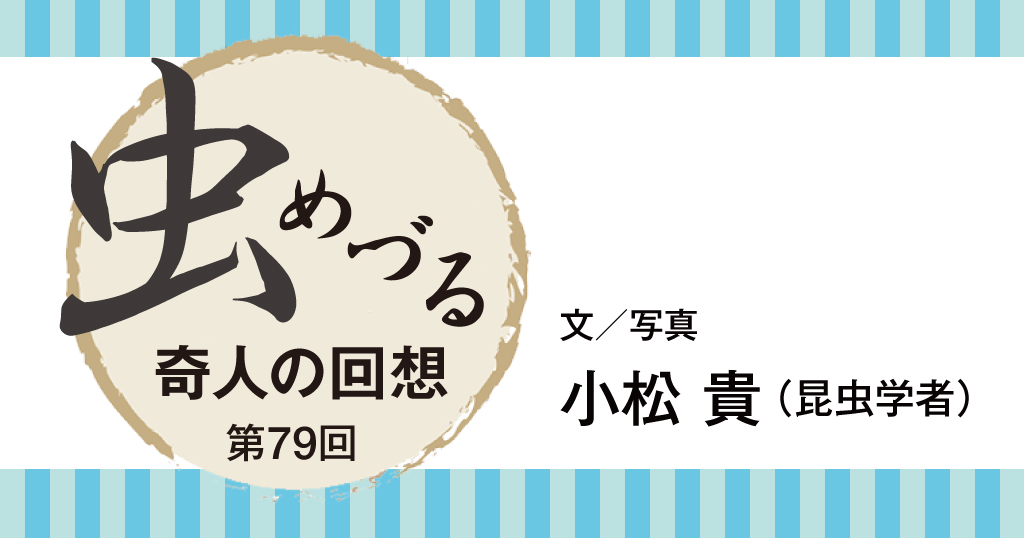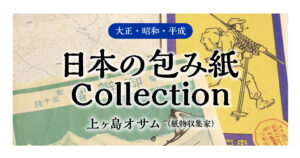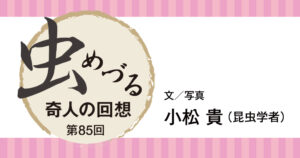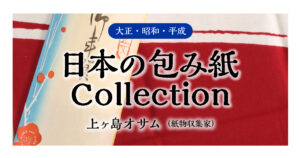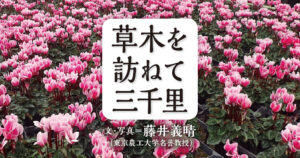第79回 草食で大人しいニジュウヤホシテントウなのに
我が家でずっと利用し続けている、近所の無農薬貸し農園。今年の春に作付けしたジャガイモの出来具合を、つい先日見に行った。青々とした大きな葉を広げているその様を見るに、育ちは上々に見えたが、葉の表面にはいくつもの虫食い痕が出来ていた。特徴的な、細い線を平行に並べたような食い方。まるで、RPGゲームに出てくる階段を思わせるようなそれを付けた犯人には、すでに見当が付いている。ニジュウヤホシテントウだ。

ニジュウヤホシテントウは、ナス科の農産物の害虫として巷に悪名高いテントウムシ(のひとつ)である。アブラムシを粛清するため有難がられるナナホシテントウやナミテントウ然り、テントウムシの仲間というのは本来肉食をする種が大半なのだが、ニジュウヤホシテントウを含むマダラテントウ族のテントウムシ類に限っては、何故か進化の過程で肉食性から草食性へと転換した。言うなれば、ライオンが菜食主義になったようなものだ。
肉食動物の牙でもって、草食動物の生活をする彼らは、純粋な草食動物たるチョウやガの幼虫のような植物の食い方が出来ない。だから、葉を丸ごとバリバリ食わず、「葉の表面に傷をつけてそこから柔らかい葉の内部組織だけを吸い取る」という奇妙な食事方法を取る。彼らの特徴的な食痕は、そのせいである。そして、その内部組織というのも、かつての餌だったであろう肉よりは遥かに消化が悪いため、彼らは今なお肉食を貫く同胞達よりも長い消化器官を体内に発達させ、ゆっくりと消化吸収せねばならなくなった。そこまで余計な苦労を背負って、彼らが草食にならなければならなかった理由とは、一体何だったのだろうか。



マダラテントウ族は温厚な性格だが、幼虫と蛹の見た目はなかなかに凶悪
アニメ然り絵本然り、創作界隈においてテントウムシはとかく愛らしく、(敵味方が存在する世界観のストーリーならば)基本的に味方陣営として描かれるのが定石だ。しかしその際、〝テントウムシ〟というアイコンのモチーフとされるのが、ナナホシテントウかナミテントウと相場が決まっているのはどういう了見なのだろうか。
か弱いアブラムシを無秩序・無慈悲に蹂躙し、ともすれば仲間内での共食いすら辞さない凶暴なそれらが好ましい存在として描かれる一方、草食で大人しいニジュウヤホシテントウがそうしたキャラクターで描かれることがまずないのは、彼らに経済害虫としてのイメージが完全に定着してしまっているからに相違ない。時に、農業界隈では「テントウムシダマシ(※)」などと、もはやテントウムシの紛い物じみた名で呼ばれることもある。どんだけニジュウヤホシテントウ嫌いなんだよ、ホモサピエンス共は。
※テントウムシダマシ科という、テントウムシ科とは全く別の甲虫分類群が既に存在するため、真のテントウムシたるニジュウヤホシテントウをこの名で呼ぶ行為は、各方面に混乱を巻き起こす害悪でしかない

ここに示した本種以外のテントウムシ全てがマダラテントウ族
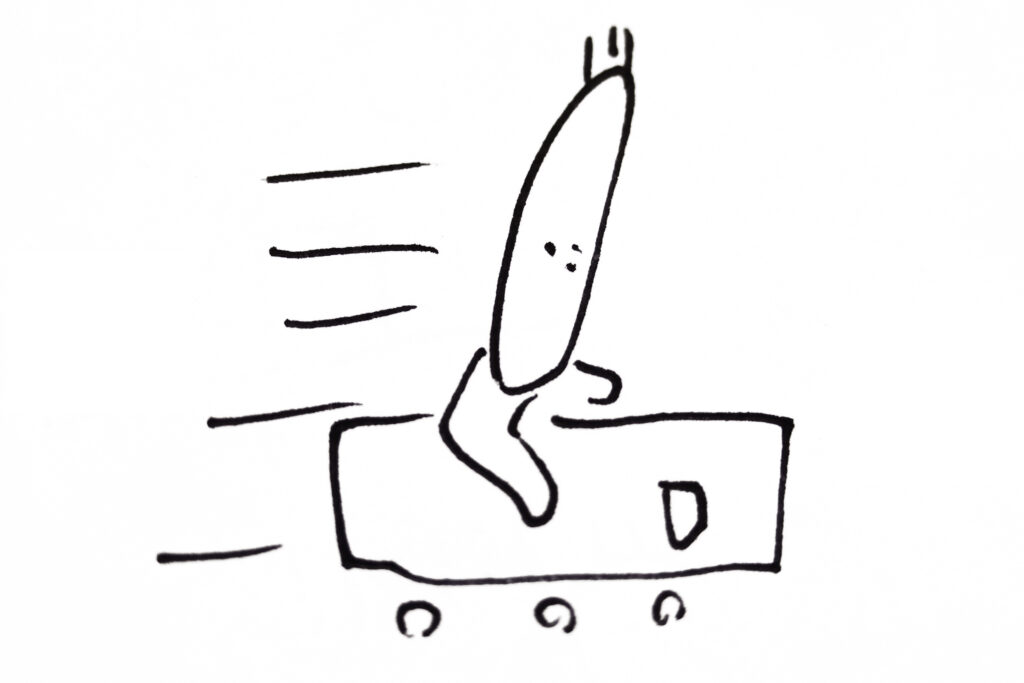
こまつ・たかし 1982年神奈川県生まれ。九州大学熱帯農学研究センターを経て、現在はフリーの昆虫学者として活動。『怪虫ざんまい―昆虫学者は今日も挙動不審』『昆虫学者はやめられない─裏山の奇人、徘徊の記』(ともに新潮社)など、著作多数。
バックナンバー