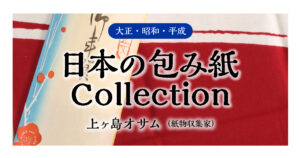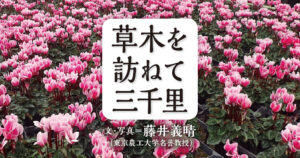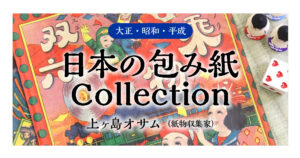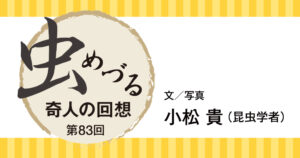第78回 クロヘリウスチャハムシをよすがに
多少虫に詳しい人間を巷に見つけるや、すぐマスコミが「日本のファーブル」などともてはやす昨今。我が国に自称「昆虫学者」数あれど、その中にクロヘリウスチャハムシの存在を知る奴など何人いようか。
体長4ミリ程、世に出回る大概の昆虫図鑑にも載っていない、すこぶる地味でマイナーな小甲虫だ。ゴマギという樹木の葉だけを食うこの虫は、日本ではこれまで本州の数箇所から点々と見出されているが、現在そのほとんどが絶滅ないし存続不明であり、目下確実な産地は表向きには箱根の仙石原のみとされる。その仙石原でも(ゴマギ自体は数多く自生するのに)、特定のたった2本のゴマギ上でしか見つからないらしく、根元が湿地であるなど何らかの条件を満たした木にしか住めないのだと言われる。図鑑でもインターネット上でも、この虫について得られる情報は概ね以上が全てだ。

既知産地のうち東京都では絶滅、青森県では現状不詳

しかし、実際には非公式ながらもう一箇所、富士山麓某所に詳細不明の生息地のあることが、ごく少数の虫マニアの間でのみ知られている。かく言う私も、そこが正にその場所かは知らねども、かの地の辺りに本種の生息地を一箇所見つけている。そこでは、生息密度こそ薄いが、複数のゴマギ上で彼らを見つけることができ、貴重な国内の既知産地と言えよう。何しろ、本種に関する情報はろくすっぽ得られないため、私がそのガンダーラに辿り着くまでには、名実ともに筆舌に尽くしがたい時間と労力を要した。
かの地は恐ろしく辺鄙で、吉幾三の某歌で言う「バスは一日一度来る」ような場所ゆえ、四輪を持たず運転も出来ない私にとって、ここは容易に到達し難い。よって、いつもここへは近場(と言うには余りに遠いが)の実家の父親に頼み込み、車を出してもらう事になる。ここ二、三年この虫の調査名目で、たかだか日帰り弾丸とはいえ実家に寄る機会が増えた。ある意味、この虫が実家帰りの口実になっているようなものだ。
かつて大学生時代、暇を拗らせていた私は事ある毎に実家に帰り、厚かましくもくつろいでいた。しかし、家庭を持って以降は日々の雑務にも追われ、自然と実家から足が遠のいた。いつの間にか両親も目に見えて年老いた。「親の面より見た◯◯」という比喩があるが、私はあと何回あの家の敷居を跨ぎ、両親の顔を見るのだろう。これからも、私は神に許される限りの回数を、あの虫をよすがとして実家帰りに費やすに違いない。

少なくとも当地では、木の根元が湿地か否かは本種の生息と何ら関係ない

地味で小型なのも手伝い、目の前にいてさえすぐには発見できない

本種の情報取得をなおさら困難にしており迷惑極まる
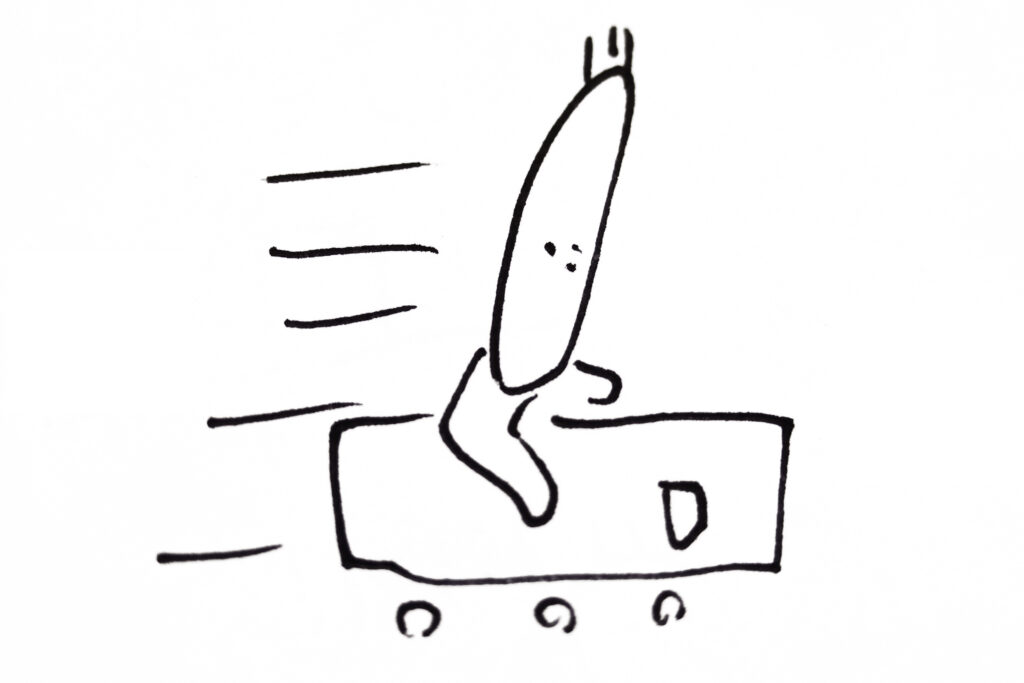
こまつ・たかし 1982年神奈川県生まれ。九州大学熱帯農学研究センターを経て、現在はフリーの昆虫学者として活動。『怪虫ざんまい―昆虫学者は今日も挙動不審』『昆虫学者はやめられない─裏山の奇人、徘徊の記』(ともに新潮社)など、著作多数。
バックナンバー