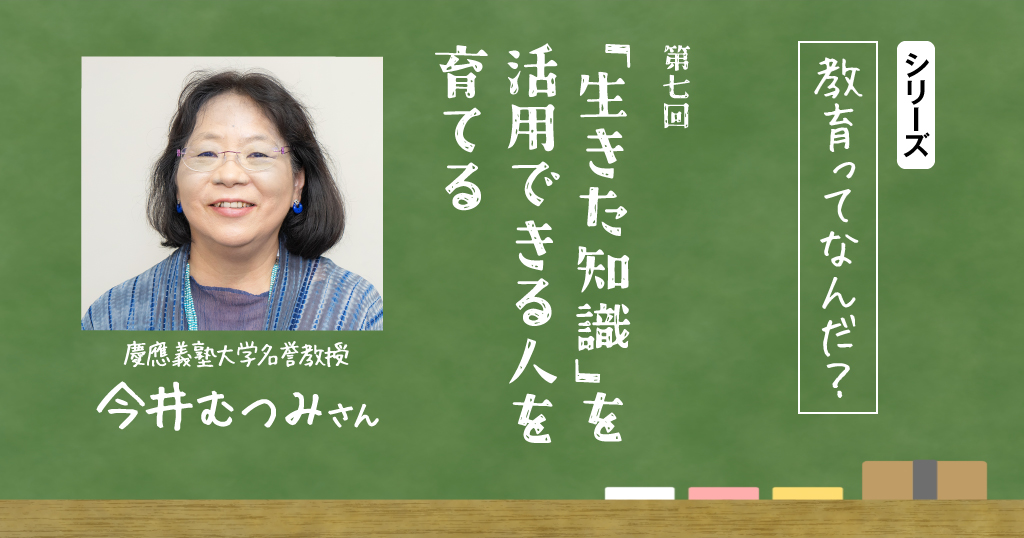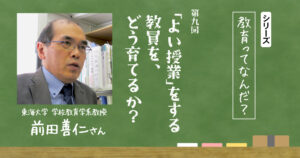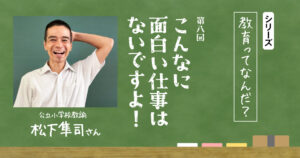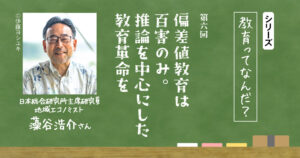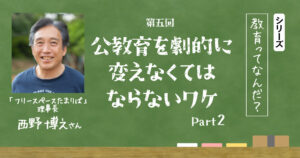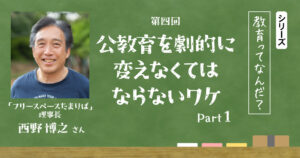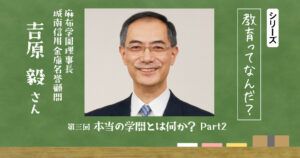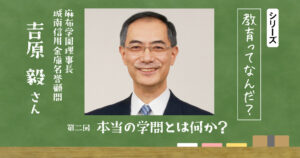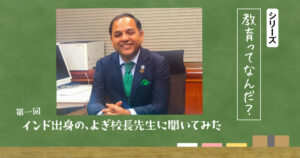間違った情報が氾濫する現代社会にあって、本質的な情報を見極め、それを活用して問題解決につなげていく。こういうことができる人を育てていくことこそが教育の役割だ。文部科学省が掲げる〝必要な学力〟も、知識の詰め込み教育から離れる方向にある。だが、それを阻止しているものがある。受験教育だ。弊害が大きすぎるのではないか。学びとは? 学力とは? 今井むつみさんに聞いた。
ドネルケバブのような知識は、ただの「死んだ知識」
――抽象的な質問からで恐縮なのですが、「学び」とは何かということについて、今井先生のお考えがあれば、まずはそこから教えていただけますでしょうか?
私がよく使う認知心理学の用語に「生きた知識」と「死んだ知識」があります。学んで覚えたことを自ら使い、何かをする・できるようになる。知識を使って創造的な問題解決ができる。そうした使える知識が「生きた知識」で、断片的な知識をどれほどため込んでいっても、使えないのであれば、それは「死んだ知識」でしかありません。
断片的な知識がたくさんあることが賢いといった考えは、昔はそれなりに大事でした。たとえば隋から清の時代にかけて、中国には科挙と呼ばれる官吏登用制度がありましたが、あの時代はパソコンなどありませんから、必要なことをすべて自分の頭の中に置いておくしかなかった。そうなると、断片的でも広範囲にさまざまなことを知っている人が賢い人であり、賢さの定義になっていたわけです
でも今の時代、断片的な知識は検索すれば手に入ります。ただし、間違った情報もたくさん出てきますので、どうやって情報の真偽を見極め、本質的な情報を手に入れて、それを上手に使うかが賢さのひとつの定義になっています。
本質的な情報を手にするためには、まず本質的な情報とは何かがわからないといけない。そのうえで、どうしたらその本質的な情報にたどり着けるかがわかること。それが前提で、その本質的な情報を使って問題解決できる人が賢い人なのではないかと考えます。ですから学びで大事なのは、断片的な知識を大量にため込んでいくことではなく、そのような賢い人間をつくっていくことです。それが学校で必要な学びなのではないかと思います。
――日本の学校教育は、どうもいまだに知識を大量にため込むほうに重きが置かれているように見えます。今井先生が著書で言われているいわゆる「ドネルケバブ・モデル」、ドネルケバブは薄切りした肉を何層にも重ねていって大きな塊にしていくトルコの肉料理ですが、ドネルケバブ・モデルの知識観から抜け出せていないのではないでしょうか。
それは学校教育の問題ではなく、今の受験制度の弊害だと思うんです。テストで問いやすいのは「死んだ知識」のほうですから。
文部科学省はずいぶん前から、断片的な知識のため込みからどうやったら離れられるかを一生懸命考えていて、次期の学習指導要領ではそれをさらに鮮明にしていこうとしています。でも受験の場合、学校や大学の階層ができていて、受験者の学力が階層に見合うかを測るにはドネルケバブ・モデルのほうがラクです。問題をつくるうえでもラクですよね。
――大人たちが考える知識観や学力観のどこが問題と感じていらっしゃいますか?
一言で言えば、学力=テストの成績と思っているところは完全に間違っています。そのテストが本当に生きた知識を測る、あるいは生きた知識をどう運用するか、運用できるかを測っているものであればよいのですが、そうではないテストがあまりにも多い。
覚えた情報がどれだけたくさんあるかを測るだけのテストになっていて、そこでの点数がよいと勉強がよくできることになっています。つまり賢さの基準を偏差値のように外にあるものに求めているわけですね。国内外の難関大学に入学できるのが賢い、一流企業に入社できることが賢いなど、外的な基準に依存してしまい、一人ひとりが賢さとは何か、本当にするべき学びとは何かを考えることを放棄している。そこが一番の問題だと思います。
経験や身体感覚と結びつけるからこそ「生きた知識」になる
――2024年9月刊行の『学力喪失』では、学校の勉強につまずいている小学生・中学生のつまずきの原因を解明されています。拝読していて、中学生でも1/2と1/3のどちらが大きいかがわからない子がいると知り、ちょっとショックでした。それは「記号接地」ができていないからだということでしたが、「記号接地」とは、ことばを身体で理解していること、と捉えてよろしいですか?
ことば(記号)の意味を経験と紐づけたり、身体感覚と結びつけたりして理解することです。たとえば「イチゴ」を食べたことがあれば、それがどのような見た目と手触りをしているか、どんな香りがするか、どんな甘酸っぱい味をしているかを知ることができます。練乳をかけて食べた経験があれば、そのときの味やおいしさといったことも身体感覚で知ることができます。
さらにリンゴやブルーベリーの味を経験していれば、そのときのことを思い出して、リンゴやブルーベリーの甘酸っぱさと、いちごの甘酸っぱさは違うということもわかる。そうやってはじめてイチゴの「意味」が理解できる。辞書で調べただけ、写真で見ただけでは、本当にわかったとはいえないわけですね。
ただ記号接地は、現実世界にある事例と記号を単に対応づけするだけではだめで、点としてのひとつの事例から「アブダクション」と呼ばれる推論で仮説を導き、点を面に拡張させていくプロセスが必要です。面に拡張させるためには、ひとつの点ではなく、いくつもの点を探して自分でつなげ、そこから抽象化して「面」にするということも必要になります。
――点から面へ拡張していく……。むずかしそうですね。
素材をポンと渡すだけで、子どもが自分で点を面にできるかというと、やっぱりそこはむずかしいんです。「イチゴ」というひとつの点から、「果物」という面に拡張させていくには、他の果物を食べたり、野菜と違うことを体験したりしていないとむずかしい。「面」を教えることもむずかしいんですね。「果物って、たとえば甘酸っぱくておいしいものだよ」と教えても、下位あるいは同じ階層にある関連する概念について記号接地できていないと、自分で推論して「イチゴは赤いから赤いトマトも果物だ」など、子どもはさまざまに誤解してしまいます。ですから自分で点を面にできるように大人が手助けをしていくことは必要です。
とくに分数や小数を含む数の概念は抽象度が非常に高い。そもそも「イチ」という概念がわからないと、分数や小数の大きさはわかりません。
――大人が手助けするとしたら、どういったことが必要ですか?
遊びや生活のなかで経験できるようにしてあげるとよいと思います。それが概念の基盤をつくることにつながっていきます。
たとえばフィンランドの幼稚園で行われている幼児教育は、小学校での学びや、抽象的な概念に向かうための基盤をつくるカリキュラムになっています。日本の小学校みたいに、机に向かって「計算の仕方を覚えましょう」「文字の書き方を覚えましょう」ではなく、生活体験の中から数を経験し、数と量の対応付けを経験して身体化させていくような学びのカリキュラムです。
日本の科目でいうと体育、図工、音楽がカリキュラムの中心で、子どもたちは手を動かしたり、身体を動かしたりして遊びながら数に関する概念とか、理科につながる概念、その他さまざまな概念を身体化させていきます。でも先生は直接には教えません。学びにつながるよう仕掛けをし、抽象化することは子どもに委ねるのです。
――まさに記号接地ですね。
身体化されるから「生きた知識」の習得になっているわけです。小さいときからスマホゲームばっかりやっているとか、動画ばっかり見ているといった状況は、記号接地からどんどん離れていってしまいます。
学びの場で活用され始めたChatGPT、その影響は?
――今井先生は長らく慶應義塾大学で教鞭をとられてきました。学生の変化みたいなものを実感されたことはありますか?
他大学で教えた経験がありませんので、学生全般の変化についてはわからないのですが、たとえば二十年前の慶大生と現在のスマホネイティブの学生とで変わった点はあるかと言われたら、あると思います。
今の学生は、ほとんどがChatGPTをはじめとする生成AIを使いこなしていて、そうしたものをいかに上手に使って効率化を図るかといった、効率性を求める傾向があります。じっくり腰を落ち着けて、やりたいことを追究していくといった方向より、効率性重視に価値観が変わってきていて、記号接地しない方向に向かっていることをひしひし感じます。
コロナ禍と、その後のChatGPTの登場の二つがターニングポイントでしたね。そこから学生たちの記号接地の度合いがすごく変わったと感じています。
――「タイパ(※)のよさ」を求める人が若い世代には増えているようですし。
昔は図書館で文献を探したり、調べたりするしかありませんでしたよね。コピーもなかなかできませんでしたから、必要な情報は書き写すしかなかった。今に比べて得られる情報量は格段に少なかったけれど、情報を手に入れたいという強い気持ちがありました。書き写すことによって情報処理も深くなっていたと思います。
今は触れる情報、得る情報の量はものすごく多くなっていますが、そのぶん情報処理が浅くなって、知識が知識の体系として統合していかないまま、うんちくで終わってしまっているような印象があります。
※タイパ タイム・パフォーマンス(時間対効果)の略語。費やした時間に対する効果や成果、満足度のこと。
――日本の教育の現場でもICT教育(※)は当たり前になってきていて、生成AIの活用もこの先進んでいきそうです。
生成AIを導入することには懸念が二つあります。一つは実体験せずにバーチャルで体験をした気になってしまうことです。バーチャルで経験しても、おそらく「おもしろかった」以上のものは残らないでしょう。記号接地ができなくなって、情報処理の深さのレベルがものすごく浅くなってしまい、「死んだ知識」をため込むだけになりかねないのは大きな懸念点です。
もう一つは、答えを教えてもらうことが当たり前になってしまいかねない点です。わからないことを自分で追究するのではなく、「わからなければAIに教えてもらえばいい」といったマインドセットができてしまったら、自ら学び探究していくことをしなくなっていきます。これは本当に危険だと思います。
※ICT教育 デジタル機器やインターネットなどの情報通信技術(Infomation and Communication Technology)を活用した教育のこと
やっぱり「遊び」「生活経験」「読書」が大事!
――生成AIの進化や浸透度合いを考えると、その傾向が強まっていきそうな感じがします。「子どもたちの学び」にも大きなマイナスの影響が出そうですが……。
どうしたらいいかを社会全体でも考えないといけませんし、どうするかを考えるのが教育現場の役割ですよね。でも少なくとも、幼児期から記号接地をすることがとても重要です。
――小さいうちから「ごっこ遊び」や外遊びをたくさんしたり、料理の手伝いや動植物を育てるなど日常生活の中でいろいろな体験をしたり、身体を使ってたくさん経験していくことがやはり大事ということですね。
そうですね。あとは読書です。子どもが小学校に上がると、「自分でもう読めるでしょ?」と読み聞かせをやめてしまう親は多いのですが、もったいないですね。中学生ぐらいまでは、まだまだ学びの最中にいる子どもたちなので、親子で一緒に読書をするとか、活字中心の児童書を読んであげることも大事だと思います。
小学校三年生・四年生向けの児童書をたくさん読んでいないと、抽象的な言葉に触れる機会が少なくなってしまうからです。
たとえば「等しい」という言葉は日常会話ではほとんど使うことはありません。「同じに分けて」といった言い方はするけれど、「等しく分けて」とはあまり言いませんよね。「等しい」がわからないと、分数はわかりません。三人で好きなように分けることが1/3と思ってしまっている子は結構います。
本を読む、本が読めるには訓練が必要です。小学校低学年の子どもに本だけ渡して「読みなさい」と言っても、すぐに読めるようにはなりません。読んでも理解できない、知らない言葉も多いとなれば読むことをやめてしまいます。そうなると語彙も増えていきません。
すらすら読めるようになれば読書が楽しくなり、わかる言葉が増えて、言葉の理解も概念の理解も深まっていきます。「小学校に上がったから」「もう中学生だから」と年齢や学年で区切ってしまうのではなく、ポジティブなスパイラルに入っていけるように大人が手助けして、子どもの学ぶ力を伸ばしていってほしいと思います。
■聞き手・文 八木沢由香

いまい・むつみ 1989年慶應義塾大学大学院博士課程単位取得退学。94年ノースウェスタン大学心理学部Ph.D.取得。専門分野は、認知科学、特に認知言語発達科学、言語心理学。2006~2025年まで慶應義塾大学環境情報学部教授。現在は慶應義塾大学名誉教授、一般社団法人「今井むつみ教育研究所」所長。 『学びとは何か―〈探究人〉になるために』『学力喪失―認知科学による回復への道筋』(岩波新書)、『親子で育てることば力と思考力』(筑摩書房)など著書多数。