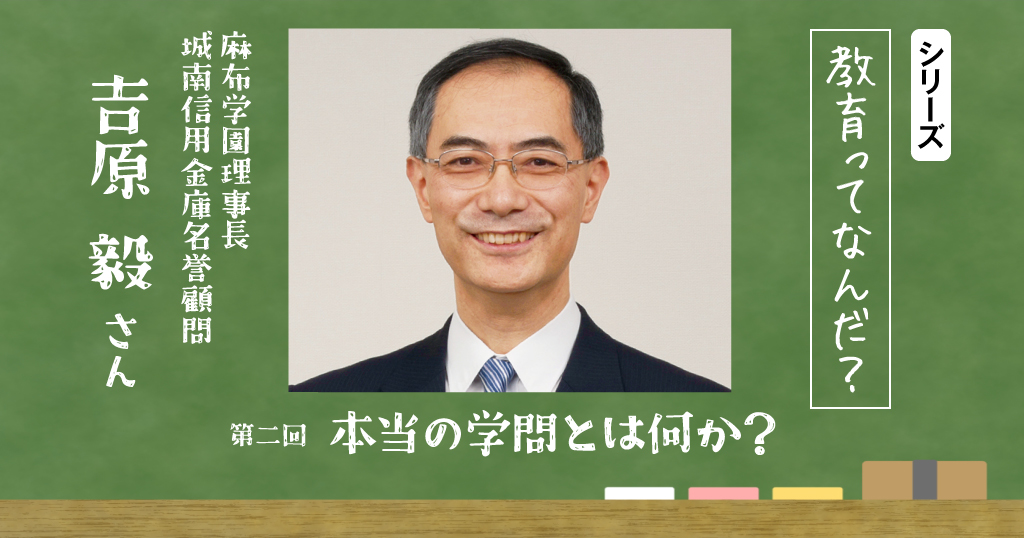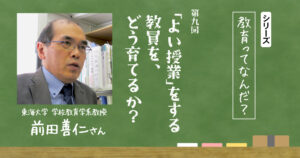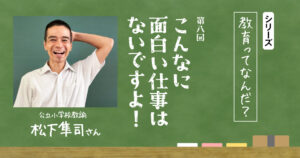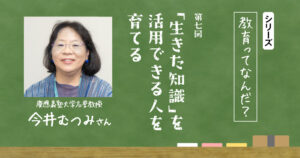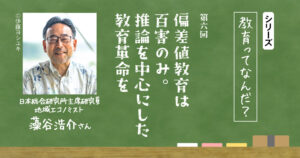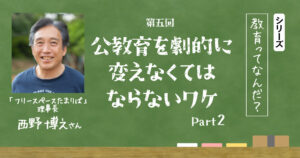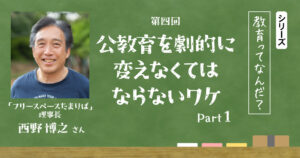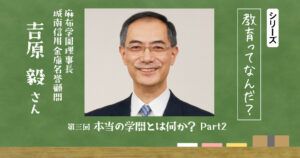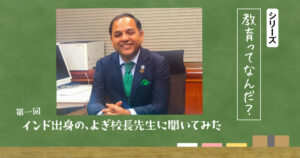経済人、実業家であり、麻布学園理事長、千葉商科大副学長として教育界にもかかわる吉原毅さんに、今の日本の教育が抱える問題点を聞いた。本当の学問とは? 詰め込み偏差値教育の害悪、金儲け至上主義がもたらした社会の衰退――日本社会は教育のありかたを変えることはできるのだろうか。
福澤諭吉が言った実学とは?
――経済人であり教育者でもある吉原さんの目に、今の教育はどう映っていますか?
まず学問とは何かということから話をしたいのですが、『学問のすゝめ』で福澤諭吉は実学ということを唱えています。しっかり読んでいないと「実用の学問を勉強すると出世してお金が儲かると福澤先生は言っているんだな」と勘違いしますが、福澤先生の言う実学は「本当の学問」という意味なんですね。
では、実学=本当の学問とは何か。それは国や社会をよくするためにあるものだと言っています。
たとえば洋学を三年間学んで洋学教師として働いたり、お手軽に役人になったり、学問の知識を切り売りして商売にするような学生に厳しい目を向けている。知識で金儲けするのは、学問のフリをしているだけで学問ではないと批判している。学問をするには志を高くしなくてはいけないとも言っています。
――日本の教育が続けてきた詰め込み偏差値教育では、国や社会をよくするための志の高い「本当の学問」はできませんね。
詰め込み偏差値教育のような体たらくになっていったのは、明治十年に東京大学が設立され、「テストでよい点を取ったら官僚として取り立てるよ、そうすれば栄耀栄華は君たちのものだ」と言って、一定期間で一定の知識を詰め込む教育を始めたからです。
それまでの日本の教育は塾でした。慶應義塾や緒方洪庵の適塾、あるいは藩校教育もそうですね。藩校教育は今の日本の教育とはまったく違います。お互いの考えを発表し、他の人とは違うけれど、自分はこのような考えをもつ。なぜなら自分はこのような生き方が崇高であると思うし、自分の生き方としてこれが正しいと思うからと根拠を述べる。オックスフォードやケンブリッジで行われている教育、あるいはフィンランドメソッドに非常に近いものです。
崇高な世の中をつくるために、まずは『四書五経』の素読[そどく]を学び、そのなかで得られる価値観のもと、どういうことを考え、どう生きていくかという目的思考をもって世界を分析・研究し、次の世の中の政策を打っていく。つまりは、あることを成すために必要なものは何か?から見えてくるものを学問の対象とし、独自に考えてきたことを基にして、『真善美』の世界に生きる存在として志をもち、生きていけ、と。そういうことを藩校教育ではやっていたんです。
近代化が教育にもたらしたもの
真善美の「真」は真理・真実、「善」はさまざまなものが互いに争い合わず共生していること、「美」は多様なものが調和を保っていることです。
人間だけでなく、あらゆる生き物が真善美の世界で生きていますよね。YouTubeには猫とヒヨコが仲良く昼寝していたり、ライオンが人にごろごろ甘えたり、猫が犬の仔を育てていたり、種の違う生き物が互いに仲良く暮らす動画がたくさんあります。ですから自然界の論理なんです。
そうした真善美の世界に至るような生き方の一環として学問はある。それを壊してしまったのが近代化です。
――どういうことでしょう?
近代化とは金儲けが優先される社会です。市場経済が中心の資本主義、つまり株式会社が中心となって、すべてを商品化し、すべてを分断し、すべてを金儲けのために奉仕させる世の中になったということです。
近代化によって、学問もまた分断化され、商品化されました。それが文系・理系で専門化された近代の大学です。
学問は本来、文系とか理系とか関係なく総合的に幅広く学ぶものでした。今でいう文理学部ですね。ところが近代になると理系・文系で疑うことなく、ただテキストを学んでいる。東大では「君たちは、ただそれを応用すればいいんだ」とテクノクラートを養成してきた。すなわち官僚と国民にものを考えさせない教育を始めたわけです。
「君たちは正解を解答するだけでいい」といった詰め込み偏差値教育で、有能で、言うことを聞く道具みたいな人をつくってきたから、日本人はものを考えなくなってしまった。そのため太平洋戦争ではコテンパンに負けましたし、自分で考えないからオリジナリティがなくなり、新しいものを生み出すこともできなくなっています。
――社会が行き詰まり、人々の閉塞感も増しています。
金儲けが優先される結果、人間は自分の利益しか考えられなくなります。自分が生き残ること、あるいは自分の欲望を満足させることが中心で、崇高な世の中をつくろうなんて意識は人の中から消えてしまいました。
真善美という根源的な生き方を踏まえていないものだから損得ばっかり考えているし、互いに対立して足の引っ張り合いをやり、妬み嫉みが横行する、こんな時代になってしまった。人間はどんどん小粒になり、しかもどんどん孤立させられ、分断させられ、貧富の格差が拡大しています。連帯しても誰も応えてくれないから諦めて、政治からも顔を背け、孤独な世界とバーチャルな世界で生きている人が増えましたよね。
私は機会あるごとにお金の弊害ということをずっと書いてきたのですが、お金がすべて、金儲けがすべてなんて社会は、理想の社会からするととんでもなくおかしいんです。
もちろん自分のやりたいことを実現するには経済力は必要ですし、市場経済そのものを全面否定する気はありません。でも、それが暴走するような資本主義社会はろくなもんじゃない。とくに今はグローバル資本主義ですから、ますます市場経済が力をもってしまい、お金がすべての社会になっています。
そのなかで、どう教育を考えていくか。私は、「お金がすべての社会を変え、よりよき社会をつくっていきたい」と考える人々を増やしていく教育が大事だと思うのです。
身につけるべき「学力」「人間力」「受験力」
――2018年の共著『「過干渉」をやめたら子どもは伸びる』では、「管理教育が進んだせいで、自分の頭で考える経験がほとんどない人たちが会社に入ってくるようになった」「管理教育ではない自由な教育を受けてきた人のほうが伸びる」とおっしゃっていました。
そうですね。自由な教育のほうが、自由にものを考えられる人が育つという話をしました。でも「自由に」だけでは足りないなと思うようになってきていまして。自由にものを考えるにしても、もっと大きな視野で物事を考えていく教育が必要ではないかと考えています。
人々が政治に目覚め、よりよき社会をつくろうとする強い使命感をもつ人が増えて、次の世界をつくっていく。それがなければ、お金がすべての社会は変えられません。これから求められるのは、人間の本当の幸せのために立ち上がれる人材です。このままでは人間は死滅していくだけですよ。
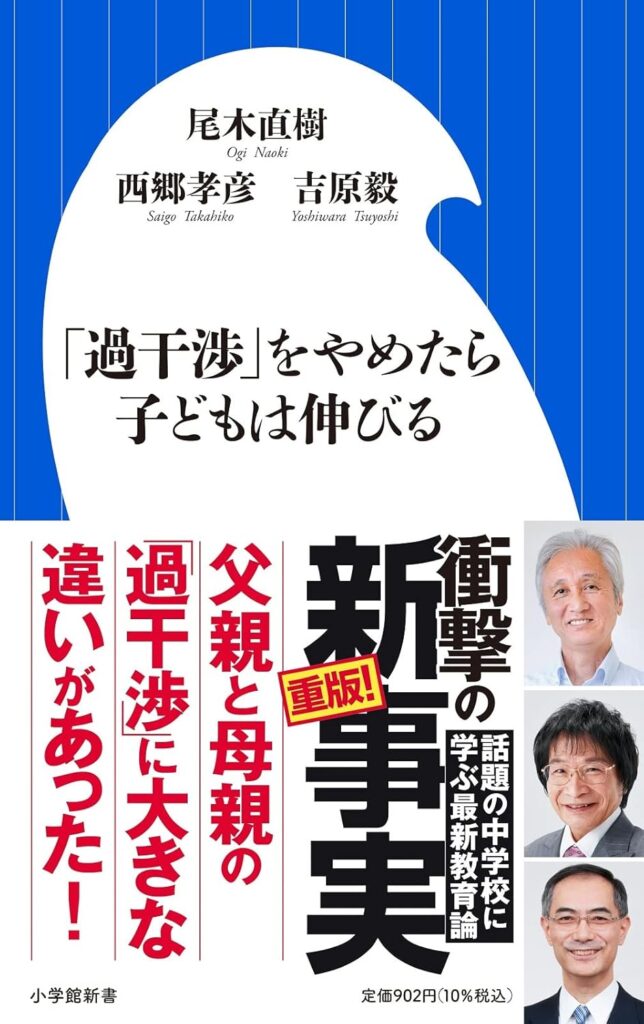
吉原さんの著作(共著)
『「過干渉」をやめたら子どもは伸びる』
(小学館新書)
――そうした人材を育てていくには、学校教育のあり方もまた重要になっていきますね。
私立有名校の多くが今は「グローバリズムとICTに対応できる力をつけて、未来に挑戦できる人間を育成したい」と言っています。対応できる力をつけるということは子どもたちが商品化するということですよね。確かにゲームのやり方を知らなければ戦えませんから、こうした力も必要でしょう。
受験のための教育も学校教育の一つの方向です。それには「学力」が欠かせませんが、麻布学園では「学力」と「人間力」の二つを目指すべきとしています。それと同時に、自らを商品として売り込んで、とりあえず権力を取りにいく力、つまりは権力奪取のための「受験力」も必要だと思っているのです。「受験力」なんて、真の学力でも、学問でも何でもないのですが、これからは「学力」「人間力」「受験力」の三つが必要だと。
――世の中を変えていこうとしたら権力は当然あったほうが有利です。その意味では権力奪取のための受験力も大事です。
もちろん根本には人間力と、それに基づく真の学問がなくてはならない。真善美を追い求めて、この世を変えていくために何が必要かという観点から学ぶ学問ですね。
――人間力を身につけていくには、どのようなことが必要でしょうか?
人間力に大事なものは何かといえば教養です。教養とは雑多な知識があり、それをただ百科事典のように述べることではありません。人間には、自分が接したさまざまな分野の事象や情報を関連付けて考え、一つの価値観に基づいて統合していこうとする知性が備わっています。社会に関心を持ち、理想や正義のために自らが考え、行動する中で、信念と情熱、そして総合的視点を持つ。ここに真の学問があり、その過程の中で、人格、教養が形成されるのです。
――そうした教養を身につけてもらうには?
古今東西の古典とか知識を学ぶだけでなく、幅広い視野をもつことが欠かせません。
自分の問題として現代社会のさまざまな状況のなかに飛び込んで、そこでいろいろな人々、いろいろな事象・現象と触れ合う。もちろん芸術に触れて芸術を知る、体育を通して自分の体と対話する、友人や大人と語らうなども大切ですし、世界で起こっているさまざまな問題に自分の問題として目を向けていくことも必要です。そこから得たものをどう統一的に考えていくかが、人間力にはまず大事だと思います。
そこに専門教育といわれるものが織り込まれていくことによって、教養の幅がさらに広がりますよね。専門知識も総合化したうえで、次に自分は何を求めていくのか。この部分を形成していくのが教育というもののあり方なのではないでしょうか。
つづきの記事はこちら【シリーズ】教育ってなんだ?――第3回 /本当の学問とは何か? PART2

よしわら・つよし 城南信用金庫名誉顧問。麻布学園理事長。1955年東京生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、城南信用金庫に入庫。2010年に理事長となり、2017年より顧問。同年に学校法人麻布学園理事長に就任。現在、千葉商科大学副学長・特命教授、横浜商科大学理事長も務める。著書『信用金庫の力――人をつなぐ、地域を守る』(岩波ブックレット)、『原発ゼロで日本経済は再生する』(角川oneテーマ21)、共著『「過干渉」をやめたら子どもは伸びる』(小学館)など。