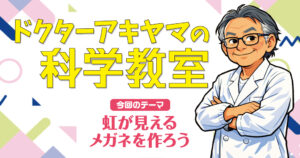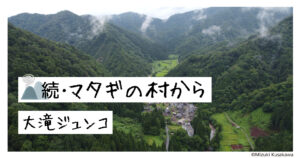第16回(番外編) ある日の「ニホンジンカ?」
国内の最高気温が更新された。群馬県の伊勢崎市で41.8度を記録したのだそうだ。聞くだけで気がとおくなってくる。私は暑いのが苦手で、夏は使いものにならない。なるべくじっとして涼しいところにいたい。
東南アジアに九年近く住んでいた。 いわゆる「常夏」である。トコナツ。
一時帰国したとき、帰るたびに行く床屋のオカミさんから
「でも冬はあるんでしょ」
と、しつこく聞かれた。
「ないっす」と言うと、「そうなのぉ?」訝しげな声をだした。そして、彼女はいつも私の注文よりも短く髪を刈り上げてしまった。納得していない証しだったのだと思う。ちなみに気象庁の2022年のデータによるとインドネシアの年平均気温(平年値)は29.3度だった。常に夏である。
そういう場所で長いこと過ごしていたのなら夏なんてへいちゃらであろうと、思われることがある。そんなことはない。暑さの質も違うし、現地で生まれ育った知人のなかにも「暑いのなんてだいきらい」と、言う人もいた。そんなものである。
そんなトコナツの国は、ココナツの国でもあった。
もう四十年も前のことである。その頃、私の暮らしていた街の飛行場に飛行機が到着してドアが開くと、近くに食堂があるわけでもないのに、ふわっとヤシ油の香りがした。今はどうか知らないが、その頃はそうだった。タラップ(今やよほど小さい空港か、なにか事情がなければお目にかかることもない)を降りると、すこし甘い香りが鼻腔をくすぐり、ああ、帰ってきた(長いこと住んでいれば、その国の国籍なんか持ってなくても「帰ってきた」と思うものである)としみじみ思ったが、それほど香り自体は好みではなかった。
長じて小豆島を訪れたとき、乗っていた船が近づくとごま油の香りが漂ってきて驚いたが、それにちょっと似ている。好きな人にはたまらないが、嫌いだったら別の意味でたまらないだろう。私はごま油は得意で、ごま油のオーデコロンをつけた人がいたら無意識に懐いてしまいそうなくらいだが、南洋に暮らしはじめたころはヤシ油のアロマをいささか苦手にしていた。
それでも、住んでいると日々慣れていって、当時通っていた学校の寮から抜け出して、街の屋台で買った、納豆みたいなテンペと呼ばれる食べ物や鶏を揚げたアヤムゴレンという料理から、ふわりとヤシ油の香りがたちのぼると、なんだか懐かしく食欲をそそられるようになった。そんなものである。
不思議なことに、だだっ広い飛行場で漂っていたヤシ油の香りなのに、街のなかがその香りで充満していることはたまにしかなかった気がする。もちろん、屋台なんかが密集している場所ではその香りが、そこそこ充満していることもすくなくなかった。
市場もそうだった。1980年代もまだ折り返していない頃、まだ中学生だった私が、市場へ行くと(同級生はまったく興味を示さなかったけれど、私は当時から市場が好きでしかたなかった)いろんな人から「どこから来たの?」と尋ねられた。
そういえば、この間の選挙のとき、海外から来た人へのサベツ発言をする候補者に抗議した人に対して、
「お前、何人だ?」
と、候補者の支援者が難詰するシーンが見られた。ダメなものに抗議するのに何人もなにもない。デマで特定の国の出身者を追い詰めるなんて、国境に関係なくダメなのは、たぶん小さな子どもでも理解できる。
ともあれ、私が市場で聞かれたのは、たいがい「あなた日本から来たの?」であった。
たまに「あなた日本人?」と聞かれることもあったが、それは、ほぼ、単に、お互いの言語を理解できるかどうかの確認であった。
さて、こういう質問をされた場合は、だいたい、
「こういうのは日本じゃ売ってないだろ、一つどうだい?」
みたいな営業トークの端緒だったりすることが割と多かった。
もちろん、当時、私の現地の言葉の能力は、「現地語の 道たづたづし」というか、拙いのは、今も変わらないのだけれど、相手もさるもので、現地の言葉が覚束ない相手にもわかるようにゆっくり嚙み砕いて話してくれたものだ。
その言葉にまんまとのって、鋭い目つきをした象型の急須を親に頼み込んで買ってもらったりした。象印ではなく、象の形の急須である。これでお茶を淹れると、象の鼻からジャーっとお茶が出てくるのである。こういう急須を中学生が使うことは日常にはほとんどなくて、それは五十代になった今も変わらないが、あの時、私に売り込んできたおばちゃまの自信満々の笑顔は忘れられない。
選挙中の「お前、何人だ?」という、ひどい発言が話題になるにつれ、急に思い出したことがある。何度もふりかえってきたが、今回は、たぶん、今まででいちばん整理して、輪郭をはっきりさせることができた気がする。
1984年だったのではないかと思う。インドネシアに住んでいた。
親について市場へ行った。市場の後、どこかで食事をすることになっていたのではないかと思う。
むせかえるような人いきれのなか、うずたかく積まれた衣類の奥から、一人のおじさんが顔を出してきて、私を手招きした。知らない人に手招きされた場合、ほとんど、良からぬ展開にしかならないことを、中学生なりに知っていた私だったが、おじさんの顔を見ると、ただならぬ真剣さ。これは知らんぷりをしてはならない、と思ってしまった。
混み合った市場でずんずんおじさんに向かっていくこともできず、人をなんとかかきわけて近づいていった気がする(ただ、そんな人ごみの中で、なぜおじさんの手招きが見えたのかわからない)。ずっと手招きをやめないおじさんに、私は笛吹男の音色に導かれた子どもみたいにフラフラと近づいていった。
そしておじさんの目の前にたどり着くと、
「ニホンジンカ?」
と聞いてきた。私はうなずくと、おじさんは、だしぬけに私の腕を摑んだのである。
私は声も出なかった。強い力で、このまま、自分の背丈よりも高く積まれた衣類の奥へと引っ張り込まれてしまうのではないかと心配になった。ふりはらおうと、二の腕にグッと力を入れようとすると、おじさんが言ったのである。
「センソウ」
「え?」
「センソウアッタ」
「はい」
「ダイトーアセンソウ」
恥ずかしいことに、十三歳になったばかりの私は、あの戦争を大東亜戦争とも呼ぶことを知らなかったから「どの戦争のことなのかしら」と、すこしポカンとしてしまった。
「ダイトーアセンソウ、ワタシ、ニホンノヘイタイ」
「え?」
「ダイトーアセンソウ、カナシイハナシ」
それだけ言うとおじさんは、妻らしき、一見して現地の人とわかる女性になにやら囁き、私の肩をポンッとたたいて衣類の奥に引っ込んでしまった。
妻らしき女性は、すぐに他の客の相手を始めて、私はすごすごとその場所を離れた。そのあと、たぶん、近くの餃子の店に行ったと思う。たっぷりの刻み酢漬けのニンニクを醤油にときながら、私はずっと、あのおじさんのことを考えていた。餃子はいつもどおり旨かったはずだが、食べすぎてもいないのに、胸焼けみたいに、ずっとモヤモヤしたものをかかえていたと思う。

太平洋戦争で日本が負けた後、南洋の国々から帰らなかった日本兵がいたことをその後、父から聞いた。おじさんは、そういう人の一人だったのかもしれない。
こういう話をすると、時々「日本に帰ることなく、南洋の国々の独立を手伝った日本兵がいた、日本兵すごい、日本人すごい」みたいな話をしだして、話を明後日のほうへ向かわせる人がいまだにいる。だが、独立軍に加わった理由は人それぞれである。 ニホン兵、ニホン人全体、のことではあるまい。
まあ、しかし、この日の「ニホンジンカ?」ほど、人生で「◯◯人」を意識したことはない、ような気がする。生まれ故郷だとか、自分のルーツに誇りをもちたい気持ちは誰でも少なからず持っているだろう。まぎれもなく、個人をつくりあげる大事な要素だ。だからこそ、なおさら、それを根拠にサベツするなんて言語道断。
先の選挙であちこちでとびだした「お前、何人だ?」には、まあ、「地球人ですけど」とお返事したい。
この連載では、いろんな国からやって来てその母国の味を提供してくれるお店をたずね、なぜ、毎年夏の最高気温を更新するのに環境問題にも取り組まず、ディスクリミネーション発言をしまくるような人が議員になれるような国まで来てくれて、美味しいものを作ってくれているのか、その経緯や理由を尋ねるのが目的だ。
ちなみに、今、日本にはどのくらいの外国人が料理店を開いているのか調べたみたが、はっきりした数字はわからなかった。ただ在留資格のうち「経営・管理」を有している人は四万人近くいる。そのうちのどのくらいがレストランなのだろうか。
一方で、海外にある日本人が営む日本食レストランはというと、二年前のデータで十八万七千軒もあるのだという。そのうち一割程度が日本人が営んでいて、ほかは違うらしい。ということは二万人くらいの日本人が海外で日本料理の店をやっていることになる。
選挙で「お前、何人だ?」と言って恫喝していた人は、この二万人が海外で、おなじように「お前、何人だ?」という言葉を聞かされる場面を想像できないのだろうか。
私の家ではすき焼きに白菜を入れることは一切なかった。大人になって白菜を入れる家庭があることを知って驚いた。どちらもニホン人の家庭である。鮨を食べないニホン人もいれば、納豆が大嫌いなニホン人もいる。辛いのが苦手なタイ人もいるし、ジャガイモが得意じゃないアイルランド人もいれば、家系ラーメンの苦手なハマっこもいる。故郷は大事だけれど、そこに線を引いて、誰かと区別することには意味はない……。
そういうことを考えながら、つぎは、どこの出身の人の店に行こうかなとアレコレ考えつつも、暑過ぎて外に出られない私がいる。

タイトル、本文内イラスト=筆者
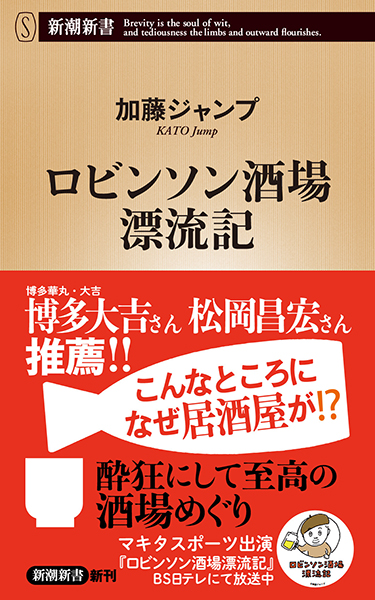
かとう・じゃんぷ 東京都世田谷区出身。横浜&東南アジア育ち。一橋大学法学部卒業。一橋大学大学院修士課程修了。1997年新潮社入社。その後フリーランスのライターに。テレビ東京系「二軒目どうする?〜ツマミのハナシ〜」に準レギュラー出演中。著作に『コの字酒場はワンダーランド ――呑めば極楽 語れば天国』『コの字酒場案内』(ともに六耀社)、漫画『今夜はコの字で』(原作担当、土山しげる作画、集英社インターナショナル 、集英社)、『小辞譚』(オムニバスのうち1作品、猿江商會)など。最新刊に『ロビンソン酒場漂流記』(新潮新書)。