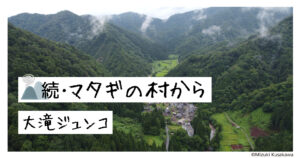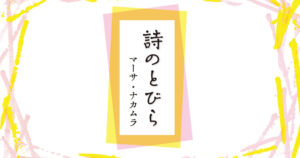第12回 トイレの「男女平等」ってなんだろう?
今回はトイレにおける「男女平等」について考えてみたいと思います。
公共のトイレで、男性用は人がどんどん流れていくのに、女性用は外まで長蛇の列。そんな場面に遭遇したことはありませんか? 高速道路のパーキングエリアや駅の構内、イベント会場、ショッピングモール等々で、私もたくさん目にしました。
正直、「男女平等」などという言葉は使いたくありませんが、トイレに関しては明らかに女性のほうが「不利」な状況です。
では、実際のところ男女のトイレの数はどうなっているのでしょう。
日本で最も乗降客が多い「新宿駅」、日本最古の鉄道駅「新橋駅」、山手線の最新駅「高輪ゲートウェイ駅」(いずれもJR東日本)で調べてみました。






表にあるとおり、いずれの駅も男性用のほうが便器の数が多いという結果でした。新宿や新橋などの昔からある駅は致し方ない部分があるのかもしれません。しかし、21世紀に誕生した高輪ゲートウェイ駅でも、差は縮まっているとはいえ、総数としては依然として男性用のほうが多いのです。昨今は、利用者のニーズを把握した上で多様な人に配慮して設計するケースが多いはずですし、当然トイレもそうだと思っていたのですが……。
それぞれの駅のトイレ案内図は充実していました。高輪ゲートウェイ駅のトイレ案内図は、便座の向きやドアの開閉ボタン、トイレットペーパーや水洗センサーの位置も分かるようになっています。こんなに進化しているのに、相変わらず女性用トイレが少ないのは不思議です。
女性用トイレに列ができる要因の一つは、用を足すのに時間がかかることです。ドアの開閉、衣服の着脱、生理中も手間がかかりますし、乳幼児には、多くの場合に母親が付き添っています。最近では、子どもと一緒に入れる個室を設けた男性用トイレもありますが、その割合はまだまだ低いのが実情です。
こうした状況から考えると、男女ともに頻繁に利用する公共のトイレは、女性用を多くするのが「平等」ということになりそうですし、私はそうしてしかるべきだと思います。そもそも男性は小用の場合、「さっと済ませられる」のに、男性用のほうが多いというのはどうにも合点がいきません。
一方、洋式便器のある個室タイプは男性用が圧倒的に少ないことが分かりました。実は、トイレの困りごとに関する調査にご協力いただいた男性から、「近ごろは仕切りのない小便器を使うのに抵抗がある男性がいるのか、個室のトイレが混みあっている。だから、バリアフリートイレに駆け込む人もいる」という話を聞きました。 単純に便器の総数だけで比べると、大事なことを見落としてしまうかもしれません。

とはいえ、多くの場合、女性の方がトイレの待ち時間は長い——。そんな状況を打破できそうなトイレがありました。大きなイベント会場が併設された比較的新しいビルのトイレです。イベントの内容に合わせて壁を移動させ、男女のトイレの比率を変更できる仕組みで、作りによっては中央部分をオールジェンダートイレにできる場合もあるそうです。
来場者の年齢や性別があらかじめ予想できるイベントの場合、男女のトイレの比率を変更できる仕組みは有効だと思います。駅のトイレも曜日によって男性用と女性用の数を変えられれば、トイレの混雑は防げるかもしれません。
ところでトイレについて話していると、快適なトイレほど、「着替え」「スマホ使用」「化粧」「ほっと一息」といった本来の目的以外で利用する人が、男女を問わずいることに気付きます。
都市部の一部のトイレには、個室の使用時間やほかの個室の空き状況が表示される装置が設置されています。一定時間を超えて使用していると注意喚起される仕組みで、これは安全対策にも一役買いそうです。
公共のトイレは、使う側のマナーも問われます。

ちなみに、平日の夕方、出張帰りと思しきビジネスマンでごったがえす名古屋駅の新幹線改札内のトイレは、男性用が多いにもかかわらず、「男性用だけ」外まで長蛇の列ができていました。また、今回調べた3つのJR駅のトイレには、いずれも「女性用だけ」にスタイリングコーナーやパウダーコーナーがありました。身だしなみを気にするのは女性だけとは限らないように思うのですが……。価値観が多様化する今、トイレの「男女平等」をどうはかるのか、なかなか奥が深い問題です……。
さて、男女のトイレ数の問題については、今年7月から「女性用トイレにおける行列問題の改善に向けた関係府省連絡会議」が開催されるなど、国も解決に向けて本腰を入れています。その動向についても注視していきたいと思います。
〈車いすユーザーとその援助者の方のトイレの困りごとアンケート〉

いしかわ・みき 出版社勤務を経て、フリーライター&編集者。社会福祉士。重度重複障害がある次女との外出を妨げるトイレの悩みを解消したい。また、障害の有無にかかわらず、すべての人がトイレのために外出をためらわない社会の実現をめざして、2023年「世界共通トイレをめざす会」を一人で立ち上げる。現在、協力してくれる仲間とともに、年間100以上のトイレをめぐり、世界のトイレを調査中。 著書に『私たちは動物とどう向き合えばいいのか』(論創社)。