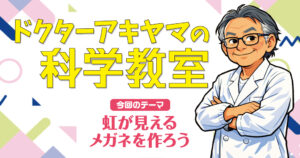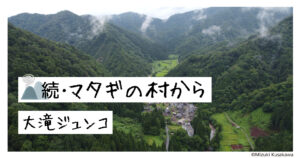第10回 INAXライブミュージアム「トイレの文化館」で日本のトイレを学ぶ①
今回は、今年4月17日にオープンしたINAXライブミュージアム(愛知県常滑市)の「トイレの文化館」へ! なぜ、日本のトイレは世界からも注目されるに至ったのか――。その歴史について学んでいきたいと思います。

撮影:梶原敏英
案内してくれたのは、同館学芸員の立花嘉乃さん。
「現在、海外から観光客の方がたくさん日本に来られますね。彼らが空港に来てまず驚くのはトイレです。公共トイレにもかかわらず温水洗浄便座がついているなど高機能で快適。もちろん清潔ですので、日本のトイレは世界からも注目を集めています」
その理由は、日本の「清浄」を重んじる文化と「おもてなし」の心にある、と立花さんは言います。
「日本では、単に〝清潔〟というだけでなく、精神的な清らかさを大切にしてきました。昔のトイレは非水洗ですから、実際には臭いもしたわけです。けれども、絵付けをした便器をしつらえるなど視覚でそれを補おうとしていました。おもてなしの心を感じます」

(右)染付花
いずれも『還情園池紋製』銘、六代加藤紋右衛門、明治時代後期
撮影:梶原敏英
私は思わず膝を打ちました!
特に「清浄」。この言葉は日本のトイレ観を考える上でとても大切なキーワードになりそうです。今後の回であらためて触れますが、日本における下水道の普及は決して早くはありません。にもかかわらず、世界で注目を集めるまでのトイレ文化を築くことができた背景には、「清浄」の精神を育んできた日本人の心があったのかもしれません。
さて、日本のトイレは、一体どのように発展してきたのでしょうか。
歴史をさかのぼると、竪穴式住居近くの遺跡から人間の糞の化石が見つかっており、縄文時代前期から「決まった場所で排泄する」という習慣があったのではないかと考えられています。
立花さんによれば、「平安時代になると、一部の貴族たちは持ち運べる木製のトイレを家の中で使用し、排泄物は外に捨てていました。史料の絵巻を見ると、庶民は塀の前など決まった場所で用を足していました。尻拭きに使った木や竹の棒、紙片が散乱しているうえ、高貴な人しか履かない高下駄を、糞尿で足が汚れないようにと、大人のみならず子どもも履いていることから、その場所がトイレであることがわかります」とのこと。なるほど!
さらに鎌倉時代になると、甕[かめ]や桶[おけ]に糞尿をため、それを畑の肥料として使用するようになります。和式の便器の前方には木の板がありました。その理由には諸説ありますが、尿の飛び散りを防ぐためだったという説が有力とされているそうです。糞尿が肥料にするための「大切な資源」として集められていたとは! このころから、〝もったいない精神〟も育まれていたのかもしれません。
同館には、江戸城本丸の「御休息之間」(トイレ)で将軍が利用した大便器である樋箱[ひばこ]が、残されていた絵図面をもとに復元され、展示されています。当時は箱に砂や灰を入れ、音を軽減させたり、掃除しやすくしたりするなどの工夫がされていました。また、臭いを少しでもやわらげるために杉葉などを入れていました。

撮影:梶原敏英
ちなみに、同じ日本でも東と西では、排泄文化がかなり違っていたようです。江戸時代で比較すると、江戸のトイレは板壁の簡素な造りで扉も半分くらいまでしかないのに対し、京阪のトイレは土壁で、扉も天井まで届く造りでした。「トイレの文化館」にはそれらの模型も展示されています。
また、尿は江戸では肥料としてあまり使われなかったそうですが、京阪では利用されていたことから、街中の店先には「どうぞ、ここでしてください」と、立ち小便用の甕や桶がおいてあったとか。糞尿は売れるし、街を清潔に保てるので、店の人にとってもメリットがあったのでしょう。今風に言えば、ウィンウィンの関係。究極のSDGsなのかもしれません。
さらに、女性が「立って小用を足す」のは西日本では日常的に見られる光景だったのに、江戸ではその習慣がなかったそうです。江戸時代の末期には陶製の便器が登場しますが、口が大きく開いた小便器は西日本では男女兼用だったそうですから、狭い日本でも〝ところ変わればトイレ事情も変わる〟のですね。

こうした違いには都市の成り立ちや人口なども関係するのでしょうが、なかなか興味深いところです。排泄物を〝臭くて汚いもの〟として忌み嫌うのではなく、肥料として、資源として利用してきた先人の姿勢には学ぶべきところがある気がします。
現在に通じる水洗トイレは、産業革命以降のイギリスで登場します。次回(第11回)では、日本の水洗トイレの普及と、その後、飛躍的に「快適なトイレ」が広まっていった過程を、立花さんの解説をもとに紹介していきます。
所在地:愛知県常滑市奥栄町1-130 TEL:0569-34-8282
休館日:水曜日(祝日の場合は開館)、年末年始
共通入館料:一般:1000円、学生 800円 、中高生:500円、小学生:250円
ホームページ:https://livingculture.lixil.com/ilm/
Facebook:https://www.facebook.com/LIXIL.culture
Instagram:https://www.instagram.com/lixil_inaxmuseums/

いしかわ・みき 出版社勤務を経て、フリーライター&編集者。社会福祉士。重度重複障害がある次女との外出を妨げるトイレの悩みを解消したい。また、障害の有無にかかわらず、すべての人がトイレのために外出をためらわない社会の実現をめざして、2023年「世界共通トイレをめざす会」を一人で立ち上げる。現在、協力してくれる仲間とともに、年間100以上のトイレをめぐり、世界のトイレを調査中。 著書に『私たちは動物とどう向き合えばいいのか』(論創社)。