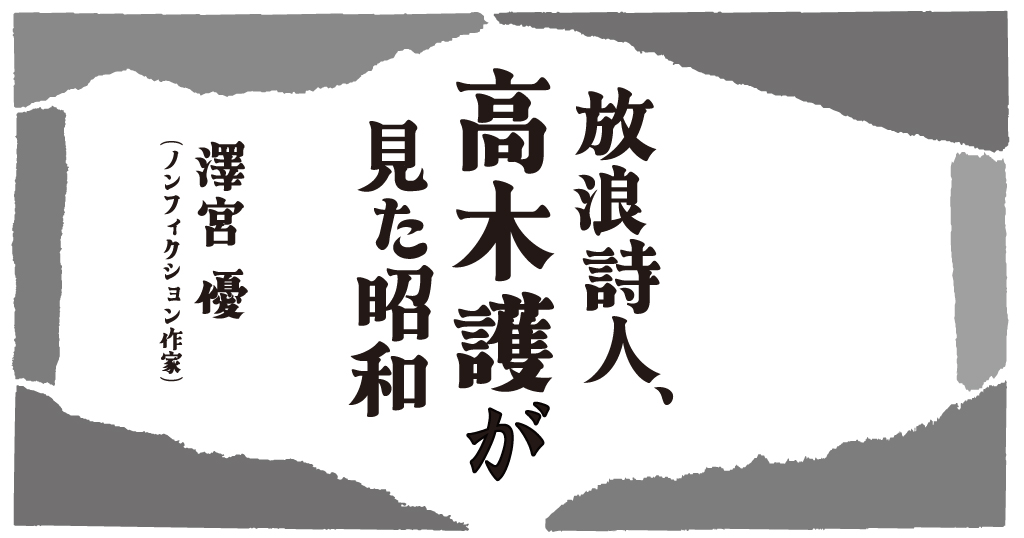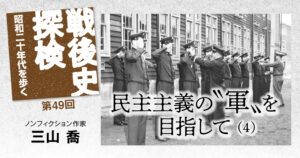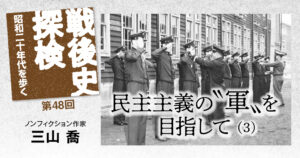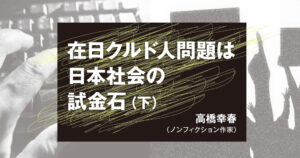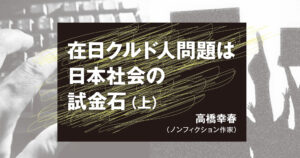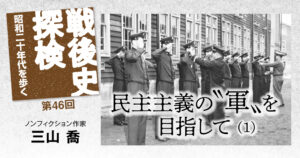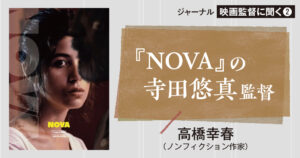前回の記事はこちら「放浪詩人、高木護が見た昭和◎澤宮優――第1話」
今年2025年は昭和でいうと百年に当たる。昭和前期、大正デモクラシーは軍部の台頭でかき消され、強烈な翼賛体制に行きついたあげく、壊滅的な敗戦へと向かった。戦後は、連合軍による占領、国際社会への復帰を経て、新幹線や東京オリンピックに沸いた。そんな時期に、一人の詩人が世の中の端っこから日本社会を見つめることを始めた。詩人の晩年、深い交流があった澤宮優さんが、詩人の言葉を紹介する(全四話)。
学生運動とテロリズム
昭和四十五年(1970)三月に大阪市で日本万国博が盛大に開催された。学生運動も70年安保を控え、過激化して行った。四十四年(1969)一月には紛争中の東大に機動隊が突入、この年東大の入試は中止された。六月には新宿駅西口広場での若者たちのフォーク集会に七千人が集まったが、これも機動隊と衝突し、六十三人が逮捕された。国の強権的な弾圧も強まり、学生たちは過激になった。やがて学生たちの組織は分派を起こし、セクト同士の対立が激化し、テロが生まれる。
この頃、高木護は東京都大田区の六畳一間のアパートで暮らしていた。結婚して、住まいを得て、腰が据わったのか、自らの放浪体験を描いた『放浪の唄』が好評で版を重ねていた。
高木はこの時代をどう見ていたのか「日録」から辿ってみる。
〝週刊読書人〟の〝テロルの荒廃、思想の荒廃〟を読む。おうよそ、ひとり合点というやつで、つまらない。テロルの意味を拡大視してはいけない。つまり、テロルには、みじんも思想がないということだ。(昭和44年10月1日)
きょうは、反戦デーとか。学生ゲリラのままごとに、いい口実で官権の目が光る。哀しいかな。ナンセンスというなかれ。(同年10月21日)
これらを総合して、この時代を俯瞰する。
テレビをつけっ放しにして、あれこれまとまりもないことを思っていると、何となく息苦しく、それからわびしくなってくる。はなやかなものと、そうでないもの。ウラとオモテの人生の、人間のあり方が、わからなくなってくる。(昭和45年1月2日)
万博という上っ面の華やかさの陰で、戦後の日本の抱える矛盾は深刻化していた。沖縄返還も秒読みだったが、「基地抜き、核抜き、本土並み」という政府の公約は裏切られる。空疎な明るさから隠れた影にあるもの。そこに目が届かず、一面的な発展に光を当て、浮かれた時代が高度経済成長であると高木は見抜いていた。


このときの負の遺産のつけを現代人は今もなお支払わされている。そんな高木が、この頃、マムシに追いかけられる夢を見た。これも意味深長な内容であった。
マムシと添い寝
というのも、高木はマムシと添い寝をした仲だったからである。彼が上京前に宮崎県と鹿児島県の境を歩いているときだった。夕方になって雨が降ってきたので、彼は丘陵に掘られた芋穴に入って夜を明かすことにした。芋穴は丘陵沿いに作られ、農家が畑で採れた芋をしまう貯蔵穴である。小さな穴で人がようやく蹲って寝ることのできる広さしかない。
穴の中は真っ暗で何も見えない。高木は雨の降る音を聞くうちにすぐに眠りに落ちた。夜中に何度か首筋にひんやりとした感覚があったが、手で払い、疲れのために再び熟睡した。朝になって、穴に光がさすと、高木は仰天するばかりに驚いた。彼の傍に三角頭の蛇がとぐろを巻いて眠っていたからである。臭みのある独特の匂いで、マムシであることがすぐにわかった。しかしマムシは飛びかかってこようとはしなかった。高木は回想する。
「ひやっとしましたが、向こうも私を見て何もしないのです。大きな奴が寝ているというくらいに思ったのでしょう。動物や生き物はこちらがじっとしていれば何もしないと知りました」
高木はマムシの穏やかな顔を見ているうちに、そのまま穴でじっとしていることにした。マムシは高木と添い寝をしてくれたのだ。やがて高木は思った。この場所はもともとマムシの寝床だった。それを自分が後からやって来て、横取りしてしまった。マムシもさぞ居づらかったことだろう。いつしか彼は眠っているマムシに向けて手を合せていた。
「断りもせんで、お前の家に泊まりこんだ。知らんじゃったけん、こらえてくれ」
そう言って穴から出た。高木は子どもの頃、野原で蛇を振り回してみたり、飲み込んだ蛙を吐き出させたりしたことを思い出していた。しかしこのとき以来、蛇も可愛いなと思うようになった。これから蛇と出会っても殺生はすまいと誓った。高木は私に語った。
「マムシは子を孕んでいるときは噛みつきますけど、いたずらなどしなければどうってことはないです。足音がすれば向こうが逃げます」
私は朝日新聞元論説委員で「天声人語」を長らく担当した辰濃和男に取材したことがある。彼は「天声人語」で高木を何度も取り上げているほどの高木ファンである。
辰濃は、開口一番「ミミズと人間、どっちが偉いと思うか」と私に聞いた。戸惑っていると、彼は教え諭すように「マムシの添い寝」を話し始めた。
「高木さんは、断りもせんでマムシの家に泊まりこんだ。マムシはお前たちこそ最近来たんじゃないかという思いだったんです。爬虫類は人間よりも長い歴史を持っていますからね。そう考えると高木さんのもつ野生の輝きには学んでも学びきれない、及ばないものを感じます。私は人間になる修行をさせてもらっているんです」
高木は「日録」で、テロルはひとり合点でみじんの思想もないと書いたが、その根にはマムシとの添い寝の経験が横たわっているように思われた。マムシの命も人間の命も、その尊さに差は無い。テロも同様で、自分とどんなに思想が違っても、命を奪う理屈はあってよいはずがない。命そのものをぞんざいに扱う時代の到来を彼は危惧していたのだ、
それは芋穴に入ったとき、そこにマムシがいれば、後から入った人間が蛇を追い払い、殺してしまう行為と同義である。それと同様な理屈を高木はテロに見いだしていたのではないか。
しかし自然を軽視した人間の横暴な振る舞いに、マムシもついに友人の高木に夢の中で刃を向けてきた。前述したマムシに追いかけられる夢は、そんなことを暗示する夢だったのではないだろうか。
高木は晩年に焼酎を飲むと決まって口癖のように語った。
「世の中で人間が一番横着になっています。もう地球は絶滅寸前です。人間は滅んで、あとの世は虫に任せればよか」
その言葉が真実味を帯びて、日々、私たちの身にひしひしと迫っている。

(つづく)

さわみや・ゆう 1964年熊本県八代市生まれ。青山学院大学文学部史学科、早稲田大学第二文学部日本文学専修卒業。戦前の巨人の名捕手吉原正喜の生涯を描いた『巨人軍最強の捕手』(晶文社、2003年)で、第14回ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。主な著書に『戦国廃城紀行 敗者の城を探る』(河出文庫)、『昭和十八年 幻の箱根駅伝 ゴールは靖国、そして戦地へ』(集英社文庫)、『イラストで見る昭和の消えた仕事図鑑』(角川ソフィア文庫)、『イップス 魔病を乗り越えたアスリートたち』(角川新書)、『あなたの隣にある沖縄』(集英社文庫)など。 最新作に高木護が経験した約120種の仕事を中心として、高木の半生を描いた『昭和の消えた仕事物語』(角川ソフィア文庫)がある。
バックナンバー