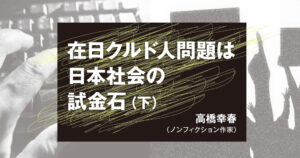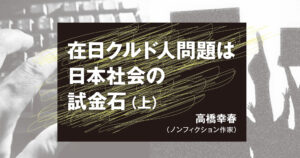第1話 成田空港第三滑走路で消える集落と二人のカメラマン
成田空港(正式には成田国際空港)の拡張工事が進むなか、移転によって消滅する集落がある。インバウンド需要増大という光の陰で、長年暮らしてきた土地から離れざるをえない人たち。二人のカメラマンが、消えゆく集落を、そして住民たちの複雑な思いを記録にとどめようとしている。国策によってふたたび揺れる成田を、澤宮優さんがルポする。
成田空港に隣接する町に千葉県山武郡芝山町[しばやままち]と香取郡多古町[たこまち]がある。この二つの町にあるいくつかの集落は、2029年3月31日に竣工予定の第三滑走路(C滑走路とも表記)建設のため数年以内に消え去る運命にある。
成田国際空港第三滑走路はインバウンド政策を推し進める日本が、空港の機能強化のために新たに建設するものだ。約3500メートルの新滑走路を作ることで、これまでの年間発着回数30万回が50万回に増えることが見込まれる。多くの訪日外国人の便宜を図るという目的がある。
これに伴い建設予定地の芝山町の加茂[かも]、菱田東[ひしだひがし]、中郷[なかごう]、中谷津[なかやつ]の四集落、約130戸と、騒音対象地区となる多古町一鍬田[たこまちひとくわだ]の約55戸は滑走路建設までにすべてが他の場所へ移転しなければならない。多古町一鍬田では土地が削られ、そこに空港関係の倉庫が作られる予定である。芝山町は滑走路の敷地になり、集落そのものが姿を消す。ともに山や谷に囲まれた中で田圃が広がる昔ながらの農村地帯で、そこで人々は伝統習俗などの行事を大切にして生きてきた。かつて日本のどこでも見られた地方の光景がそこにあった。それも間もなく見られなくなる。
人々は空港側の用意した集団移転の場所に移るか、家族などを頼って個別に移転するかの二者択一を迫られる。住み慣れた土地を離れる人々の胸に去来するものは何だろう。
2024年7月から筆者も何度かこの地域を訪れたが、そのたびに土砂工事の箇所が増え、赤土がむき出しになり、耕作が行われていた田圃が徐々に荒れ地になっている。まだ存在していた先祖代々の墓も移転して、集落の変貌の大きさも増している。刻一刻と集落の消滅が迫っている事実を突きつけられる。

そんな人々の気持ちを汲み取るように、集落の光景を撮り続ける二人のカメラマンがいる。多古町一鍬田を写真に撮る齊藤小弥太[さいとう・こやた](37歳)と芝山町の移転対象集落を動画で撮影を続ける株式会社シマワークス代表の中島誠二[なかじま・せいじ](72歳)である。
齊藤はモノクロで撮影し、30点の写真は「土地の記憶」と題され、2023年、ドキュメンタリー分野で活躍し、かつ新進写真家を奨励する第18回「名取洋之助写真賞」(公益社団法人日本写真家協会)「奨励賞」を受賞した。
中島は千葉県の各地域の民俗行事、祭礼など、一貫して庶民の生活に視線を向けたビデオを残すベテランカメラマンである。
二人に共通する思いは、この暮らしの光景を後世に伝えたいという強い思いである。彼らの目に変わりつつある集落はどう映っただろうか。
二人のカメラマンの目を通して、この集落での残り短い生活を送る人々の心情を追ってみた。
多古町一鍬田 齊藤小弥太の思い
多古町は「多古米」という良質な米を産出し、ブランドになっており、一鍬田でも米作りは盛んである。また昔ながらの街道も多く、牛馬を守るための馬頭観音が何体も並んでいる。
齊藤が一鍬田を初めて訪れたのは2019年で、「多古町城郭保存活用会」から集落にある城跡の写真を撮って欲しいと依頼されたのがきっかけである。そこで集落が第三滑走路建設の影響を受けることを知った。
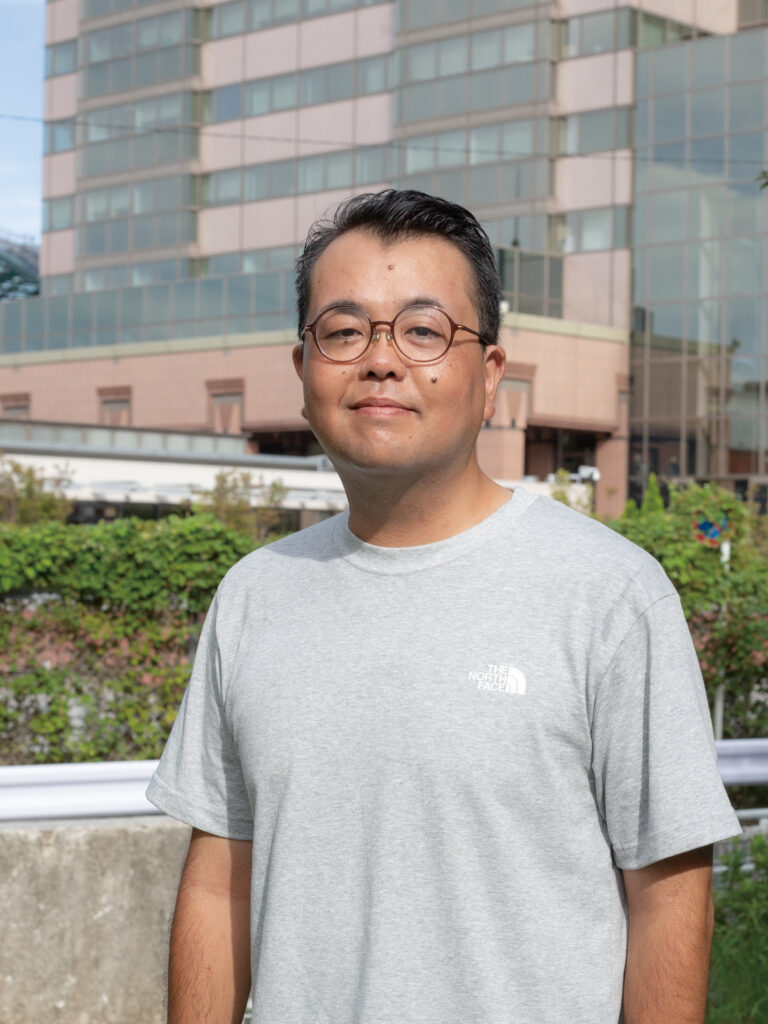
一鍬田の印象は、昔ながらの農村の集落が広がり、家も長屋門など古い造りが多く残っており、一昔前の日本の光景を連想できるものだった。一鍬田は多古町の中心部から離れている。そのため非常に静かだった。そのときは集落を撮り続ける気持ちはなかったが、やがて彼の心境を変える出来事が起こった。
農道で廃城の壕跡を撮影しているとき、一台の軽トラックとすれ違った。運転席には農作業衣姿の初老夫婦が乗っており、二人がとても朗らかな表情で話をする姿が、齊藤には印象的に映った。
「私の真向かいからふらっと軽トラが走ってきたんです。とても睦まじくて、すごくいい表情だなと心打たれました。このときこの土地に生きている人を通して、この集落の自然を見つめたい気持ちがごく普通に湧いてきました」
齊藤は千葉県の都市部に住んでいるため、人が介在しない自然の風景が自分の概念の中に作られていた。山なら山だけ、川なら川だけの自然の光景が浮かび、人と一体になった自然風景の写真という概念がなかったのである。しかし一鍬田の自然に溶け込むような老夫婦の姿を見て、自然の光景に人間が介在することで作品がさらに生き生きしてくることを知った。以来彼は一鍬田に惹かれ、月に五回足を運び、集落の写真を撮るようになった。以来延べで百回以上も足を運んでいる。
一鍬田は空港に近いが、この地では空港建設反対運動の「三里塚闘争」とは無縁だった。
昭和40年代に闘争が激化したときも、新左翼の活動家が集落に逃げ込んで来ることを土地の人々はひどく嫌ったため、闘争に巻き込まれなかった。そのため後に外部から人がやって来ても、活動家や土地収用を行う「新東京国際空港公団」(以下、公団)の関係者かと疑う風土がない。そのため齊藤は集落で地元の人とすんなり会話ができたのである。
齊藤は語る。
「一鍬田の人たちはすごくいい方たちで、警戒されませんでした。ただ移転の話はお金が絡むことなので集落民同士でこの話はしづらかった面があったようです。山や畑を持っている人といない人では補償額が違いますからね。そのため自分たちの思いを伝える場所がなく、そこに第三者のぼくが来たので、感情を吐露できると思われたのでしょう」
農村を襲う高齢化問題
齊藤が一鍬田に初めて行ったときは、72世帯が暮らしていた。しかし今秋には、子どもや親戚を頼って早々と移転する人もおり、33世帯に減っていた。以前親しく話をした人たちも、次回来たときには集落にはいなかったというケースもある。そこには高齢化と農業の不振があり、農業を手放して新しい生活を早く始めたい人たちもいたからである。家に農業を継ぐ後継者もいない。戦後満州から引き上げて、この土地を開墾して頑張ってきたが、農業の収入も減り、年も取ったので、潮時と辞める決心をした人も少なくはない。
そこには切実な生活の問題があった。その人はこう本音を洩した。
「周囲では農業を辞めた人も多くいます。でも自分だけはここに残ってやってきたけど、移転の話がきて、子どもにもまとまったお金を渡せるし、農業を辞めるにはいい機会になった」
一方、先祖代々五百年にわたってこの地で暮らした人は、土地を去ることに気持ちの整理がつかないでいる。彼は齊藤に呟いた。
「土地の歴史が自分の代でスパッと終わってしまうのが、大変心苦しい」
たとえばこの地で無農薬による野菜栽培を行ってきた人は、新しい土地で同じことを始めれば軌道に乗るまで三年はかかるという。そうなると新しい土地で最初からやるには無理がある。移転先で同じ方法でできないのなら、もう辞めるしかない。公団側が代替地を用意しても解決する問題ではない。自分はこの土地にいられる限界まで、農業を続けると話してくれた。
このようなことを見聞きすると、土地を離れる人々の思いは一言では言い表せないことが齊藤には見えてきた。
心のグラデーション
人によって思いの違いはあっても、農家の人々の根底には「できるものなら農業を続けたいが、時代の変化で苦しくなった。移転には反対しない、何ともやりきれない思いもある」という無念さが齊藤には感じられた。
ある日、齊藤がさつま芋畑の写真を撮っていると、年老いた女性が単車で近づき、手に持ったさつま芋の何本かを彼に渡した。彼女は「うちの家を撮りに来てよ」と声を掛けた。それは四十年間ひたすら野菜を売って、建てた家だという。家に行くと、使い古した農機具とともに、コンテナには収穫されたたくさんのさつま芋があった。

(齊藤小弥太「土地の記憶」より=齊藤氏提供)
家はむくり屋根という、勾配が円形の一部のように膨れ上がり、下方に下がっていく独特の作りをしている。これは京都の商家で見られる屋根で、柔らかな曲線を描くのが特徴だ。
仕事場では、先ほど声をかけてくれた女性がさつま芋の箱詰め作業を行っていた。そのとき齊藤は彼女のある指の第一関節が外側に曲がっていることに気づいた。これは「ヘバーデン結節」という激しい手作業をする人がかかる病気である。彼女が言うには、ここらの農家は皆、このような指になり、指のきつい痛みに耐えて作業を続けている。彼女は齊藤に訴えるように言った。
「自分は悔しくて仕方ない。四十年間野菜を売り続けて、孫に誇れる家を建てて、その借金もやっと返し終わった。そうしたらこの土地を出ていかなければならない。だけど自分は出ていきたくない。納得できるまでここにいる」
ある老婦人は結婚したのち、夫と朝から日の暮れるまで大根を作った。トラックに積んで毎日のように東京に売りに行った。お金を少しずつ貯め農協から金を借りて、ようやく家を建てた。しかし夫は脳梗塞による麻痺のため、大根作りができなくなった。毎日の夫のささやかな楽しみは杖をつきながら家の近くの林道を歩くことだった。
夫にとって見慣れた愛着のある場所を散策することがもっとも心を癒やされる時間だった。道は防風林の役目を果たす巨木に囲まれている。その風景を夫は好んだ。しかし道は砂利道だから滑りやすい。夫が躓かないように彼女は道を整備した。その間も妻は夫を介護し、農業を続けた。その夫も四年前に亡くなり、2023年に婦人は農業を辞めた。今では巨木のすべては滑走路の工事で失われ、更地の中に小道だけが残っている。

(齊藤小弥太「土地の記憶」より=齊藤氏提供)
齊藤は語る。
「写真はすべての事象が止まって見えることで、風景に想いを馳せることができます。心のグラデーションですね、心の濃淡、色彩、明暗などを見る人にそのまま伝えることができます。ああいった砂利道とか、第三者だと見過ごすような細やかな光景でも、その人にとっては深い思い出ですね。それは誰にでもあるわけで、それを残すことができるのは大変大きな仕事だと思います」
「私、貧しくなっちゃうわ」
齊藤がとても重視したのは、住民との対話である。撮影に来たのに、三時間も雑談し、結局一枚も撮らずに帰ったこともある。
「その日はお話だけをして帰って、また別な日に伺っていろんな話を聞いて写真を撮りました。そうすると今まで見たその人の顔が全然違って見えるんです。さきほどの砂利道の話もそうですが、話を伺うことで、自分の認識が変わって何気ない道も違った光景に見えるんです。そのとき自分はこの土地の人や風景に受け入れられた思いがしました」
齊藤には忘れられない言葉がある。80歳の女性で大きな家に一人暮らしをしていた。たわいもない話を六時間ほどした。それは亡くなった夫の話であり、集落の楽しい思い出であったりした。夕方になって辞去するときに、その女性は突然表情が翳り、しんみりとした声で齊藤にこぼした。
「私、貧しくなっちゃうわ」
彼女はその理由を話してくれた。家には亡き夫の品物がたくさんある。旅行で買ったお土産、夫の思い出の品があちこちに置かれてあった。それが彼女にとって何物にも代用できない、土地で暮らしたアイデンティティに繋がるのである。しかし移転ではこれらの品物を持って行くことができず、捨てるしかない。それはこの土地に生きた自分の実存を失うことである。それが「貧しくなる」という言葉で表現されたのだった。ちょうど家には夕日が差し込み、彼女を照らし、とても美しい光景だった。彼は写真を撮らせてくださいとお願いした。
齊藤は回想する。
「そのおばあちゃんが一人という点の存在ではなくて、過去から延々と今に続く土地の人々の営みの象徴のように感じられたんです。そのときの印象は今も強く残っています」
子どもたちからは、早くこの家を出て一緒に住もうよと声をかけられる。しかし彼女は決意できないでいる。齊藤は言う。
「家の中も見させていただいたのですが、埃をかぶっているけど、思い出の品がいっぱいあるんです。だから家から離れられない気持ちも痛いほど分かるんです。早く引っ越しなと言う人もいるそうですが、そうはいかない心の葛藤を痛切に感じます。大きな反対運動ではないですが、小さな心の葛藤です。そういう想いを汲み取って写真に残さなければと思いました」

(齊藤小弥太「土地の記憶」より=齊藤氏提供)
齊藤がこの地に通って四年が過ぎた。そのたびに感じるのは集落が更地になっていく光景が急速に増えたことだ。彼はそれを「狐につままれた感覚」と言う。かつて写真を撮った場所なのに、更地になった土地を見ると、かつてここに何があったのか思い出せないこともある。
「過去の暮らしの営みが幻だったのかという感覚になりますね」
最近になって、彼に「貧しくなるわ」と心情を吐露した女性も移転したことを知った。
今秋、筆者は一鍬田の竹林に囲まれた1559年開山の曹洞宗福泉寺へ行った。2023年7月に96歳で死去した僧侶で教育評論家の無着成恭がいた寺で、昔は住職による寺子屋教育が行われた場である。
寺子屋は後に多古第二小学校一鍬田分校に引き継がれ、1986年まで存在した。広々とした寺の敷地と、正門の二本の門柱に分教場の名残を見いだせる。
その境内に五人ほどの人が集まっていた。老婦人から中年の男性まで世代は様々である。やがて小型のトラックが荷台に荷物を載せて現れた。運転手がチャイムの音を鳴らす。荷台には日用品や飲み物、お菓子、数々の野菜などが積まれていた。移動スーパーだった。
店のないこの地域では、移動スーパーが貴重な買い物の場であり、村人がふれあう時間なのである。移動スーパーにいた中年の婦人が分教場の跡地を指さし、「私もここで学んだんです」と話してくれた。彼女は分教場跡地を眺めながらしみじみと呟いた。
「淋しいですねえ。ここにいられるのもあと二、三年ですね。この一帯も皆移るんですよ。皆いなくなります。この竹林の光景もお寺も門柱も消えます」
集落の便宜を図る移動スーパーもいつまで続くのだろうか。以前はもっと多くの人で賑わっていたという。訪れる人が少なくなった今でも、目の前には人々の生活が広がっている。筆者はこの光景が消えてしまうことを、にわかには信じることができなかった。
おそらく齊藤はそんな惜別の思いを胸に写真を撮っているのだろうと思った。
(つづく)
タイトル写真=齊藤小弥太「土地の記憶」より
つづきの記事はこちら「【ジャーナル】消えるムラを撮り続けたい――第2話」

さわみや・ゆう 1964年熊本県八代市生まれ。青山学院大学文学部史学科、早稲田大学第二文学部日本文学専修卒業。戦前の巨人の名捕手吉原正喜の生涯を描いた『巨人軍最強の捕手』(晶文社、2003年)で、第14回ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。主な著書に『戦国廃城紀行 敗者の城を探る』(河出文庫)、『昭和十八年 幻の箱根駅伝 ゴールは靖国、そして戦地へ』(集英社文庫)、『イラストで見る昭和の消えた仕事図鑑』(角川ソフィア文庫)、『イップス 魔病を乗り越えたアスリートたち』(角川新書)など。 最新作に故郷と沖縄との縁を描いた『あなたの隣にある沖縄』(集英社文庫)がある。
バックナンバー