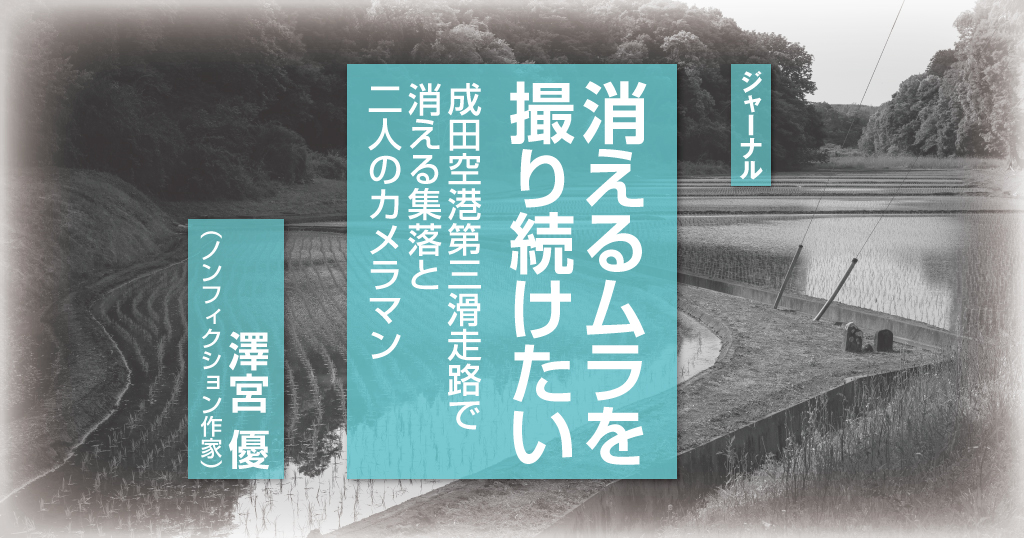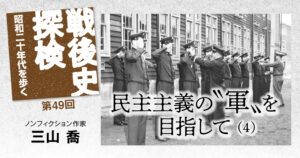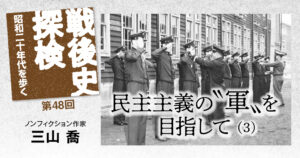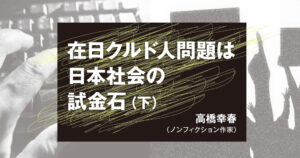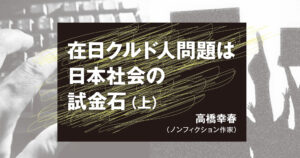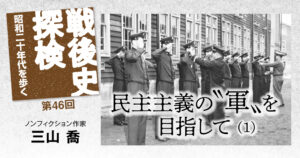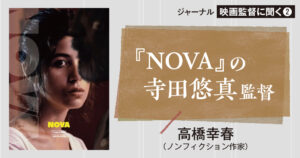前回の記事はこちら「【ジャーナル】消えるムラを撮り続けたい――第2話」
成田空港(正式には成田国際空港)の拡張工事が進むなか、移転によって消滅する集落がある。インバウンド需要増大という光の陰で、長年暮らしてきた土地から離れざるをえない人たち。二人のカメラマンが、消えゆく集落を、そして住民たちの複雑な思いを記録にとどめようとしている。国策によってふたたび揺れる成田を、澤宮優さんがルポする。
警戒から信頼へ
千葉県山武郡芝山町の各地区では、一月から二月にかけて「オビシャ」という稲荷神社の産土様[うぶすなさま]に祈る祭礼がある。男女別に「男オビシャ」と「女オビシャ」に行事は分かれ、「男オビシャ」では五穀豊穣、悪疫退散を祈り、「女オビシャ」では子安様に安産と子孫繁栄を祈る。移転地区である加茂では「女オビシャ」が行われる。
菱田地区の中郷にある鹿島神社では、七月には「宮薙[みやなぎ]」と呼ばれる、境内や周辺の道の草刈りがある。鹿島神社は、茨城県鹿嶋市にある神武天皇元年に創建されたといわれる鹿島神宮の分霊を勧請している。菱田東集落と中郷集落の境界付近にあるので、氏子総代は両地区から出て、「宮薙」なども両集落の氏子が行っている。
鹿島神社では毎年八月二十四日に五穀豊穣と無病息災を祈念して奉納相撲が行われる。八月にはお盆、九月にはお月見、十月には自宅にある氏神様を祀る祠に、早朝から赤飯と甘酒を供える「氏神祭り」がある。十一月には再び「宮薙」があり、神社の清掃だけでなく、初日の出が拝めるように、林を伐採する。年末には正月を迎えるために、鳥居にはしめ縄が飾られる。これらの行事の後には皆で飲食を共にする「直会[なおらい]」が行われる。
日常の生活では、三月には成田用水から田圃に水が引き入れられ、水田耕作の準備が整う。四月には田植え、八月後半には稲刈りと続く。それはかつての日本ならどこにでもあった光景だが、今では地方に行っても過疎化が進み、見る機会は減りつつある。
神社には精巧な古い彫刻が施されている。移転後、神社は建て替えられ、彫刻を残すことができるかという懸念もある。
せめて映像としては残したい――。移転予定の集落に残る、生活を彩る日常を広く伝えることに芝山町役場の山﨑一矢は、カメラマンの中島誠二同様、意義を感じた。

芝山町とタイアップして中島の撮影が始まったが、集落の住民は警戒感を露わにした。牛を飼っている家にカメラを向けると「何撮っているんだ。何でうちなんだよ。ほか行け」と言われた。お盆で墓参りをしている風景をカメラに納めると「何撮っているんだ!」と怒鳴られた。車で走るだけでも住民たちは警戒の目を向けた。そう言われながらも、彼は芝山に通い詰めた。その粘りは実を結び、三年かかってようやく住民とうちとけて話ができるようになった。
今では撮影をしていると住民から声をかけられる。移転が決まっても最後まで農業を続ける人がいた。その人はカメラを向ける中島に言った。
「今年で最後だろうね」
彼は稲穂が実った田圃を見やりながら、淋しそうに呟いた。田圃で黙々とトラクターを運転する農家の人たちは本当にいい表情をしている。この人たちは農業をするためにこの地に生まれ、この地で精一杯生きてきたのだという思いを、彼らの姿から中島は感じた。
牛を飼っていた農家の老人は、最初は中島が撮影に来ると怒鳴っていたが、今では本音を漏らすようになった。すでに牛も売り払い、かつて牛を飼っていた小屋は空になり、建物だけが残っている。老人の奥さんは中島に語った。
「移転が迫ったら、せめて牛小屋だけは業者に頼まないで、自分の手で壊したいとお父さんは言っています」
自分が人生をかけた酪農の終焉は、他人の手によってではなく、自分で始末をつけたいというせめてもの願いがある。

お盆に中島がある家族の墓参りの光景を撮影した。以前は警戒感を露わにした家族が、中島を見て微笑んだ。
「もう墓参りも最後になるから、皆で写真を撮ってもらおうよ」
中島はようやく住民の信頼を得たことを実感した。彼が撮影した集落の記録映像は、芝山町教育委員会の2021年度事業として編集され、『ムラの暮らし~成田空港第三滑走路用地移転地区~』というタイトルで完成、芝山町の公式ユーチューブチャンネル(ムラの暮らし~成田空港第三滑走路用地移転地区~)で公開されている。
映像からは、貴重な祭礼や農業の風景とともに、行事を通して地域共同体の繋がりと家族の絆が感じられる点は特筆すべきことだと思う。
お盆の墓参りには、地元の両親だけでなく帰省した子どもや孫たちの姿もあった。墓の掃除、墓にお酒をかける。家族に亡くなった人が出た初盆には墓に提灯を掲げる。迎え盆には死者が現世に戻って来るので、屋号の描かれた提灯に火をつけ、仏様となった死者を家に連れて帰る儀式がある。
八月十四日早朝には一家揃って墓参りを行い、花と線香を添え、「アラヨネ」というナス、胡瓜を賽の目に切って洗った米に混ぜ、これを里芋の葉に載せて墓前に供える。翌十五日の夕方には再び家族が墓を訪れ、紙の札に経文「盆会精霊井也」と書き、近くの小川に流し、死者をあの世に見送る行事が行われる。流れてゆく紙札に子どもたちが「バイバイ」と手を振り、「引っかからずにきれいに流れてゆくね」という声が聞こえてくる。
これでも昔に比べると儀式は簡略化され、失われたものもあると中島は言うが、行事を繰り返しながら人々は歳月を重ねてきたことがわかる。
画面の区切りに鳥の姿、轟音とともに飛ぶ飛行機、さらには旅人の無事を祈り、ムラの境を守る道祖神や、招福除災を祈る民間信仰の庚申塔、馬頭観音が映し出される。芝山町には庚申塔は四十一基あるといわれる。そんな集落の細部までくまなく撮影したことで、人々の生活が見えてくる。
「オビシャ」のときだった。行事が終わって中島と山﨑が地元の人たちと集会所で話をしていると、部屋の隅に段ボール箱に入れられた幟旗があるのに気がついた。かつては「オビシャ」のときに立てたが、長く使わないようになって箱の中で眠っていたのである。第三者には価値があるように思われても、地元の人たちには代々伝わっているというだけのものらしく、ずいぶん開けていない箱があることもわかった。中島はそこに集落の生活史を今に伝える無二の史料がある筈だと考えた。
「たとえば金銭出納帳や昔の写真でもいい、そこから昔の風俗や暮らしが見えてきます。こちらから具体的に実例を挙げて、住民に家を壊す前に見つかったら教えてください、さらに徹底するため役場に回覧板で通知してくださいと町に言いました。実例を示さないと実際に暮らしている人はわからないですからね」
撮影中に新型コロナが蔓延したため、祭礼の一部が行われず、十分に撮れていない行事もあった。そのためより完全を目指して、コロナ禍が収まった今日も撮影は続けられている。
中島は語った。
「このムラには特筆すべき行事や文化財はありません。何もないけど、この土地に生きた人たちはふるさとに大変な愛着を持っています。その哀しさに多くの方は気づいて欲しいと思います。そこから『ふつうとは何だろう』という問いに辿り着きます。何もない集落こそ日本のかけがえのない生活を明確に表していると思います。それをいつまでも伝えてゆくことが民俗学の原点です」
住民たちの心境は・・・・・・
この集落は、そうとう古くから代々住んできた人々が住む地域と、明治時代の開墾で移り住んできた人々の住む地域がある。現在ではサラリーマン世帯も増えた。移転に対する思いに温度差はある。しかし違いはあっても「誰もが好き好んで移転するわけではない」という心情があるのは事実である。
菱田在住の石毛博道(75歳)は、かつて成田空港反対闘争の事務局長を務め、後に反対闘争を話し合いで解決するため、国や空港側とシンポジウムや円卓会議を推進した人である。
石毛は第三滑走路を2012年のある会合で成田市民や空港会社副社長に提案したことがある。その根底にあったのは、日本の構造的な不況を打開するために、観光立国として海外から観光客をさらに受け入れる空港整備が必要だという思いがあったからである。
そういう石毛も成田国際空港のB滑走路建設(1988年起工、2009年運用開始)で、騒音下からこの地に移転した。自分も推進した立場の一人とはいえ、二度目の移転をしなければならない。
石毛は言う。
「俺自身も今回で二度目の移転をすることになります。この地に移り、今年で二十一年住んできました。一回目の移転の時は四代に渡って住んだ土地でしたから離れるのはとても嫌でした。今回は二十年ほどしか住んでいないので前回ほどではないですね。でも淋しさはありますよ。それにもう七十歳を超えましたから二度目の移転は正直きついですよ。でも自分も新滑走路を推進した立場ですから仕方がないですよ」
観光立国を推進するという大儀があっても、土地を離れることは理屈ぬきに淋しさに襲われるものなのだろう。小川総夫(67歳)は現在、芝山町の菱田に住む。「しばやま郷土史研究会」副会長で郷土史研究家の彼も、1994年に移転してから去年の一月に印西市に二度目の移転をした。集落の歴史を踏まえて小川は語ってくれた。

かつての家の前で。現在は印西市に転居している
「そりゃ失う土地に対して心情的に割り切れないところはありますよ。家を片付けていると、古い史料が一杯出てきました。集落がなくなる前に調べたいと思っています。菱田は戦国時代末期には交通の要衝だったとわかりました。そんな大事な場所だったんです。我が家の祖先も江戸時代の初期から菱田に住んでいることがわかりました」
小川の家は菱田村の名主、組頭を務めたため、村について書かれた古文書がすでに多く見つかっている。今回さらに調査すると、さらに古い史料が出て来た。「しばやま郷土史研究会」も、今後他の家からも出てくる古文書や地域の記録を調べてどう整理して保存するか、道祖神などの石造物をどう残してゆくのか、新たな課題に取り組んでいる。
小川は移転したが、菱田にある家は今も残っており、片付け作業に追われる日々である。
「今回の移転では空港会社は以前と違い丁寧な手順を踏み説明もしてくれました。ですから大きな反対はほとんどありません。でも心情としては、ウサギ追いしかの山という『ふるさと』の歌詞を思い浮かべ、どうしても集落へのなつかしさに思いを馳せてしまいます。切ない気持ちになりますね」

小川の思い出は、菱田にある野山に子どもを連れて歩き、野イチゴをちぎって食べさせたときの子どもの喜びようである。今も子どもたちは「ここには野イチゴがあったんだよね」と話してくれる。
「この土地での思い出は風景だけではなく、人々とコミュニケーションを取りながら過ごした思い出が風景と一体となっての記憶ですね。できることなら、この土地の古い家を空港会社が買い取って、どこかに残してくれるといいですね。移転した人が『こんな家に住んでいたんだよな』と故郷を懐かしむために帰ってこられる場所をつくってもらえたらと思います」
菱田東に住む小川武志(45歳)は、生まれも育ちもこの集落である。彼の幼少の頃の思い出は成田国際空港の灯である。夜になると飛行機を誘導する塔が黄色と緑色に一晩中光り、彼の家からも灯は見えて、鮮やかだった。一方で子どもの頃から警察や機動隊がこの集落を何度も行き来していたのが日常の光景だった。子ども心に「三里塚闘争のなごりが、まだある」と感じた。
小川は仕事の関係で都会にいることが多かったが、ようやく故郷の地に骨を埋めようと戻ってきた。すると滑走路の建設で故郷が消滅することを知らされた。彼の実家は農業をしながら、百年以上この土地で暮らしていた。
「移転になると知ったとき、自分の土地への愛着を改めて実感させられました。移転は時代の流れもあって仕方ないですが、いろんな行事が存続できない哀しさ、集落がなくなるという漠然とした淋しさがあります。今思うのはこの集落は間違いなく自分の原点だったということです」
農業をやっていた小川裕(73歳)は、かつて成田空港反対闘争に参加し、青年行動隊の一員だった。空港側が強制的に土地を代執行したとき、機動隊と激しく闘い、二回警察に捕まった。その後、酪農に従事してきたが、二十五頭いた牛は三年前に売り払い、今は一頭もいない。
「酪農をやっていた夢をみますけどね。もう大変なことしか覚えていないですね。牛が出産のときは、苦しくて鳴くわけですよ。すると連鎖して他の牛も鳴く。数年前台風が来たときは一週間停電が続きましたが、牛の乳が張っても機械で絞るから出してあげられない。痛がって鳴きますし、水も機械でやるから飲ませることもできませんでした」
子どもたちは成田空港の関連会社で働き、都市部にいる。数年前に子どもたちが孫を連れて田植えを手伝ってくれた。一家総出での田植え。それを中島が撮影した。その映像が最後の田植えになった。小川は七十歳の誕生日を境にすっぱりと農業を辞めた。
「子どもを大学までやっていくだけのことはできました。だけど歳も取っていつまでも農業をやるわけにもいかないし、そろそろよかっぺと思っていたら、空港で移転の話がきたので、これを潮に辞めました。いい辞めどきだったのかもしれない」
(次回最終回につづく)
次回の記事はこちら【ジャーナル】消えるムラを撮り続けたい――第4話
タイトル写真=齊藤小弥太「土地の記憶」より

さわみや・ゆう 1964年熊本県八代市生まれ。青山学院大学文学部史学科、早稲田大学第二文学部日本文学専修卒業。戦前の巨人の名捕手吉原正喜の生涯を描いた『巨人軍最強の捕手』(晶文社、2003年)で、第14回ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。主な著書に『戦国廃城紀行 敗者の城を探る』(河出文庫)、『昭和十八年 幻の箱根駅伝 ゴールは靖国、そして戦地へ』(集英社文庫)、『イラストで見る昭和の消えた仕事図鑑』(角川ソフィア文庫)、『イップス 魔病を乗り越えたアスリートたち』(角川新書)など。 最新作に故郷と沖縄との縁を描いた『あなたの隣にある沖縄』(集英社文庫)がある。
バックナンバー