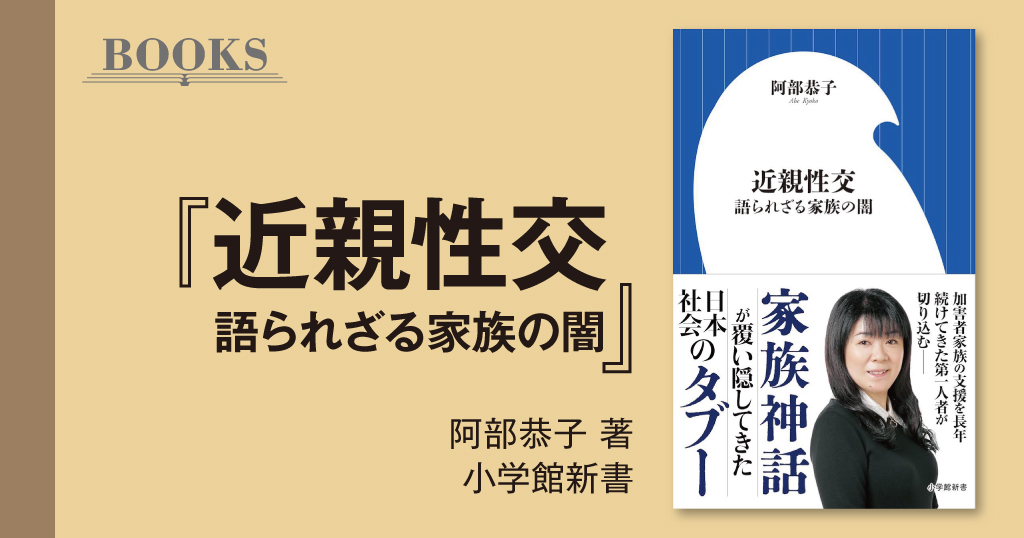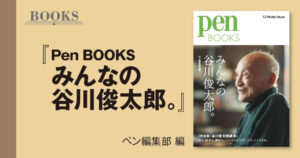「親・きょうだい」は暴力装置にもなる
地方の町で、二十七歳の青年が同じ歳の男性を刺殺した。加害者Aと被害者Bは高校まで一緒で、Aは大学卒業後、父が経営する不動産会社の役員となったが、貧困家庭出身のBは大学中退後、犯罪を重ねて服役後に帰郷、Aと再会した。犯行の動機はAがBにゆすられ、BがAの親にまで危害を加えようとしたためだと見られた。だが、犯罪加害者家族支援のためのNPO「World Open Heart」代表としてAとその両親に接触した著者は、違和感を抱いた。
数年後、服役中のAと、その父とに面会した著者は真実を告げられる。父親は同性愛者で、Aは幼い頃から性交を強いられていた。祖父も男色だったが、地方名士の家系で同性愛はタブー。さらに父親は跡取りの男子をもうける「義務」があった。「欲求は欲求で処理すればいい」という祖父の「助言」に従い従順な妻を迎えたが、外で欲求を満たすことができない父は、息子に恋着し、性的に支配した。
成長したAは自身も同性愛だと気付き、父親を恨んだ。一方、逆境でも勉学と部活に励み、女子にも人気のあったBに、Aは憧れを抱いていた。再会したBにAは恋情を告白し、Bはそれを受け容れたかに見えたが、それをAの親をゆするネタに用いた。愛する者に裏切られた……。これが犯行の動機だった。Bを刺すとき「父親の姿も重なっていました」と、Aは告白している。
本書の第一章「父という権力」は凄惨な事件が紹介される。世間体に縛られ、男尊女卑が根強く残る地方で、タブーを抱えるが故に孤立する家族。その中で潜行する性的暴力。「世間」のバッシングにさらされ、孤立に追い込まれる犯罪加害者家族支援に尽力する著者は、支援に不可欠な事件の真相を聴き取る過程で、近親性交の事実が次々に明らかになったと語る。
個人が特定されないよう注意を払いながら、父子、母子、兄妹姉弟等、あらゆる近親性交の事例を紹介する。なかでも陰惨なのは、父親による性暴力だ。小学生の娘に虐待を重ねて死なせた父親、娘を強姦したと告白する父親。どちらも四十代のその実像は小心者で、むしろ「世間が求めるあるべき家族像」にこだわり続けていた。就職氷河期に社会に投げ出された彼らは安定した職に就けず、親の支援で家庭を維持せざるを得なかった。伝統的な家族観、父親像に囚われていた彼らは、外に悩みを打ち明けられずにいた。そこに反抗期の娘の一言が引き金となって、自身の中にあった〝あるべき父親像〟が崩壊、世間から「鬼畜の所業」と指弾される凶行に及んでしまった・・・。
陰惨な犯罪を防ぐ手立てはないのか? 著者は「社会に開かれた家族、家族を受け容れる社会」の必要性を説く。先著『家族間殺人』(幻冬舎新書)でも説いたように、孤立した家族は暴力犯罪の温床と化す可能性が大きく、それは近親性交にも至る。そしてつねに立場の弱い者が苦しめられる。
代々医者の家に嫁ぎ、息子の「お受験マネージャー」と化すことで自我を保っていた母親が、息子の子を出産する事例(第二章「母という暴力」)もあるが、生まれた子に将来、誰がどのような形で真実を伝えるのか。著者は近親性交で生まれた子どものケアにも言及する。「事実を直視しなければならない」と。
本書には、父や兄の性暴力に抗い、自分を失わなかった姉妹も登場する(第四章「近親性交で生まれた子どもたち」)。権力、暴力、世間の同調圧力、そんな「力」は絶対ではないのだ。そして著者は、近親性交を公権力による厳罰化のみで規制する方策には、反対の立場だ。


いけがみ・しょうじ 1960年、静岡県旧清水市三保生まれ。東海大学大学院中退。専攻は日本史。現在、熊本市西区の日蓮宗寺院、本妙寺住職。ループタイは二十代から愛用。
バックナンバー