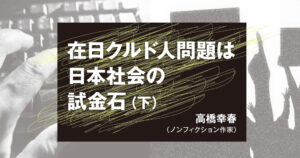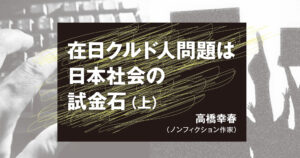前回の記事はこちら「【ジャーナル】戦後史探検──第35回 占領軍の闇(上)」
謎の失踪
月刊『文藝春秋』が1960年の年初から12回にわたって連載した松本清張の『日本の黒い霧』。その第9話・鹿地亘事件の章のタイトルは単行本ではシンプルに事件名だけに変わったが、雑誌記事の段階では「白公館の秘密」という小説ふうの見出しが付いていた。
この言葉は果たして何を意味するのか。
昭和27(1952)年12月7日夜、鹿地は神宮外苑の路上で米軍車両から降りるよう命じられ、そこからタクシーで新宿に移動して、家族や友人が待つ自宅へとたどり着く。米軍による拉致監禁が疑われる鹿地の謎の失踪は、すでに新聞や雑誌で騒がれ始めていて、取材陣の殺到を心配した友人は用意した隠れ家にすぐさま彼を連れ出した。ここでようやく落ち着いた鹿地は、それまでの約一年間、知る術のなかった〝外界の動き〟をこの友人から聞かされた。
それによれば、前年の11月25日日曜日、藤沢市で忽然と消え去った鹿地の身に何が起こったか、家族や友人らは約ひと月後におおよその事態を察知できたという。
キャノン機関の目を盗み、組織の料理人・山田善二郎が内山書店へのメッセンジャーとなったのは翌年の春。しかし実際にはそれよりもかなり前、〝拉致監禁〟という事態そのものは家族に伝わっていた。それはただひと言、この「白公館」というキーワードが鹿地からもたらされたためだった。
囚われの身となった次の日曜日、鹿地が川崎市のアジト「T・Cハウス」で自殺を試みたことは、前回の記事で触れた。
キャノンらはこの事態に驚愕し、そしてまた結核を病む鹿地の容体が想像した以上に悪いことを確認して、ベッドに縛ったり殴ったりする扱いを取りやめた。そして短期決戦から長期の拘束へと対応を切り替えて、鹿地の根負けをゆっくり待つことにした。何よりも自殺騒ぎのとき、鹿地の顔面は大量のクレゾール液により焼けただれ、そのままでは早期に解放しようにも、人目がはばかられた。
キャノンはこうした事態を受け、鹿地が交通事故に遭い、治療を受けているストーリーをつくり上げ、これに沿って家族を安心させる手紙を書くように要求した。車で彼をはね、介抱しているのは鹿地の知り合いだが、密貿易に携わる中国人のため、具体的な居場所は明かせない。それでも間違いなく回復後は家に帰るから心配する必要はないという手紙の筋書きはすべて指示された。
現実を伝える手がかりはもちろん盛り込めない。ただ鹿地はとっさの判断で、手紙の末尾に「白公館にて 鹿地亘」という署名を書き添えた。
「白公館」とは何か
月日を経て『謀略の告発』(新日本出版社)などの著書で鹿地はそんな種明かしをしたうえで、「白公館」という言葉の意味合いをこう説明した。
それによれば、白公館は日本の敗戦が色濃くなったころ、国民党軍と米国OSS(戦略情報局、CIAの前身の機関)が共同して中国・重慶郊外に建設した施設群の通称なのだという。両者は日本の敗戦後、国共内戦の再発を想定して共産党勢力に送り込むスパイをこの施設で養成した。
日中開戦前、中国で内山完造や魯迅と知り合った鹿地は、そのつてで国民党軍に捕らえられた日本人捕虜と面会を重ねるようになり、在中国邦人の平和運動組織「日本人民反戦同盟」をつくり上げた。しかし日米開戦後は、その左翼的なスタンスを国民党に警戒され、同盟は解散を命じられる。国民党の反共姿勢はやがて目に見えて強まり、中国人の労働者や学生、インテリ階層の人々を数多くこの施設群に連行し、スパイになるか殺されるか、究極の選択を迫るようになる。
(共産党軍の勝利により)そこが解放されたとき、国民党軍が火をつけて逃げたその廃墟から(略)三〇〇余の死体が発見され、一九五〇年初頭の人民日報や新華月報などに、鬼気迫るその写真が公表されていた(略)。(『謀略の告発』)
日本への帰国後も、反戦同盟の仲間とつながりを保っていた鹿地の周辺には、「白公館」のひとことで、そんな恐ろしいスパイ養成所を想起できる引揚者が数多くいたのである。
『謀略の告発』の刊行から九年後、1972年に出た鹿地の著書『暗い航跡』(東邦出版社)は、山田善二郎を通じて鹿地の状況をより詳しく知った元反戦同盟員らの憤激をこう描いている。
(血気盛んな面々は)東京でも関西でも寄り合いをもち、(キャノン機関のアジトを襲撃する)決死隊をつのり、「いつ召集がいくかもわからんから、身辺を整理して待機するように」と申し合わせていた。
わたしは(後日)それをきいて冷やっとした。彼らならそれくらいはやりかねない(略)。だが、そうなると、手榴弾の二三個もとび、たいへんな騒ぎをおこしたことだろう。

ちなみに山田善二郎がT・Cハウスなどで数々目にしてきた日本人拘束者(キャノン機関の関係者は彼らを「お客さん」と呼んだ)、あるいは朝鮮戦争の戦場から連行されてきた中国人捕虜などは、そのほぼすべてが暴力や脅迫で、米軍のスパイになることを強いられたが、キャノンは鹿地に対しては「話し合い」や「友人になること」は求めても、具体的な要求を明確には口にしなかった。
キャノンの狙い
それでも鹿地本人は、拘束された当初からキャノンらの狙いは彼の持つ反戦同盟員の人脈にあるはずだと踏んでいた。拉致される少し前、胸部の手術のため入院していたとき、次のような出来事があったことも思い出していた。
それは昭和24(1949)年、国共内戦に共産党が打ち勝って、中華人民共和国が誕生した直後のこと。病院に出版関係の友人が訪ねてきて、中国の著名作家の作品を多数翻訳・刊行したいのだが、翻訳権を持っていないという理由からGHQがこれを許可しない、何とかならないか、という相談ごとだった。
そこで鹿地は自身の名で中国政府に許可申請を出すように手配、すると郭沫若をはじめ五十人以上もの作家から翻訳権委任状が送られてきた。この事態に驚いたのがGHQだった。病院に担当官が駆けつけて、その経緯を鹿地に尋ねてきた。
この出来事をきっかけに、米軍から目をつけられたに違いない。鹿地はそう想像した。
一時は(結核のため)再起不能としてかれら(米軍)の眼から消えていたはずなのに、わたしはもう一度かれらの視野のうちに生き返ることになった。もちろん戦争中の反戦同盟の活動、同盟員一七〇名が戦後の日本に帰り、各地の人民運動に加わっている事実、そして米国側にとってはその集団との「協力」をはねつけられたかつてのにがにがしい記憶(※)とともに。蒋(介石)政権の台湾落ちのため、かれらは大陸に足がかりを失っていた。(『謀略の告発』)
※戦争中の中国で、米国OSSは日本人民反戦同盟と交流し、正式な協力関係を求めたが、米側の出す条件が同盟に従属を強いるものだったため、鹿地はこれを断っていた。
「英文の怪文書」と 虚実入り交じる記事
「鹿地がどうして米軍の監禁から釈放されたのか。そのきっかけは、(昭和)二十七年十一月二十三日号(正確には二十三日発売の三〇日号)の『週刊朝日』の記事からである。この号には、鹿地の失踪についていろいろな推測を試みていて興味深い」
『日本の黒い霧』に松本清張はそう書いている。ただ、この記述も正確ではない。『週刊朝日』に先立って、9月にまず「米軍の手で鹿地が拉致監禁されている」とする「英文の怪文書」がいくつもの新聞社や通信社に届き、社会党機関紙の『社会タイムス』を皮切りにいくつかの媒体がその内容を記事化した。
鹿地の監禁場所が茅ヶ崎から東京の代官山に変更され、最後には沖縄へと変わったのは、こうした情報漏洩に驚いたCIAが鹿地を隠そうとしてのことだった(キャノン機関はこの春にすでに解散、鹿地の身柄はCIAに移っていた)。
山田善二郎は自身の〝裏切り〟が発覚することを恐れ、茅ヶ崎のアジトでの仕事を辞め、横須賀の米海軍基地に新たに職を得ていたが、自分の行方を追うCIAの動きを察知して、恐れおののく日々を送っていた。
「英文怪文書」を撒いたのは、どうやら鹿地の友人たちだったらしい。鹿地の著作にはそうほのめかす記述がある。一連のメディアの動きを鹿地に解説する友人の表情を「にやにやしている」と描写するくだりである。
しかしやはり社会に決定的なインパクトを与えたのは、清張の言うとおり11月の『週刊朝日』だったろう。
「姿を消した鹿地亘氏 失踪事件を推理する」
そう題した巻頭八ページもの大特集である。半年ほど前にサンフランシスコ講和条約が発効するまではGHQのプレスコードに引っかかり、到底発表が望めない類の記事だった(この年の8月に出た『アサヒグラフ』は戦後七年目で初めて広島の原爆被害を大々的に報じた写真記事として、大反響を呼んでいた)。
記事は51年11月25日、「チョット出て来るよ」と付き添いの看護師に声をかけ、藤沢市鵠沼に借りていた療養先の住宅から散歩に出る鹿地の描写から書き起こされている。そして12月27日付と1月29日付、前述したように交通事故に遭ったという内容の手紙とハガキの文面が記されている(記者は手紙の現物でなく写しの文章を引用し、その文末にあったはずの「白公館にて」とする五文字はない)。
そして9月下旬、大阪の国際新聞社に届いたという英文怪文書の説明記事。おそらく鹿地の友人か内山書店周辺の関係者の手による文章と思われるが、その内容には想像で書いたと思われたり、明白な事実誤認だったりする記述も多々あって、文字通りの〝怪文書〟となっている。
たとえば、鹿地を捕らえたのをキャノンでなく、そのあとを受け継いだ「G大佐」(CIA責任者のガルシェ大佐と思われる)としてみたり、拘束理由を中国で鹿地のもとにいた日本人牧師が彼のことを「中共のスパイ」だと密告したせいだと解説してみたり(そのような人物は存在しなかった)、初めの監禁場所は「横浜周辺」でその後「伊豆山中」に移されたとしてみたり、そのような不正確な記述が多かった。
また『週刊朝日』のこの記者にどの程度情報を明かすべきか、事情を知る関係者の間でも足並みは乱れていて、一部の人間は米機関内部の協力者として「山田という人物」の存在を明かしてしまっていて、一方で鹿地の妻は(山田の安全を考慮すれば当然のことなのだが)そんな人のことは「全然知らない」としらを切っている。
このほか、米軍の秘密機関でなく国民党による拉致だと推理したり、中国共産党による誘拐説を唱えたりするコメントも取り上げられていて、記事全体は本当に虚実入り交じる混沌としたものになっている。
それでもこうした報道にCIAがうろたえたことは間違いなく、『週刊朝日』の発売から六日後の11月29日、鹿地は代官山のアジトから突然「国外に移る」と説明され空路沖縄に移動させられたり、それからわずか七日後に東京に戻されたり、その身辺の動きは急速に慌ただしくなっていった。
救出
一方、横須賀に潜んでいた山田の生活に異変がもたらされたのは、11月22日のことだった。「英文怪文書」をきっかけに伊豆に住む山田の父親を見つけ出し、その父親を引き連れて『社会タイムス』の記者が山田の下宿を訪ねてきた。
「これを見てください」と記者が差し出したのが、翌日発売の『週刊朝日』だった。そして記事のなかに自分の名があることを山田は発見した。
わたしの全身はガタガタと震え出した。抑えようとするとさらに激しく震える(略)。いくつかの間違いがあるけれど、「山田」「伊豆」などの文言はまさしくわたしのことである。わたしの身震いを見て、その記者も震えた(略)。父は、ただ呆然としていただけだった。無理もないことだった。(『アメリカのスパイ・CIAの犯罪』)
とにかく一刻も早くここから逃げなくてはならない。山田は着の身着のままで社会タイムス記者に同行し、横須賀線に乗り込んだ。その夜は結局、社会タイムス社の社屋に泊まることとなり、山田と記者は内山完造や鹿地夫人、あるいは鹿地の反戦同盟の仲間などと集まって、鹿地救出に向けた方策を協議した。
一同が頼ることを決めたのは、社会党左派の衆議院議員・猪俣浩三であった。翌日、議員会館に彼を訪ねた一行は、猪俣に鹿地救出への助力を訴えた。
実はこの訪問に先立って、内山や加地夫人らはその前にも猪俣に助けを求めていた。猪俣はそのときのことを自著『占領軍の犯罪』(図書出版社)に記している。
いずれにしても、アメリカの諜報機関による鹿地亘の拉致監禁が、もし事実だとすれば、許されるはずがない暴挙であった(略)。しかしながら、かりに鹿地の拉致監禁が虚構にすぎなかったとしたならば(略)私の政治家としての生命は致命傷を喫するに相違なかった。
夫人や内山らの訴えを信じるか信じないか。結局その判断の切り札になったのは、山田善二郎という〝生き証人〟の存在であった。猪俣は山田にその体験をすべて文章に書くように求め、可能なかぎり裏付け調査をした。
「結果はすべて山田の告げるとおりだった」
真剣な作戦会議の末、猪俣が国家地方警察本部長官の斎藤昇に掛け合って、鹿地の救出を直談判することになった。結果から言えば、その交渉の成功で鹿地は監禁を解かれることとなるのだが、鹿地らにとってそこからが戦いの第二幕だった。戦場は国会審議と法廷での闘争。その相手は明らかに米軍と気脈を通じている日本の警察権力であった。
〝敵側〟は鹿地をソ連のスパイだと主張、鹿地はその容疑を払いのけるため、それから十七年もの歳月を費やすこととなる。
(つづく)
つづきの記事はこちら「【ジャーナル】戦後史探検──第36回 占領軍の闇(下)」
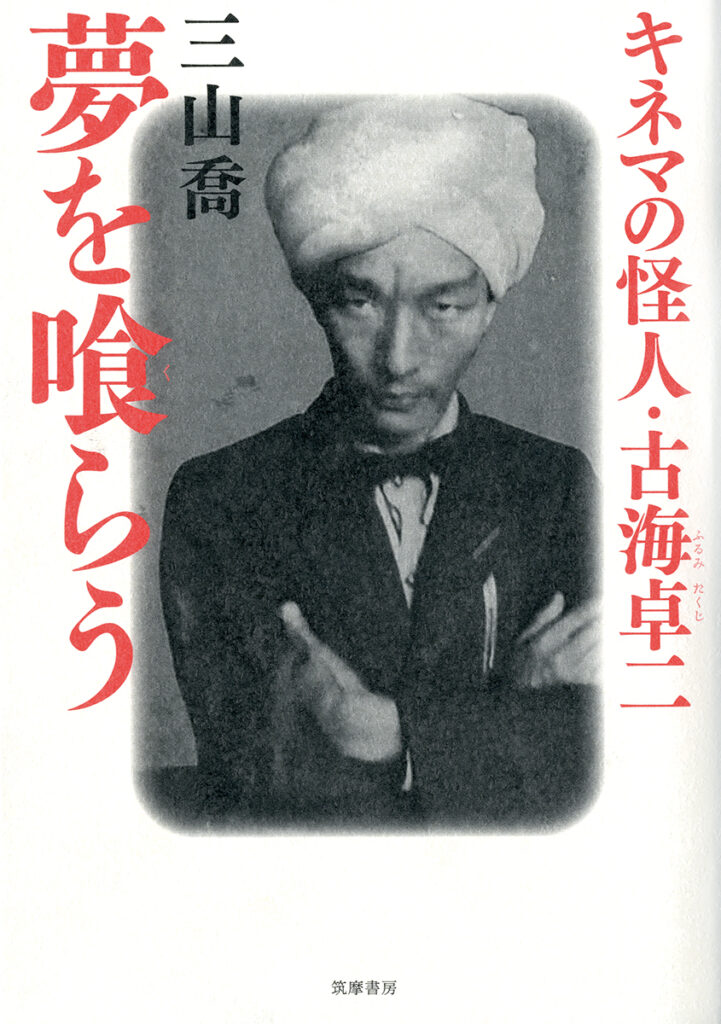
みやま・たかし 1961年、神奈川県生まれ。東京大学経済学部卒業。朝日新聞学芸部、同社会部記者を経てフリーに。2000年から06年にかけ、ペルーを拠点として南米諸国のルポルタージュ記事を各誌に発表。帰国後、ルポやドキュメントの取材・執筆で活躍している。著書に『日本から一番遠いニッポン――南米同胞百年目の消息』(東海教育研究所)、『さまよえる町――フクシマ曝心地の「心の声」を追って』(東海教育研究所)『ホームレス歌人のいた冬』(東海教育研究所、のち文春文庫)、『夢を喰らう――キネマの怪人・古海卓二』(筑摩書房)、『国権と島と涙――沖縄の抗う民意を探る』(朝日新聞出版)、『一寸のペンの虫――〝ブンヤ崩れ〟の見たメディア危機』(東海教育研究所)などがある。
バックナンバー