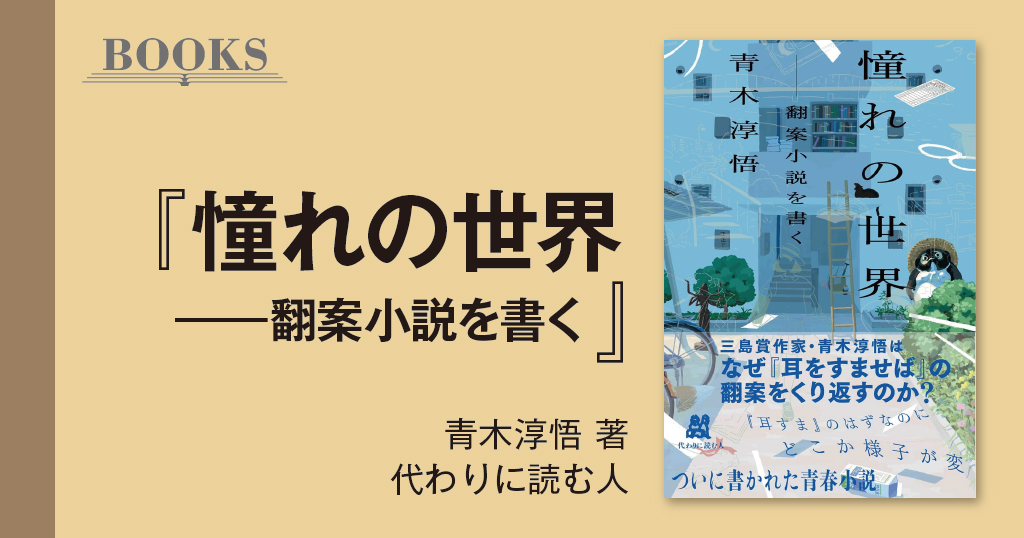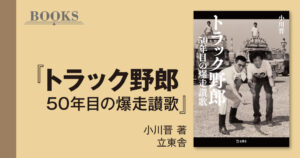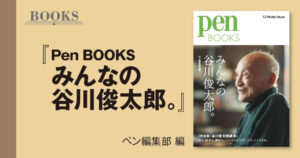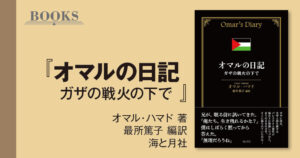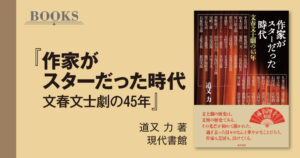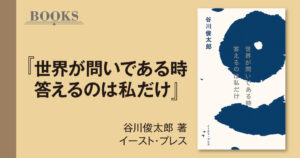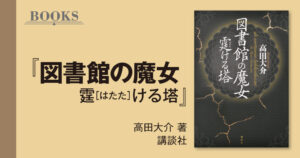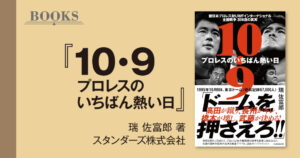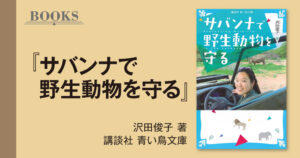自縄自縛の試行錯誤
1995年公開のアニメ映画『耳をすませば』(近藤喜文監督、宮﨑駿プロデュース)は、ヒロインの中学生・月島雫が謎の少年と出会い、将来の夢を互いに触発しあう青春恋愛譚[たん]である。本書にはその「翻案小説」が二作収録されている。
翻案とは、原作をもとにしつつ、作りかえること。そもそも、アニメ映画『耳をすませば』も、柊あおいの同名漫画を原作としつつ、脚本担当の宮﨑駿がストーリーや設定に大きく手を加えた〝翻案映画〟だった、といえる。たとえば漫画版では少年・天沢聖司が画家になる夢をあたためていたのに対し、映画版ではバイオリン職人を目指している、といった具合に。
では本作はというと……。翻案小説の一作目「私、高校には行かない。」において、天沢聖司的な人物は、名前だけしか作中に顔を出さない。つまりはヒロインが少年と出会えぬまま、話が終わってしまう。二作目「憧れの世界」では、ちゃんと登場するものの、少年の夢が仏師に変更されている。バイオリンではなく仏像を彫るのだ。なぜにこうなった?
ほかにも、語り手が唐突に中年男性っぽくなったり、登場人物が図書館の個人情報保護について執拗に言及したり、出てくる書物が1995年のベストセラーに偏っていたり、別のジブリ作品が混入したりと、様々な翻案が為されているのだが、アレンジがあまりに奇妙だ。いったい何を読まされているんだ⁉ と、何度もキョトンとさせられた。
そういった、変な読書体験に誘[いざな]われる点が、青木淳悟の小説を読む醍醐味なのだが、それにしたって今回は度を越えているためか、本書には創作秘話風のエッセイも二作収められており、一粒で二度おいしい。しかも内容は、一作目がどうして「失敗」したかを深掘りし、二作目でどう立て直したかを赤裸々に語るものだ。自作を失敗例として取り上げるなんて、きわめて珍しい試みに思える。
執筆にあたって青木は「純粋な想像力をバネにしない、さらにパロディや諷刺や批評よりも視界のきかない一段低いところで書くような、(サンプリングでもリミックスでも、コラージュでもカットアップでもない)『翻案的』であろうとする創作」を目指したという。おそらくこの縛りが小説をカオスに導いている。
宮﨑駿脚本による翻案映画は、ある意味、漫画版への批評であった(原作漫画の連載を途中まで読み、物語の結末を勝手に空想していた宮﨑は、実際の最終回を読んで「ストーリーが違う」と怒り出した、という逸話がある)。同様に翻案小説のほうも、映画版に対する批評がメインであれば、アレンジの意図はわかりやすくなったろう。
本作にも一応、批評的なアレンジ(映画版には偶然が多すぎ、あるいは、天沢聖司のキャラは現実離れしすぎ、といったツッコミをもとに書き換えられた箇所)は見られる。しかし前述の縛りから、そこに力点を置こうとしない。そのため、批評にも諷刺にもパロディにも還元できない何かが前に出てくる。
縛りがもう一つ。登場人物の感情や舞台設定の細部を、地の文で説明できるのが小説の強みといえる。にもかかわらず、翻案小説の特に一作目では、地の文のないアニメ(映像表現)に近づくべく、なるたけ地の文での説明を禁じようと努めているのである。
そんなこんなで、仕上がりは鵺[ぬえ]的だ。小説の未踏の地を探り、しち面倒な無茶に挑む、自縄自縛の試行錯誤っぷりが、おかしくて素敵だ。
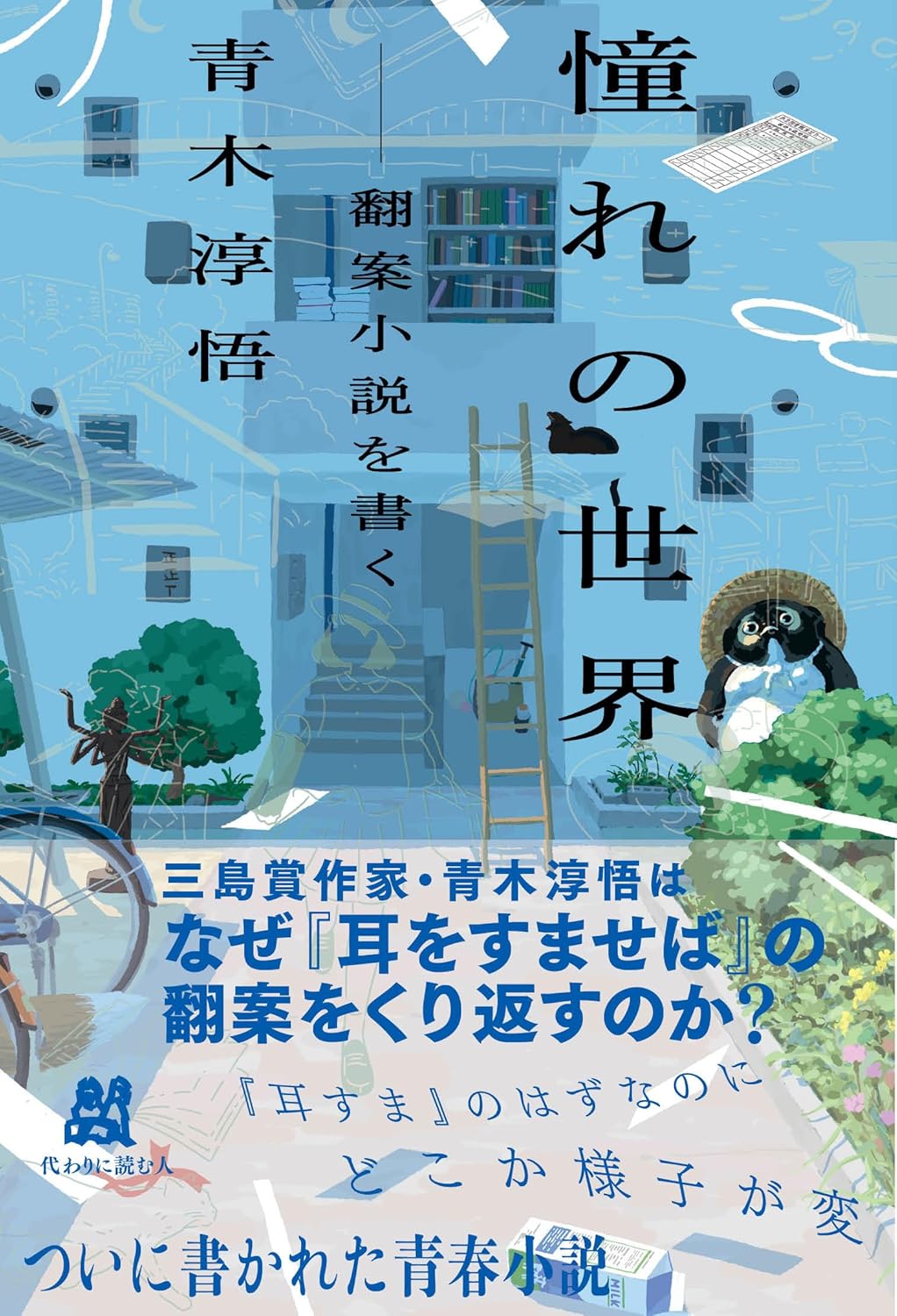

さとう・やすとも 1978年生まれ。名古屋大学卒業。文芸評論家。 2003年 、「『奇蹟』の一角」で第46回 群像新人文学賞評論部門受賞。その後、各誌に評論やエッセイを執筆。『月刊望星』にも多くの文学的エッセイを寄稿した。新刊紹介のレギュラー評者。
バックナンバー