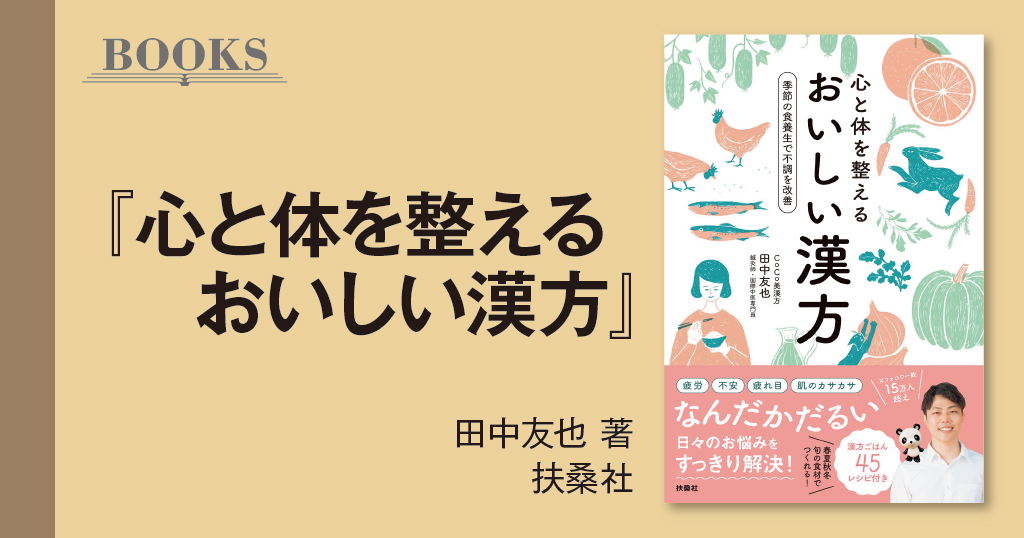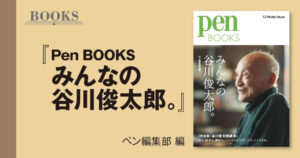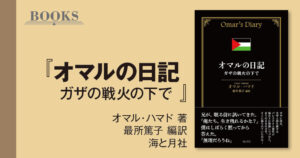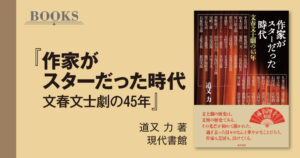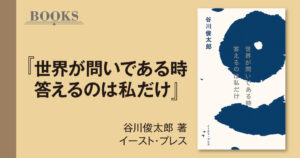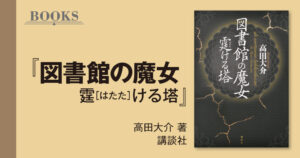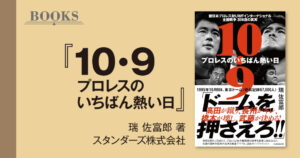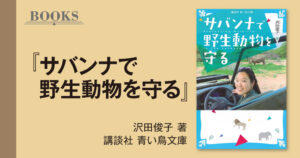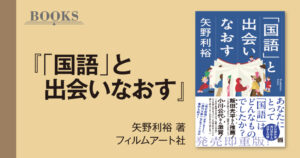旬のものを食べるのがいいのは、なぜか?
東洋医学において最も大切とされる概念のひとつ、「養生」は奥深い言葉だ。一般に養生とは、生活習慣に注意して健康維持を心がけること、あるいは病やケガからの回復に努めることを指す。漢方における養生で重視されるのは、そうしたセルフケア全般だけではない。まず自分の体をよく知ること、心のありようを見つめ直すこと、さらにいわゆる「気血水」や「五臓」のバランスを整えることも含まれる。
養生のうち、食事に関するものは食養生または食養と呼ばれ、体質や体調に合う食材を用いて健康維持・促進を図る。薬膳料理も食養生の一種だが、本書で扱うのは本格的な薬膳ではない。それぞれの食材のもつ性質や効能に着目し、いつ何をどのように食べたらよいかというアドバイスを季節ごとにまとめたものなので、薬膳よりもシンプルで、気軽に日々の食事にとり入れやすい。
著者の田中さんは鍼灸師で、国際中医専門員の資格をもつ。まだ三十代半ばの若さながら、養生やツボ押しなど、漢方に関する著作はすでに八作を数える。
本書では「人間の体も自然の一部」とする漢方の基本的な考え方に触れたうえで、「肝・心・脾・肺・腎」(五臓)と、「酸味・苦味・甘味・辛味・鹹味」(五味)との関連性、「熱性・温性・平性・涼性・寒性」といった食材の性質(五性)についてかんたんに説明し、それぞれどんな意味をもつのかを平易に解き明かしてゆく。
たとえばこれから夏へと向かう六月は、五臓のうち「心」の季節にあたる。おすすめの食材は体にこもった熱を冷ますトマトやゴーヤ、肌トラブルに効果のあるさくらんぼ、気の巡りを良くし、胃腸の働きを回復させるシソ等々。とくに梅雨どきに適しているのは、溜まった「湿」を排出する冬瓜やスイカ、血行を改善して老廃物を排出する玉ねぎやニラ、胃腸を整え水分代謝を促進する米やブロッコリーなど、驚くほどきめ細かい。その多くが旬の食材と重なる。
「悪夢にうなされる人は緑豆もやしを」という一風変わったアドバイスまである。わかめ、春雨、のり、小豆、しじみなども同様に水分代謝を回復させ、快眠に導く働きがあるという。「目のしょぼしょぼにはにんじんを」「寒のかぜはしょうが、熱のかぜはりんごで対策」「気分が沈んだらたまご料理」など、ちょっと試してみたくなる記事である。
こうした食養生はすぐに効果が出るものではなく、習慣を少し変えることで心と体を変化させるものだ。西洋医学にのっとった現代栄養学とは、考え方もアプローチ方法も異なる。けれども両者を連携させ、実際の治療に役立てる試みは日々進んできている。中国にルーツをもち、日本独自の発展を遂げてきた漢方の知恵を日々の食事にとり入れ、体の内側からの変化をめざす本書もまたその一助となるはずである。
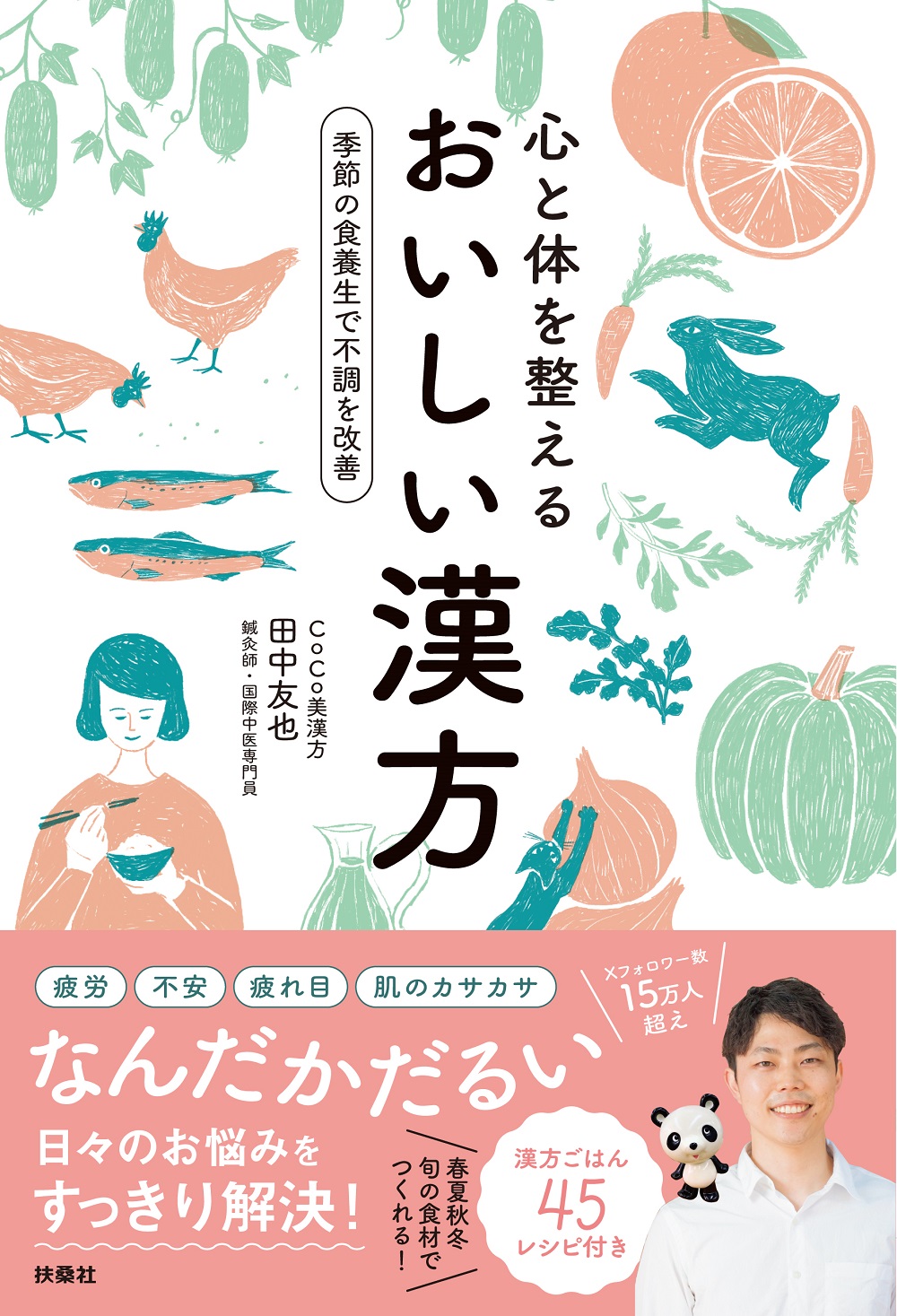
たなか・ともや 鍼灸師、国際中医専門員(国際中医師)、国際中医薬膳管理師、登録販売者資格保持。関西学院大学法学部卒業後、「イスクラ中医薬研修塾」にて中医学の基礎を学び、北京中医薬大学、上海中医薬大学などで研修。幼い頃より母親のもと、漢方や薬膳を身近に過ごし、現在、兵庫県にあるCoCo美漢方(ここびかんぽう)で日々、健康相談にのる傍ら、鍼灸師として施術も行う。四季折々に感じる体から心までの不調の解消法などをSNSで発信するほか、コラムやセミナーなどを通じて親しみやすいトーンで、漢方や中医学など東洋医学の普及に努めている。主な著者に『こころと体がラクになる ツボ押し養生』(学研プラス)、『いちばんやさしいおうち食養生 疲れた日の漢方ごはん』(KADOKAWA)などがある。
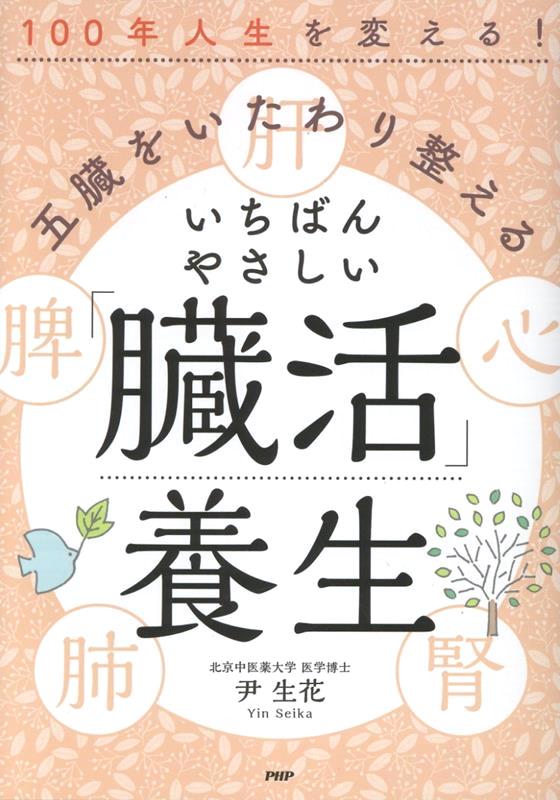
『五臓をいたわり整えるいちばんやさしい臓活養生』
(尹 生花著、PHP研究所、2025年1月)
まつなが・ゆいこ 1967年東京都生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。千代田区・文京区界隈の中小出版社で週刊美術雑誌、語学書、人文書等の編集部勤務を経て、 2013年より論創社編集長。