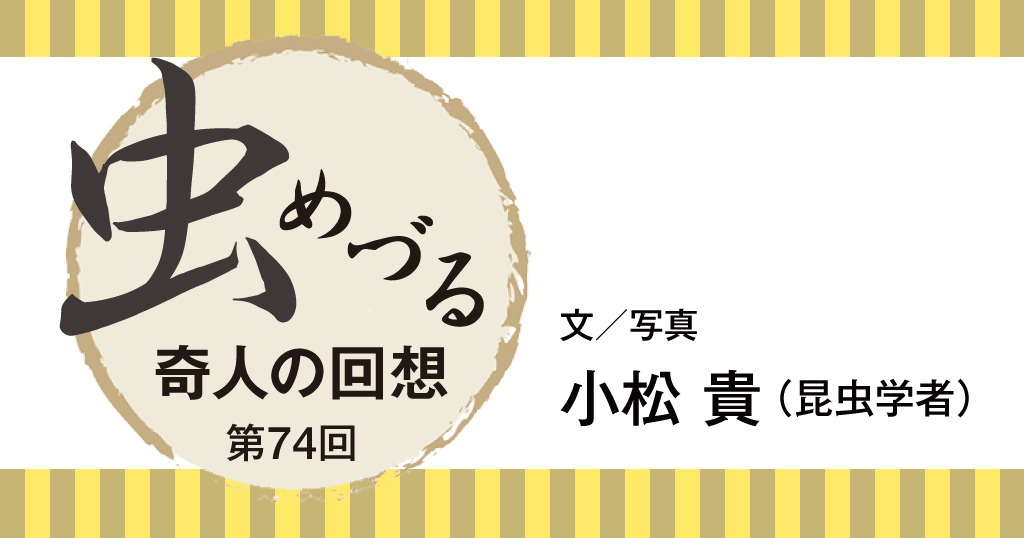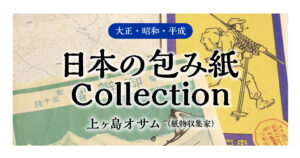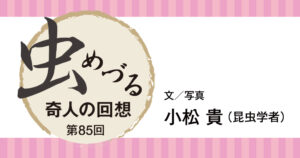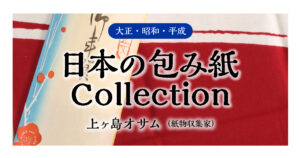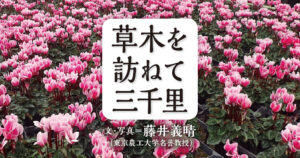第74回 日本は地下性生物大国
昨今、巷では深海生物が大人気だ。リュウグウノツカイやらダイオウグソクムシやら、毎年のように各地の博物館で深海生物の企画展示が行われている。深海生物のぬいぐるみやマスコットさえ、作られて売られているほどの人気ぶりである。しかし、同じ暗黒の世界に住む地下性の生物に関しては、驚くほど世間では一顧だにされないのは何故だろうか。日本は世界に誇る地下性生物大国だというのに。
我々は普段、自分らが立つ大地の下のことを、ただ土が詰まっただけの場所と思って生きているが、実際には岩や砂利同士の隙間が随所にあるもので、そうした隙間に生息することに特化した生物たちが存在するのだ。
通常、我々が「洞窟」と呼んでいるのは、そうした地下空隙の中でも自分たち人間が出入りできるサイズのもののことを指す。しかし、地下性生物たちの多くは体長わずか数ミリ程度の微小なものたちばかりなので、彼らにとっては洞窟も幅数ミリの砂利同士の隙間も自由に出入りできることには変わりない。彼らは、そんな大小の地下空隙をすり抜けながら生きている。
とはいえ、完全に自由という訳にはいかない。地下性生物は、湿潤な地下環境下で生きることに特化しているからだ。彼らは地下水脈の周辺から遠く離れることが出来ず、また場所によっては生息地の四方を移動困難な地質に囲まれている場合もあるため、それぞれが現在生息しているエリアに長年封じ込められてきた。その狭いエリアの中で他の仲間と交わることなく代替りを延々と続け、そこ固有の生物として進化してきたのだ。彼らは軒並み、世界でも今まさに生息しているそのエリアにしか見られないのが普通である。

他の弱小な生物を捕殺する獰猛な性格

メクラチビゴミムシの名前の是非に関する議論は辟易しているので、ここでは触れない
日本各地の地下空隙には、そんな地域固有性の高い生物たちがそこかしこに息づいている。火山島であるガラパゴス諸島は、一度も余所の大陸と地続きになったことがないため、この島固有の珍奇な動植物が多数生息することで知られるが、それとよく似ている。言わば、日本全国どこの地下にもガラパゴス諸島があるようなものだ。
深海生物の面々は、究極に深いエリアに住むものは別にして、暗闇に住む割には眼が発達したものが目立つ。僅かに上から差し込んでくる日光を効率よく拾い、周囲をよく見るための適応である。しかし、同じ暗闇でも地下は違う。感光紙をいつまで設置していても変化がない程、光が絶無の世界だ。いくら視力を発達させても、ここでは何の用もなさない。そんな暗黒世界に住むのを反映して、地下性の生物たちは眼を退化させたものが多い。種によっては、眼の痕跡すら残さずのっぺらぼうになったものも珍しくない。
また、有害な紫外線を浴びることもないため、体に光線を吸収するための色素がほとんどなく、地上に住む近縁種に比べて血色の悪い色をしているのが普通だ。薄い赤や黄色、場合により純白と、非常によく目立つ派手ななりをしているが、何しろ何も見えない世界ゆえ、それが原因で敵に襲われることもない。彼ら全てが、誰も見ていない煌びやかなファッションショーの主役である。

奥多摩の地下より得たが、同地一帯でかようなマシラグモは記録がなく、正体不明

眼を欠き、感覚毛の生えたハサミで他の生物を捕らえる。奥多摩の地下より得た

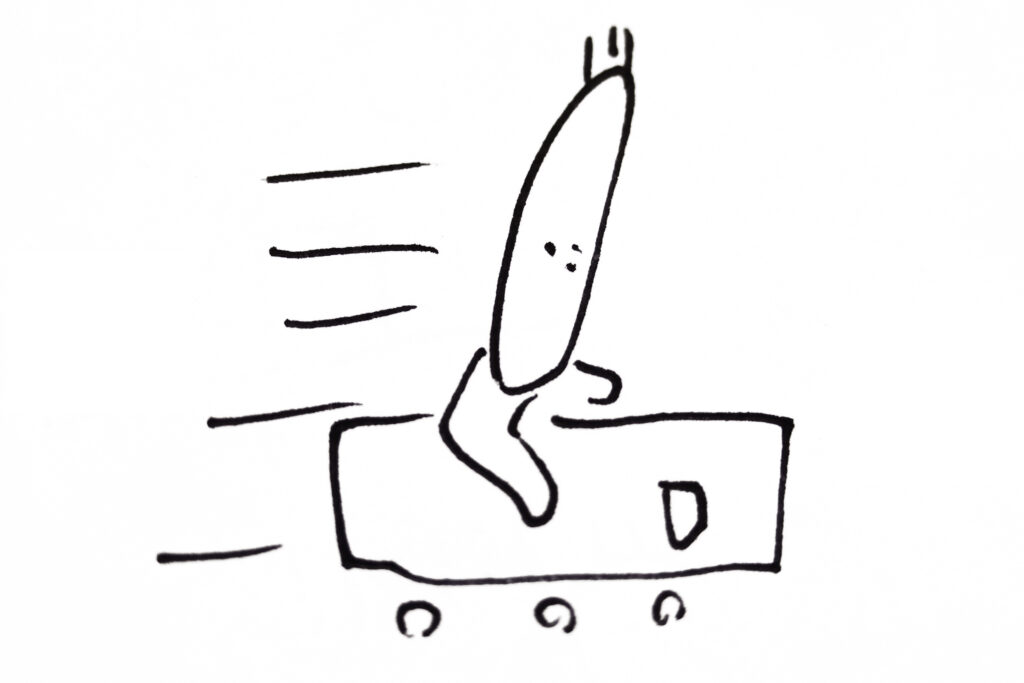
こまつ・たかし 1982年神奈川県生まれ。九州大学熱帯農学研究センターを経て、現在はフリーの昆虫学者として活動。『怪虫ざんまい―昆虫学者は今日も挙動不審』『昆虫学者はやめられない─裏山の奇人、徘徊の記』(ともに新潮社)など、著作多数。
バックナンバー