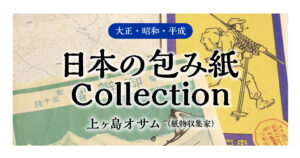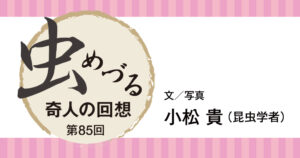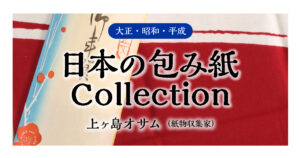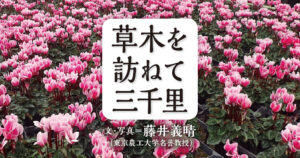第27回 美しく歩く姿は、なぜ百合なのか
今年も猛暑の毎日ですが、百合[ユリ]の花は負けずに元気に咲いています。
立てば芍薬座れば牡丹歩く姿は百合の花
日本の美人を形容する古い言葉ですが、芍薬[しゃくやく]が咲くのは五月中旬、牡丹[ぼたん]が咲くのは四月下旬、百合が咲くのは七月~九月なので、順番が異なっています。咲く順番でいえば、牡丹→芍薬→百合ですね。それに、最初は座っている人が、立って、歩くというほうが自然な順番なので、「座れば牡丹立てば芍薬歩く姿は百合の花」としたほうがよいと思うのですが……。
芍薬が真っ先に出てくるのは、三つの植物は婦人用の生薬として重要で、その筆頭が芍薬だからという説があります。牡丹も芍薬も百合も、婦人病に効く重要な生薬で、この言葉は生薬の使い方を意味しているというのです。
芍薬はいちばん有名な婦人薬で、とくに当帰芍薬散は有名です。虚弱体質の女性が飲むと、すっくと立てるようになる。女性特有の病気で弱ってしまい、座ってばかりいる女性には、牡丹皮(大黄牡丹皮湯など)が効果がある。百合の球根は、百合(ビャクゴウ)という生薬で、滋養強壮に効果があるので、服用すれば元気よく歩くことができるという説です。



ユリは古い大和言葉で、語源はよくわかっていませんが、花が重たいので、風に吹かれて揺れるので、ゆり(揺り)と呼ばれるとの説があります。
上のように写真を並べてみると、立っているところも美しいのですが、座っている姿も美しいし、すこし揺れ動きながら、しゃなりしゃなりと歩く姿も美しい、と日本美人をほめたことばとして、やはりオリジナルの順番がしっくり来るようです。
ところで、ユリという名前は、イヌやネコと同様、ユリの仲間すべてをひっくるめた名前で、〇〇ユリと呼ばれるたくさんのユリがあります。
牧野富太郎さんは、『植物知識』の中で、百合という漢字は、白い花が咲く中国の百合を意味し、日本固有の百合とは全く異なるので、「日本のユリに『百合』という漢字を使ってはいけない」と怒っています。
ユリ科はとても大きな科で、遺伝子に基づく分類のAPG体系で再分類される以前は、ネギ、ニンニク、ニラなどを含むヒガンバナ科、アスパラガスやリュウゼツランを含むクサスギカズラ科(キジカクシ科)、イヌサフラン科などの多くの科も含みました。現在も分類に関する研究が続いているようです。
日本固有のユリとしては、カノコユリ(鹿の子百合)が有名です。シーボルトが球根を持ち出してヨーロッパで知られるようになりました。シーボルトは日本の植物の多くをヨーロッパに持ち出してかなり儲けたようで、いわば園芸業者のさきがけといえるでしょうか。
カノコユリの学名は「Lilium speciosum Thunb.」。Thunb.は、命名者であるツンベルク(Thunberg チュンベリーとも発音する)を意味しています。ツンベルクは鎖国時代に長崎に医師として来日し、日本の植物を研究して多くの在来種に名前をつけたスウェーデンの大植物学者です。植物の学名の三番目は命名者になるのですが、「Thunb.」がついている植物は、だいたい日本在来種であることが多いですね。
環境活動家として有名なグレタ・トゥーンベリ(Greta Thunberg)さんも同じ姓なので、ツンベルクの子孫なのかもしれません。

花に鹿の子の斑点があるのが特徴
カノコユリの根はユリ根として食用になり、天明の飢饉のときや太平洋戦争のときには、食料として食べたとの記録があります。昔は山にたくさんあったようですが、最近では自生地でも数が減りつつあるので、環境省レッドリストで、絶滅危惧II類(VU)に指定されています。
オニユリ(鬼百合。学名はLilium lancifolium Thunb.)も、ツンベルクさんが命名した大型のユリで、草丈は1~2mになります。朝鮮半島や中国にも自生しており、日本のオニユリは3倍体(※)なのに、朝鮮半島や対馬には2倍体のオニユリがあるので、古い時代に朝鮮半島や中国から渡来したものではないかとされます。ヒガンバナも、日本にあるのはすべて3倍体で、中国南部に2倍体のコヒガンバナがあるので、中国南部が原産地とされます。
※ゲノムのワンセットをいくつ持っているのかという性質を倍数性と呼ぶ。ヒトの場合、23本の染色体セットを2つ持っているので2倍性となり、そのような生物を2倍体と呼ぶ。自然界には3倍性・3倍体や、4倍性・4倍体の生物もいる。
オニユリは、花が強く反り返るので、巻丹[けんたん]という名前もあります。巻きあがる丹(あかい)花の意味です。現在、日本で食用にされるユリ根の多くは、北海道のJAようていで栽培されているコオニユリのユリ根です。私の家ではお正月の茶碗蒸しに入れる縁起物です。

花が上向きに巻きあがっているのが特徴
スカシユリ(透百合、Lilium maculatum Thunb.)も、ツンベルクさんが命名した日本原産のユリです。花を上向きにつけるのが特徴で、花の根元が透けているので、透かしユリと名付けられました。
全国各地に、ミヤマスカシユリ、ヤマスカシユリ、イワトユリ、イワユリなどの変種があります。これらのユリも現地では数が減っていて、ミヤマスカシユリは環境省レッドリストで絶滅危惧IB類(EN)に、ヤマスカシユリは準絶滅危惧(NT)に指定されています。

花が上向きに咲き、花の根元が透けている
ヤマユリ(山百合、Lilium auratum Lindl.)も日本固有の大型のユリで、草丈は1.5mにもなります。地下のユリ根は、オニユリやカノコユリと同様に食用・薬用になります。上質なデンプンを多く含むので、縄文時代には食用にされていたとされます。
ヤマユリを自治体の花にしているところも多く、神奈川県、遠野市と滝沢市(岩手県)、八王子市(東京都)、柏崎市(新潟県)、松阪市(三重県)、行方市(茨城県)などが指定しています。他のユリに比べて、ヤマユリの花には、かなり強い芳香があります。

山の中でよく目立つユリ
ユリの花の匂いの成分は、安息香酸メチルやリナロール、オシメンといった芳香族化合物で、虫媒花であるユリが、昆虫を誘因するための手段のひとつと考えらますが、この匂いは、とくにカサブランカなどの栽培品種で多いことが分かっています。
カサブランカは、ヤマユリ、カノコユリなどを交配して、アメリカで作られ、オランダで品種として固定され命名された栽培品種で、ヨーロッパでは結婚式のブーケとして人気があるようです。しかし、西洋人と比べて、日本人はあまり強い芳香を好まないようで、日本の結婚式やレストランなどでは、その強い匂いが嫌われることがあります。
そこで、ユリの花の匂いを消す研究が行われました。
ユリの花の匂いは、フェニルアラニン・アンモニア・リアーゼ(PAL)という酵素によって生成することが分かっており、この酵素のはたらきを阻害する物質を加えることで、匂いの発生を抑制する技術が、2008年に農研機構(※)の大久保直美さんたちによって開発されています。切り花にしたとき、水にこの物質を加えると、強い匂いを抑えることができるので、栽培ユリ品種の需要拡大に貢献しているようです。
日本原産で、ヨーロッパで大人気となり、栽培品種が日本に逆輸入されたユリですが、日本美人を表した言葉にある在来のユリも大切にし、お正月にはユリ根でお祝いする伝統を保ちたいものです。
※国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

ふじい・よしはる 1955年兵庫県生まれ。博士(農学)。東京農工大学名誉教授。鯉渕学園農業栄養専門学校教授。2009年、植物のアレロパシー研究で文部科学大臣表彰科学技術賞受賞。『植物たちの静かな戦い』(化学同人)ほか著書多数。
バックナンバー