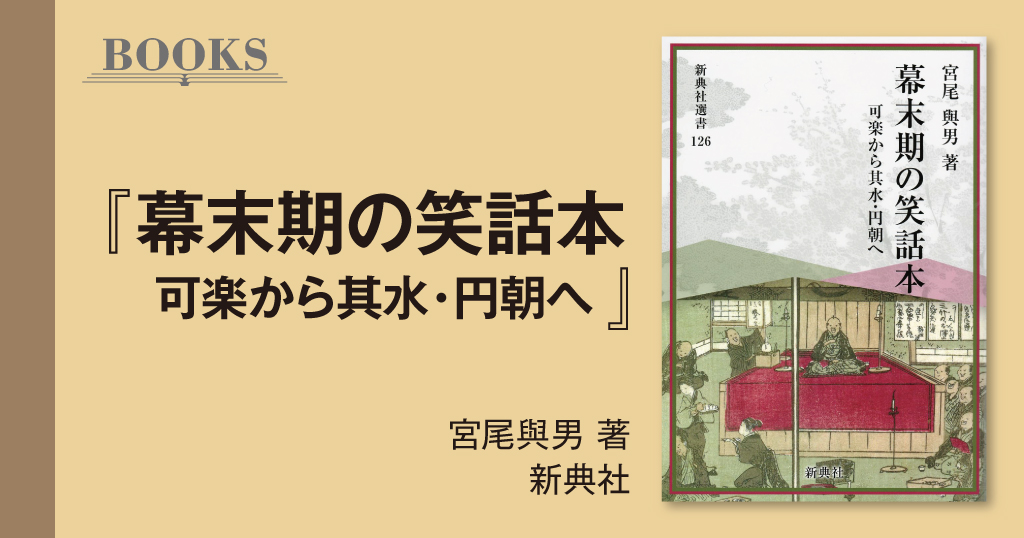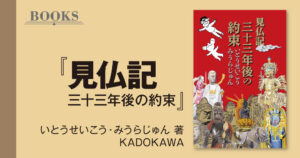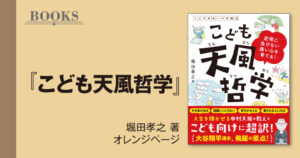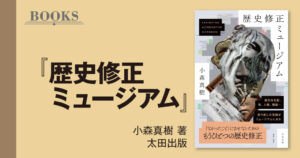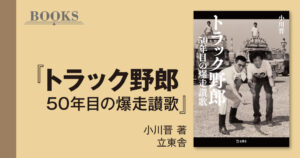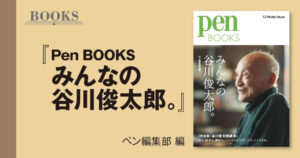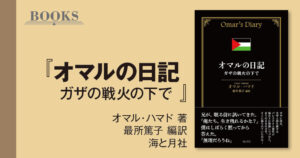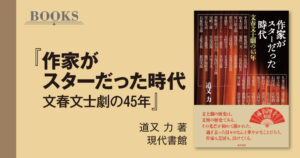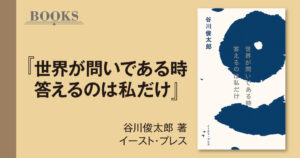三題噺の代々のダイナミズム
観客から三つのお題をもらい、それらを盛り込んでオチのある話をこしらえるのが三題噺[さんだいばなし]である。かつて朝日放送制作の『ざこば・鶴瓶らくごのご』というテレビ番組では、桂ざこばと笑福亭鶴瓶が毎週、この三題噺に挑戦していて、私は楽しく視聴していた。
寄席でも、池袋演芸場にて三遊亭白鳥が、師匠円丈の衣鉢[いはつ]を継ぎ、三題噺でトリをつとめるのを何度かきいたことがある。物語の生まれる臨場感が伝わってきて、興奮した。
本書によると、江戸の落語家・三笑亭可楽[さんしょうてい・からく]が文化元年(1804)、落語会で披露したのが三題噺の起こりという。現代だと、長めの落語に仕上げる感があるが、可楽の三題噺は落語の合間に演じられる余興の一つであり、分類としては笑話[しょうわ]と呼ばれる、ごく短い、小噺[こばなし]のような仕上がりだったようだ。
可楽没後、三題噺の火は途絶えかけたが、万延元年から文久元年(1860~1861)の頃に、それを組織的に復活させたのが、狂言作者、戯作者、落語家、浮世絵師、役人らの同人が集った「三題噺の会」だった。
メンバーは、仮名垣魯文[かながき・ろぶん]、山々亭有人[さんさんてい・ありんど]、柳亭左楽[りゅうてい・さらく]、河竹其水[かわたけ・きすい](のちの黙阿弥)、三遊亭円朝[さんゆうてい・えんちょう]等々。
彼らは月一で集まり、前日までに与えられたお題でそれぞれ三題噺を自作自演し、評価しあい、優秀作には景品をふるまった。その切磋琢磨の中から、古典落語の名作「鰍沢[かじかさわ]」も生まれ……。
《三題噺の会の存在は、個人の力で乗り越える創作の世界を、共同の意識をもった同人組織で乗り越えることを可能にし、あたらしい時代の文化の基礎をつくったのである。》
新出資料を含む笑話本の数々を吟味し、「鰍沢」の成立に迫るとともに、幕末期における〝三題噺魂〟のリレーを詳述するのが本書である。最近でいうところの「実験落語」や「SWA」のような創作落語集団の研鑽が、幕末にもあったのだなあと驚いた。
当時の三題噺の作例が多数、紹介される。ただ、現代ではあまり耳にしない語彙もけっこうあり、解説を手掛かりに何となく笑い所がつかめるといったものが大半ゆえ、読んで笑うというよりは、勉強になる感じだ。江戸人の共通理解が垣間見られる。
創作のコツについても紹介され、興味深い。
たとえば可楽が即座に三題噺を創作できたのは、俳諧に通じており、『俳諧類舩集』[はいかいるいせんしゅう]のような付合語集(ある語から連想される語を列挙した書物)を熟知していたからではないかと著者は類推する。となると、連想語を時代ごとにアップデートすれば、現代の三題噺づくりにも応用可能かもしれない。
可楽が三題噺のヒントを得た可能性のある書物(『新撰勸進話』)には、お題をもとに新作を創る際の、こんな指南が書かれているという。「卽席作のことなれば、おとしのおもしろく、利屈の詰[つまり]たることは出來ぬもの也。なんとか成共、こぢ附て、おとしさへすればよし」(即席で作るものなので、オチが面白くて理にかなった話は出来ないものだ。どうにかこうにかでいいので、お題をこじつけて、オチをつけさえすればいい)。
作り手の肩の力を抜いてくれそうな、現実的なアドバイスで笑ってしまった。
本書を機に、三題噺ブームがまた来てほしい。
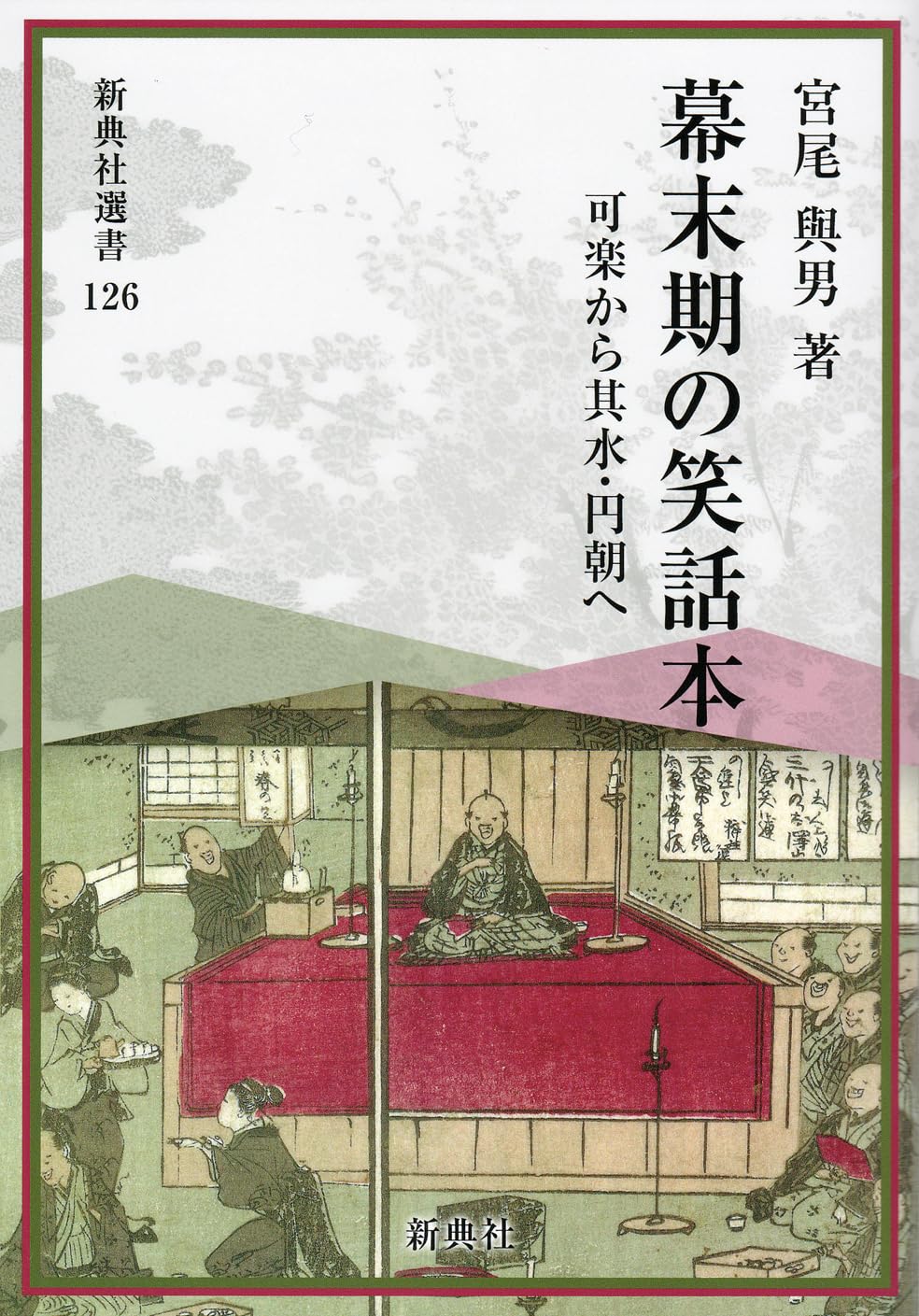

さとう・やすとも 1978年生まれ。名古屋大学卒業。文芸評論家。 2003年 、「『奇蹟』の一角」で第46回 群像新人文学賞評論部門受賞。その後、各誌に評論やエッセイを執筆。『月刊望星』にも多くの文学的エッセイを寄稿した。新刊紹介のレギュラー評者。
バックナンバー