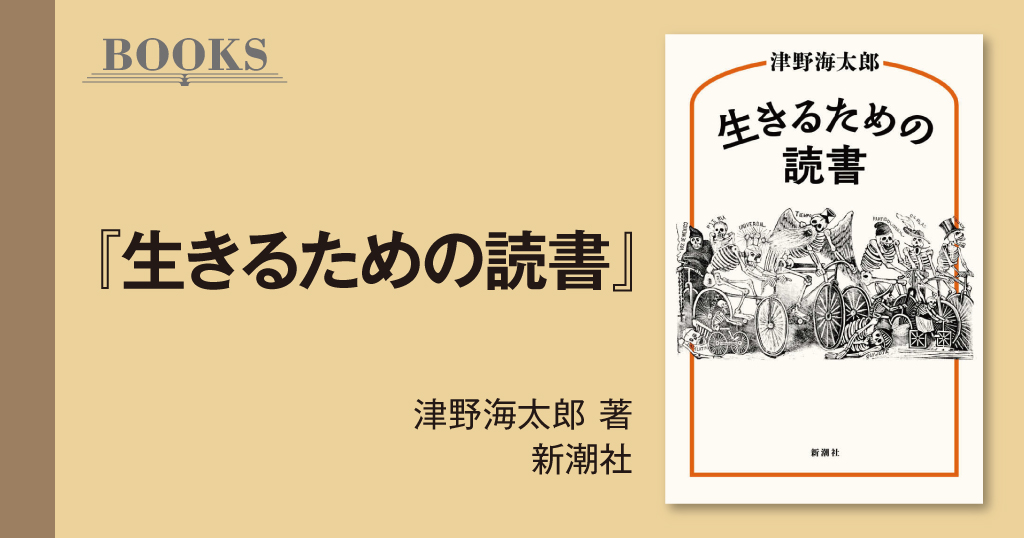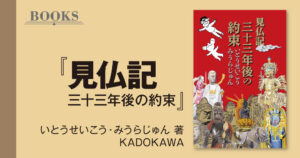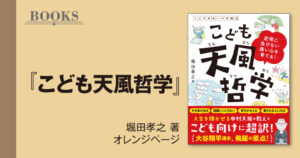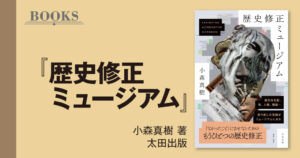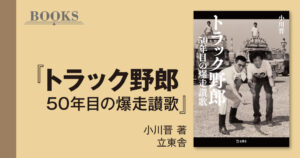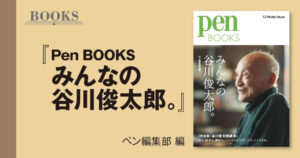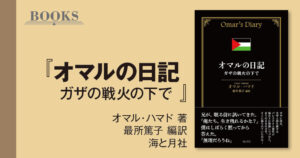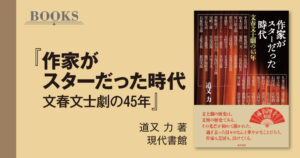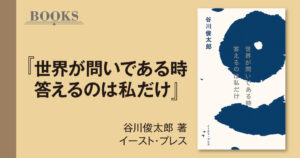敬遠してきた若い人の本と向き合ってみたら
晶文社で編集者として働いてきた津野海太郎氏。電子書籍が出てきたころ『季刊・本とコンピュータ』の編集長となり、電子書籍の可能性や出版とコンピュータがつながることがメディアにもたらす未来を探った。一方で劇団「黒テント」の演出、ほか多くの評論やエッセイを発表してきた。
多彩な活躍をしてきた津野氏が今年八十六歳になった。老人として生きていることに飽きてしまった、というか「このまま老化のつづきとして、この世から淡々と消えていくのも、ちょっとなあ」と揺れのごときものが生じてくる。あと何年生きられるかは不明。その残された短い時間を「もうじき死ぬ人」として生きてみる――と、津野氏は新たな読書の冒険に乗り出す。
氏には「お祭り読書」という自前の読書法がある。なにか新しい問題にぶつかるたびに、それと「直接間接にかかわる本を、ひとまず満足できるだけの量、むちゃくちゃに読む」というもの。
「お祭り読書」の最中に気がつくと、これまでは敬遠していた若い人たちの本、なかでも三十代から四十代半ばまでの人々、主に人文系の研究者たちの本を読むことが多くなった。今の幼い子どもはこれからの未来、気候変動・土壌破壊・大地震・格差の拡大など、暗い世界で生きることになるかもしれない。氏が注目する書き手の世代は、その幼い子どもを育てている親たちの世代だ。
伊藤亜紗氏の『目の見えない人は世界をどう見ているのか』。伊藤氏は東京大学の理系コースで生物学を学ぶも、3年次で文系に転じ博士号を取得。美学を専攻する研究者だ。自分と異なる体の人が感じている世界を知りたい、とのこと。伊藤氏がインタビューした視覚障害者のひとり、生まれついての弱視で十六歳で失明した男性と東急・大岡山駅から東京工業大学(現・東京科学大学)大岡山キャンパスに向かう道を歩いた。男性は「大岡山はやっぱり山で、いまその斜面を降りているんですね」とつぶやいた。それを聞いて、この坂を大学に向かう道順の一部としか思っていなかった伊藤氏は、かなりびっくりしたという。視覚を使わない男性は、大岡山という地名と、足の裏で感じる傾きで山というイメージを得ているらしい。
森田真生[まさお]氏の『数学する身体』。森田氏は幼少年期をシカゴで過ごし、東京大学文科二類、工学部を経て理学部数学科に学士入学。卒業後「独立研究者」として研究・執筆するかたわら、2009年から数学の世界を紹介するためにトークライブをつづけていた。それが少し変わったのは、日本では2020年1月にはじまった新型コロナウイルス感染症流行のため。京都の自宅に妻と二人の幼い息子とで閉じこもる生活。「ねぇ、おうちも、おにわも、ぜーんぶようちえんにするのはどうかな!?」という四歳の長男の提案から、裏庭の開墾をはじめた。そこから農業、土壌や環境の問題まで、その道の専門家とつながって進んで世界を広げていく。
津野氏は注目する若い書き手の本について、ほかにも四人をこの本で紹介し、感慨にふける。研究者はこれまで世間から遠く離れたところで、かたい文章で持論を発表してきた。だが、このごろは世間の小さな人々について自分の心身で触れ、やわらかい文章で書いている。このことはますます息苦しくなる世界に押しつぶされずにいるための読書、つまりは「生きるための読書」を求める読者と対をなしているらしい、と津野氏は言う。
本を書く者と読む者のあいだに、これまでとはちがう性質の対話が生まれ、社会と文化のありようが変化しはじめた気配を感じる。津野氏は「ややかたい頭」の自分たちの世代が消えていくのを惜しみつつも、新しい変化にわくわくしているのだ。
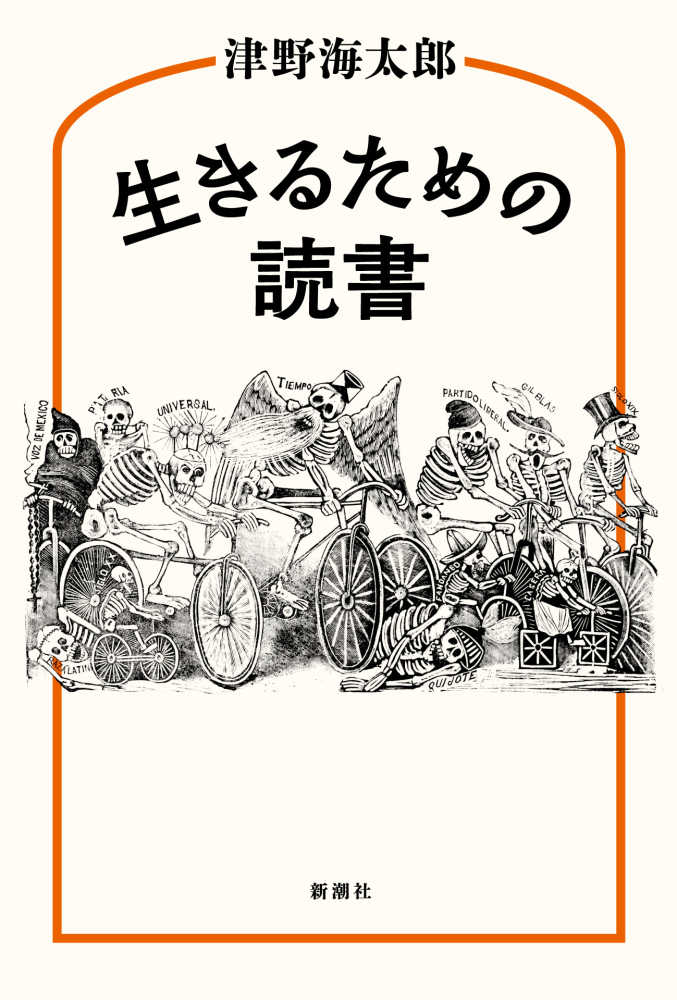
つの・かいたろう 1938年、福岡生まれ。評論家・編集者・演出家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」の演出に携わる。晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授、同図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人——坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝——日本の暮しをかえた男』『百歳までの読書術』『読書と日本人』『最後の読書』(読売文学賞)、『かれが最後に書いた本』『編集の提案』ほか多数。

さわ・いずみ 1968年、神奈川県生まれ。大学院修士課程修了。専攻は中世アイスランド社会。出版社勤務を経て司書。公共・博物館図書室・学校図書館とさまざまな図書館を渡り歩いたあと、現在介護休業中。最近はアイスランドの火山噴火が心配。写真は近所の公園の白梅。香りが清々しいです。今年は寒波のせいか、花が咲くのがやや遅めのようです。
バックナンバー