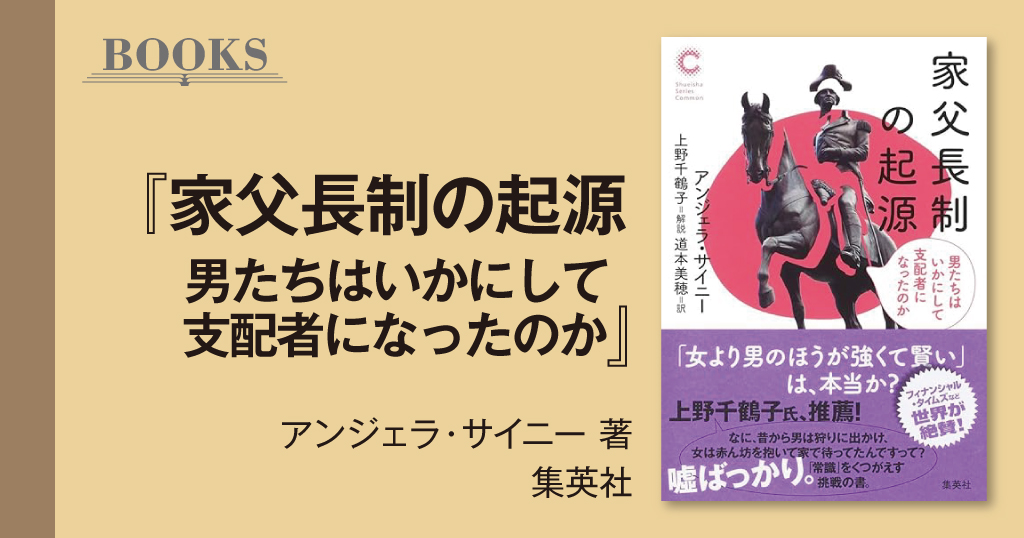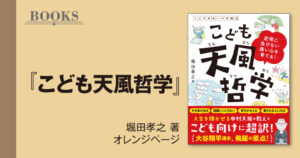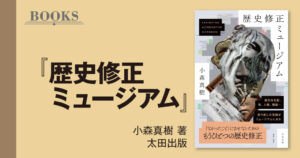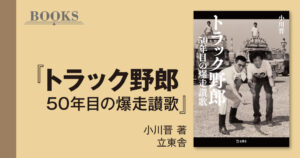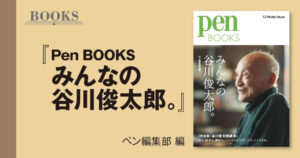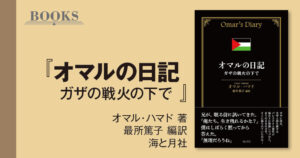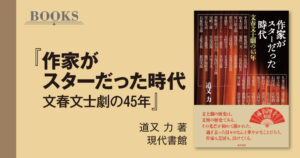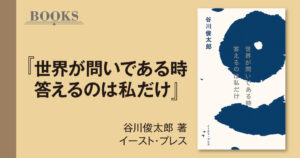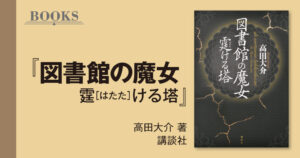家父長制はなにをもたらしているのか?
ヒンズー教にカーリーという女神がいる。神話によると、悪魔との戦いのために出現した恐ろしく猛々しい神で、青黒い肌に四本の腕、首に生首または髑髏をつないだ首飾り、腰に切り取った手足で作った腰巻という恐ろしい姿。悪魔を殺戮すると勝利に酔って踊りだした。その激しさは大地を砕く勢いで、衝撃を弱めるために足下には最高神シヴァが横たわらなければならなかった。
科学ジャーナリストの著者・アンジェラ・サイニーによると、カーリーはインドの植民地時代においてナショナリズムを掲げる革命家らの植民地支配への抵抗のシンボルだったそうだ。そして現在では、女性の権利を主張する活動家に支持されているという。ヒンズー教徒が多数派のインドでは、女性の殺害や不条理な暴力、児童婚が続いている。この強く恐ろしい女神は、虐げられた者にとっては社会秩序を打ち砕きたいという怒りのよりどころなのかもしれない。
家父長制とは、家長である男性が家族全員に対して支配権を持つ父系の家族形態。現代では家族内にとどまらず、企業や国家にも存在する。17世紀イギリスの政治思想家ロバート・フィルマーは、著書『家父長論』でこう書いている。国家は家族のようなもので、国王は実質的に父で臣民は子ども、国王は神から任命されたこの世の絶対的な家父長である、と。
家父長制とは違う母系社会は世界の各地に痕跡がある。インド南部ケララ州のナヤール族は母系大家族で暮らしていたことで有名だ。しかし19世紀ごろから大家族は解体された。またインド北東部のメガラヤ州のカーシ族は今も母系制を守っている。
一方、家父長制社会でもさまざまな形がある。父系でのみ継承される社会や父系母系の双方で継承できる社会など。スウェーデンにあるヴァイキング時代の都市遺跡ビルカで見つかった墓で、副葬品から埋葬されているのは身分の高い戦士と考えられていた。だが遺伝学的証拠からそれが女性だと判明した。ヴァイキングの世界で戦う女性は神話や伝承では語られていたが、実際に戦闘をするとは考えられてなかった。その女性は軍の指導者だったが、社会の支配層に属していたから、その地位に就くことができたのかもしれない。
そして近現代の家父長制。男性は外で働き、女性は家の中で家事・育児・介護をし、夫に従い夫のために陰で尽くすのが最良、でなければ男性より低給与でやはり男性に従って労働するしかない。なぜこんな形になったのか。著者は近代の欧米型国家のありようが大きいと考える。国家の戦争と植民地支配・経済競争に人員をつぎ込むため、国家は家族に介入した。男性はみな家長で兵士候補で労働者、女性が従属者で家庭内の仕事を一手に引き受けた。当然、政治家も企業の重役も男性ばかり。家父長制は、国家のために人を統制するシステムとなった。ソ連の共産主義下で外で働く女性は大幅に増えた。だが家事や育児を担う男性はほとんどいなかったため、家庭内の仕事も女性が担った。
憲法は、国家は国民の幸福に尽力することを掲げている。しかし著者は言う。国家の要求よりも個人の要望を大事にし、世の中の仕打ちから私たち一人ひとりを守ってくれる政治体制を私たちは今もつくり出せていない、と。これまでの家父長制から個人を守る体制に変えることは、女性だけを助けるのではない。男性に望まない戦争や生き方を押しつけることがなくなる。国家も個人も変わる時が来た。
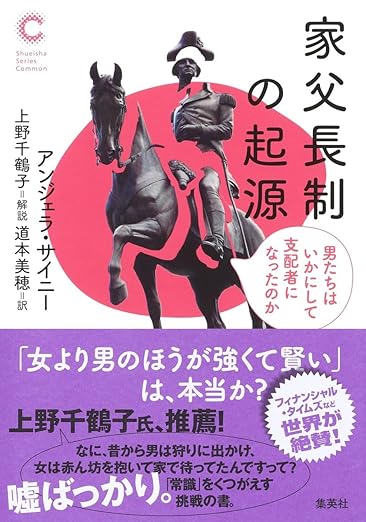
科学ジャーナリスト。オックスフォード大学で工学、キングス・カレッジ・ロンドンで科学と安全保障の修士号を取得。オックスフォード大学・キーブルカレッジ名誉フェロー。BBCやガーディアンなど英米の主要メディアに多数登場。著書に『科学の女性差別とたたかう』『科学の人種差別とたたかう』など。

さわ・いずみ 出版社勤務を経て司書。さまざまな図書館を渡り歩いたあと、現在介護休業中。
秋に宮島へ旅行しました。宮島の鹿たちは、観光客に危険がないように角を根元から切られていました。鹿たちは観光客といっしょに写真に入ったり、食べ歩いている観光客の後ろをついて歩いたり、コンビニの前で昼寝したり。そんな鹿たちのなかで、この鹿だけが立派な角を立てて、人通りの少ないところでくつろいでいました。毛が白いところが多いし、たぶん高齢の鹿だと思いました。鹿の群れの長なのかもしれません。偉い家父長なのでしょう。
バックナンバー