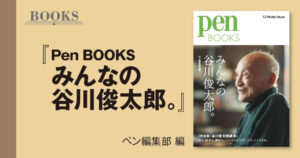芸術か!? 爆発か!?
しゃれたストリートアートを展開し、〈日本のバンクシー〉と世間から呼ばれる正体不明の存在「ブラックロータス」の意図を、フリーライターの「私」が探る第一部。日本各地を二十年近くボムってきたグラフィティライター「TEEL[テエル]」が、彼に憧れる若者からゴーイング・オーヴァーを挑まれる第二部。以上からなる本作は、グラフィティをめぐる今を多角的に描いた、2024年の松本清張賞受賞作である。
グラフィティとは、60年代末のニューヨークに始まった、主に公共空間に自身のタグ・ネーム(グラフィティ用の名義)を書き残していく文化を指す。街の電信柱や看板、高架下の壁などに、アルファベットの謎の文字がスプレーで落書きされていたり、やはり謎のステッカーが貼られていたりするのを見かけることがある。あれだ。署名であること、あるいは自分が書いたという書き手のシグナルが根底にあることが大事な要素であり、へのへのもへじや、戯歌[ざれうた]の類とは一線を画している。
街にグラフィティを残す行為をボムと言う。ライター同士が互いの署名に上書きしあって競うのがゴーイング・オーヴァー。上書きにも然るべき流儀が伝わっていたり、ステッカーをどこに貼るかについても独特の美意識が問われたりするらしい。日常の物陰に、そんな世界が広がっていたとは!と驚かされる点では、たしかに松本清張っぽくもある社会派ミステリーに思えた。
討論劇的な側面も色濃い。登場人物たちは各々の立場から、グラフィティとは何かを語る。ただの軽犯罪なのか。芸術なのか。カウンターカルチャーなのか。心の叫びなのか。大衆受けするストリートアートはグラフィティとは呼べないのか。その行く末をどう見据えたらいいのか。一筋縄では概念化しにくいグラフィティにまつわる争点がいくつも浮かび上がり、読者に問いかけてくる。
読んでいて思い出すのは、鶴見俊輔の『限界芸術論』だ。広義の落書きをはじめ、絵馬や鼻歌、盆踊りやなぞなぞ、日常の身ぶりや、笑い方泣き方といった、非専門的な芸術者によってつくられる、芸術と生活との境界線にあたる作品を、鶴見は限界芸術と呼んだ。本能のようにボムする第二部のTEELの姿に、なんだかスカッとした魅力を感じるのは、そこに誰もが持つ限界芸術的な、表現せずにはいられぬ気持ちの根っこが、ほの見えるためかもしれない。
かつてプロレスラーの蝶野正洋が、新日本プロレスのチャンピオンベルトにスプレーを噴射した逸話も思い出した。蝶野は「IWGP」のベルトに、当時自身が所属していたユニット名である「nWo」の文字を上書きした。たしか「IWGPのIは猪木のIだから消す」と言っていたはず。実際のIはインターナショナルのIだが、あの行為も蝶野なりのゴーイング・オーヴァーだったのだろう。
本作のクライマックスの舞台が神奈川県川崎市と東京都狛江[こまえ]市とを結ぶ多摩水道橋であることからは、山田太一脚本のテレビドラマ『岸辺のアルバム』を想起した。狛江市の堤防が決壊した多摩川水害を題材に、家族の決壊と再生を描いたドラマである。家庭にがんじがらめになっている主婦役の八千草薫が、自宅のガラスにクリーナーのスプレーをかけていく場面(第2話)があったが、あれも〝私はここにいる!〟と示す、一種のボムだったのでは?
そして今後は、街でグラフィティを見かけるたび、必ずや本作を思い出すことになるだろう。
いのうえ・さきと 1994年愛知県生まれ。成城大学文芸学部文化史学科卒業。会社員。

さとう・やすとも 1978年生まれ。名古屋大学卒業。文芸評論家。 2003年 、「『奇蹟』の一角」で第46回 群像新人文学賞評論部門受賞。その後、各誌に評論やエッセイを執筆。『月刊望星』にも多くの文学的エッセイを寄稿した。新刊紹介のレギュラー評者。
バックナンバー