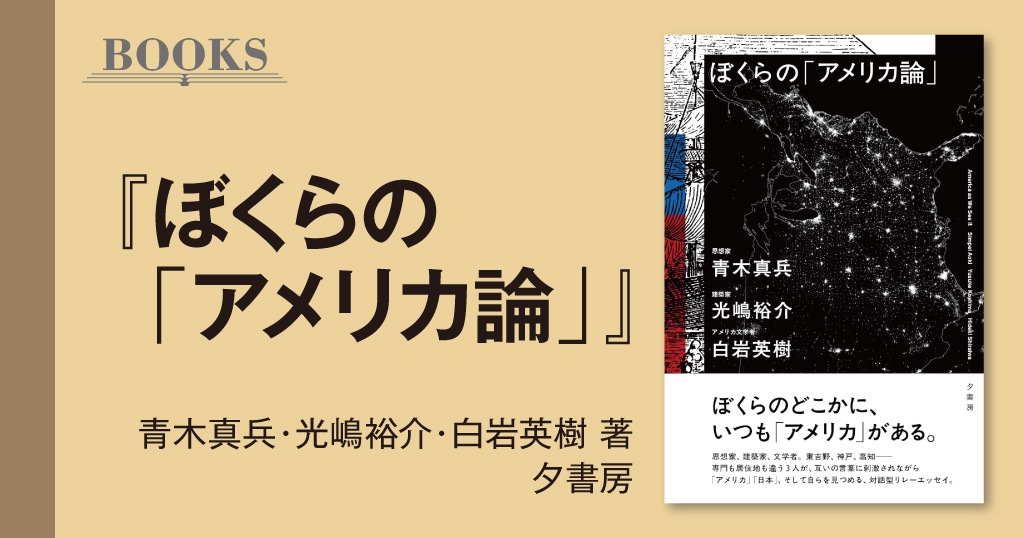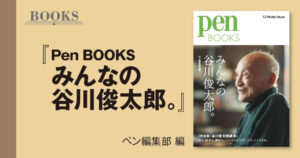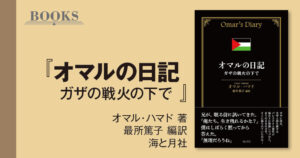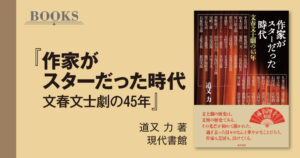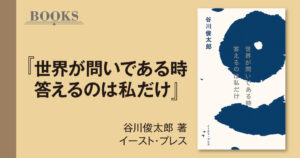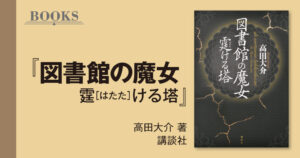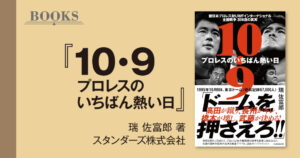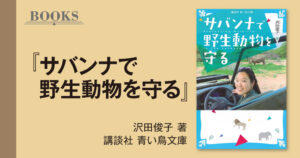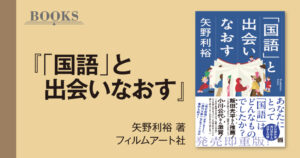アメリカの「草の根デモクラシー」は再生をめざす
2017年に第四十五代アメリカ大統領となったドナルド・トランプ氏が、今年再び第四十七代の大統領に就任した。今、世界のニュースがトランプ氏主演の劇を上演しているように見える。
この本はアメリカについて三人の書き手によるリレーエッセイがもとになっている。昨年までWebサイトで連載していた。書かれた時期はアメリカ大統領選の前。当時トランプ氏をふくめた候補者たちが選挙活動にしのぎを削っていた。リレーエッセイを発案したのは「人文系私設図書館ルチャ・リブロ」キュレーター青木真兵氏。青木氏はほかにも、ネットラジオ「オムライスラヂオ」で市井の小さな個人の声を配信、社会福祉士ほか本の執筆など多彩な活動をしている。
考古学を学び、古代フェニキア人が北アフリカの地中海沿岸に作った都市国家カルタゴの研究で博士号を取得した青木氏は、学者としてはアメリカにそれほど興味はなかった。だが現代社会を見ると、アメリカの影響は日本にも行きわたっている。障害のある人の就労支援の仕事をしていて、現代社会でいかに生きるかを探るには、アメリカ的なるものを知る必要がでてきた。
アメリカ的なるものを知るための企画で青木氏の呼びかけに応えたのは、アメリカで生まれ育った建築家・光嶋裕介氏、アメリカ文学の研究者・白岩英樹氏。この三人がそれぞれのアメリカを語る。別々の方面からアメリカを書いた三人の文章のリレーは、輪になってアメリカ論を形成する。
アメリカ文学研究者の白岩氏は、アメリカは「生き直し・再生」の国だと言う。イギリスの植民地だったアメリカが、アメリカ革命から独立戦争を経て国家として独立を得た。アメリカ独立宣言には「すべての人間は平等に創られている」とはっきり書き記された。だが「すべての人間」に先住民族や黒人奴隷は入らないものと見なされてこぼれ落とされ、長いあいだ未完の革命の犠牲者に甘んじねばならなかった。女性もまた「すべての人間」には入れられず、生きる場所を制限され、そこに閉じ込められてきた。そして世界各国から移民がやってきたが、貧富の差と民族差別が人々を分断した。その分断はアメリカ独立宣言が掲げる「すべての人間は平等に創られている」という理念と対立するものだった。
「すべての人間」からはじかれた人々は、アメリカ社会での自らの権利を取り戻すため公民権運動やウーマン・リブをはじめ市民による社会運動を立ち上げ、社会のなかでの「生き直し」をめざした。その結果、公民権法は何度も修正を加えられ、民族や性別による差別のない領域がだんだん広くなっていった。アメリカの「草の根デモクラシー」は国家を大きく揺るがし、政府に「再生」を迫り続ける力がある。アメリカ革命は今も継続している未完の革命なのだ。
建築家・光嶋氏にとって、生まれ故郷であるアメリカは自身の自我の形成に大きな位置を占めている。不確実な世の中において、他者をわかり合えないと決めつけ、無関心や不寛容を募らせていては、社会の分断が深まるばかりだ、光嶋氏は言う。同質的な集団にぬくぬく安住して閉じこもっていては、見えないものがある。未知なるものと遭遇しながら、敬意をもって終わりのない対話を重ねていくしかないだろう、と。
アメリカで意見や立場が違う者が対立するとき、解決をめざすために公的な場で対話や討論会が行われる。対話を重ねながら歩みよりの道を探ることができる社会なのだ。日本でも社会の分断や外国人移住者の是非が問われているが、対話を重ねるには至っていない。現在、トランプ大統領のアメリカでは、アメリカとしての政治・外交・経済や民族問題や性別の在り方についての考えで、国民の分断が広がっているそうだ。だがアメリカは、市民が活動し対話を重ねることで人々が歩み寄り、再生してきた。これから、また同じように歩み寄りと再生が起こると信じたい。
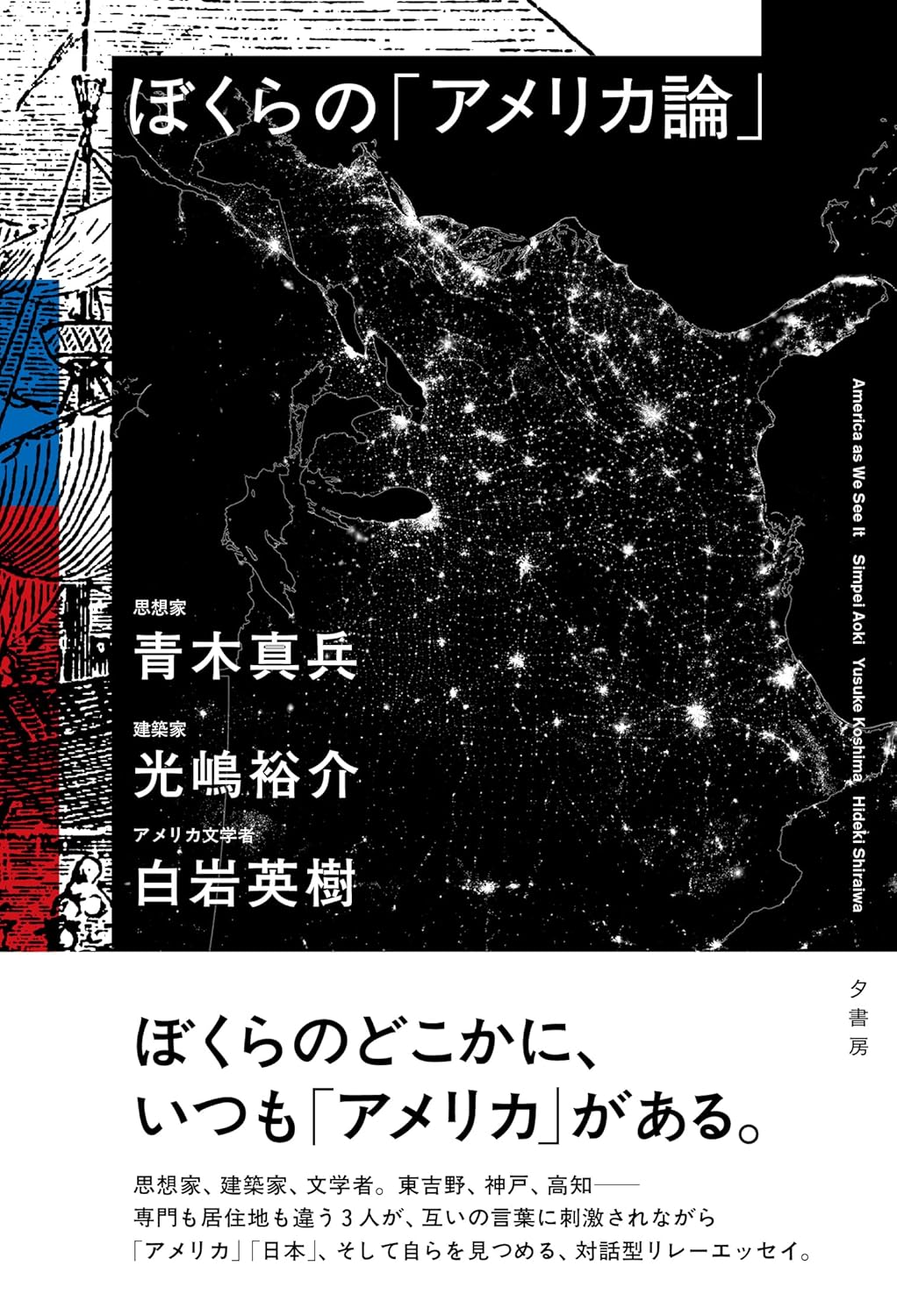
あおき・しんぺい 1983年生まれ、埼玉県浦和市(現・さいたま市)に育つ。「人文系私設図書館ルチャ・リブロ」キュレーター。博士(文学)。社会福祉士。2014年より実験的ネットラジオ「オムライスラヂオ」の配信をライフワークとしている。2016年より奈良県東吉野村で自宅を私設図書館として開きつつ、執筆活動などを行っている。著書に『武器としての土着思考 僕たちが「資本の原理」から逃れて「移住との格闘」に希望を見出した理由』(東洋経済新報社)、『手づくりのアジール 土着の知が生まれるところ』(晶文社)、妻・青木海青子との共著に『彼岸の図書館 ぼくたちの「移住」のかたち』(夕書房)、『山學ノオト』シリーズ(エイチアンドエスカンパニー)、光嶋裕介との共著に『つくる人になるために 若き建築家と思想家の往復書簡』(灯光舎)がある。
こうしま・ゆうすけ 1979年、アメリカ・ニュージャージー州生まれ。建築家。早稲田大学理工学部建築学科修了。ドイツの建築設計事務所で働いたのち2008年に帰国、独立。建築作品に内田樹氏の自宅兼道場《凱風館》、《旅人庵》、《森の生活》、《桃沢野外活動センター》など。著書に『ここちよさの建築』(NHK出版 学びのきほん)、『これからの建築 スケッチしながら考えた』『つくるをひらく』(ミシマ社)、『建築という対話 僕はこうして家をつくる』(ちくまプリマー新書)、『増補 みんなの家。建築家一年生の初仕事と今になって思うこと』(ちくま文庫)などがある。
しらいわ・ひでき 1976年、福島県郡山市生まれ。高知県立大学文化学部/人間生活学研究科准教授。専門はアメリカ文学、比較思想、比較芸術。早稲田大学卒業後、AP通信などの勤務を経て、大阪芸術大学大学院芸術文化研究科博士後期課程修了。2020年4月より高知市に在住。著書に『講義 アメリカの思想と文学 分断を乗り越える「声」を聴く』(白水社)、共著に『ユニバーサル文学談義』(作品社)、翻訳書にキャスリーン・マシューズ『祝福の種 新しい時代の創世神話』(作品社)などがある。

さわ・いずみ 1968年、神奈川県生まれ。東海大学大学院博士課程前期修了。専攻は中世アイスランド社会史。出版社勤務を経て司書。公共図書館・博物館図書室・学校図書館勤務のあと、現在介護休業中。アイスランドに行きたい毎日。写真は、今は亡き愛犬クリス。
バックナンバー