第14回 私小説作家・木山捷平の後ろ姿を追って
フランク・シナトラvs刑事コロンボ
映像配信のサイトをひまつぶしに逍遥していたら、時に「宝」とも呼ぶべき物件に出合い、これはこれはと胸を躍らせる。そんな中、ディーン・マーティン司会のテレビショー番組に瞠目した。ハリウッドの大スターを集め、ゲストを壇上に上げ、ディーン・マーティンが軽妙にいじるという趣向らしい。1969年にはNHKでも放送されていたようだ。ジョン・ウェイン、ダイナ・ショアなど俎上に載るのは大スターばかり。そんななか、盟友フランク・シナトラの回があり、ここになんと刑事コロンボが登場する。
正確にはコロンボ警部を演じたピーター・フォークの登場なのだが、おなじみのボサボサ頭、よれよれコート、右手に葉巻と、役になり切ってるから受けるに決まっている。「ちょっと一言だけ」と断って延々喋る。招待状が電報で5時5分に届き、数えたら65文字もあった、これはそのコピーで実物はカミさんが銀行の金庫に……など、細かいこだわりがコロンボファンにはいかにもで、たまらない。あげく紙ナプキンと他人から拝借するペンで(これもおなじみ)、シナトラにサインを所望するのだが、宛名を何度も言い換え、最後に「やっぱりローズへとしてください」(ローズはコロンボ夫人)。壇上に並ぶジェームス・スチュアートもジーン・ケリーもゲラゲラである。

これぞハリウッドの伝統、エンターテインメントの華ともいうべき時間で、すでに何度か見たが見飽きない。同種のことを日本で成立させるなら、山田洋次の回に渥美清が寅さんの恰好で祝辞を述べる……これしかない。「これ、つまらないものだけど」と安直なお土産品を手渡し、「いや、おいちゃんやおばちゃんも挨拶したいって言ってたんだけど、ほら、都会人の俺と違って、あの人たちは田舎者だから。タコ? とんでもないよ、あんなバカ」と笑わせる。実現すれば、ぜひ見てみたかった。
焚火の燃え残りの釘代金は3円
自著の紹介は避けたいところだが、この新刊は編者ということでお許しいただいて、ちくま文庫から10月に出た『駄目も目である 木山捷平小説集』の話をする。
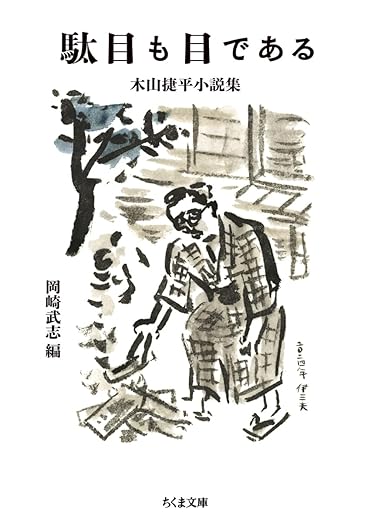
木山捷平(1904~68年)は地味な私小説作家で、生前には1冊も文庫化されなかったが、死後ブームが起こり、まず旺文社文庫が収録し、講談社文芸文庫からは10冊以上刊行された。自由闊達な生き方に「飄逸」を織り込んで独自の世界を築き上げ、山口瞳、常盤新平ほか同業者にもファンは多い。私もずっと敬愛する作家として後ろ姿を追ってきたが、このたび自由に好きな作品を選んでアンソロジーを作ることができたのである。 こんなにうれしいことはない。
好きな作品は多いが、ここでは「軽石」を取り上げる。昭和42年発表の短編。「十年あまり前、正介は焚火に凝ったことがある」と書き出される。「正介」は作者の分身として、他の作品にも多く登場する。ベースは作者の周辺で本当に起きたことが材料となるが、そこに虚構がまぶされている……というのが日本の私小説に共通するスタイルである。
「十年あまり前」とあるから、昭和30年ごろの話か。正介という中年男が庭で焚火をすることに熱中する。最初は紙くずや不要物を燃やしていたが、次第に熱中して、わざわざ八百屋へ行って蜜柑箱ほか果物を詰める木の箱をもらってきて燃やすようになった。当初の目的から逸脱し、焚火をすることが趣味となる。この日常から逸脱した力の抜け具合がつまり木山の味である。
段ボール箱が広範に流通する前は、ものを詰めるのに木の箱が主流であった。そこには釘が打たれているため、燃やすと灰に釘が残る。この釘を磁石で拾い出すのが「楽しみ」になる。なんとお金のかからない「楽しみ」か。しかし、気持ちはわかりますね。しかもこの釘を海苔の空き缶に貯めるようになる。無から有が生じるわけだ。そして出入りの「屑屋」にこれを買ってもらうことから、なぜタイトルが「軽石」なのかに話が展開していく。
木山の作品は周辺にいた井伏鱒二、太宰治、上林暁などと比べても国語の教科書に採択されることは少なかった。それも当然で、庭で焚火をして燃え残った釘を売る小説など教えようがない。心理分析の余地がない作品でそこが魅力とも言えるのだ。海苔の缶いっぱいの釘の代金は「3円」。あまりの安さに拍子抜けする正介だが、これを有効に使おうと、3円で買えるものを求めて街をひたすら歩く。ただそれだけの話だが、妙なギアの入れ方と脱力ぶりが心地よく、これまで何度も読み返してきた作品だ。
さて、昭和30年ごろの「3円」とは現在の物価換算でいくらぐらいになるか。こういうときいつも参照する週刊朝日編『戦後値段史年表』(朝日文庫)によると、昭和26年に木村屋のあんぱんが10円。昭和30年にコーヒーが50円。昭和31年の地下鉄乗車賃(初乗り)が20円だ。ものによって物価変動の差異はあるが、ざっと12倍くらいと踏んで当たらずとも遠からずではないか。すると「3円」は現在の36円、四捨五入して40円ぐらい。もう少し高く見積もってせいぜい50円とみていいか。いや、2024年だってこれではほとんど何も買えません。
ところが100円となると、がぜん有効価値が上がる。消費税を含めず考えれば、まず大人気の「100円ショップ」がある。なかに300円、500円の商品も混じるが、おそらく9割方は100円だ。文房具、食品、家庭用品、衣類、手芸用品、化粧品、玩具、一部電化製品とたいていのものはここで揃う。「100円」商品のみで生存も可能だ。安かろう悪かろうとも言えなくて、5本入り100円(本体価格)のシャープペンシルなど、家の中のあちこちに置いてけっこう重宝している。100円の価値は、木山捷平の時代よりむしろ上がっているかもしれないのだ。「100円でポテトチップスは買えますが、ポテトチップスで100円は買えません」という藤谷美和子の秀逸なCM(1977年)もいま思い出した。
公団の博物館は現物展示で観覧無料
さて最後に、映画『パーフェクトデイズ』を一緒に見て結成された「大人の遠足」トリオによる「URまちとくらしのミュージアム」探訪記を。場所はせんべろ激戦区として有名な東京都北区赤羽。駅北西の赤羽台にはかつてマンモス団地があった。さらに昔は軍用地。1962年入居開始で、3373戸は23区最大規模を誇った。老朽化が進み、2000年ごろから建て替えが始まり、現在は未来都市のような公共団地の都市が作られている。

本来、全て取り壊されるところを、UR都市機構によりスターハウス(上から見ると星型)3棟と中型フラットタイプが保存され、日本の公共団地の歴史をたどる博物館として敷地内に建てられたのが、今回訪れた「URまちとくらしのミュージアム」だ。ミュージアム棟は4階建てで各階に同潤会アパート、蓮根団地、晴海高層団地、多摩平団地テラスハウスなどが一部、解体時に保存され、本館に再現展示されている。以下は、HPの説明。
「UR都市機構は、前身となる1955年設立の日本住宅公団の頃からわが国のまちづくりの先導的役割を果たしてきました。ミュージアム棟では、歴史的に価値の高い集合住宅4団地計6戸の復元住戸をはじめとして、充実した映像や模型展示をとおして、都市と集合住宅のくらしの歴史やまちづくりの変遷を紹介します。」
事前予約制で1日3回、ガイド付きでここを見学(約90分)できると知り、申し込んだ。驚くべきは、実際に使われたインテリア、柱に畳や窓、壁や天井の建材、扉あるいは洗面所、風呂などが完全に近い形で復元されていること。しかも、通常は張られたロープの外側から覗きこむだけの博物館が多い中、ここは室内に入れることができ、配慮は必要だが置かれたものに触れることもできる。その鷹揚さに私は感心した。

晴海にあった高層アパート(前川國男設計)には、たしか評論家の種村季弘が住んでいたはずだが、10階の高層にエレベーターつき。ただし止まるのは3階ごとで、不便のようだが、エレベーターの止まらないフロアはそのぶん広いなど、構造的にも興味深い試みがなされていた。90分の体験は少し疲れたが、現物に触れた実感と初耳の団地学は余りある恩恵を感じた。これが無料とは、都内在住の方々は行かなきゃ損ですよ。
夕暮れの赤羽駅までトリオは戻り、もちろん紅灯の巷に黒い影となってアルコールの海へ沈んでいった。中央線族の2人は赤羽駅前から環七を南下して高円寺へ。これはらくちんのショートカットの交通手段。夜のバスは妙に切なくなるのであった。
タイトル、本文イラスト、写真=筆者

おかざき・たけし 1957年大阪生まれ。立命館大学卒業後、高校の国語教師、出版社勤務を経てフリーライターに。「神保町ライター」の異名を持つ。近著に『憧れの住む東京へ』(本の雑誌社、2023年)、『古本大全』(ちくま文庫、2024年)、『ふくらむ読書』(春陽堂書店、2024年)などがある。









