第19回 春雷に大雪の朝
誕生日月の3月(28日で六十八歳)、中旬早朝、雷の音で目が覚める。バスに乗り遅れそうになり、必死で走っていると、肩に猿をのせた中国人からオレンジ色の紙幣の束を渡されるという夢を見ていた。春の雷は、春の訪れを告げる奇瑞であろう。朝刊を取りに外へ出たら雪だ。驚いたなあ。
春雷や麦の穂先に触れぬ音 芭蕉
春雷に小川さざめく音添えて 子規
どちらも「春雷」を詠んで繊細な「音」に注目している。俳句はこうした、触れるとこわれそうな小さな世界を捉えるのに向いている表現形式なり。しばらく玄関前の庇の下で、雪景色にとどろく雷の音を聞く。
私が住む北多摩地区では、2月になると、あちこちで紅白の梅がほころび始める。桜の淡いピンクと違い、はっきりした色彩で小さな花をたくさんつける。遊歩道や人の家の庭先など、ずいぶん方々で梅を見る。関西にいた頃、とくに京都では梅が見られたはずだが、ほとんど記憶にない。そんな風流を持ち合わせていなかったのだろう。いつも腹をすかせ、お金の心配ばかりしていた。うつむいて歩いていたかもしれない。
上京してからもずいぶん長い間、梅が咲いていることを気にも留めなかったように思う。やはり年齢がもたらした功徳だろうか。桜よりむしろ梅を美しいと思う。
吉田大八監督『敵』を観る
報告するのが遅れたが、今年1月末に、吉田大八監督、長塚京三主演の『敵』を例の、映画を観てから一緒に酒を飲む六十代トリオで観る。
原作は筒井康隆(未読)。これは不思議な映画だった。いまどきモノクロ。
老いた独居の元仏文教授・渡辺儀助が、朝、ベッドで目覚めるところから始まる。米を研ぎ、炊飯器にかけ、炊ける間に顔を洗い、歯はとりわけ丁寧に磨き(糸ようじも使う)、汚れ物を洗濯機に入れ……という折り目正しい日常。だらしなさとは無縁である。床に積まれた本、脱ぎ捨てた靴下はなく整然としている。きれいな老人だ。
東京都中野区(と郵便物で住所がわかる)の古い二階建て日本家屋。そこそこの広さの庭がある。退職したあとも、教え子(幾人かは編集者となり仕事をくれる)がけっこうひんぱんに出入りし、世話をやいてくれたりする。パソコンが置かれた仕事部屋もみごとに整理され、書物はガラス扉つきの立派な書棚にすべてきちんと収まる。とにかく、同じ文章を書く仕事ながら、散らかし魔人の私とはえらい違いだ。
この穏やかで、ルーティンの日常を脅かすのが、老いによる夢、幻想である。その夢がすべて現実と地続きでつながり、観客はいっしゅん、それが現実なのか夢なのか判別できなくなる。性の欲望もからむ。やがて夢に、亡くなった妻が現われ、隣り町まで迫った暴徒がついに家に乱入する。夢と現実のリセットがひんぱんになると、見ている側は不安定な気持ちに襲われるのだ。長塚京三扮する元仏文学者は七十七歳の設定。十年後の私、だと思うと「敵」の正体が見えてくる気がした。
主人公は行きつけのバーで働く可愛い女子大生と口をきくようになるが、仏文の学生でバタイユ『青空』を読んでいる。むかし晶文社から出た黄色い表紙の版(天沢退二郎訳)に覚えがあるが、小さい活字がびっしり詰まっていて、とても今では読めない。その女子大生が「先生みたいな人に教わりたかった」などと言う。私も教師をしていたが、これはイチコロの殺し文句。お金を貸すがかえってこないという落とし穴にはまってしまう。
庭と部屋の間に板を渡した縁側があり、雨の日、庭を見ながら儀助がぼんやり腰を下ろすシーンがある。これが妙に印象に残った。縁側に座って、雨の庭を眺める。そんなことをしてみたいと思ったのだ。老人の楽しみはたいていお金がかからない。
アップリンク吉祥寺はシニア世代でほぼ満席だった。ハリウッド発のCGを駆使した派手でバカっぽい映画はもうたくさんだと思う人たちが、こうして地味なモノクロ映画に足を運んでいる。小津安二郎や成瀬巳喜男の特集を組めば、おそらく詰めかけるだろう。いまはなき銀座「並木座」で小津特集を観た日のことを思い出す。
佐田啓二が出ると(『秋刀魚の味』)、「あらいい男ねえ、やっぱり。息子(中井貴一)はかなわないわ」とか、山田五十鈴が画面に現れると(『東京暮色』)、「ベルちゃん(山田のあだ名)若いわあ」なんて、客席からもれるオールドファンの会話を聞くのが楽しみだった。
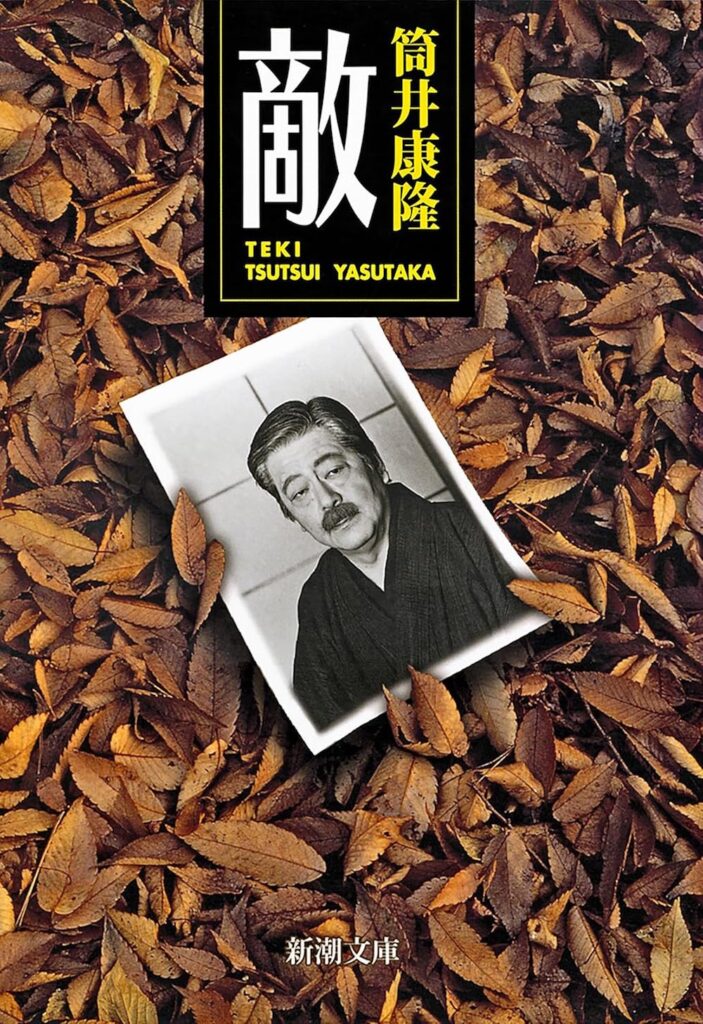
トリオで『敵』を観たあと、まだ日は天に高く、井の頭公園を散歩する。ここは広くて、中央に池があり、くつろぐのにいい公園だ。この日は気まぐれに「水生物園」へ入園する。道を挟んで反対側にある動物園には、娘が小さかったころ、何度か連れていったがこちらは初めて。両館が使えるチケットは、六十五歳以上二百円。申し訳ない気持ちになる。
戸外の展示のほか、正面に小ぶりの建物があり、ここに水生動物が飼われている。ガラス張りの水槽の中に、淡水魚、カメ、イモリ、オオサンショウウオなどがいる。大阪在住体験があり阪神ファンという分かりやすい中高年トリオが、じっと水槽に見入る姿はあまり絵にはならない。ふざけて、コイを見ると「これは洗いにして」、イワナは「やっぱり塩焼きか」、ウナギは「かば焼きにしたらうまそうや」などとコメントをして歩く。はっと気づくと、そばに母親に連れられて来園した四歳ぐらいの女の子がいた。私のふざけたコメントを聞いてトラウマにならなければよいのだが。「お母さーん、あのおじいちゃん、水槽のお魚、食べたらおいしいって」と言われたら、ひんしゅくものである。大いに反省した。

モデルはオオサンショウウオたち

福神漬とは何か
カレーの添え物として、ほとんど必ず付くのが福神漬。ほかの漬物は、沢庵にしろキムチにしろ、もっと幅広く副食として食べられるのに、なぜか福神漬のみがカレーとしか手を組まない。不思議な話だとずっと思っていた。
ところが京都で学生生活を送っていた二十代、あれはどこの食堂だったか、テーブルにつくと箸立てや調味料といっしょに、どんぶりに山盛りになった福神漬が置いてあった。カレーもメニューにあるのだが、専用というわけではない。周りを見渡すと、みな定食のご飯の上に福神漬をのせて食べている。私が知る、カレーに依存しない、独立採算制の例である。
クラスの友人たちと京都の夜を飲み歩き、気づいたら財布には小銭しかなく、下宿まで歩いて帰ったのはいいが、月末のアルバイト料が入るまで、二~三日耐乏生活を過ごしたことがあった。このとき、食堂の独立採算制を思い出し、福神漬と海苔の佃煮を買い、ご飯だけ炊いてそれのみをおかずにして暮らした。それでもべつにみじめとも思わなかった。 あの時君は若かった。
丸谷才一のエッセイ集『夜中の乾杯』(文春文庫)を読んでいたら、意外なところに福神漬が出てきた。「駅弁とビール」という掌中の一編に「周作人を尊敬している」とあり、明治末期、魯迅を兄に持つ中国の作家が日本に留学していた頃のことが書かれている。法政大学に学ぶ若き日の中国人作家は、明治四十年刊の『東京案内』を愛読していた。明治の日本には、中国では失われたものが残っていると考えていた。たとえば床の間、座布団、下駄などはいずれも中国の古俗だという。へえ、知らなかった。
周作人は本郷に下宿し、日本の食べ物を細かく記録していた。その中に「福神漬」があった。中国語では難しい漢字で表記されるので省略。音は「チャンゴタ」で「かぶらの味噌漬」を指す。福神漬は非発酵の漬物でちょっと違う気がするが。
ほか周作人が自国と違う食習慣で気づいたのは、日本人が冷や飯を食べること。中国は熱い飯を好むそうである。そこで、丸谷のエッセイのタイトル「駅弁とビール」と結びつくのだが、ここでは違う話をする。つまり、江戸時代には冷や飯を食べていた。江戸後期、一日二食が三食になるが、朝に炊いた飯を昼も食べ、夜は茶漬けにするのだと、杉浦日向子がどこかに書いていた。
もっぱら白飯で腹をふくらませ、副食は味噌汁、漬物、佃煮などほんのささいなもの。朝は目玉焼きにベーコンにトーストとサラダ、昼はとんかつ定食、夜は焼魚に芋とタコの煮物……なんて現代は、カロリーの取りすぎである。
つまり金欠の大学生だった私が、白米と福神漬で空腹をごまかしていたのは、江戸時代の再現だったのである、いま考えてみると。

福神漬がますます食欲をそそる。福神漬、バンザイ!
しかしもっとていねいに盛りつけるべきだろう
タイトル、本文イラスト、写真=筆者
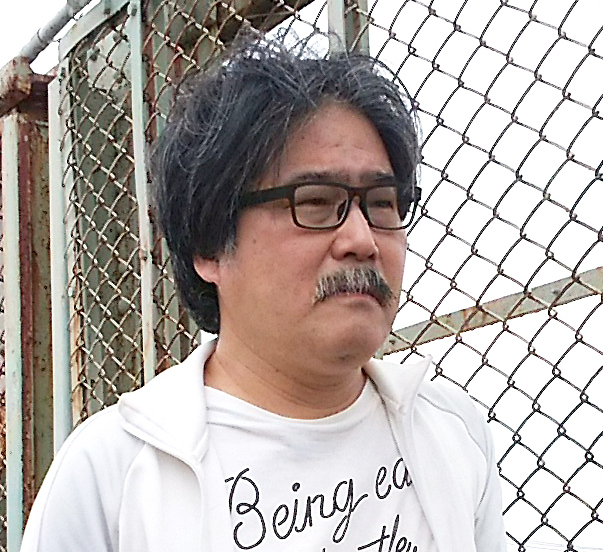
おかざき・たけし 1957年大阪生まれ。立命館大学卒業後、高校の国語教師、出版社勤務を経てフリーライターに。「神保町ライター」の異名を持つ。近著に『憧れの住む東京へ』(本の雑誌社、2023年)、『古本大全』(ちくま文庫、2024年)、『ふくらむ読書』(春陽堂書店、2024年)などがある。









