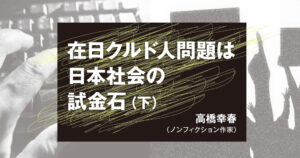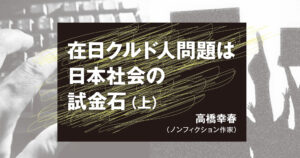『麦と兵隊』と『生きてゐる兵隊』
2012年刊行の今村修『ペンと兵隊』は、従軍小説の代表的な書き手であった火野葦平の戦争観について多角的に分析を試みた論考だ。
その切り口のひとつは、火野と同時期に中国戦線を描きながら、公職追放を免れた石川達三との比較である。石川の場合は、その作品『生きてゐる兵隊』が日本軍の残虐行為を赤裸々に描写したことで、掲載誌『中央公論』が発禁処分に遭い、石川本人も有罪判決を受けている。
火野は同じ1938(昭和13)年に発表した『麦と兵隊』で、国民的作家になる栄誉を受けたのに、石川の作品は筆禍事件を引き起こしてしまったのだ。ところが両者の明暗は敗戦を挟んだ価値観の転換で、完全に入れ替わることになる。戦争協力の責任を問われたのは火野のほうだった。

ふたりの作品が両極端の運命をたどったことについて、『ペンと兵隊』では、戦時中の当局者が恣意的な判断した結果に過ぎないとシニカルな見方をする。
『生きてゐる兵隊』が問題視されたのは、「皇軍兵士の非戦闘員殺戮、掠奪、軍規弛緩の状況」を記述した点。その一方、火野が『麦と兵隊』を書くにあたっては「日本軍が負けているところを書いてはならない」「戦争の暗黒面を書いてはならない」「味方はすべて立派で、敵はすべて鬼畜でなければならない」などと七項目にわたって事前に上官から釘を刺されていた。
実際、火野の作品では「戦場における日常性」を描くことに重きを置き、勝敗の描写は重視されていない。とは言っても、『麦と兵隊』にも捕虜殺害などをほのめかす記述はあり、さらには憎々しく描くべき敵国人、中国の民衆に親近感を示すという〝問題点〟が存在した。
『生きてゐる兵隊』による残虐行為への言及は、分量こそ多いが告発調でなく、「戦場という異常事態では起こり得るもの」と、それらを追認するトーンで書かれている。
このような対比から『ペンと兵隊』の今村は、敵への同情や親近感、筆者の動揺などを書き記した火野作品のほうが、読者の戦意を削ぐリスクがあったはずだと見る。
ただしこの議論はあくまでも、上記二作品に限定した場合の話であり、公職追放に抗った火野の抗弁そのものには、今村は厳しい見方をする。火野本人や擁護者たちによる「自由主義」「ヒューマニズム」等々の言葉による正当化に、疑問の目を向けるのだ。「戦争が始まった以上、国に殉じなければならないと思った」。火野のそんなスタンスには「戦争そのもの」を問う視点が欠け、「我が身を大状況にまかせたまま」流されてしまった自己批判がないと言うのである。
難しい問題である。〝戦争という大情況〟を個人では動かし難い大前提と受け止める──。あの時代、一般国民のスタンスは大多数がそうだっただろう。そのうえで個人に許される範囲内で、誠実な人間であろうと心がける。文化人の場合、それではやはりダメなのか。だとすれば私の祖父・古海卓二などは火野とは比較にならないほど、不誠実な人間だったことになる。
「卑怯者でゐよう。家庭の中に逃げ込むことで、心の傷を癒すより、今は方法はない」(『追放者』)。火野の戦後の自己批判は、普遍性のあるレベルには到達せず、結局は非難の集中砲火から己を守るため、家庭に逃げ帰る選択をした。『ペンと兵隊』は、そんなふうに火野葦平を捉えたのだ。
確かに『追放者』や『革命前後』といった戦後の作品で、火野は自分を攻撃する共産党への反発を隠そうとしていないし、戦争という国策への協力を、個人として抗うべきことだったと考え直している気配もない。
それよりも、はっきりした根拠のない個人的な〝印象〟だが、火野自身は同胞にも多大な犠牲者の出たあの戦争によってベストセラー作家となり、周辺民家の約10倍もの価値を持つ1000万円以上の豪邸(河伯洞)を建てることができた(※前々回の記事で100万円と書いたのは誤りで訂正します)。そんな否定しようのない現実に、わかりやすい後ろめたさを感じていたのではないだろうか。両作品に見られる河伯洞への言及に、そんな心情が透けて見える気がするのだ。

伏せられた火野の自殺
1960年、戦後15年目を迎えようとする1月に、火野は河伯洞二階にある書斎にて他界した。享年52歳。戦争末期から続いた煩悶の日々を振り返る『革命前後』という大著を書き上げた直後のことだった。
この突然死の真相が遺族により公表されたのは、12年余りのちの、『文藝春秋』1972年4月号誌上でのことだった。英文で「ヘルス・メモ」と題されたノートに「遺言」という見出しのふたつの文があり、睡眠薬自殺をした亡骸のすぐそばにそれは置かれていたのだが、当時はまだ火野の母・玉井マンが健在で(2年後に死去)、精神に不安定な面も持つ妻・良子のショックも心配されたため、その事実は限られた身内(7人いる子どものうち息子3人と火野の秘書、火野の親友の作家・劉寒吉の計5人)以外には伏せられていた。
『文藝春秋』の記事に東京在住の次男・英気が書き添えた「十三回忌にあかす父の自殺」という手記によれば、死の半年ほど前から火野は眼底出血のため右眼が失明状態となり、高血圧症と闘いながら小説を書いていた。そして、彼の十三回忌のタイミングで真相の公表を決めたのは、何よりも彼らの母(火野の妻)良子が1月に他界したことが大きかったという(一部マスコミに火野自殺の噂が流出したことも影響した)。
死の前月から日記ふうに記されたメモには、淡々と健康状態などが記されているだけで、「遺言」と題された部分にも、家族協力して経済的再建を図るよう求める言葉がある程度で、自ら命を絶つ理由は明示されていない。
火野の弟の玉井政雄(玉井金五郎・マンの次男、文学研究者)は、兄の死が自殺だったことを『文藝春秋』で初めて知るのだが、その著書『兄・火野葦平私記』のなかで、自身の健康への不安、大家族を養うことへの疲弊、作家としての才能が枯渇することへの心配など、メモの行間から読み取れる諸事情が原因となった可能性に触れたあと、遺作となった大著『革命前後』を書き上げたことの意味合いに言及した。
敗戦前後を克明に描いたこの作品は、兄が遺書として書ききったものかもしれない、兄はこの作品で、自分のなかの戦争と兄なりに決着をつけたようにも思われる。それは遺書である「ヘルス・メモ」には記されていない。私の想像でしかない。
奇しくも似たような「想像」は、火野の三男でその晩年、北九州市の文化財として買い取られた河伯洞で管理人をした玉井史太郎の著書『河伯洞余滴』にも書かれている。史太郎は火野の死の秘密を当初から知っていた〝五人衆〟のひとりである。
この(自殺の)決行に、一番大きな要因となっているのは、『革命前後』の完成ではなかったろうかと私には思えてならない。(略)その完成の結果は、自分のなかに安堵とともに、巨大な空洞を感じさせるものができたのではなかったろうか。書き上げたという充実感の裏で、胸のつかえを全部吐露してしまったという虚脱感が大きく支配し、これから先、何を書くことがあろう、という空しさが、うつ病との併合で、身辺に重畳する煩わしさとも相まって、急速に自殺への誘惑に取りつかれていったのではなかったろうか。
火野の死の前後から7人の子どもは各地に散り、維持費が嵩む河伯洞は企業の社員寮などとして貸し出された。
河伯洞に最後まで関わった史太郎も2021年に他界、このシンボリックな邸宅の管理・運営する「火野葦平資料の会」に玉井家の親族はいなくなった。ただ河伯洞から200メートルほどの距離にいまも住まう親族がひとりいる。本稿の(上)=連載第31回=で取り上げたプロサッカーチーム「ギラヴァンツ北九州」会長の玉井行人がその人だ。
史太郎と同じく金五郎・マン夫妻の孫。父親は先に引用した『兄・火野葦平私記』の著者、玉井政雄である。政雄は両親が戦前、若松で「玉井組」を立ち上げた際の事務所跡に結婚後の新居を建て、行人はいまその家に暮らしている。
現在67歳の行人からすると、伯父・火野葦平は物心つく前に他界した親戚で、対面した記憶は一切ない。ただ小学生のとき、級友から火野について聞かされた「戦争犯罪者だ」という言葉が強烈なトラウマになり、中年期まで火野との血縁関係に蓋をして生きてきた。そのことは(上)の記事で行人の言葉を紹介したとおりだ。
だがこれまでの半生では、火野との血縁を否応なく突き付けられる場面にも遭遇した。その最も象徴的な瞬間が、地元紙・西日本新聞社の採用試験だった。「火野葦平について君はどう思うか?」。父・政雄も地元では知られた大学教授だったため、火野との関係は当然、会社側にも知られていた。
だが、火野作品をほとんど読んでこなかった行人は、面接でのそんな質問に狼狽した。「新聞記者になることと火野葦平への評価は関係ありますか? そんな質問に答える必要はないと思います」。動揺と反発で、思わずそんな啖呵を切ってしまったのだ。結果はもちろん不採用だった。
行人は父・政雄に悩みを打ち明けた。初めてきちんと聞く弟から見た火野葦平像。政雄はこんな言い方をした。
「あの人はとても寂しい人、孤独な人だった。若松では有名な作家として持て囃されていたけれど、悩みを本当に理解する人はいなかった。東京にも本音で話せる相手はいなかった。私はそんなふうに思っている」
新聞記者職にこだわりがあった行人は、翌年も西日本新聞社を受け、今度は合格した。このときの面接でも火野について聞かれたが、父の助言を参考に自分なりの思いを述べ、無事内定を得た。

従兄弟・中村哲の言葉
そもそも父・政雄も、火野とは距離を置いてきた人だった。目と鼻の先にある河伯洞にも、めったに行かなかった。現在の河伯洞邸内には、火野の文学仲間の梁山泊のようだった往時の写真が多数飾られている。親分肌だった火野は、火の車だった家計を顧みず、豪放磊落に酒食を振る舞った。酒を好まない政雄はしかし、その雰囲気が苦手だった。「文学はひとりでもできるはずだ」と、徒党を組む兄にむしろ反発した。
行人も大学生のとき、そんな父の感覚を追体験している。古賀市に住む叔母・秀子の伴侶であり、青年時代から火野と交友した中村勉が他界して、その葬儀の酒席に出たときのことだ。そこには老齢になった火野の仲間たちも数多くいた。二十歳前後の若者の参列者は行人ひとり。すると酒に酔ったひとりが近寄って来て、「顔を上げてみない(みなさい)」と手持ちの扇子で行人のアゴを持ち上げた。
無頼の徒を気取る文学者らの一種独特の酒席。これこそが父が苦手とした河伯洞の雰囲気に違いない。行人には身の置き所がなかった。
そのとき、行人の心中を察知したように「ちょっと外に出ようか」と、近くの喫茶店に連れ出してくれる人がいた。弔われる故人の子・中村哲。のちにアフガンで英雄的活躍をするボランティア医師、行人より11歳年長の従兄だった。
「哲さんはボクの気持ちもわかってくれ、『堪らないね』と同情してくれたけど、彼自身は苦悶する(晩年の)葦平の姿も見ていたから、葦平に共感する気持ちも持っていた。葦平の本は相当読み込んでいましたよ」
少年期以来の〝火野葦平トラウマ〟を、行人が中年期以降に拭い去っていけたのは、折々に交わした中村哲との対話から火野のイメージが変わっていったためだという。火野葦平の本を読む気持ちになれない──。そんな相談をしたとき、次のようなアドバイスをくれた。
「戦争が終わった日本では、一夜にして価値観変が一変した。それに合わせられる人たちもいたけれども、葦平はダメだった。愚直な人だから、戦争のことをずっと考えてね。いつまでも彼の戦争は終わらんかったんよ。そういう目で彼の本は読んだらいいんじゃない?ってね」
もうひとりの従兄、中村哲よりさらに11歳年長の玉井史太郎とよく話すようになったのはさらにあと。行人が転勤を繰り返す新聞記者の暮らしをやめ、サッカーチームの運営をするために若松に帰ってきた十数年前からだという。
史太郎は若き日に火野に反発し、転々と職を変えながら労働運動に半生を捧げてきた。シニア世代になり、河伯洞管理人を任されたのをきっかけに、〝不肖の息子であり続けた償い〟をしなければと亡父の著作群を読み込んだ。そのうえで、河伯洞来訪者への応接やさまざまな刊行物を出す活動で、火野に貼りついた〝兵隊作家〟というレッテルを何とか剝がすことはできないかと努力を重ねていた。
彼の著書『河伯洞余滴』には、火野関連の本をまとめるプロセスで、驚くべき発見をしたことが書かれている。1953(昭和28)年になり、新潮文庫として再刊行されることになった〝兵隊三部作〟のひとつ『土と兵隊』(昭和12年、杭州湾上陸作戦の従軍記)の校正本に挟まれた原稿用紙の切れ端を見つけたのだ。そこには、豆粒のような字がびっしり書き込まれていたという。
行軍中に仮眠から覚めると、先ほどまで数珠つなぎにしていた捕虜たちが見当たらない。すると近くの壕の中、折り重なって36人の死体が投げ込まれているのに気がついた。よく見ると、その中には血まみれで蠢く肉体もあった。
彼は懇願するやうな眼附きで、私と自分の胸とを交互に示した。射ってくれと云ってゐることに微塵の疑ひもない、私は躊躇しなかった。急いで、瀕死の支那兵の胸に照準を附けると、引鐵を引いた。(略)山崎小隊長が走って来て、どうして、敵中で無駄な発砲をするのかと云った。どうして、こんな無惨なことをするのかと云ひたかったが、それは云へなかった。
火野は公職追放を解除されたあと、復刻される戦争中の作品に、わざわざそんな加筆をしていたのだ。
史太郎の〝発見〟は直ちに新聞各紙で報じられ、とくに『日本経済新聞』が全国版の記事にしたことから、思わぬ反響を呼ぶ。中馬辰猪[ちゅうまんたつい]という鹿児島出身の自民党衆議院議員(のち建設大臣)から河伯洞に電話があり、後日当人から手紙が送られてきた。そこには、彼が陸軍主計大尉だった1944(昭和19)年、旧ビルマ(現・ミャンマー)でのインパール作戦に従軍中、現地取材に来た火野と二時間ほど語り合う機会があったと記されていた。
火野はこの中馬に「(インパールは)この世の地獄だ。とてもペンをとることはできない」と嘆いたあと、「僕はこの戦争には反対だった。日中戦争も早くやめてほしいと思っていた。一日も早く戦争をやめないと日本は崩される」と熱弁を振るったという。
自身も敗戦を予期していた中馬は、母校の旧制七高(現・鹿児島大)に宛て、空襲による焼失を防ぐため図書の疎開を進めるよう伝えてほしいと相談した。そのメッセージは火野から学校に伝えられ、図書の一部は実際に疎開により空襲を免れたという。
戦争という〝大局〟の全否定には至らずとも、敗戦から死の間際まで身を削るように自身の責任を問い続けた。それほどまで戦争と向き合おうとした作家はあの時代、どれだけいたのだろう。私には、そんな彼の作家人生には、やはり〝誠実〟という形容がふさわしく思える。
タイトルにある写真は戦場でメモを取る火野葦平(「火野葦平資料の会」提供)
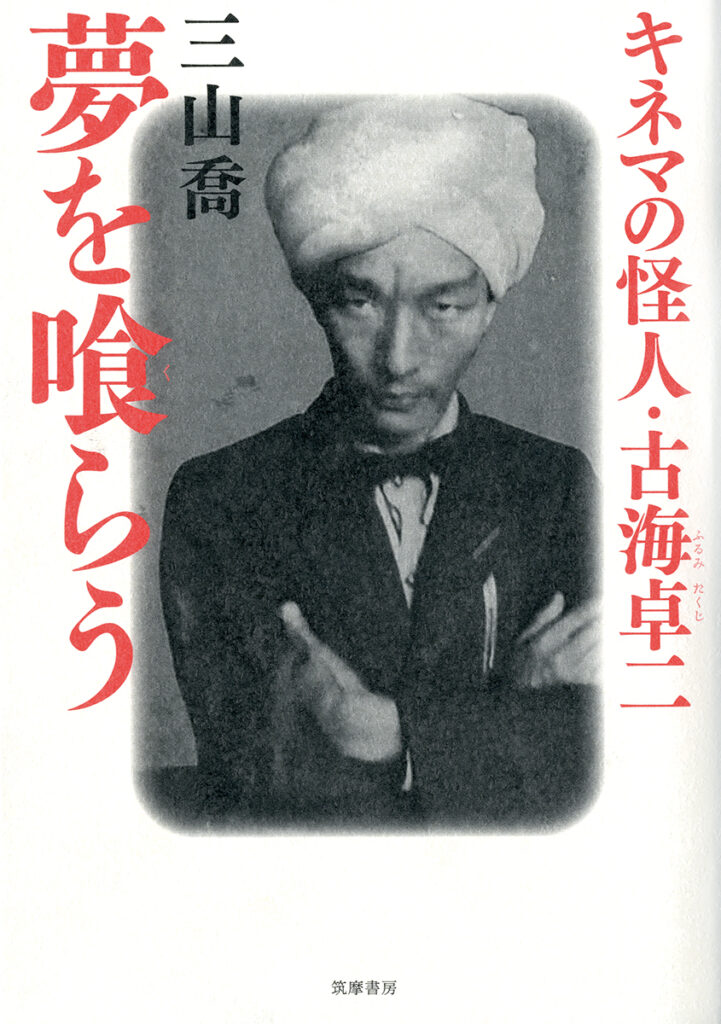
みやま・たかし 1961年、神奈川県生まれ。東京大学経済学部卒業。朝日新聞学芸部、同社会部記者を経てフリーに。2000年から06年にかけ、ペルーを拠点として南米諸国のルポルタージュ記事を各誌に発表。帰国後、ルポやドキュメントの取材・執筆で活躍している。著書に『日本から一番遠いニッポン――南米同胞百年目の消息』(東海教育研究所)、『さまよえる町――フクシマ曝心地の「心の声」を追って』(東海教育研究所)『ホームレス歌人のいた冬』(東海教育研究所、のち文春文庫)、『夢を喰らう――キネマの怪人・古海卓二』(筑摩書房)、『国権と島と涙――沖縄の抗う民意を探る』(朝日新聞出版)、『一寸のペンの虫――“ブンヤ崩れ”の見たメディア危機』(東海教育研究所)などがある。
バックナンバー