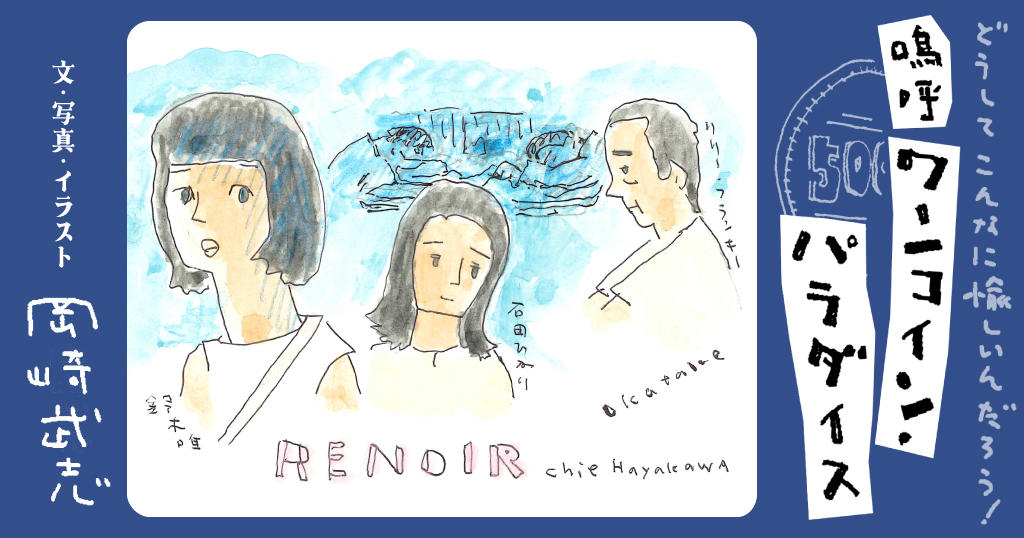サッポロ一番で人格がわかる
近所に住み、仲良くしてもらっている年下の画家・牧野伊三夫は宴会好きで、よく知人友人を招いて酒宴を開く。私もときどきお呼ばれにあずかり、手料理と酒でもてなされ楽しく過ごしている。
そこでは雑多な話題が上がるわけだが、ある時「サッポロ一番」の話になり、主力の三種のうちどれが好きかという話になった。牧野さん曰く、「しょうゆ、塩、味噌のうち、どれが好きかでその人の性格までわかる」というのだ。後日、この件に関して牧野さんに確かめたら「え、そんなこと言いましたっけ?」などと言う。まあ六十を過ぎたヨッパライはこんなものです。そこで、このバカバカしい推論を、自力で復活させようと今回考えた。

まずは基本情報。「サッポロ一番」はサンヨー食品が製造・販売する袋麺。若き日より、私もずいぶん食べました。同社ホームページと検索により、以下叙述する(「叙述する」というほどのものでもないが)。
袋麺は毎年一千種、新商品が発売されるが、この「サッポロ一番」は、発売されて五十年、ほぼ首位を保ってきたという。すごいなあ。
現在の価格はメーカー希望小売価格(税別)が一個136円で、五個パックが680円。しかし、実際にはスーパーなどで五個パックが500円以下で売られていたりする。私は今回、百均「ダイソー」にて各108円(税込)で買ってきた。多少物価上昇に合わせて値上がりしたのかもしれないが、それでも安いなあ。百円程度で一食、腹を満たしてじゅうぶん満足するのだから、コスパ抜群の食品である。一日三食がこれ、となるとキツイが。
うーん、書きながらちょっと白熱してまいりました。ちなみに発売された順は「しょうゆ」1966年、「みそ」1968年、「塩」1971年。シェアとなると「みそ」43.4%、「塩」30.6%、「しょうゆ」13.0%になる。こんなこと覚えなくていいですよ、試験に出ませんから。
意外だったのは「しょうゆ」の人気が一番低いこと。私の場合、よく買うのはこのシェア順位の逆になる。つまり「しょうゆ」が基本で、「塩」「みそ」がそれに飽きたら、という具合。
牧野さんによる三種性格占いについては忘れたが、たぶんこういうことなのだと思う。「しょうゆ」派は冒険を嫌う保守的性格で、毎日のルーティンをなるべく崩さず生活している。高校の同級生と結婚……というのはこのタイプ。
「塩」は基本保守なのだが、みんなと一緒というのを嫌い、ときどき安全を踏み外す。麺をそのままゆでるのではなく、もやしを入れたり、コーンやバターを入れたり、自分なりのレシピを持っていてアレンジする。自由業に多いと思われる。
「みそ」は、自分では個性的で友人も多いと思っているが、じつはけっこう統計上の多数派に属する。これじゃなきゃダメだと主張が強く、「しょうゆ」や「塩」を選ぶ人たちを低く見る傾向がある。だからほかの味に乗り換えたりしない。「サッポロ一番は断然味噌ですよ」とこれまで一万回以上、口に出している。
どうでしょうか? いや、いい加減な話ですよ。
今回、三種を揃えて食べ比べてみたのだが、「あれ? けっこう味噌がうまいな」というのが感想。残った汁に冷凍ご飯をチンして加え、卵まで割って入れて改めて煮たのだが、けっこういけます。しかし、私は極力アレンジを加えない派で、よく袋麺のアレンジレシピをネットにアップしているのを見るが、しゃらくさいと一蹴する。袋麺は最低限生存できればいい、貧しい学生のよって立つべき基本的食事で、ネギやら野菜やら、いわんやチャーシューやしなちくを加えるのは邪道ではないか。それならラーメン店で食えばいい。許容されるのは、ネギ、卵、バターまでにしたい。写真は「塩」でバターを落としました。

袋麺を鍋で煮て、そのまま箸を突っ込んで食べるのが青春の王道である。私は柔らかい麺が好きなので、時間は三分とあれば四分煮ます。あと、今回三種を買って、初めて裏の原材料を読み比べてみたのだが、味によって麺の材料が多少違っているのですね。「しょうゆ」にしょうゆ、「みそ」に味噌が練りこんであるのは、それはそうだろうと思うが、「塩」に山芋粉が加わっているのは驚きました。麺のグラム数も一グラム単位だが違いがある。「塩」には別分けの小袋にきりごまが付いていて、これがいい仕事をするんです。「みそ」の七味もいいです。
「マニアックでごめんね」
八月中旬のまだ暑い盛り、落語好きの本サイト編集長のIさんと待ち合わせ、上野広小路にある老舗演芸場「鈴本」へ落語を聴きにいった。「この日は出演者がいいんです」とIさん。もらったパンフレットで確認すると、たしかに当代の人気者と実力者が顔を揃えている。色物(漫才など落語以外の諸芸)を除いて出し物と一緒に列挙しておく。

桃月庵黒酒「茗荷宿」、隅田川馬石「浮世床」、柳亭市馬「あくび指南」、三遊亭白鳥「インド人のソバ屋」、入船亭扇遊「狸賽[たぬさい]」、古今亭菊之丞「酢豆腐」、柳家小ゑん「いぼめい」、春風亭一朝「鮑のし」、トリが桃月庵白酒。白鳥は新作でタイトルは違うかもしれない。白酒の噺も初めてで、「妾馬」の一部を改良したような、そこつな殿様と侍従のやりとりから成る。

馬石、市馬、扇遊、菊之丞、一朝、白酒はTBSテレビ「落語研究会」の常連で、いずれもしっかりした腕の持ち主。どれも楽しめた。これにジャグリング、漫談、紙切り、粋曲を挟んでの約三時間半が四千円はお値打ちである。同じ観客でも、歌舞伎や能狂言、オペラやミュージカルといった、やや肩の張るジャンルと違い、演芸場はぐっとハードルが低く、脱力して対することができる。飲食も自由だ。
落語については本もたくさん出ていて、雑誌で特集が組まれたり、「落語研究会」はじめテレビ放送もあるので、触れる機会は多いだろう。私が寄席へ足を運んで、一つの楽しみにしているのが「色物」と呼ばれる諸芸だ。多くは知らない芸人であり、目新しく心がなごむ。この日でいえば、粋曲の柳家小菊は和服で三味線を抱えて登場し、小唄や都々逸、民謡を歌う。三味線の音を聞くということ自体がほぼ日常になく、寄席ならではの空気が流れ、非常にいい気分になるのだ。
五十歳前後の男性コンビ「ロケット団」は、寄席中心に活躍する漫才師だが、ずいぶん方々で見た。客席ではまたよく受けるのである。娘が小学生のころ、家族三人で新宿末広亭へ行ったとき、彼らが登場した。私は初見。見終わったあと「ロケット団、気に入った」と娘が言い、そのことをブログに書いたら演芸通の女性がそれを読み、「ロケット団はいいんですよ。娘さん、目が高いです」と言われたことがあった。
この日の色物の出演者で触れておきたいのは、ウクレレ漫談のウクレレえいじ。ウクレレ漫談といえば、古くは牧伸二がいて、現在ではぴろきという芸人がよく出演している。ナイツの塙が話していたが、地方の営業で出演者の希望に挙がるのがナイツ、U字工事、そしてぴろきらしい。丸眼鏡、小太りのおじさんだが、髪の毛を頭頂でしばって、なんだかかわいらしい。ぴろきが電車に、そのままの恰好で乗っていたら、外国人たちが彼を見て「キュート!」と叫んだと聞いたことがある。
あ、そうそうウクレレえいじの話。ウクレレ漫談で使われるウクレレは、たいてい簡単な循環コードを弾くだけだが、彼の場合曲弾きといっていいスピードで演奏する。短いネックと四本の弦で、ベンチャーズから津軽三味線まで自由自在に駆け巡る、そのテクニックにまず驚いた。リストの「ラ・カンパネラ」も……。いや、これは大したもんだわ、と感心したのだった。
ネタも面白い。「マニアックでごめんね」と歌いながら繰り出すのが、たとえば『七人の侍』の志村喬(勝ったのはわしたちではない、農民だ)に続いて、『ゴジラ』の志村喬。映画『ゴルゴ13』の高倉健のフランス語(ジュテーム)、『浪人街』の原田芳雄と勝新太郎(何を言ってるのかわからない)などと短時間に畳みかけていく。たしかに「マニアックでごめんね」だが、たまらなくおかしい。テレビ番組「いい旅・夢気分」の西岡德馬と舞の海まで来ると、見たことはないが笑えるのだ。
テレビに登場する、よく知られた芸人というのはじつはほんの一部。寄席をメインの場とする芸人たちは、客を目の前にして、十分とか十五分ぐらいで世界を作ってしまう。それも前後に登場する落語家の邪魔にはならないようにする。これがじつにいいアクセントとなる。落語家はよく、小中高の学校寄席に呼ばれる話をまくらでするが、このウクレレえいじのネタなど、小学生が相手じゃ全滅かと思われる。この日の鈴本の客席を占めたのも、だいたい六十代から七十代が中心。この客層であるからこそ、『ゴルゴ13』の高倉健のフランス語はハマるのだ。
だからといって、ウクレレえいじを追いかけて、浅草、池袋、新宿と演芸場をめぐることはしない。そういう芸ではないだろう。どこかでまた、偶然巡り合ったとき、「ああ、やってるやってる。やっぱり面白いわ」と思えばいいのである。それは私が考える、理想的な芸人の在り方でもある。
ちょっと検索してみたら、ウクレレえいじは1967年生まれ。東京乾電池、ワハハ本舗など劇団の出身で、ウクレレ漫談を始めたのはわりあい最近。とんねるず司会の「細かすぎて伝わらないモノマネ選手権」に出場し優勝経験もある。知らなかったなあ。
映画『ルノワール』
受賞は逃したが、カンヌ国際映画祭で話題となった早川千絵の監督第二作『ルノワール』を見た。1980年代後半、十一歳の少女フキのひと夏の物語。入院中の父、キャリアの座をはずされた母親とともに郊外の集合住宅に暮らす。自分の葬式の場面を想像し作文に書くフキは、オカルトに興味を持つなど感性豊かながらどこか危うげな少女で、彼女の心の動きを説明過剰にならず、カメラという視点で追う。
タイトルの「ルノワール」は、フキがルノワールの複製画を買って壁に飾るという、それだけのことからついた。しかし、抑えた色調といい、静かな画面展開はたしかにルノワールの静物画を想起もさせるのだった。とにかく主演のフキを演じた鈴木唯がいい。子役の名演技、というようなわざとらしさはなく、独立した世界観を持つ少女として映像の中で生きる。ストーリーはあるが、同じ年齢のフキという少女としてそこにいる、という意味でドキュメント性もあるのだった。父親はリリー・フランキー、母親は石田ひかり。いずれも好演。
1980年代後半はたしかにこうだった、と思い出すのは、たとえばテレビの画面が小さい(パソコンぐらい)、もちろんパソコンや携帯電話の普及はずっと後だ。伝言ダイヤルという課金される電話の通話システムが、現在でいう出会い系サイトのように使われていたのもこの映画で「ああ、そうだった」と懐かしかった。一人で家にいることの多い不安定なフキは、この伝言ダイヤルで危険な目に遭う。じつに危うい。
母娘の外食はもっぱらファミレスで、疲れた二人がタオルを敷いたテーブルに伏して眠るシーンがいい。ファミレスのテーブルは大きいからな。なにもかもに疲れてしまったという倦怠に詩情がある。
大きな川の土手や競馬場が映ることから、最初、東京の府中市とか多摩川近辺かと思ったら、長良川の鵜飼いが登場し、岐阜が舞台なのだとわかる。大人たちがみなどこか危うげで、しっかりしたところを見せてくれよと言いたくなるが、その狭間で揺れ動く思春期の十一歳がみごとに映像に定着している。大ヒット、とならずとも、見た者の心に必ず新しい絵が残るはずだ。あれはどこで撮影されたか、フキ一家が住む設定で団地が登場する。四階とか五階の中層階で、そこに不安も生み出される団地映画でもある。
タイトル、本文イラスト、写真=筆者
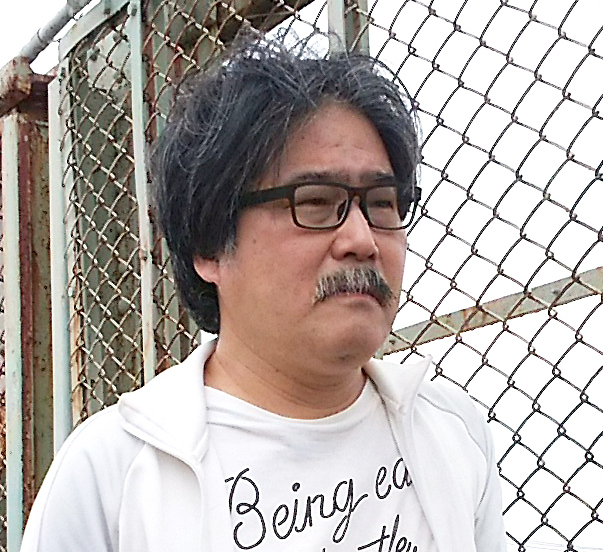
おかざき・たけし 1957年大阪生まれ。立命館大学卒業後、高校の国語教師、出版社勤務を経てフリーライターに。「神保町ライター」の異名を持つ。近著に『憧れの住む東京へ』(本の雑誌社、2023年)、『古本大全』(ちくま文庫、2024年)、『ふくらむ読書』(春陽堂書店、2024年)などがある。