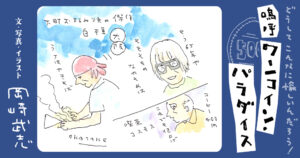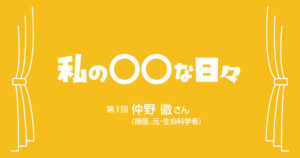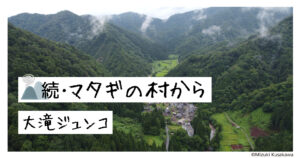講評
◎は佳作(作品掲載あり)、〇は選外佳作、それ以外は作品の投稿順に掲載しています。
◎「カイ」更科 憬
タイトルの「カイ」は「貝」「海」「改」へと繋がっていく。貝合わせは夫婦の象徴としてよく用いられるものだが、この世でたった一人の「母」こそが自分の対であり、そのつながりを断ち切ったあとのまなざしの描き方も良い。母から生まれた語り手が、母を母という役割から解放することで、語り手が「母」を産みなおして旅立たせるような、不思議で印象深い情景だった。散文詩であるが、独特な意味の揺れがあり、海の波のように心地よかった。
◎「墨野」三明十種
聞いたことのないはずなのに、不思議と近しい気がする「墨野」。「コナラ」の「枯レ枝」と「焚火跡」、そして「団栗」が、「墨野」のイメージをはっきりと浮かび上がらせる。薄暗い「墨野」と、まるで病院の待合室のように無機質で真っ白な「新世界」の対比も面白い。「新世界」では、外の景色も見えない。大事な旧仮名遣いは残しつつ、そうでもない箇所は現代仮名遣いにした方が、令和時代に生まれた詩であることを強調できていいのではないかと思ったが、読む人によって判断は分かれるだろう。
◎「群青の空」三明十種
「許す」ではなく、「赦す」という漢字を用いることで、この語り手が長い間何かに囚われている状況であることを暗に伝えている。「吸い込まれていく」ではなく、「編み込まれていく」という表現も、タワレコの黄色い袋が、青い空にいつまでも留まって取れなくなるような情景を思わせていい。青い空をあおむく、その動きも快かった。
◎「川べりの生活」浅浦 藻
現実離れした「古老」とのやりとりが良い感じに飛んでいて心地よかった。カメラワークがうまいために、単なるショートショートになっていない。最後がうまく着地しすぎているために、オチっぽく見えて少しもったいない。これから探しに出かける、または探している最中の情景描写で終えた方が、良い余韻が残るかもしれない。
◎「扉の向こう」あられ工場
卓球台の上を軽快に跳ねるピンポン玉とサンバの音。そして打って変わって、いつまでも退職について頭を悩ませている語り手の対比が面白い。語り手の身動きは静止しているが、思考はピンポン玉のように、いつまでもうろうろしているのだろう。空間的にも広々と描いた世界が心地いい。「腕がまっすぐ伸びる」という箇所では思わず目を奪われる。独特なメリハリのつけ方をしている。
○「夜のために」浅浦 藻
述語をもたない「それが」がうまく効いて、冒頭の言葉がまさに「満たすように」「溶ける」のを感じた。今後別の機会で発表することがあるかもしれないと思ったので、なるべく引用しないが、「町」で暮らす情景の表現がうまい。もう一方の作品を佳作として、この作品を選外佳作としたのは、最終行「思った」がせっかく広がった情景を無理に閉じているような感じがしてもったいないと感じたからだ。語り手の心情吐露で詩をとじると、作品は小さくまとまってしまう傾向がある。「手紙」が締めくくりとして欠かせないなら、手紙を書こうと決意する様子を情景描写の形で描くのはどうか、試してみてほしい。
○「読書」道下 宥
仮に、タイトルを隠した状態で、「この詩のタイトルは何だと思う」と尋ねられたとして、「読書」と答えられる人は、著者以外にはいないと思う。だからこそ、詩の言葉がダブルミーニングのように効いて面白い。二連目「柘榴」が飛び出したのは意外だったが、強い必然を感じた。最終行はまるで時報にハッとするようなインパクトがある。
○「一滴も濁らせないで」福富ぶぶ
「タコさん公園」にいる「チャッピー」は、『タコピーの原罪』という漫画のオマージュだろうかとも考えたが、偶然の符合かもしれない。「チャッピー」は賢い犬とも読めるし、道化を演じるこどもの姿とも読める。「チャッピー」の存在感が強いが、一方で、影のある「私」にも目が離せなくなる魅力がある。動脈と静脈の色の違いを描写できたら、より直感的にこの作品世界に入り込むことができるかもしれないと思ったのは、同じ血でも、たしかに色合いが異なるような気がしたからだ。
○「豊かさや豊ならざる五月かな」村口宜史
「五月の雨」のやわらかな足先をも見たような気がした。語り手は「人間」と「鹿」のはざまにいて、中間的な視点をもつからこそ、この最終連の言葉が強く響くのだと思う。「おろかな」という主観の言葉をあえて付けなければ、読み手の心も、語り手と同じように、柔らかな若葉のごとく、心地よく揺れ動くことができる。
○「一筋の光」藍 眞澄
この詩を締めくくる言葉がうまく効いている。「光」が作品世界を通り抜けて、この現実世界にも差し込むような力がある。やや説明的な感じがあるが、それだけ確固たるイメージがあるということだ。短編映画をつくるようにイメージをまず整理して、情景描写で書き起こしていけば、説明的な感じは薄れてより洗練された作品になるのではないか。
○「百五十キロ」白木ニナ
伝統的な「水田」の景色に映る「コーラルピンク」、「夕日の本丸」という独特な言葉の合わせかたが面白い。モチーフの重ね方の独自性が強いために、「ぴりり」といった簡単なオノマトペや、「ずっと」「うっすらと」「つまんない」という言い方が浮いて見えてしまう。モチーフ自体はそのままにして、夏目漱石、森鷗外、内田百閒が使いそうな言葉遣いでこの詩を語り直すと、より普遍的で洗練された作品になるのではないかと感じた。
○「福音の側は」碧 はる
散文詩かと思いきや、実は二十字で厳格に断ち切られた行分け詩である。フォントや構成によって、作品世界を視覚的に描写・演出している。大きな鋏で布を断ち切ったような最終行は、思わず惚れ惚れと眺めた。情景描写が濁流のように流れ、イメージがやや拡散してもったいないような気がした。それはこの作品の面白さでもあるが、一度語り手が立ち止まる時間を設けることで、緩急が生まれてより良い余韻が残るのではないか。
○「太陽を呼ぶ儀式」アリサカ・ユキ
女の歩く足音と、その足下にある「露草の心臓音」が徐々に重なっていく。映像だけでなく、音にまで著者は感覚を伸ばしている。この作品中の重大なモチーフである「女」は、ある種典型的な女神的印象を振りまきながらも、なにもものを言わずに立ち去るという振る舞いから、自動人形的な不気味さもある。あるいは人間の「女」ではなく、「光」の使者なのかもしれない。
◯「言えなかったものたち」緒方水花里
「明日死ぬくらいなら優先席座れよ」という言葉がカウンターパンチのように、苦しい吐露を連ねた詩の流れを変えて、ハッと目を覚まさせる。本谷有希子の言葉の鋭さを想起した。イルミネーションの箇所などのコミカルなくだりが、沼のように重たい情景を強く掻き回すようで良い。情景描写から場面が呼び起こされるのではなく、台詞から場面が想起される。女性は、それぞれ自身の実体験に基づいた生々しい場面が想起されるのだろう。
○「浮き足」佐藤悠花
自転車という語を出さずに、自転車を漕いでいるシーンをいきいきと描き出している。二連目の「依然浮くのは、」が「いつまで続いていいのか見えないためである。」へとつながる一文の意味が直感的に読み取れず、すこしもったいないように感じた。「進んでいけば」からの文は削除して、三連目に繋いでしまった方が、まわりの景色が流れて行く感じが伝わりやすくなるかもしれない。
○「祝福」吉岡幸一
「世界が三千回回転して仏壇の扉が開く」。三千世界を思わせる仏教的な世界観を、地球という科学的な視野へと展開していく様子が面白かった。「三」という数字を丁寧になぞっていくが、仏の道へと通ずる適切な「三千」という数字に達するのは冒頭だけで、あとは「三億」であったり、「三百」であったり、過剰すぎたり、少なすぎたり、解脱へと達せないもどかしさを感じ取った。「悲しくないはずなのに」「不機嫌そうな」といった説明的な形容詞句は、情景描写に変えればより洗練される。
○「珈琲」井上正行
不可逆の「時間」が「あとずさり」しながら、ジーンズの色を褪せさせるという矛盾の書き出しが面白い。一文一文を連として分けているが、それがイメージをぶつりぶつりと切ってしまっているような気がする。あえて繋げて、情景の化学変化をみるような楽しみ方をしてもいいのではないか。完成度が高いが、最終連の沈鬱な情景が、この『珈琲』という軽やかで上品な作品を持ち上げられないほど重たくしているので、この言葉はあえて最終連には置かない方が活きると思った。カップに残るコーヒーの描写も良い。
○「場所」井上正行
「自販機」・「ブルーな箱」、「小刻みに揺れている」・「はばたく」など、対応関係から情景が展開していく様子が面白い。「キラキラ」という簡単なオノマトペも、皮肉のようにあえて使っていて、それも「きらめかせる」という語へとつながっていく。自販機の光が「キラキラ」と見えるほどの暗さがある作品だが、あくまで生の光に向かって進もうとする強さに好感をおぼえた。八連目の「差し出す」と、九連目最終行の「差し出している」が、その前の連での対応関係と比較すると差を感じる。「差し出している」情景を絵のように描写して、「差し伸べている」などとした方が、隅々にまで手が行き届いている感じを与えるかもしれない。
○「寂しき亀は」三波 並
一、二連目の、「光」と「闇」の描写が特に冴えている。二連目「しずかに広がってゆく」「暗闇」は、光がわずかにとけた淡い闇ではなく、漆黒の闇を表しているという書き方も面白かった。卓越した想像力と情景描写力がある分、最終連の「ほんとうの寂しさ」をまだ知らないということを語り手が仄めかしたのがなんとなく謙遜にも読めて、もったいないように感じた。詩を愛するように、「私」を愛することで、より詩に力がみなぎる詩人であるようにも感じる。
「探しています」まつりぺきん
著者の作品は、どこか懐かしさを感じさせる色彩がある。「ちり紙」や「おかっぱ」という語からだろうかとも思ったけれども、仮にそこを「ティッシュ」や「ボブカット」などと今風の言葉に置き換えても、この不思議な褪色の印象は残るだろうと思った。どこか笑いのある空気感が、行分け詩の中で不気味さへと変化していく。最後、女の子の「鍵っ子」のさびしさが音として残る感じもいい。
「ため息」cofumi
口から出た「ため息」が「足のつま先を冷やす」という距離感が面白い。一時的な憂鬱ではなく、まるで雪女の息のように、骨まで凍らす冷たい憂鬱を読み取った。一方で、温かな「眠りかけた猫」、まるでスポンジケーキのように「やわらかく崩れていく記憶」などの言葉は心地良い。冒頭の冷たさから、ほの温かな最終連に辿り着いたとき、心身をほぐされた読み手は新たな気持ちで「光」をまなざすことができるだろうと思った。
「金箔の娘」吉岡幸一
「父」の夢の世界。現実世界の「父」にとっては歓びなのか、恐ろしいものなのか、その判断はあえて余白にされている。「星」から捻出された「金箔」、「銀河製のスプーン」といった言葉から、娘を閉じ込める「父」はいま地球にはいないことが伝わる。「夜が夜になるまで」という言葉から、窓の外にある宇宙の暗闇を見た。
「世界平和①」福富ぶぶ
世界平和の形は一つではなく、パターン①や②があると思わせるタイトルが面白い。「シンギュラリティ」はAIにまつわる語としてまず読んだが、この作品は、AIよりもずっと「肛門」の方が世界を左右する重大なものであることを伝えている。目に見えない「オバケ」が登場する一方で、「あの子の笑顔」、切り方に厳格なきまりのある「トマト」、「自転車」など、物質主義的な世界観が展開されていく。「我慢してる」「うんち」は、目には見えず、「オバケ」と同じ仲間だ。「世界」も、目に見えているようで、目に見えてない、まさに「我慢してる」「うんち」と同じ存在である。
「寵児の弓形」角 朋美
一連目は「吹き閉じよ」の言葉から、「天つ風雲のかよひ路吹きとぢよをとめの姿しばしとどめむ」の一首が強く浮かんだ。僧正遍昭のこの一首は天女の姿を名残惜しく思う歌だが、この作品は愛しい「馬」への思いが強く伝わってくる。空に帰る天女と、どこまでも駆けていきそうな馬の対比は、遠野物語のおしらさまの伝説をも彷彿とさせた。著者の精神にたしかにある世界が、原始的な気配をはなっているのが面白い。「視界」は「視線」にした方が、風を切る「鏃」とも合うのではないかと思ったが、「視界」とすることで、顔も動かさず馬を見つめ続ける語り手の姿が思い浮かぶ。
「栞」雪代明希
たががはずれたように「壊れ」ていく世界のなかで、「あなた」だけがその崩壊を止めることができる。実際には崩壊は止まっておらず、ただ「あなた」がいれば、どんな世界でも許すことができる、ということなのかもしれない。そんな異質な「あなた」を「栞」と呼ぶ声が美しく響く。最終行に予想外の「ハリセン」が登場し、その独特なコミカルさに思わず笑ってしまった。
「水門」雪代明希
「南国の海」と「空」、そして「宇宙の彼方」へと続く、青色のグラデーションが美しい。青の情景に挿入される「黄色い小花」も、良い差し色になっている。青と黄の組み合わせは、生の根源を表しているようですがすがしい。地面に沈んだ「僕の国」と「巨大な鳥」というモチーフは、児童文学のファンタタジー世界を彷彿とさせる。そんな美しい水の世界へと誘うタイトルも良い。
「真昼の月が消えるまで」紺野真
「昼の月」は、ある時期が去れば、明るい空からしばらく姿を隠してしまう。そうした特質を「君」に重ねている。どうして「昼の月」ではなく「真昼の月」なのだろうと考えた。月は「君」で「僕」は太陽であって、対照的な二人が、再接近した特別な時間を表しているのだろう。他者を描くことで、自分の存在が浮かび上がる試み。水沢なおの詩集『美しいからだよ』は良い参考になるかもしれない。
「五月の雨」末埼鳩
不思議と、この筆者の書く食い物は美味そうにみえる。二連目の「食パン」「カフェオレ」、「水気をたっぷり含み」という表現から、「白い星形の小さな花」の「ジャスミン」まで、思わず生唾を飲んだ。特に生々しく表現しているというわけではないのに、これは著者の特徴の一つだと思う。五感を刺激する全てのものを、心から愛しているからかもしれない。憂いもきちんと表現されているが、喜びの箇所の方が、生き生きとした血が通っている。喜びを表現すれば、その根にある憂いも言外につたわってくる。
「朝」藍 眞澄
「両手を広げる/からだいっぱいに」という冒頭は、読み手の心と体をまるでストレッチさせるように爽快に響く。有限な「からだ」が、もし無限に伸びたなら、この地球を丸ごと愛せるものなのかもしれない。「要らないもの」を全て捨て去り。「時間の隙間に足を踏み入れる」ことで、人は何度でも、今「産まれ落ちた」ように生きることができるのかもしれないと、この作品を読んで思った。
「サイレン」露野うた
冒頭の「足の裏に残った/ざらりとした感触」という言葉が伏線となって、この作品を通り抜けた後には、読み手の胸には不思議な跡が残る。人の温かな息遣いがある一方で、「思い出を殺した」「咲かなかった花」「街に響く笑い声」など、氷よりも冷たい死のイメージが描かれる。柔らかな草の上を裸足で歩いていたはずが、気がつくと、氷の刃の上を歩いていたような不気味さがある。本来、定位置で人を導く「サイレン」が「近づいて来る」という表現も面白い。
「忘却の庭」露野うた
語り手の言葉はまさに「風」のように、傷を癒し冷やしていく。傷を負った光景を吹き過ぎていくような感じも心地良い。癒しの先には「忘却」がある。行の一字目で「あなた」「雨」「忘れていく」「合わない」と、丁寧に韻が踏んでいる。声に出して読んでみると、雨音のように、ぼうっとしながら、自然な形で作品世界を感じ取れた。
「ベランダの東」白木ニナ
タイトルは『エデンの東』をオマージュしているのだろうか。「獄に繋がれた」という言葉のインパクトが非常に強いため、冒頭は「私は獄にいた」などと、あえてさらりと述べてしまった方が、直感的に世界観に入り込めるかもしれない。「新緑の鮮やかさが響きもしなかった」、視覚から心の振動へとつなげる書き方が印象的。最終連の「この世の重なりにも」という言葉は、独自の世界観を感じた。
「チル、アウト」早乙女ボブ
穏やかな日常をうたう詩は同じようなものになりがちだが、この著者の描く日常の景色には独特のブルーの色合いがあって、「他のものと似たような感じ」という印象にはならない。「むすめの寿司」、「わたし」が注文した「冷めた菜」、「むすこの重湯」、「ガム」と、味覚から世界へと入り込んでいく感じが面白い。二連目、うまそうな「天津飯」に「妖かしの」「にごった目玉」が落ちるというのは、まるで自分の食べ物が汚されたかのように思わず憤った。「妖かし」は、最終連で語り手が抱える不安の化身なのだろうか。
「湖畔にて」工藤もこ
目の前にある「穏やかな湖」と、「忙しなく/車がとおる」「背後」。表裏で展開されるシーンの対比が面白い。その情景に託された語り手の心情が強く伝わってくる。誠実な詩だと思った。音に対する繊細な感覚から、やがて読み手も「足元で咲く桜」の蕾が開く音も聞くような気分になる。「足元に」魚の「死骸」が浮いてきて、知らぬ間に自分が湖に足を浸していたことに気づく。
「映画を観た」七十里悠
まっすぐで素朴なタイトルと、はっきりとした起承転結がユニーク。一方で、二連目にある映画の投影を「目に映る光」と屈折的に表現した点が鮮やかに印象に残った。こうした自分にしか書けない情景描写を意識することで、より筆者の世界観は鮮やかに広がっていくだろう。意識的に好きな詩集をなるべくたくさん見つけるといい。
「火事」為平 澪
家に火を放たれた「私」は、誰かに対する憎しみを述べているわけではないにもかかわらず、怨念に似た怒りが作品全体に満ち満ちている。最後、あたかも周囲への発覚を防ぐかのように囚われている自身の「右手」も、意味深な闇の暗がりにあって、読者は作品を読み終えた後も、真実は何だったのか、闇に目を凝らそうとするだろう。詩とモノローグの境界に挑戦した作品だと感じた。
「女神さま」いちのちかこ
「耳にできた/小さな湖」が、天罰のように虐げる者たちを飲み込もうとするイメージ。独自性が強く光る一方で、普遍的な光景のようにも思えて面白かった。少年の語り口を思わせるからなのか、闇の中にもかすかな光がある童話のような世界を思わせる。しかし、性への困惑を真正直に告白し、自分の始末を母親に懇願する少年の姿は、寺山修司のあの奇妙な世界観にも通じるような気がした。
「花見」緒方水花里
だらしなく伸びていく「ハナの下」を「見上げる」という書き方が、語り手の身体が少女であることを暗示している。語り手を「めしべ」側として読んでいたが、最終連で男に向かって繰り出された「行きなさいわたしの子供達」は、まるで雄花から散らされる花粉、精子の暗喩にも読めて印象に残った。「炸裂的な太腿で」という表現の勢いに、思わず笑っていた。言葉もまた、「わたしの子供達」なのだろう。
「寝返り」多賀嶋
「橋」がひっくり返るのではなく、「寝返」りをうつ、というのが面白い。最終行は重く暗いが、この二行目によってコミカルな空気もある。「彼岸」「此岸」をあらかじめ明示させておくことで、「寝返り」をうたれたのが「此岸」側の生者で、「愚者」は「生者」であることが直感的にわかる。それならばこの光景を見ているのはだれだろうと考えると、背筋が寒くなる。
「途上」森江純子
男尊女卑、「性差」へのまなざしが、鬼にもそそがれる。「藍の剣」は神代の剣を思わせる。あるいは、「鬼」を斬ったという伝説がある天下五剣を指しているのかもしれない。独自の世界観を描いている分、語り手の姿を探してしまう。この鬼の宴に、こぶとりじいさんのようにさっそうと現れる語り手の姿を見ることができれば、より作品に血が通うような気がした。
「あお空」森江純子
「激しい気候変動」による灼熱から、1945年の広島の焦土がよみがえる。その契機となるかけ声をかけた「お姫さま」は、宮城県から皇居に向かってやってくる。宮城県から来たこの「お姫さま」は修学旅行生なのか、それとも語り手自身なのか、知りたくなった。修学旅行生であれば、「百人のお姫さまが おしゃべりをしながら」などといれると伝わりやすくなると思う。過去の記憶が、誰の上にもひろがる「あお空」のように、私たちにもつながっているというメッセージも印象深い。
「春」花山徳康
地下・屋根瓦・海・化学物質・道路とめまぐるしく視点が変わり、万華鏡のような世界を展開する。「竹の子」「まじないの紙」「鉄塔」など含みのある、妖しい美しさを放つモチーフが次々と登場するが、一つの情景が結ぶ前に拡散してしまっているような感じも同時にあってもったいないような気もした。「道路に撒かれた緑の中」という一行、雨に濡れた道路に反射する葉の色あいを的確に表現している。
講評を終えて
どの作品にも強い個性があって良い。これらの作品どれもが、筆者の孤独な執筆作業からうまれてきたものだと思うと感慨深い。自分の内にある宇宙を耕す時間も良いが、外にある宇宙にハッと目を奪われる瞬間もかけがえない。詩を書く時間に息苦しさを感じた時は、やはり、詩の窓を開けた方がいい。ノーベル文学賞受賞者ハン・ガン『そっと 静かに』というエッセイ集は、彼女が書いた詩を読むこともできる。気になる方はぜひ。
詩を好きになるほどに、詩は光る。投稿欄を運営していると、本当に強くそう感じる。 (マーサ)

1990年埼玉県生まれ。詩人。第五十四回現代詩手帖賞受賞。『狸の匣』(思潮社)で第二十三回中原中也賞、『雨をよぶ灯台』(思潮社)で第二十八回萩原朔太郎賞受賞。