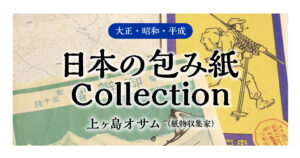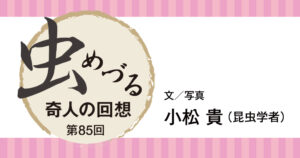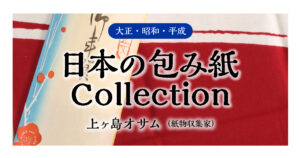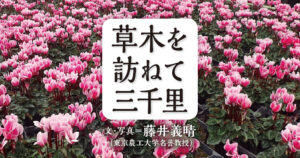第22回 桜草は見かけによらず、したたかです
桜草はサクラソウ科サクラソウ属の多年草で、日本原産の美しい植物です。花びらが五枚に分かれサクラの花に似ているので桜草と呼ばれます。
花の色や形に変種ができやすいので、江戸時代に武士の間で栽培が流行し、数百の園芸品種がつくられました。明治維新でやや廃れましたが、現在も約三百種の栽培品種があります。

江戸時代、五段の雛壇に配色を考えて美しく配置した鑑賞法
ヨーロッパにもサクラソウ属植物があり、園芸店でプリムラ・ポリアンサ(西洋桜草)、プリムラ・マラコイデス(乙女桜)、プリムラ・オブコニカ(常盤桜)などが「サクラソウ」として売られています。
前回、ダーウィンが自宅で行ったつる植物に関する素晴らしい研究を紹介しましたが、サクラソウに関しても詳しく観察しており、めしべとおしべの高さが逆の二種類の花があること、この構造によってハチによる受粉を確実にしていることを発見しています。
園芸種グループ

花の切れ込みが深くなり美しい

古い園芸品種


藤紫色で抱え咲き
日本在来のサクラソウは、江戸時代、荒川の湿地帯など、湿った場所や原野の草の中に生え、ときには群落して美しい光景をつくっていました。
さいたま市桜区の「田島ケ原サクラソウ自生地」は国の特別天然記念物に指定されている貴重な群落です。田島ケ原は周辺が開発されるにつれて群落が減少しました。その後ボランティアの方々の努力で自生地を守る運動が行われ、サクラソウ群落が回復し、環境省のレッドリストカテゴリーでは、ランクが絶滅のおそれがある絶滅危惧Ⅱ類から下がり、準絶滅危惧に指定されています。
野生種グループ


野生でも白い花が見つかる


サクラソウは花が桜に似て清楚で美しく、多くの日本人に好かれています。しかし、サクラソウ属植物はアレロパシー活性(※)が強く、根や葉から他の生物に影響を及ぼす物質を出して大群落をつくる傾向があるようです。
特に、葉や茎に生えている細かい毛にはプリミンという毒素が含まれています。そのため葉に触れると皮膚炎を引き起こすことがあり、「サクラソウ皮膚炎」と呼ばれています。
この物質はセイヨウサクラソウ、とくにプリムラ・オブコニカ(常盤桜)の葉に多く含まれており、日本のサクラソウでは少なく、セイヨウサクラソウでもプリミンが少ない品種が選抜されていますが、肌が敏感な人は注意するといいでしょう。「きれいな花には棘(毒)がある」のたとえのように、サクラソウも花は美しいけれど、けっこうしたたかで強い植物なので、可愛いからといって葉を撫でたりしないほうが無難です。
サクラソウの仲間には、クリンソウのように大型の山野草があり、アレロパシー活性が強く、葉には鹿も食べ残すほど毒性が強い種があります。また、近縁種のオカトラノオ、クサレダマ、コナスビなどのオカトラノオ(リシマキア)属植物には、野生で大群落をつくり、ときには雑草化する強い植物があります。
※アレロパシー活性 他の植物の生長を抑える物質(アレロケミカル)を放出したりすること。日本語では「他感作用」という。筆者・藤井さんの専門分野。藤井さんの研究拠点は「他感作用研究所」。
サクラソウの仲間

筑波実験植物園で撮影

昭和薬科大学植物園で撮影。
有毒成分は薬用にもなるので研究されている

リシマキアという名前で園芸種が販売されグラウンドカバープランツとして優れた品種がある
今回のサクラソウの写真は筑波大学で保存・研究されていた花を撮影したものです。

ふじい・よしはる 1955年兵庫県生まれ。博士(農学)。東京農工大学名誉教授。鯉渕学園農業栄養専門学校教授。2009年、植物のアレロパシー研究で文部科学大臣表彰科学技術賞受賞。『植物たちの静かな戦い』(化学同人)ほか著書多数。
バックナンバー