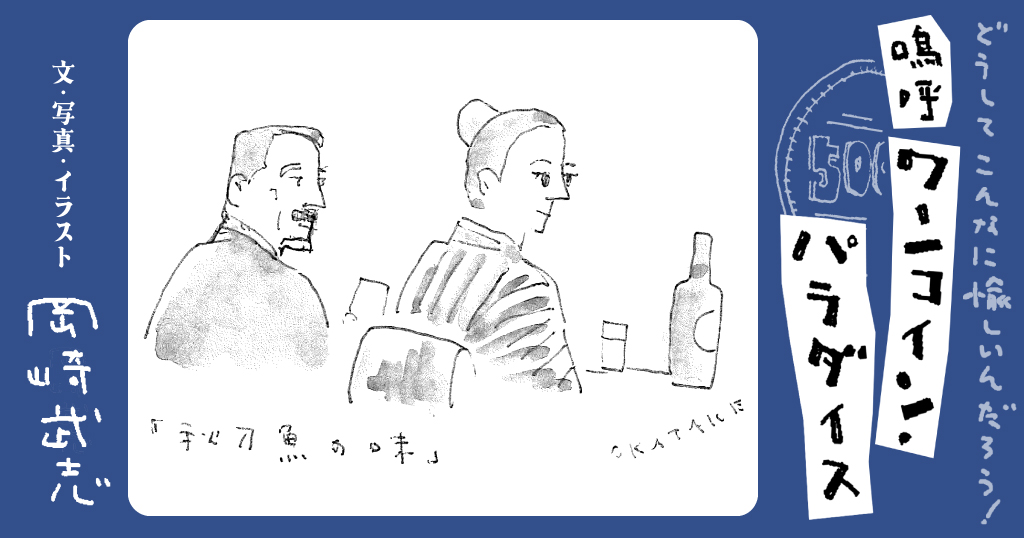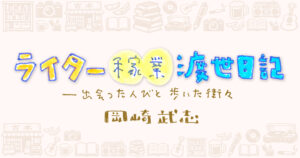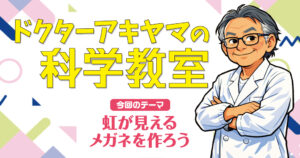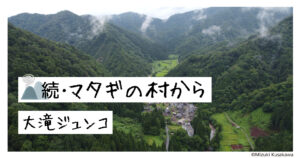第16回 秋刀魚の味は目に沁みる
過去に七、八回は見ているのに、テレビで放映されるとあって『秋刀魚の味』をブラウン管の前で釘付けになってまた見た。小津安二郎の1962年作品。翌年12月12日に六十歳で死去する小津の最後の映画となった。奇しくも命日が誕生日。しかも還暦と、きれいに円環して閉じた人生だ。 北鎌倉「円覚寺」に、ただ一文字「無」と刻まれた墓がある。
母親が早く逝き、働きながら家を差配する二十四歳の美しい娘(岩下志麻)を手放したくないと思いつつ、結婚を勧める父親(笠智衆)の話だ。昭和三十年代、二十四歳未婚はやや遅め。『晩春』(1949年)で原節子と笠智衆で演じられたテーマの反復であり、父親を母親(原節子)に代えて『秋日和』(1960年)でも試みられた。『麦秋』(1951年)も婚期の遅れた長女(原節子)が紆余曲折を経て、意外な人物と結ばれる。
実生活では独身で、子のない小津だったが、作品においては娘の縁談を繰り返し描いた。私は独身時代から小津の作品を何度も見続けたが、『秋刀魚の味』を今年(2024年)、違った思いで受け止めていた。というのも、六月にたった一人の娘を嫁がせたからである。娘がいなくなり、妻と始まった二人暮らしだったが、思いのほか堪えた。いつも夜の食卓を囲み、言葉を交わした相手がいない。それは最初想定したより淋しい出来事だった。片腕をもぎとられたような欠落を感じて、少し夜中のリビングで酒の杯を空けながら泣いたのである。
娘を嫁がせた日、酔った平山(笠智衆)は、一人、台所の椅子に腰かけている。ラストシーンのこの背中に寂寥と喪失がにじみ出て胸を打つ。つまり台所の椅子に座ってうなだれているのはまさに私だ。
これが息子だったら、淋しいには違いないが感慨は別だろう。森鷗外と茉莉、幸田露伴と文、萩原朔太郎と葉子など、作家としての父親を追憶して回想を書くケースが多く、彼女らはそれで文壇デビューを果たす。息子が父親を、という場合もあるが数は少なく、しかも思い入れの深さが違う。父と娘は疑似恋愛の関係に相当する。文豪の娘たちはほぼ皆ファザコンで、茉莉など、鷗外を「パッパ」と呼び、吐く痰まで美しいというのだ。
ところで『秋刀魚の味』とタイトルには挙げるが、秋刀魚を食べるシーンはなく話題にも上らない(出てくる魚は「鱧」)。これはやはり佐藤春夫の名詩「秋刀魚の歌」に由来するのであろう。
あはれ
秋風よ
情[こころ]あらば傳へてよ
――男ありて
今日の夕餉に ひとり
さんまを食[くら]ひて
思ひにふける と。
このわびしさは、鮪や鯛、鮃など他の魚では出ない。
百年を経て遠い昭和を思う
2025年は昭和に換算すれば百年目に当たる。さぞ昭和を回顧する企画が次々と繰り出されることだろう。私も一つ企画を立てて、うまくいけば原稿が書けそうだ。
昭和、平成、令和と三つの元号を生きるとは思いもよらなかった。昭和の終わり、1989年に三十二歳だった私は、幼少期から青年期を昭和に生きてきた。すでにその倍する時間が経過したが、圧倒的に濃い記憶は高度成長期を含む前々代にある。
平成と令和は長い停滞期にある気がしていたが、次のような文章を読むと、やっぱり昭和は遠くなったぞ、と思うのだった。
関川夏央のエッセイ「駒が勇めば花が散る」(新潮文庫『水のように笑う』所収)は不思議なタイトルだが、「咲いた桜になぜ駒つなぐ、駒が勇めば花が散る」という都都逸の一節で、「駒」は馬のこと。
「咲いた桜の木になぜ馬をつなぐのか、馬が何かの拍子に暴れれば花が散るではないか」という意で粋な文句である。
長い海外生活を終え帰国した新渡戸稲造が、酒席で芸者が三味線を持ってこの都都逸を歌ったところ、「日本にもこのような素晴らしい詩があるのか」とすっかり感心したというエピソードをどこかで読んだ。
関川はいかにも日本らしい情景を歌った詩としてタイトルに引用したのだろう。エッセイはそしてこんな内容。関川の女友だちが外国暮らしをしていて、ちょうど桜の季節、久々に日本に帰ってきた。その外国に慣れた目で、あらためて日本を眺めて気づく。「日本はかわっている」という。
花見するサラリーマンを見て「外人てさ、ああいうふうに地面にすわらないもんね、絶対。そのほか、『日本にあって外国にないもの』として、空港の見送りでする万歳。背広と下駄の組み合わせ(岡崎注/田中角栄を指すのだろう)。フォークの背中にのせるライス。電車の中の読書」と羅列する。この文章が書かれたのは1985年ごろ。昭和でいえば60年。
たしかにあったなあ、と頬がゆるむのだが、令和になって、気づけばどれも消えてしまった風俗習慣である。「フォークの背中にのせるライス」なんて、どこから広まったマナーなのかわからないが、たしかに四十年前に見た光景だし、よくあんな器用なことをやっていたものだと感心する。
そしてショックなのは、やはり「電車の中の読書」だろう。外国人観光客が来日して驚くことの一つだったようだが、いまやあっさりと消え去ってしまった。私は意地を張って、逆に電車の中では本を読むようにしているのだが、真冬に上半身裸でパンツ一枚になるようなもので、誰も関心を持たない(危ない奴か)し、孤立を深めるだけである。
あと二十年もして、私がまだ存命なら、やっぱり電車の中で本を読むだろう。それを見た子どもが傍らの母親にこう聞く。
「ねえママ、あそこで紙の束を開いて見ているおじいさんがいるけど、いったい何をしているの?」

大月の冬はなにもない冬です
よく友人や知人から、酔っぱらって電車に乗り寝落ちして、降りる駅を乗り過ごし終点まで行ったという話を聞く。たいてい最終に近く、もう帰りの便はない。ホテルに泊まるかタクシーに乗るか。朝までネットカフェに転がり込むか……という話は滑稽かつ哀愁を帯びる。珍しく笑える失敗話なのである。
それを半ばうらやましいような心持で聞くのが私で、まったく可愛げのない奴なのだが、これまで乗り過ごして終点まで行った経験がない。どんなに泥酔しても、たいてい本を読んでいるのでそれが抑止力になるのか。四十年近い飲酒人生で、もののみごとに降りるべき駅で降りてきた(一つぐらい乗り過ごしたことはある)。
私は中央線乗車人なのだが、下車するのは国立駅。同じ路線の乗り過ごしの名人たちに聞くと「高尾まではざらですよ」となる。恐ろしいのは大月まで行ってしまうことで、そこはもう山梨県。しかもホテルは少なく(東横インあり)、タクシーを使って帰るとすればとんでもない金額になる(八王子駅まで約2万5000円)。「やってしまった」感がひしひしと迫るシチュエーションなのだ。 それでも冒険者が月に四、五人はいると聞く。
そんな話を聞いて、よし大月で降りてみようと計画した。ただし昼間。これまで中央線には塩山、甲府、松本などけっこう足を延ばしてきたが、大月といえば富士急行線への乗り換え駅で、改札を出たことがない。通り過ぎるだけの大月はいったいどんな街なのか。立川駅から特急に乗れば約三十五分。意外に近い。

大月は古く甲州街道の主要な宿場として栄えた町で織物産業を基幹とするが、高度成長期の後、すっかり寂れてしまった。大月駅ではけっこう降りる客があったものの、ほぼすべてが富士急行へ乗り換えていく。改札を出ると人影はまばらで「富士山の眺めが日本一美しい街」が売り文句のようだが、駅前からは拝めなかった。お土産店を兼ねた観光案内所で数種パンフレットをもらい、まずは中央線沿いに延びる旧甲州街道を東へ歩いてみる。道がくねくねと曲がっているのが、いかにも旧街道っぽい。飲食店はいくつかあるものの、夜営業の飲み屋主体で行列のできる店はなさそうだ。
観光というものの「光」が観えない。郵便局の角を折れ、路地へ入ると「イオン」の文字が。日本全国いたるところにイオンあり。ただし大月のイオンは町の小さなスーパーといった風情。こんなに「佗び寂び」のあるイオンは初めて見た。 ネコさえ歩いていない。
国道の信号近くに「三嶋神社」。806年創建とあっていかにも時代を帯びている。参拝客はなく国道を疾走するトラックの爆音のみ境内に響き渡る。家内安全を祈願してお参りし、それでもう大月駅前まで戻ってきてしまった。この先、西へ向かえば桃太郎伝説の神社があると聞いたが、まあいいだろう。
結局、大月観光の売りは富士山ビュースポットと「岩殿山」、あと強力なのが奇橋「猿橋」だろう。ここでバスに乗りたくなって、駅前ロータリーで「猿橋」行きの便を待つ。ベンチにこしかけた老女から「どこまで行きなさる」と言われ「猿橋」と答えたら、「汽車で行ったほうが早い」とアドバイスされる。令和の世になって鉄道を「汽車」と言う人がいることに驚いた。記憶は昭和あたりで止まっているのだろう。なおも一人語りで話しかけられるところによると、このご老女(八十代)は長野から嫁いできたが、いまだに大月より長野が恋しいとのこと。
人生の切れ端を乗せて、バスは「猿橋」へ向かう。さすが天下の奇橋は外国人も多く観光客を集めていたが、名曲「襟裳岬」になぞらえれば、大月の冬はなにもない冬、であった。

長さは約31メートル、幅3.3メートル、水面からの高さ約31メートル。
現在の橋は1984年復元され、国指定の名勝
タイトル、本文イラスト、写真=筆者
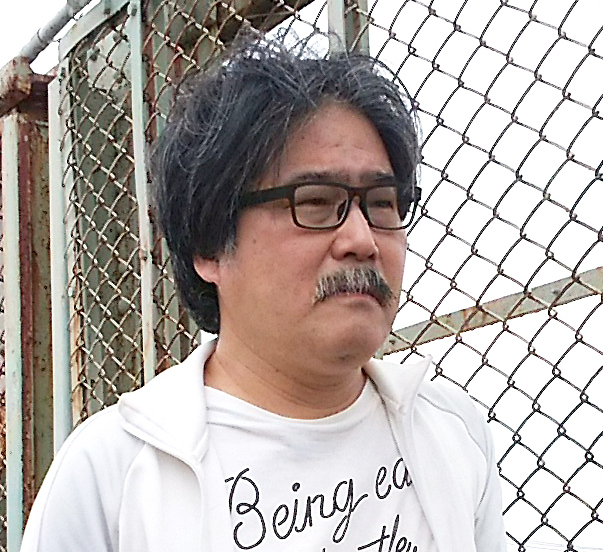
おかざき・たけし 1957年大阪生まれ。立命館大学卒業後、高校の国語教師、出版社勤務を経てフリーライターに。「神保町ライター」の異名を持つ。近著に『憧れの住む東京へ』(本の雑誌社、2023年)、『古本大全』(ちくま文庫、2024年)、『ふくらむ読書』(春陽堂書店、2024年)などがある。