第6回 「光景」を呼び覚ます言葉
転勤のために、栃木県宇都宮市に住むことになった。住まいとして選んだのは「宇都宮市ゆいの杜」という地区にあるアパートだった。
ゆいの杜地区のすぐそばには、「宇都宮市清原」という地区がある。車を走らせると、五分もたたないうちに清原地区に入る。配属された事務所は、清原地区から来ている人ばかりで、ゆいの杜には転勤してきた者ばかりが住んでいた。
自己紹介で「ゆいの杜に住んでいる」と話すと、清原地区の人は、みな口を揃えてこう言った。
「ゆいの杜は、もともと『原生林』みたいな場所だった。そこにぽつんと、ラーメン屋さんがあって、そこだけ行列していた」
ラーメン屋さんの場所を尋ねると、そこにはもう新しいアパートが建って、店は跡形もないらしい。ゆいの杜は、前は清原地区の一部だったのかと尋ねると、
「さあ、とにかく『原生林』だった」
と答えるのだった。
私はアパートの二階に住んでいた。暗くなってから帰宅すると、こうもりくらい大きな蛾が、外廊下の照明電球に体を打ちつけている。幸い、私が住んでいる部屋の前にある照明は、入居した時から電気が点かないから、まわりに蛾は飛んでいない。それでも、すり抜けるようにして家の中に入ったら、パラソルチョコに似た形状の、蛾とガガンボを合体させたような、大きく細身の虫が、玄関で私を待ち構えていた。もともと、埼玉県の田舎町で生まれ育ったので、昆虫についての見識は広い方だと考えていたが、この虫は、本当に今まで見たことがない。住宅街にいる虫ではない。ジャングルにいそうな虫だと思った。
靴箱の上に常備している殺虫剤を噴射したところ、この虫が、まるで傘を広げるように飛び上がり、いきなり数メートルも移動した。私は思わず悲鳴をあげた。なんとか退治することはできたが、その日は布団に入って電気を消してからも、その虫の輪郭が目から離れなかった。「もともと『原生林』みたいな場所だった」という、地元の人たちの言葉が、ふと蘇った。まるでジャングルにいそうな虫だと思ったが、本当に、元々はジャングルにすんでいた虫だったのだろう。あの虫は、この場所にかつてあった大きな木にとまるような気持ちで、私の部屋の壁に張り付いていたのかもしれない。いま自分が寝ている部屋の下に、元々は巨大な森の根があり、多くの動植物のねぐらをつぶして自分がいるのだと思うと、不思議な気持ちがして、居心地の悪さのようなものを感じた。土地を塗り替えてしまったのだ。
それからしばらく、体の中央がバネのように五メートルくらい伸びて跳び回る虫から逃げるという夢を見続けた。当時私が書いた詩の中にも、何度かこの虫が登場する。そのためか、透明な翅にあった斑点模様まで、今でも生々しくこの虫を記憶から呼び起こすことができる。
齋藤恵美子さんの詩のタイトル「雪塚」は、不思議な印象を残す言葉だ。
一里塚、庚申塚、首塚、耳塚、包丁塚、梅若丸の塚……。「塚」を名にもつ場所は各地にある。「塚」には、土を盛り上げた目印、または墓という意味がある。
雪は、音もなく痕跡もなく消えていくものだ。「雪塚」は、雪のように消えていったものたちを悼む場所を想起させ、同時に、その場所もやがては雪のように消滅していくことを暗示しているようでもある。
一連目の、「生まれた家の跡」にたつ「霜柱」。家の柱は失われ、いまは「霜柱」がたっている。幼い頃、すがりつき、身をもたせ、背丈の傷を残した柱は消滅し、今は、その柱の名残とも読める「霜柱」を踏み砕いている。人は、家の中で育つ。そう考えると、家はまるで人の母のようでもある。家の産道を通り抜けた一人の人間が、家の最期に向き合い、すがる柱を失いながらも、一人で歩き出す。それはまさに、「一つの生誕」(三連目)なのではないか。
この詩は、文脈が少しずつずれていく。それが階段状になって、語り手自身の非常に個人的な記憶から、人間自身が抱える原始的な情景へと広がっていく感じがある。
作品中では、数字の「一」が繰り返し用いられている。 これは「雪塚」に土を寄せあげて、その上に挿した杭の形状であり、墓石であり、霜柱であり、家の柱であり、背骨であり、これまでの「一日」「一日」を支えてきた柱であり、そしてこの杭が永久に倒れないことを祈る信仰を表しているようでもある。
そして繰り返されてきた「一」という数字は、最終連で「ひとつ」という言葉に姿を変えている。失われた景色、いなくなった人、もう二度と起こり得ない出来事を、言葉はいつも生々しく甦らせる。
光景を呼び覚ます言葉は、「雪塚」につながる唯一の鍵となるのだ。
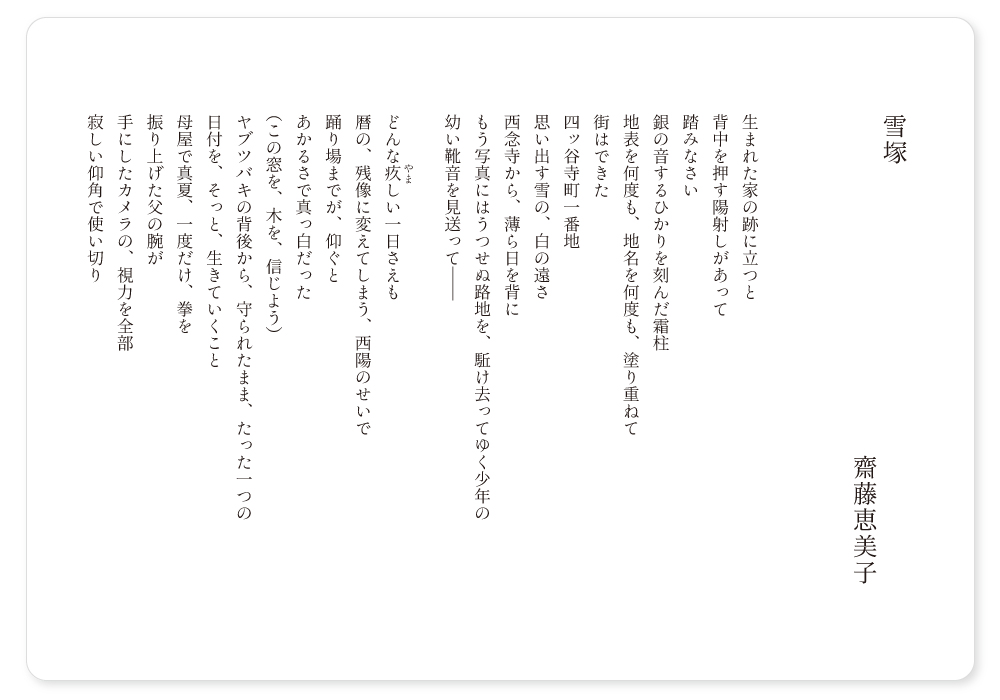
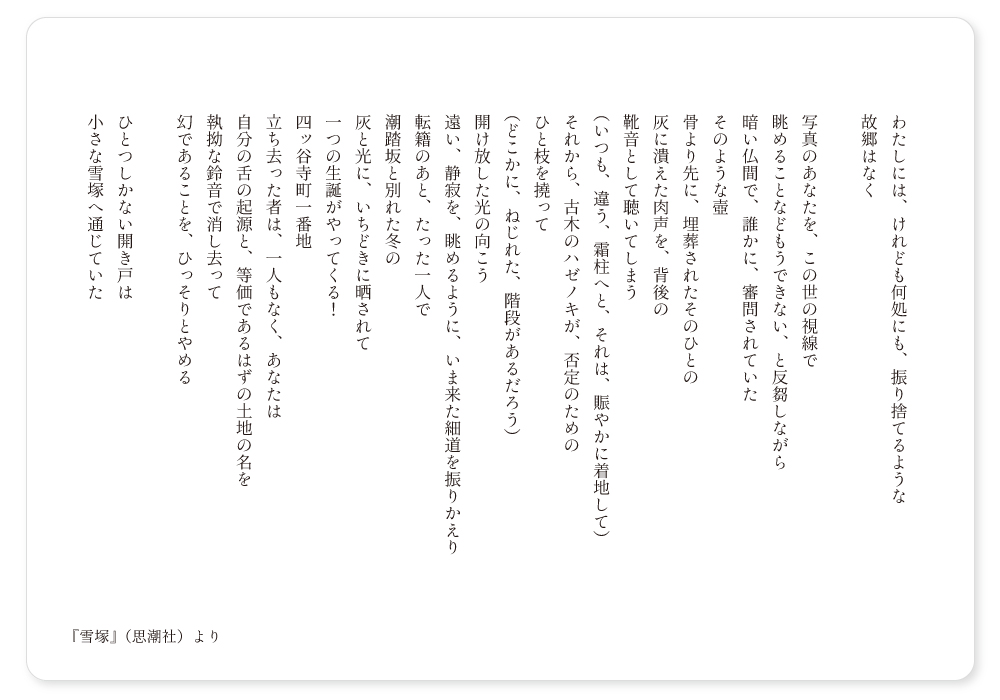
雪塚 齋藤恵美子
生まれた家の跡に立つと
背中を押す陽射しがあって
踏みなさい
銀の音するひかりを刻んだ霜柱
地表を何度も、地名を何度も、塗り重ねて
街はできた
四ッ谷寺町一番地
思い出す雪の、白の遠さ
西念寺から、薄ら日を背に
もう写真にはうつせぬ路地を、駈け去ってゆく少年の
幼い靴音を見送って――
どんな疚[やま]しい一日さえも
暦の、残像に変えてしまう、西陽のせいで
踊り場までが、仰ぐと
あかるさで真っ白だった
(この窓を、木を、信じよう)
ヤブツバキの背後から、守られたまま、たった一つの
日付を、そっと、生きていくこと
母屋で真夏、一度だけ、拳を
振り上げた父の腕が
手にしたカメラの、視力を全部
寂しい仰角で使い切り
わたしには、けれども何処にも、振り捨てるような
故郷はなく
写真のあなたを、この世の視線で
眺めることなどもうできない、と反芻しながら
暗い仏間で、誰かに、審問されていた
そのような壺
骨より先に、埋葬されたそのひとの
灰に潰えた肉声を、背後の
靴音として聴いてしまう
(いつも、違う、霜柱へと、それは、賑やかに着地して)
それから、古木のハゼノキが、否定のための
ひと枝を撓って
(どこかに、ねじれた、階段があるだろう)
開け放した光の向こう
遠い、静寂を、眺めるように、いま来た細道を振りかえり
転籍のあと、たった一人で
潮踏坂と別れた冬の
灰と光に、いちどきに晒されて
一つの生誕がやってくる!
四ッ谷寺町一番地
立ち去った者は、一人もなく、あなたは
自分の舌の起源と、等価であるはずの土地の名を
執拗な鈴音で消し去って
幻であることを、ひっそりとやめる
ひとつしかない開き戸は
小さな雪塚へ通じていた
『雪塚』(思潮社)より

1990年埼玉県生まれ。詩人。第五十四回現代詩手帖賞受賞。『狸の匣』(思潮社)で第二十三回中原中也賞、『雨をよぶ灯台』(思潮社)で第二十八回萩原朔太郎賞受賞。









