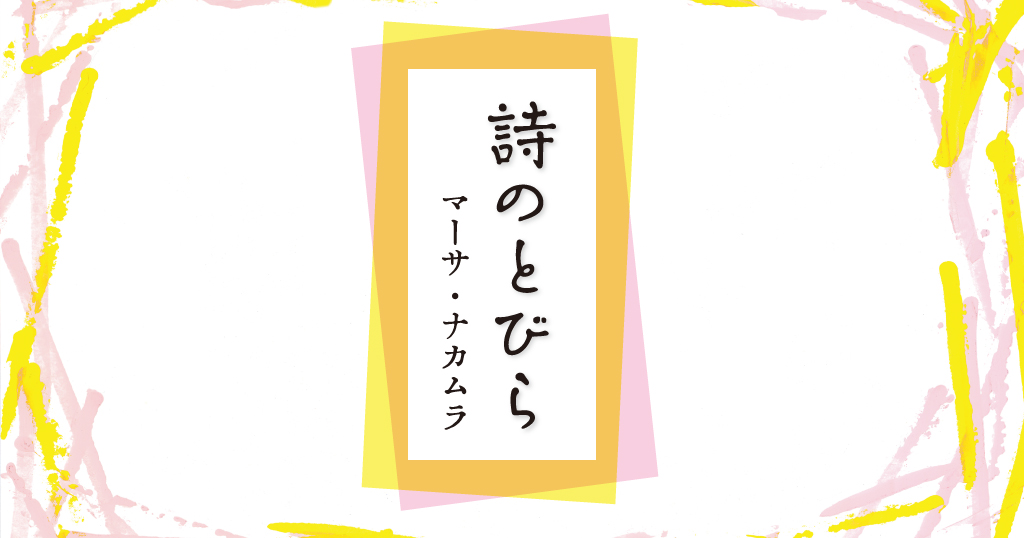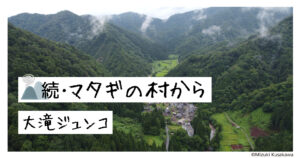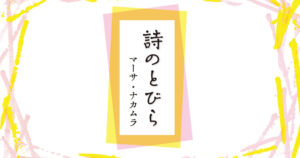第7回 子どもは「宇宙人」なのか
近所にある図書館には、閲覧席とは別に、読み聞かせコーナーがある。なだらかな小上がりになっていて、靴を脱いでマットの上に直に座ることができる。ガラスの引き戸を閉めれば、そこで声を出して本を読んでもいい。円形のその空間には、絵本から出てきた動物たちが食事会でもするように、子ども用の低いベンチが丸く並べられている。
絵本を見ているというよりは、絵本と自分の間に浮かぶ宙を眺めているような赤ん坊に、絵本の言葉を読み上げる母親。忍者のように、低いベンチの上を飛び跳ねていく小学生。母親が読み上げている絵本の結末を待たずに、新しい絵本を求めて書棚に走っていく幼児など、昼下がりになると、そのコーナーには小さな子どもたちが集まっている。
ある日、子どもたちが真面目な顔つきで、読み聞かせコーナーの前に設置された戸付きの荷物棚の中に、何かを押し込んでいるのを見た。「他の誰にも借りられないようにしよう」という声。みんなで頷いている。そっと覗きこむと、絵本『よるのびょういん』(谷川俊太郎作/福音館書店)が暗い棚の奥に隠されていた。
『よるのびょういん』は、主人公の少年が深夜に腹痛を訴えて、母親の通報のもと、救急車に乗るところから始まる。総合病院に送られた後、盲腸が判明し、そのまま緊急手術を受けることになる。可愛らしい童画ではなく、すべて白黒写真でつづられる。そのため、ドキュメンタリーに近い味わいがある。
二〇二三年九月に谷川俊太郎さんにお会いしたとき、この図書館で見た子どもたちの様子を話した上で、私は谷川さんに「子どもとは何か」と漠然と問いかけた。
逆に「あなたはどう思っているの?」と問い返されて、私は「宇宙人」と即答した。谷川さんは、僕はそこまで外的なものとしてとらえてはいない、と呟いてからこう答えられた。
「もうひとりの自分だと思っている」
「子ども」という存在に対する私の視点は、この時に確かに反転したのだった。
花氷[はなか]は昨年四月に、現代詩手帖賞を受賞したばかりの詩人である。
十一月に刊行された『オ・ラパン・アジルの夜』(思潮社)は、石川啄木『一握の砂』を彷彿とさせる詩集だ。「はたらけどはたらけど猶わが生活[くらし]楽にならざりぢつと手を見る」とうたった、石川啄木の生活苦を感じたという意味ではない。『オ・ラパン・アジルの夜』に収録された詩篇は、筆者自身の強い実感のもと生まれた詩だと感じたからである。
特に心惹かれたのは、「ちいさな渚」(ページ下に全文掲載)という作品だった。
「図書館の児童室で/返却された絵本を書棚に戻していると/ときどき〈ちいさな渚〉たちがやってくる/ずざざざ―――。/お客さま、走ると危ないのでご遠慮ください/うん、と、/ひとつうなずき、/また、ずざざざ―――と、駆けていく」
詩の語り手は図書館の司書をしており、〈ちいさな渚〉は、子どもを表しているようだ。「ずざざざ―――」という効果音は、図書館の床を駆け抜けていく子どもの足音であり、打ち寄せてきた渚が、また海へと帰っていく波音でもある。
司書から注意されて頷いたにもかかわらず、〈ちいさな渚〉たちはなおも駆け出していく。いたずらと観察。脈絡のない会話。図書館という非日常に置かれた子どもたちは、まるでシャーレの上にのせられた生物のように、その立ち居振る舞いが常以上に際立つようだ。
この作品が面白いのは、語り手自身が、おそらく、子どもという存在を「得意」とは感じていないであろうことがじわじわと伝わってくる点である。〈ちいさな渚〉–––近くて遠い〈子ども〉という存在を、こわごわと観察している。おそらく彼も、子どもを「宇宙人」としてとらえている。子どもは「子ども」という生物ではなく、人間のある一時期に過ぎないが、彼にとって「子ども」時代は、二度と戻れない、触れることすらできない、宇宙のように隔絶された場所なのだろう。渚の向こう側には、海がある。その海に、宇宙を見ている。いたずらをした子どもが、「鬼海星[おにひとで]から逃げるように/ぱちぱち、と何処かの星々へ駆けていった」という詩行からも、子どもに宇宙の遠さを見ている点が伝わってくる。
それがある日、海に足を浸す瞬間が訪れる。
卒園を前にした女の子がつぶやいた一言をきっかけに、子どもと自分を隔絶していた氷の壁が崩れ、自分もまた、海から無心に駆けてきた一人の〈ちいさな渚〉であったことを思い出す。
「いつだって波打ち際にいる/どちらが〈向こう〉で/どちらが〈こちら〉かもわからなかった」
〈ちいさな渚〉に足下をさらわれて、宇宙の彼方にあると思っていた大きな海が、まだ自分の足下に続いていたことに気がつくのだ。
この作品からは「何気ない日常」という言葉が思い浮かぶ。「何気ない日常」とは、言い換えれば、意図も期待もなく生きる普段の生活のことである。常に目的意識と向上心をもって生きるべきだと説くメッセージが巷に溢れ、私自身、そうした啓発本を焦ったように読むことがあるが、生の根源に触れる奇跡のような出来事には、不思議と、何気ない日常の中で出会うものだ。
奇跡とは知るものではなく、気がつくものなのかもしれない。「ちいさな渚」という作品は、ただ何気なく生きている日々、それ自体が奇跡であることを気づかせる。
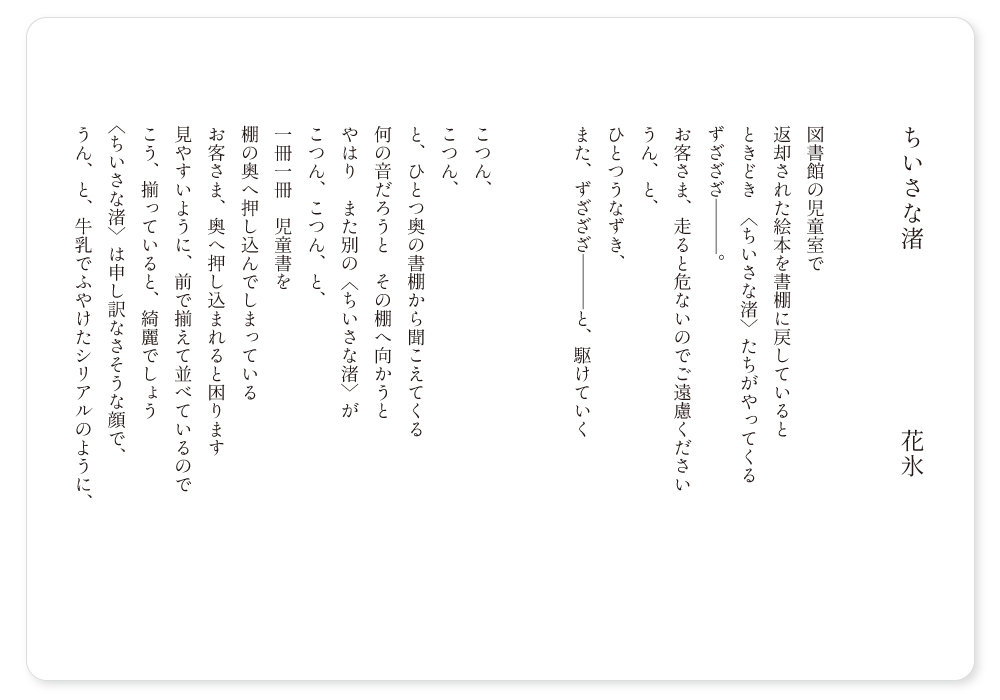
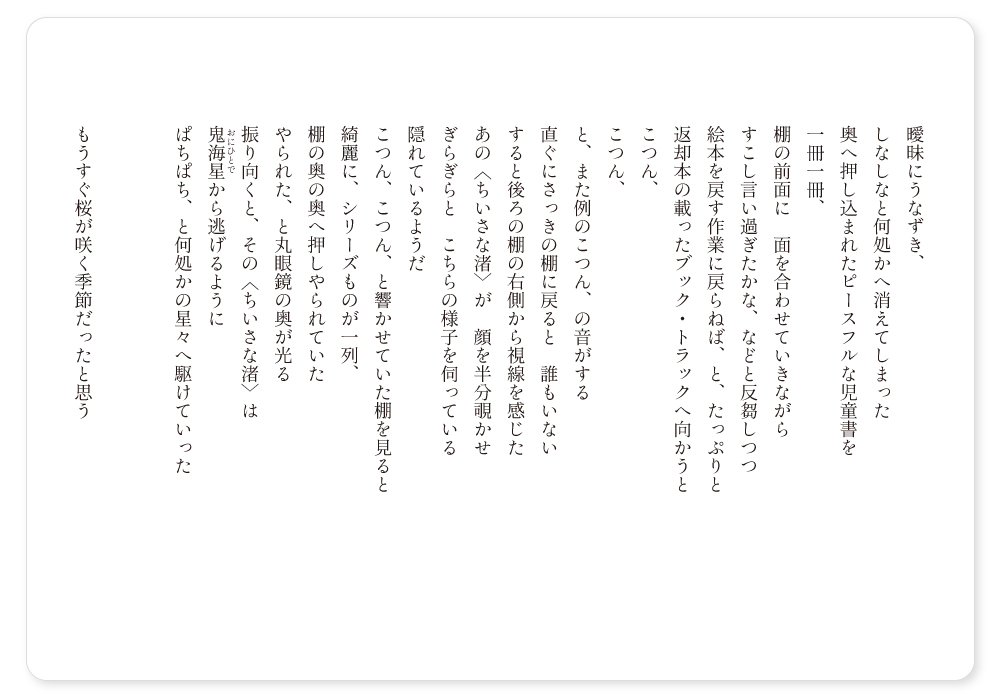
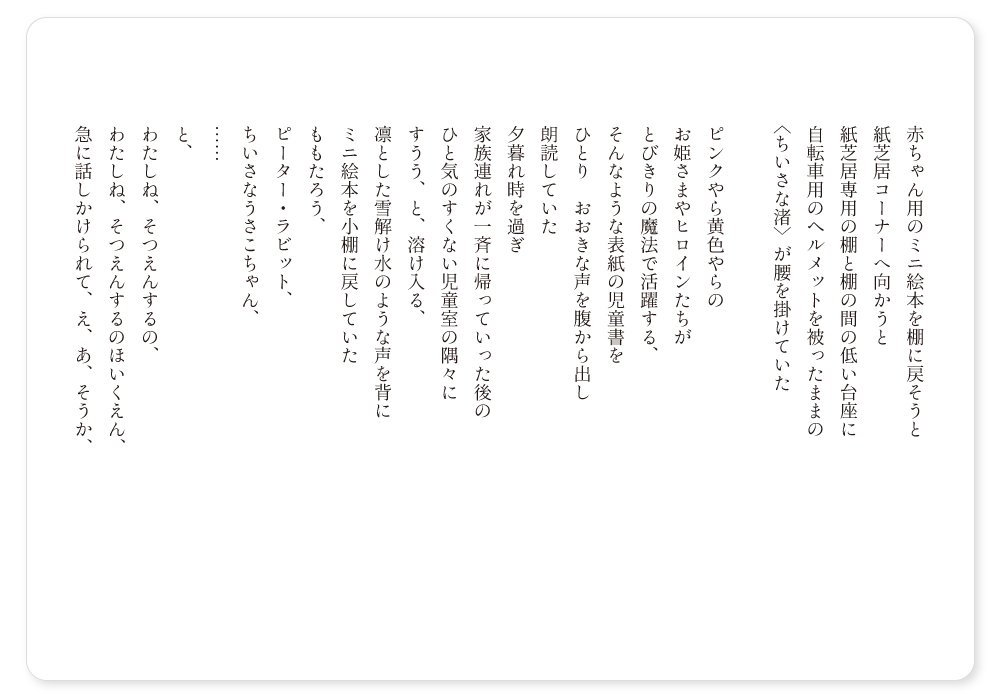
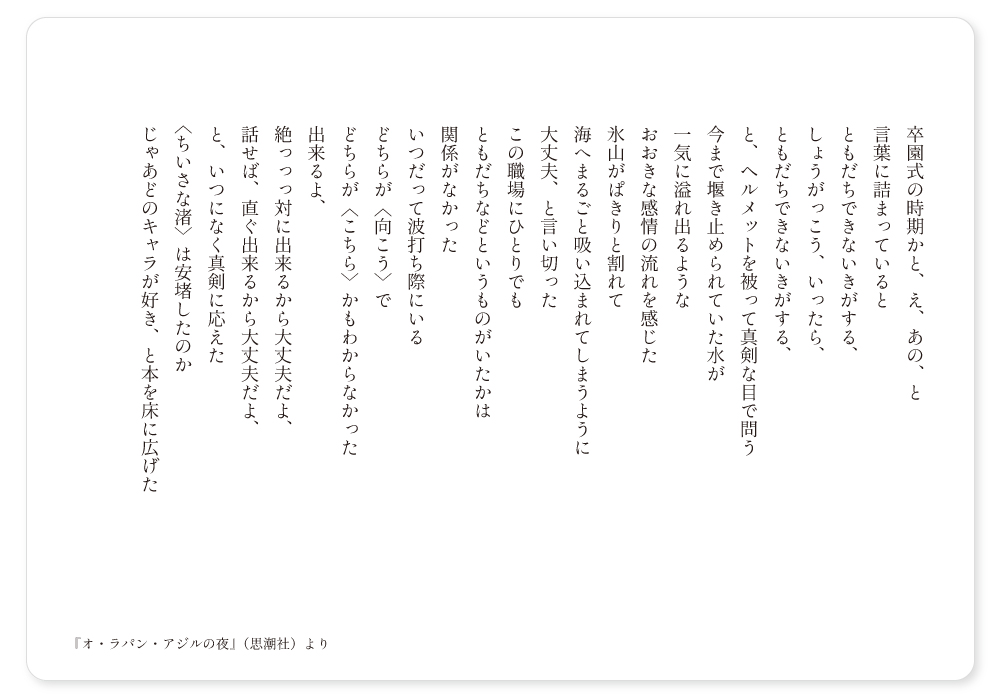
ちいさな渚 花氷
図書館の児童室で
返却された絵本を書棚に戻していると
ときどき 〈ちいさな渚〉たちがやってくる
ずざざざ―――。
お客さま、走ると危ないのでご遠慮ください
うん、と、
ひとつうなずき、
また、ずざざざ―――と、駆けていく
こつん、
こつん、
と、ひとつ奥の書棚から聞こえてくる
何の音だろうと その棚へ向かうと
やはり また別の〈ちいさな渚〉が
こつん、こつん、と、
一冊一冊 児童書を
棚の奥へ押し込んでしまっている
お客さま、奥へ押し込まれると困ります
見やすいように、前で揃えて並べているので
こう、揃っていると、綺麗でしょう
〈ちいさな渚〉は申し訳なさそうな顔で、
うん、と、牛乳でふやけたシリアルのように、
曖昧にうなずき、
しなしなと何処かへ消えてしまった
奥へ押し込まれたピースフルな児童書を
一冊一冊、
棚の前面に 面を合わせていきながら
すこし言い過ぎたかな、などと反芻しつつ
絵本を戻す作業に戻らねば、と、たっぷりと
返却本の載ったブック・トラックへ向かうと
こつん、
こつん、
と、また例のこつん、の音がする
直ぐにさっきの棚に戻ると 誰もいない
すると後ろの棚の右側から視線を感じた
あの〈ちいさな渚〉が 顔を半分覗かせ
ぎらぎらと こちらの様子を伺っている
隠れているようだ
こつん、こつん、と響かせていた棚を見ると
綺麗に、シリーズものが一列、
棚の奥の奥へ押しやられていた
やられた、と丸眼鏡の奥が光る
振り向くと、その〈ちいさな渚〉は
鬼海星[おにひとで]から逃げるように
ぱちぱち、と何処かの星々へ駆けていった
もうすぐ桜が咲く季節だったと思う
赤ちゃん用のミニ絵本を棚に戻そうと
紙芝居コーナーへ向かうと
紙芝居専用の棚と棚の間の低い台座に
自転車用のヘルメットを被ったままの
〈ちいさな渚〉が腰を掛けていた
ピンクやら黄色やらの
お姫さまやヒロインたちが
とびきりの魔法で活躍する、
そんなような表紙の児童書を
ひとり おおきな声を腹から出し
朗読していた
夕暮れ時を過ぎ
家族連れが一斉に帰っていった後の
ひと気のすくない児童室の隅々に
すうう、と、溶け入る、
凛とした雪解け水のような声を背に
ミニ絵本を小棚に戻していた
ももたろう、
ピーター・ラビット、
ちいさなうさこちゃん、
……
と、
わたしね、そつえんするの、
わたしね、そつえんするのほいくえん、
急に話しかけられて、え、あ、そうか、
卒園式の時期かと、え、あの、と
言葉に詰まっていると
ともだちできないきがする、
しょうがっこう、いったら、
ともだちできないきがする、
と、ヘルメットを被って真剣な目で問う
今まで堰き止められていた水が
一気に溢れ出るような
おおきな感情の流れを感じた
氷山がぱきりと割れて
海へまるごと吸い込まれてしまうように
大丈夫、と言い切った
この職場にひとりでも
ともだちなどというものがいたかは
関係がなかった
いつだって波打ち際にいる
どちらが〈向こう〉で
どちらが〈こちら〉かもわからなかった
出来るよ、
絶っっっ対に出来るから大丈夫だよ、
話せば、直ぐ出来るから大丈夫だよ、
と、いつになく真剣に応えた
〈ちいさな渚〉は安堵したのか
じゃあどのキャラが好き、と本を床に広げた
『オ・ラパン・アジルの夜』(思潮社)より
「投稿のひろば」はこちら

1990年埼玉県生まれ。詩人。第五十四回現代詩手帖賞受賞。『狸の匣』(思潮社)で第二十三回中原中也賞、『雨をよぶ灯台』(思潮社)で第二十八回萩原朔太郎賞受賞。