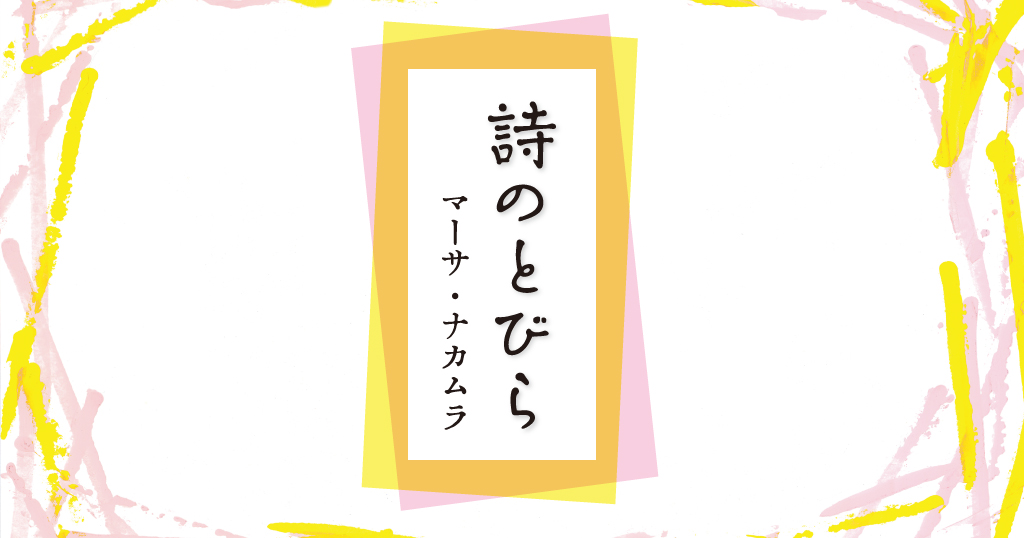第8回 「本当の私」をさがして
「詩の書き方を教えてほしい」という、ワークショップの依頼を受けることがある。
そんな時は、青色と茶色の絵の具、画用紙二枚、水を入れた紙コップ、紙皿、絵筆を準備する。
まず紙皿に、青色と茶色の絵の具を出す。絵筆に水を十分に含ませてから、二色の絵の具をぐるぐると混ぜていく。そして、絵の具をすくい、画用紙に思いきり塗りつける。最後にもう一枚の画用紙を上からのせて引き剥がすと、無作為の、不思議な紋様が浮かび上がる。
その紋様が、何に見えるか。「誰が(何が)、どこで、いつ、何をしているのか。その理由」。そこに「私」が登場していない場合には、「私はその時、どこで、何をしているのか」をプリントに記入し、作文を書いてもらう。それを詩の形で語り直す、ということをしている。
この方法は、わたしが中学生の時に、美術の先生が教えてくれた、自画像の描き方がもとになっている。
自画像を描く、というテーマが発表された時、しばらくの間、美術室で小さな鏡とにらめっこすることになるのだなと思っていたら、一時限目は座学だった。そして、「私はいま、どこで、何をしているのか」という短い作文を書くように指示された。
自画像を描くのに、作文を書くという工程に疑問を持ちながらも、言われた通り、配られたプリントに記載された質問に向き合った。
「質問一 あなたは今、どこにいますか?」
わたしは中等部校舎一階三年六組の教室の、後方下手[しもて]側の席に座っていた。
けれどもわたしはわたしに、(「私」は、今、どこにいる?)と問いかけてみた。
昼間の人通りの少ない、古びた商店街を、一人で歩いている私を、上から見た気がした。
「昼間の、人通りの少ない商店街」と、プリントに書き入れる。
「質問二 あなたはそこで、何をしていますか?」
わたし自身は、冬服を着たクラスメイトたちの黒い背中と、目の前にある白いプリントを交互に眺めている。
商店街を歩いている私は、とある焼き鳥屋に入るのだと思った。
これら二つの答えをもとに、作文を書いた。
私はいま、人通りの少ない、昼間の商店街をひとりで歩いている。甘い香りに誘われて、焼き鳥屋の引き戸を開く。厨房にいた主人に声をかけると、四人がけのテーブルに通される。
店内で、客は私ひとりだけである。それなのに、店内にはもうもうと鳥を焼く煙が充満していて、妙な活気がある。店主は、私の注文を受けて、焼き鳥を焼き始める。
熱いおしぼりに触れてから、木目調のテーブルに手を置くと、ぬるぬるとしている。
そこまで書いて、授業終了の鐘が鳴り響いた。
聞き慣れた鐘の音なのに、いつもより妙に大きく、心臓が縮むほど、ギョッとしたことを覚えている。
わたしはその時、いわゆる「ゾーン」に入っていたのだと思う。
休み時間になって、机と椅子の脚が引きずられる音、クラスメイトたちのざわめきで騒がしくなった教室の中で、わたしは席も立たず、そのプリントを眺め続けていた。
どうして、教室で作文を書いていたのに、自分は今、古びた商店街を歩いていると思ったのか、不思議でならなかった。
当時中学生だったわたしは、埼玉県の、最寄駅もない田舎町で、中学校教諭をしている両親たちと暮らしていた。
どこか懐かしい風景だと思ったが、客足が多くなるであろう昼時に、ひとけの全くない商店街など見た覚えもないし、どこかに存在するとも思えない。それに、焼き鳥屋という類の店に入った経験もなかった。
おそらくそれは、この世には存在しない、わたしだけを待っていた商店街だったのだろう。毎朝七時に、送迎を受けながら中学校に登校するわたしと、不思議な商店街で彷徨う私、どちらが「本当の私」なのか、考え続けた。
いま振り返ると、これがわたしにとっての、詩を書く行為の原体験だった。
詩を書く行為は、身体をおいて彷徨う「本当の私」を、探しに出かける遊びでもあるのではないか。
私の名前は長崎の有明海に由来する
この辺は長崎という地名だから
夕焼けの時だけ長崎がみえるような気がしていた
野崎有以「ネオン」(ページ下に全文掲載)
野崎有以の書く詩の語り手の多くは、長崎県が故郷であることをほのめかす。
野崎有以は、『現代詩手帖』二〇一七年七月号での対談の中で、自身は長崎県出身ではないことを明らかにしている。
短歌とは異なり、現代詩に私性[わたくしせい]の制約はない。しかし、野崎氏は単に、そうした現代詩の特色を利用したのではない。彼女の本当の部分、実在する彼女の身体ではなく、言うなれば無意識の「私」、彼女の心の暗がりにいた「本当の私」は、長崎県から東京にやってきたばかりの少女なのだろうと思う。
東京生まれ、東京育ちのわたしの友人が、「自分には故郷がない感じがある」と言ったことがあった。わたし自身も、埼玉県生まれでありながら、大好きな祖母が暮らしていた宮城県こそが、自分の本当の故郷だと感じることがある。
噓偽りのない、もう一人の「本当の私」であるからこそ、彼女の詩の声は、切れば血が出るように生々しく、熱く感じる。
ボクサーは詩人で 詩人はボクサーだ
リングを去っても 詩が書けなくなっても たたかいつづける運命なのだ
私は自分の過去とかあるいはもっとこわいものとたたかっている
「ネオン」のこの言葉に、わたしは何度救われたことかわからない。
かつて、NHKで放送された『詩のボクシング』という伝説的な番組があった。先日、谷川俊太郎さん追悼の一環として、谷川さんとねじめ正一さんが実際にリング上にあがって、自作詩を朗読しあいながら互いを圧倒し、最後は審判によって勝敗をつけられた場面が放送されていた。この企画が奇抜で面白いのは、本来、詩そのものに勝ち負けはないからである。
わたしは職業として「詩人」とは名乗っていない。意志の表明として「詩人」だと名乗っている。すると、わたしの名乗りを聞いた人は必ず、わたしの経済状況を心配する。わたしは詩でお金を稼ぐことができなくても、詩が書けなくなったとしても、「詩人」と名乗り続けるに違いないと考えている。
誰かと競争したり、相手を打ち負かしたり、判定勝ちで社会的信用を得るために、ペンを握り続けるのではない。ただ、生き続けるという意志と、ペンを握り続けるという意志が、ほとんど同義なのだ。ノックアウトされて、ペンをなくしたまま生きることなど考えられない。だからこそ、死にものぐるいになる。
詩の教室には、詩が書けなくなったという人も訪れる。
詩の書き方を教えてほしいという依頼をはじめて受けた時、わたしは少なからずうろたえた。わたし自身も、どうやって詩を書けばいいのかわからないと思っていたからだ。
すでに教室を開いた経験のある人に、どうやって詩の書き方を教えているのか、聞いてみたところ、本当に十人十色だった。つまり、詩の書き方というものはないのだ。
野崎有以は現代詩手帖賞、中原中也賞をたて続けに受賞した詩人であるが、そんな彼女でさえ「詩が書けなくなっても」とつづっているのだ。
「ネオン」の詩が一番好きだと言う人に、わたしは何度か出会ったことがある。わたし自身、詩の教室をやる際に、必ず紹介する作品でもある。詩の書き方というものがあるなら、「ネオン」という作品が、詩を書く多くの人の胸を打つことはなかっただろう。
詩の書き方がないなら、詩を書ける人もまた、存在しないのかもしれない。無我夢中で生きて、ふと振り返ったたたかいの跡が、詩の形をなしているだけなのかもしれない。
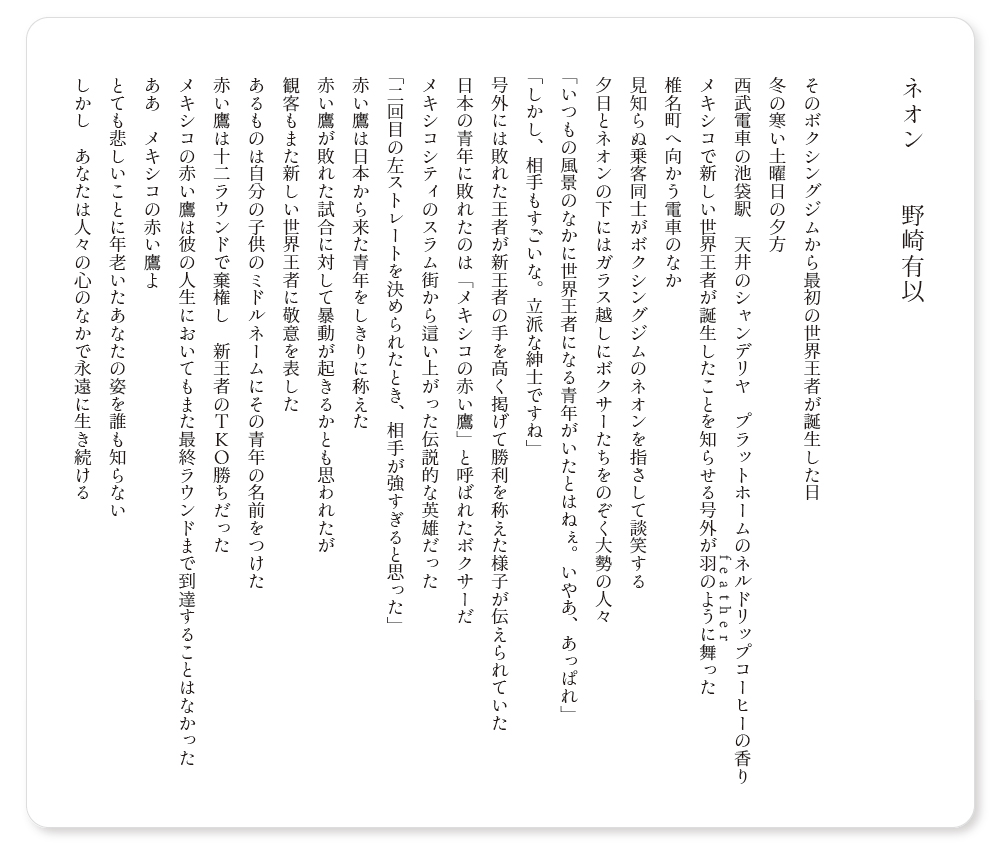
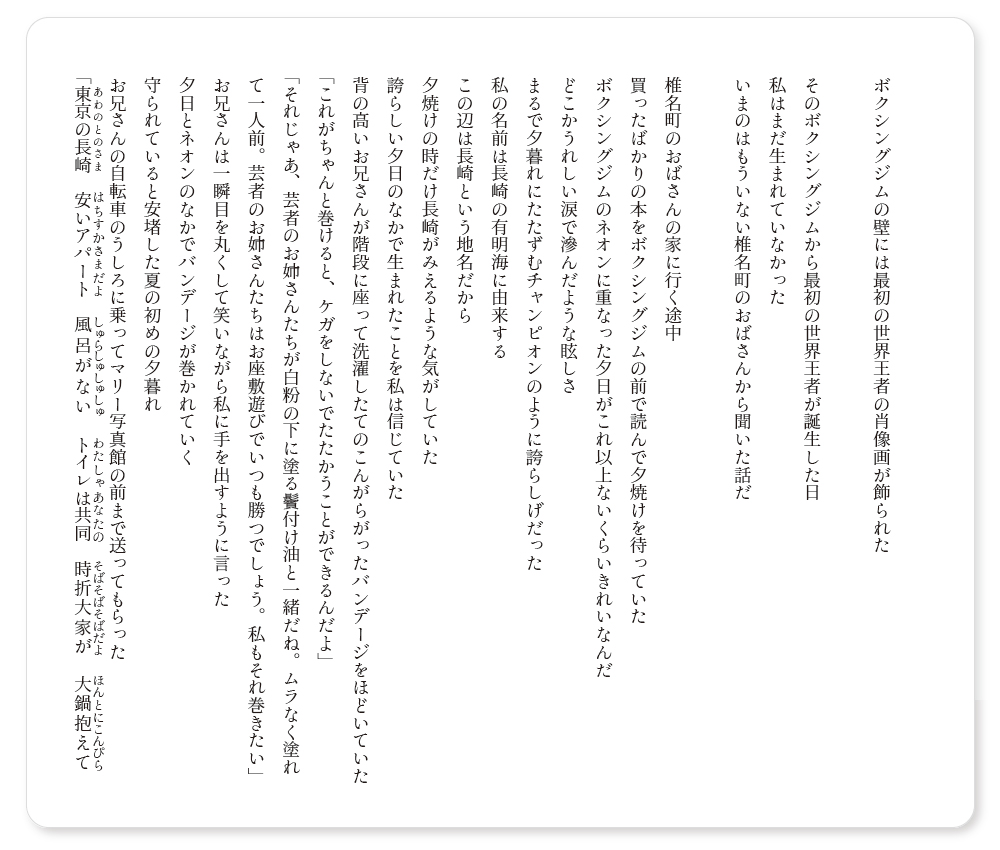
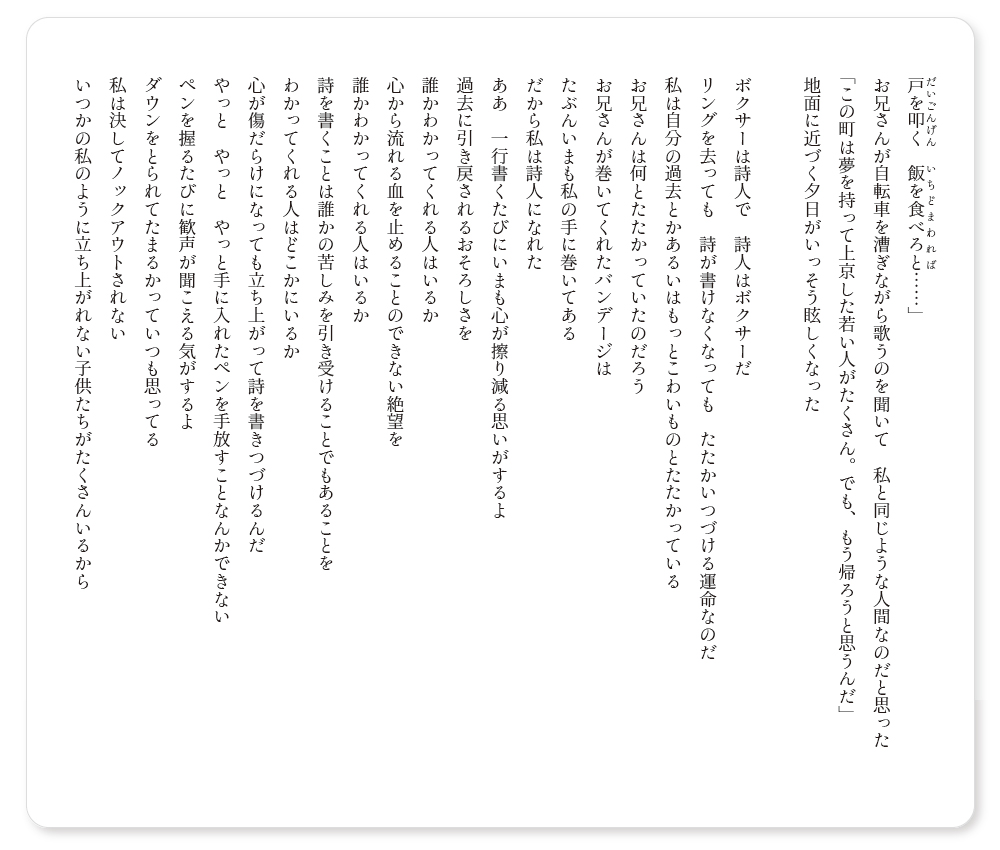
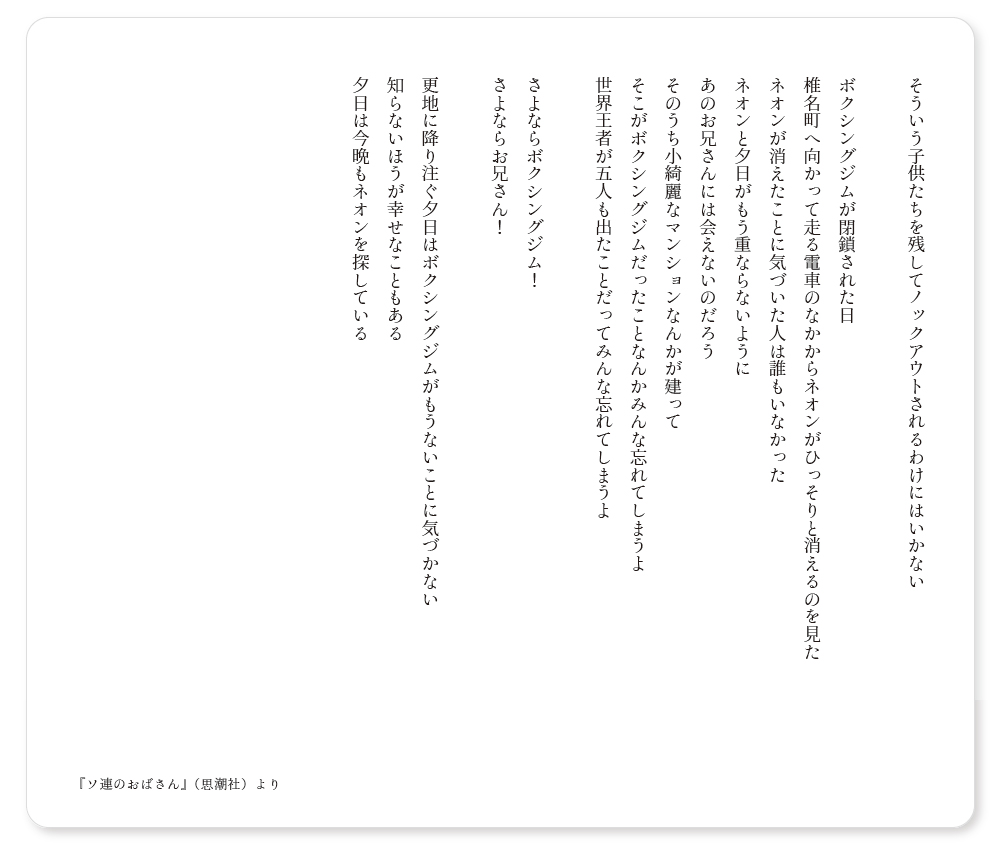
ネオン 野崎有以
そのボクシングジムから最初の世界王者が誕生した日
冬の寒い土曜日の夕方
西武電車の池袋駅 天井のシャンデリヤ プラットホームのネルドリップコーヒーの香り
メキシコで新しい世界王者が誕生したことを知らせる号外が羽のように舞った
椎名町へ向かう電車のなか
見知らぬ乗客同士がボクシングジムのネオンを指さして談笑する
夕日とネオンの下にはガラス越しにボクサーたちをのぞく大勢の人々
「いつもの風景のなかに世界王者になる青年がいたとはねぇ。いやあ、あっぱれ」
「しかし、相手もすごいな。立派な紳士ですね」
号外には敗れた王者が新王者の手を高く掲げて勝利を称えた様子が伝えられていた
日本の青年に敗れたのは「メキシコの赤い鷹」と呼ばれたボクサーだ
メキシコシティのスラム街から這い上がった伝説的な英雄だった
「二回目の左ストレートを決められたとき、相手が強すぎると思った」
赤い鷹は日本から来た青年をしきりに称えた
赤い鷹が敗れた試合に対して暴動が起きるかとも思われたが
観客もまた新しい世界王者に敬意を表した
あるものは自分の子供のミドルネームにその青年の名前をつけた
赤い鷹は十二ラウンドで棄権し 新王者のTKO勝ちだった
メキシコの赤い鷹は彼の人生においてもまた最終ラウンドまで到達することはなかった
ああ メキシコの赤い鷹よ
とても悲しいことに年老いたあなたの姿を誰も知らない
しかし あなたは人々の心のなかで永遠に生き続ける
ボクシングジムの壁には最初の世界王者の肖像画が飾られた
そのボクシングジムから最初の世界王者が誕生した日
私はまだ生まれていなかった
いまのはもういない椎名町のおばさんから聞いた話だ
椎名町のおばさんの家に行く途中
買ったばかりの本をボクシングジムの前で読んで夕焼けを待っていた
ボクシングジムのネオンに重なった夕日がこれ以上ないくらいきれいなんだ
どこかうれしい涙で滲んだような眩しさ
まるで夕暮れにたたずむチャンピオンのように誇らしげだった
私の名前は長崎の有明海に由来する
この辺は長崎という地名だから
夕焼けの時だけ長崎がみえるような気がしていた
誇らしい夕日のなかで生まれたことを私は信じていた
背の高いお兄さんが階段に座って洗濯したてのこんがらがったバンデージをほどいていた
「これがちゃんと巻けると、ケガをしないでたたかうことができるんだよ」
「それじゃあ、芸者のお姉さんたちが白粉の下に塗る鬢付け油と一緒だね。ムラなく塗れて一人前。芸者のお姉さんたちはお座敷遊びでいつも勝つでしょう。私もそれ巻きたい」
お兄さんは一瞬目を丸くして笑いながら私に手を出すように言った
夕日とネオンのなかでバンデージが巻かれていく
守られていると安堵した夏の初めの夕暮れ
お兄さんの自転車のうしろに乗ってマリー写真館の前まで送ってもらった
「東京の長崎 安いアパート 風呂がない トイレは共同 時折大家が 大鍋抱えて 戸を叩く 飯を食べろと……」
お兄さんが自転車を漕ぎながら歌うのを聞いて 私と同じような人間なのだと思った
「この町は夢を持って上京した若い人がたくさん。でも、もう帰ろうと思うんだ」
地面に近づく夕日がいっそう眩しくなった
ボクサーは詩人で 詩人はボクサーだ
リングを去っても 詩が書けなくなっても たたかいつづける運命なのだ
私は自分の過去とかあるいはもっとこわいものとたたかっている
お兄さんは何とたたかっていたのだろう
お兄さんが巻いてくれたバンデージは
たぶんいまも私の手に巻いてある
だから私は詩人になれた
ああ 一行書くたびにいまも心が擦り減る思いがするよ
過去に引き戻されるおそろしさを
誰かわかってくれる人はいるか
心から流れる血を止めることのできない絶望を
誰かわかってくれる人はいるか
詩を書くことは誰かの苦しみを引き受けることでもあることを
わかってくれる人はどこかにいるか
心が傷だらけになっても立ち上がって詩を書きつづけるんだ
やっと やっと やっと手に入れたペンを手放すことなんかできない
ペンを握るたびに歓声が聞こえる気がするよ
ダウンをとられてたまるかっていつも思ってる
私は決してノックアウトされない
いつかの私のように立ち上がれない子供たちがたくさんいるから
そういう子供たちを残してノックアウトされるわけにはいかない
ボクシングジムが閉鎖された日
椎名町へ向かって走る電車のなかからネオンがひっそりと消えるのを見た
ネオンが消えたことに気づいた人は誰もいなかった
ネオンと夕日がもう重ならないように
あのお兄さんには会えないのだろう
そのうち小綺麗なマンションなんかが建って
そこがボクシングジムだったことなんかみんな忘れてしまうよ
世界王者が五人も出たことだってみんな忘れてしまうよ
さよならボクシングジム!
さよならお兄さん!
更地に降り注ぐ夕日はボクシングジムがもうないことに気づかない
知らないほうが幸せなこともある
夕日は今晩もネオンを探している
「投稿の広場」はこちら

1990年埼玉県生まれ。詩人。第五十四回現代詩手帖賞受賞。『狸の匣』(思潮社)で第二十三回中原中也賞、『雨をよぶ灯台』(思潮社)で第二十八回萩原朔太郎賞受賞。