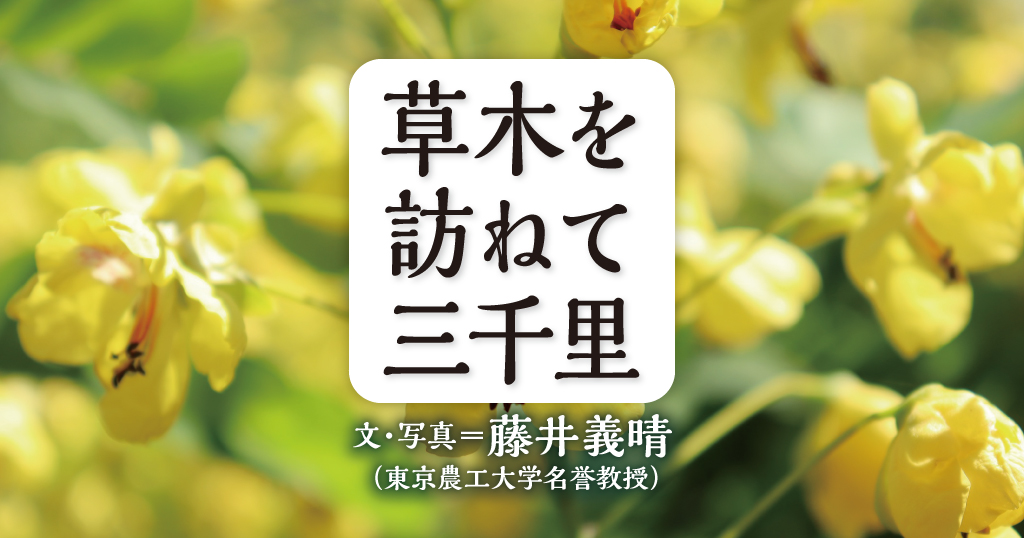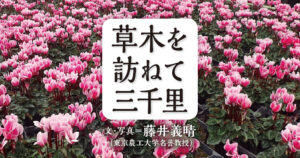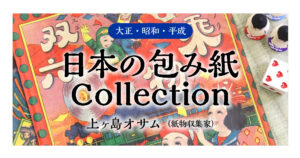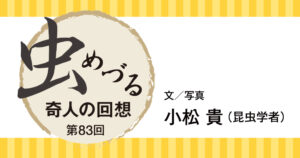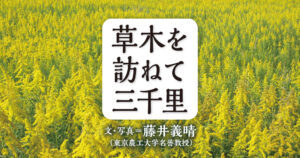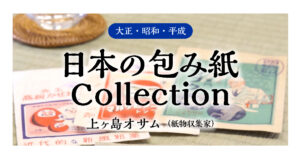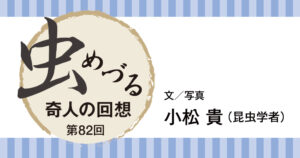第20回 ヘビの名がつく植物は美しい
2025年は巳年。ヘビは脱皮して成長するので、飛躍、金運上昇の象徴とも言われます。そこで今回はヘビにちなんだ植物を紹介しましょう。
まず、そのものずばり蛇瓜[ヘビウリ]。インド原産で東南アジアに多く、実がヘビにそっくりの形をしています。日本でも観賞用に栽培されますが、実はゴーヤーに似た味で、東南アジアでは食用にされています。


ヘビウリの親戚で、金運に関係するのが烏瓜[カラスウリ]。英語名がJapanese Snake Gourdで、日本のヘビウリと呼ばれます。秋から冬に散歩していると朱色の実が見つかります。種子を取り出して水で洗ってよく乾かすと、金の粒のように光る種子が取れます。財布に入れておくと金運が良くなるとされますが、最近は電子マネーを利用する人が多いようなので、スマホに種子の写真を入れておくとよいかもしれません。



蛇の寝茣蓙[ヘビノネゴザ]というヘンな名前の植物もあります。重金属汚染にめっぽう強く、体内に金を大量に貯める植物として知られています。山でこの植物の群落を見つけたら、こっそり教えてください。金鉱脈を発見できるかもしれません。

でも、よく似た犬蕨[イヌワラビ]は日本中至るところに生えているので、ぬか喜びは禁物です。

蛇結茨[ジャケツイバラ]もヘビにちなんだ名前です。古くから日本にあります。
菎莢[ぞうきょう]に延ひおほとれる屎葛[くそかづら]
絶ゆることなく宮仕へせむ高宮王[たかみやのおおきみ](『万葉集』巻十六・三八五五)
と歌われた菎莢はジャケツイバラとされます。ヘクソカズラがジャケツイバラに巻き付いている情景を詠んでいますが、昔はかっこいい植物と考えられていたようです。

蛇苺[ヘビイチゴ]もヘビがつく植物です。黄色い花は美しく、赤く熟した果実は美味しそうですが、甘味も酸味もないのでがっかりします。美味しくないのでヘビが食べるいちごと考えたのかもしれません。


蝮草[マムシグサ]は怖ろしい名前ですね。茎の模様がマムシに似ているためとされますが、全草に猛毒があり、調理しても食べられません。よく似た植物に浦島草[ウラシマソウ]があります。花の形はマムシグサそっくりですが、花から釣り糸のようなものが出ていて、小舟に乗った浦島太郎が釣りをしているようです。どちらも春に林の中を歩くと見つかります。触っただけでもかぶれるので鑑賞するだけにしておきましょう。


蛇の髭[ジャノヒゲ]もヘビに因んだ植物のようですが、ヘビには髭はありません。細い葉が、お能で老人の面である尉[じょう]に生えている細長いあごひげに似ているので、〝尉のひげ〟がジャノヒゲに転化したものとされます。リュウノヒゲという別名もあり、私はこのほうが好きです。根は麦門冬[ばくもんどう]という漢方薬になります。私たちの研究で、根には大量のサリチル酸が含まれており、他の雑草を抑制することが報告されています。
悲しみはいまもせつなしじやのひげの
紫の玉を見つつ思へば
という短歌があります。作者は木俣修。冬に目立つ瑠璃色に光る実(種子)は美しく、弾力に富んでおり、スーパーボールのようによく弾むので、遊びに使われました。
三十歳という若さでこの世を去った妻を偲んだ歌とのことです。



ふじい・よしはる 1955年兵庫県生まれ。博士(農学)。東京農工大学名誉教授。鯉渕学園農業栄養専門学校教授。2009年、植物のアレロパシー研究で文部科学大臣表彰科学技術賞受賞。『植物たちの静かな戦い』(化学同人)ほか著書多数。
バックナンバー