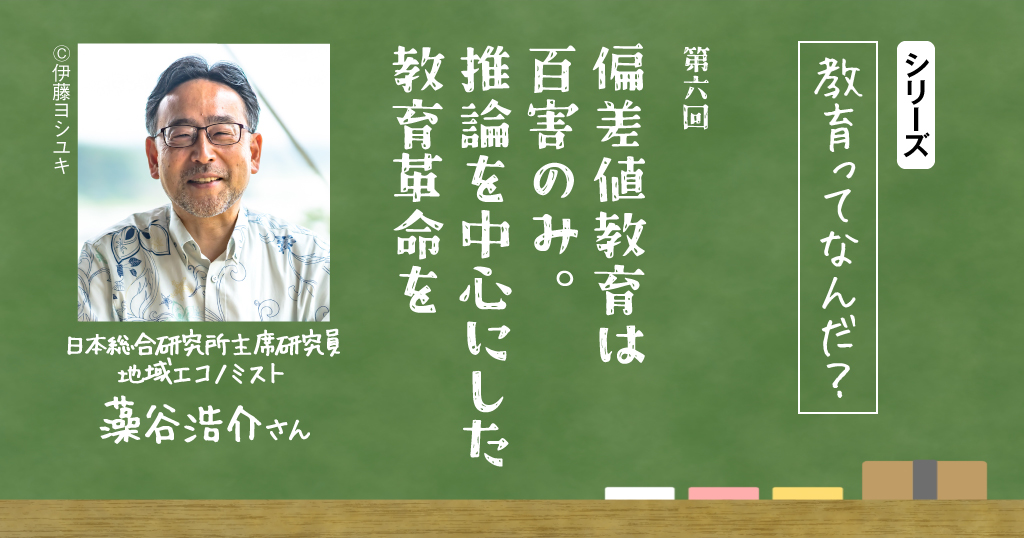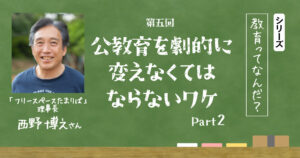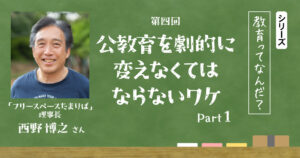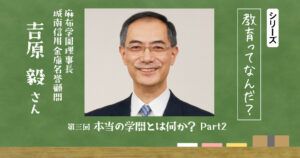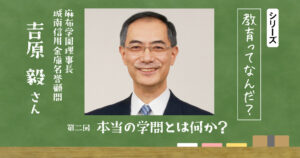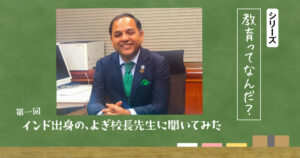「一流校合格者一挙掲載」的な見出し記事を見かける。街中の進学塾も外壁に「○○校合格者ウン百人!」と盛んに謳う。学歴の良し悪しだけが、人生の最重要課題だといわんばかりだ。しかもタチが悪いのが、多くの人たちがその風潮を後押ししていることだ。本当だろうか? 有名校に入るとシアワセになれるのか? 絶対、そんなことはない。偏差値・学歴重視社会には弊害しかないのに、なぜ教育は変わらないのか。さまざまな分野で鋭い指摘をし、多くの人に指針を与え続けてくれている藻谷浩介さんに話を聞いた。藻谷さんの言う「教育浄土真宗」の本意ってなんですか?
学歴と頭の良し悪しは無関係
――今の日本の教育について、藻谷さんはどんな実感をおもちですか?
私は学歴完全否定論者です。入試の成績や偏差値には、知るべき意味がないのです。
それどころか、「学歴エリートにすら、たまには頭のいい人がいる。いわんや学歴エリートではない人に、頭のいい人がいないはずがない」という意見なのですが、これを私は「教育浄土真宗」と自称しています(笑)。本家には申し訳ないのですが、親鸞聖人の悪人正機説「善人なほもて往生をとぐ。いはんや悪人をや」の言い方を借用しました。
「では藻谷さんは、頭の良し悪しを、偏差値や学歴ではなく何で判断しているのか?」と聞かれそうですね。実際のところ、記憶力に、意思伝達力に、美的感覚に運動神経、味覚や嗅覚、人の気持ちを推察する能力だとか、身体に触ることで健康状態を把握する能力だとか、人と協働する能力とか、「頭の良さ」は何十種類もあります。ですが、お受験教育が本来試そうとして失敗しているのは、「論理的に推論し、客観的に事実を認識する能力」でしょう。
事実認識力(=私のいう頭の良さ)は、話してみればわかりますし、一緒に何か仕事をすればもっとよくわかります。そしてその力と、偏差値はぜんぜん関係がありません。この状況は、飲食店の味の良し悪しと、店の前に並んだ客の列の長さやグルメ情報サイトなんかの星の数がまったく連動しないのに、よく似ていますね。
でも世の中の一定数の人は、実は味の良し悪しはよくわからない。自分では判断できないので、ネットの評価や列の長さを基準にしてしまう。同じように、頭の良し悪しについても実は自分では判断できない人は多く、だから偏差値や学歴がのさばるのです。
そんな私もたとえばファッションセンスがなく、「他人がいいというのならいいのだろう」という程度の判断しかできない。だからこそ、味がわからない人や頭の良し悪しがわからない人が、安易に数字に頼る気持ちも理解はできるのですが。
――試験の点数で評価する学校教育の方向性がそもそも間違っている?
繰り返しますが、偏差値は頭の良さと連動しません。それに、そもそもその前に、人の頭の良さをランク付けすること自体が、百害あって一利のないことだと、どうして皆さんは気付かないのでしょうか。教育の使命は、各人が自分なりの個性や能力を前提に、実社会に居場所を持てるようにすることですよ。点数でのランク付けなんて、その使命を歪めるだけです。「自分は成績がいい」と増長させるのも、「成績が悪い」とコンプレックスを植え付けるのも、社会に適合しにくい人を増やすだけ。
ましてや最近のお受験教育は、出題パターンを教えてその解き方まで指導するという、いわば「自分で考える機会を根こそぎ奪って、条件反射ばかり鍛えさせる」ものになっています。これではむしろ〝頭の悪い人〟ばかりが勝ってしまいますし、実際にその傾向を感じます。
学校教育が行うべき四つのこと
――どのよう学校教育をすべきでしょうか。
四つあるのではないでしょうか。
まずは、その人がもっているポテンシャルを花開かせてあげること。英語ではデベロップと言いますが、その本来の意味は「包まれているものを解いて開く」。本人がもともと持っている蕾を開かせてあげるのがデベロップの概念であり、教育がやるべきことです。
ありもしない蕾を開かせようとするのは悲劇です。私がどんなに野球を練習しても大谷翔平になるどころか、草野球でも勝てません。努力が足りないとかいった問題ではないのです。同じように、一人で答案を書くという作業にそもそも向いていない子どもに、無理にお受験させて、落ちたら「頭が悪い」とするのは、狂気の沙汰です。仕事をさせたら、グループの中では結果を出すかもしれない。大切なのは自分を社会の中でどう役立てるかなのです。
さらには、各人のポテンシャルを比較して優劣をつけるのも全く無意味。ポテンシャルを100%開花させることこそが素晴らしいのであり、開いた結果を他人と比べてどうこうと比較して格付けする必要が、どこにあるのでしょうか。
二番目は、人が生まれつきもっている志向・指向性の中に、他人の人権を侵害してしまうようなものもあるわけで、それは出さないようにする訓練をする。簡単なところでは、人をねたむのはみっともないと教える。極端な例では、生まれつき小児性愛の傾向をもっている人には衝動を抑える訓練をし、場合によては治療的支援につなげる。愛し合う人相手の行為と性暴力の区別がつくとか、ハラスメントしない人間に育てるとか、他人の人権を侵害するようなことはやらないように、暗い思いをどう発散するかを含めて訓練するといった教育が重要なのではないでしょうか。
三番目が、推論を教えること。別な言い方をするとファクト・ファインディングを教えるということ。さらに言えば、後で触れますが、「何が事実かはわからなくとも、何が真偽不明で、何が間違っているか見分けることができる」ことが大事です。
四番目が、チームの中で自分は何を分担して貢献するのかを、さまざまなパターンで訓練することです。これは実際に仕事をする際に、最も重要な能力ですよね。「学歴はいいが仕事はできない」という人が無数に出るのは、この力を試験では測れないからです。
――学校という集団の中で、その時々の他人とのうまい距離の取り方を学んでいくということですね。
その通りです。そしてこの力は、大規模校の大人数学級では身に付きません。過疎地の小規模校の方が、クラスのサイズが実社会の課やチームと同じ規模なので、現実的に仕事ができる人材が育ちやすいのです。お受験校を目指させる親は、このあたりもわかっていません。
頭を「ChatGPT化」させないためにも推論を教えよ
――藻谷さんが挙げた四点は、確かに日本の教育に欠落しているように感じます。
中でも最も欠けているのは三番目の推論の教育です。大学教育ですら、定理の証明にばかり偏っていて、現実に照らして間違いを見分けることが、視野に入っていません。だから、たとえば東大生の中からも、当時のオウム真理教に入信する人が続出しました。
同じく東大からフェイクニュースを広める側の人間が続出した例が、たとえばアベノミクスの異次元金融緩和です。安倍政権発足時に私は、「金融緩和を幾らやっても経済は成長しない」と断言し、実際にその通りになりました。判断の根拠は、その時点ですでにバブル期と比べて三倍もの金融緩和をしていたにもかかわらず、経済成長がなかったという事実です。
しかるに東大卒の黒田東彦日銀総裁(当時)は何を思ったのか、そこからさらに五倍に拡大をしました。しかし、やはり経済成長率は微々たるものにとどまりました。
新型コロナへの対応もひどい例でした。日本で最初に感染が確認されたダイヤモンド・プリンセス号では、当初一カ月は船内での感染拡大に無警戒で、ウイルスも変異前で毒性が強かったのですが、亡くなった人は最終的に乗客乗員の0.2%と、実はインフルエンザとあまり違いませんでした。これを日本の総人口に当てはめれば20万人ほどで、一部の「専門家」が騒いだ死者40万人以上などには、最初からなりようがなかったのです。
アベノミクスへの快哉も、国立感染症研究所の遺伝子解析結果の発表を理解しようとしなかったコロナへの過剰反応も、当時の世論では圧倒的でした。これでもわかる通り、「事実から推論」の反対にあるのが「世の空気に流されること」です。そして、「みんなはなんと言っているか」を集めて文章をつくるChatGPTが登場したことで、推論できずに世に流される学歴エリートはますます増えるでしょうね。
そもそも人は、生物の中で唯一、「皆が口にしていること(=世の空気)を自分も信じる」能力をもっています。ChatGPTは、人間のその力をITで再現したものなのです。
自分で推論せずに空気に流される人は、「手足のついたChatGPT」のようなものです。その時々でみんなが言っていることに大きく左右され、意見や態度がくるくる変わる。
最近の残念な例が兵庫県知事の出直し選挙です。斎藤元彦氏のパワハラ問題がメディアで大きく取り上げられた当初は、大勢が「この知事はダメだ」と言っていました。ところがその後SNSで、「斎藤氏は濡れ衣を着せられた」との情報が拡がると、有権者の四人に一人ほどがそれを信じて、パワハラに反省のない彼を再選させてしまった。ChatGPT化した人が、ネット上の噂だけを根拠に、短期間に認識を正反対に変えたのです。
――生成AIは大勢が言っていることを編集して、最も多い情報を「正解」にしている。それと同じような人が今は増えているというわけですね。
そうです。そもそも「正解は多数決で決まる」と思う人をたくさん生んでいる時点で、日本の教育は「推論」というものの存在自体を教えることにも失敗しているのですが。
最近、遠くの町から岡山駅の西口まで車で迎えに来てもらったことがありました。落ち合う場所を指定しようとしてネット検索したところ、「西口には一般車用の送迎スペースがないから、少し離れたホテルの駐車場を利用しろ」というAIの回答が真っ先に出てきたんです。
「そんなわけないだろう」とAI以外の情報を調べ直したら、案の定、送迎場は駅前にちゃんとある。「送迎場はない」という間違いが多く拡散された結果、AIがそのように回答し、それを「正解」だと思い込む人が増え、ますます誤情報が拡散するという悪循環です。
AIは「世の空気」を文章化するだけのもので、その真偽は人間が判断せねばなりません。だからこそ、教育では推論、それも間違いを見分ける推論を中核に据えるべきなのです。
定理、定説よりも「無知の知」をこそ教えるべき
――ChatGPT人間にならないためには推論できるようになることが大事ということですが、推論能力をつけていくにはどうしたらよいのでしょうか?
これも逆から言い直しましょう。推論で間違えないためには、事実と間違いが区別できるだけではだめで、審議不明なものを「まだよくわからない」と分類できることがいちばん重要なのです。これはつまり、ソクラテスが二千七百年前に気付いた「無知の知」ですね。
残念なことに人間は、本当はわからないことにまで、いろいろ妄想して理由付けをして、わかったふりをしたがる生物です。陰謀論やフェイクニュースを信じるのは、そういう欲求が特に強い人たちです。推論の失敗はほとんどが、まだ真偽不明の段階で「正しい」と判定することから起きます。
ですから、皆が正しいと思ったが、後になって間違いとわかったような実例を挙げて、「わからないことについて、安直な説明を信じてはダメだよ」と、教育しなくてはなりません。
――ところが学校教育でそれができていない。
「正解」ばかり丸暗記させる教育に、それができるはずがない。試験の答案に「わからない」と書いたら0点になってしまいますよね。むしろChatGPT能力の高い人ほど、点数が高くなるのがお受験教育です。「偏差値や学歴と頭の良し悪しはまったく関係しない」と言ったのは、私の実体験に基づいているわけですが、現実がそうである理由はここにあるのでしょう。
米国でトランプ大統領をサポートするエリートが多く出てきている理由も、同じだと思います。
人の多様な能力を点数だけで輪切りにするのは間違い
――ChatGPT化による「まずい」ことが、もうすでにあちこちで起きているように感じます。多様な社会をつくる方向に向かったはずなのに、それに逆行するような言説が声高になると一定の支持を得たり……。
まだ真偽がわからないことまで、今すぐ「正しい」「間違いだ」と分類したがる人ほど、多様な事実をまず「事実」として受け入れることができません。
たとえばLGBTについて、頭ごなしに一種の精神疾患であると決めつける人がいますね。しかし同性愛は、日本を含め世界中に歴史の初めから普通にあるばかりか、他の動物種にも広くみられます。親は異性愛だからこそ子どもが生まれるのですが、その中にLGBTの人が出るということは、遺伝子レベルや環境などの要因も影響しているのではないかということですね。
もしLGBTが人類の生存に都合の悪いものであれば、なぜそんな遺伝子が広く残るのでしょうか。逆に、LGBTは人類の生存に大事だからこそ残っていると推論することもできる。人間は集団で子育てをする動物なので、「自分は子どもをもたないが、他の人の子どもを喜んで育てる」保育士さんのような存在がいるほうが、生き残りに都合が良かったのかもしれません。
今ある多様性は、人類十万年の進化の過程で遺伝的に淘汰された結果なのだと推論することもできます。
お受験教育は一切やめ、東大は全入にすべし
――事実をもとに推論する能力を身につけた人が増えていけば、主観や先入観だけで決めつけたり、みんなが言っていることが判断基準になったりすることも減っていきそうな気がします。それにはやっぱり偏差値が幅を利かせている教育制度を変えていく必要がありますね。
後の世からは、今の学歴は江戸時代の身分差別と同じレベルでナンセンスだったと判定されるでしょう。明治維新後に活躍した諸人材のほとんどは、下級武士や農民の出でした。しかし江戸時代が続いていたら、彼らは上級武士から見下されたままだったでしょう。上級武士こそ、殖産興業の能力もなければ世界にも通じない、無能力な人たちだったのに。
今の時代に低学歴の人を見下しているような、国内限定の高学歴者も同じことです。結局、実力がないから学歴という身分を売り物にするしかないのですが、それ自体が低学歴とされる人の価値を勝手に貶めている情けない行為だと、気付かないのでしょうか。
そもそも人は、誰かと比べて偉いから尊いのではありません。誰でも生きているだけで価値があるのです。精子と卵子がたまたまくっついて生まれている時点で奇跡なのですから。
その上で、蕾として持って生まれた力を開花させてその人なりに社会参加していくことが尊いのであって、そこに上下をつける必要は皆無です。
それなのに一方的で単線的な序列付けを公的に続けているから、相模原市の「津久井やまゆり園」の事件の犯人のように、障害者をダメな存在だと決めつけて殺めたりするような許しがたいことが起きるのですよ。学歴を鼻にかけて周囲を見下す人は、あの犯人と自分が実は地続きでつながっていることを自覚せねば。
お受験教育はもう明日からでも、一切やめるのがよろしい。そうすれば、いわゆる「国際競争力」だって上がりますよ。実際問題、日本の若者がいま世界に雄飛しトップクラスの評価を得ているのは、プロスポーツ、調理、理髪、アートなどの分野でして、活躍しているのは国内限定のお受験競争から脱落したり、自ら「一抜けた」人たちです。逆に学歴エリートから出た経営者や学者などのほとんどは、世界には通用していません。
東大などは、全員入学させて中でどんどん落第させるシステムにすればいい。リモート授業にすれば収容力の問題はなく、試験はすべて学生のプレゼンテーションに対し質疑するかたちにすれば、人工知能の悪用だけで乗り切ることはできなくなります。
教育から「学歴身分を生み出して序列付けする」という機能を取り除くことこそ、日本が本当の意味で江戸時代や昭和を脱する、唯一最大のポイントだと確信します。
(構成・文 八木沢由香)

もたに・こうすけ 1964年山口県生まれ。東京大学法学部卒業。平成合併前の3200市町村すべてと海外 142カ国を私費で訪問。地域の特性を多面的に把握し、地域振興、人口問題、観光振興などで研究・執筆・講演を行う。著書『デフレの正体』『里山資本主義』(共にKADOKAWA)など多数。近著は『誰も言わない日本の「実力」』(毎日新聞出版)。